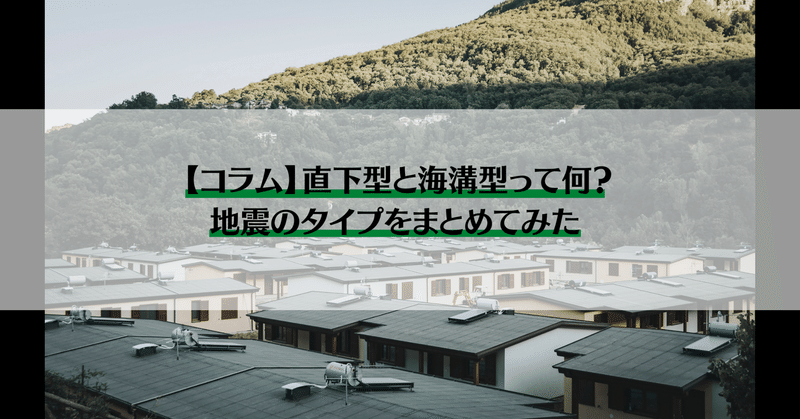
【コラム】直下型と海溝型って何?地震のタイプをまとめてみた
あまり一般には知られていないことですが、地震には大きく分けて2つのタイプがあります。
ここでは、それぞれのタイプについてコラムという形でまとめてみました。
それぞれのタイプで自宅や家屋にどんな被害が想定されるのか、またどんな影響があるのかについてご紹介いたしますので、日頃の防災意識を高める上でのご参考にされてください。
地震のタイプは2つ
地震は、直下型と海溝型の大きく分けて二通りに分かれます。それぞれのタイプについてその特徴をご紹介します。
【直下型地震の概要】
■直下型地震とは:
文字通り土地の直下で発生する地震です。ガタガタと縦に突き上げるような揺れ方が特徴で、マグニチュードが比較的小さなものでも震度としては大きなものになりやすいという特徴があります。
直下型地震は局地的に大きな震度や被害を出す傾向にあるものの、震源が深い場合は広域的に大きな被害をもたらすケースもあるため注意が必要です。
特に、活断層と呼ばれる過去に地震を起こしたことのある断層が近いエリアでは、注意しておくべきです。なぜなら、過去に大きな地震を起こした断層があるということは「今後もその断層の上で地震が発生する可能性が考えられる」からです。
日本国内で発生したものだけをまとめても、直下型地震の例は枚挙にいとまがありません。
【直下型地震の例】
・1995年阪神淡路大震災
・2004年新潟中越地震
・2016年熊本地震
・2018年胆振東部地震
など、多数の事例があります。
そしてそのどれもが激甚な被害をもたらし、復興までに多くの年月をかけることになりました。
【海溝型地震の概要】
【海溝型地震とは】
いわゆる「海地震」と呼ばれるのが海溝型地震です。こちらは震源が海底というパターンで、日本国内の地震情報で震源が「茨城県沖」「関東東方沖」「三重県南東沖」など「沖」とつくのが特徴です。
津波のリスクが伴うのは、主に海溝型地震の場合です。
震源が陸地から遠く離れていると地震波が陸地に届くまでにエネルギーが減衰しますので、そこまで大きな被害にはなりません。一般的に、マグニチュード3.5~4.0程度で震源が遠く離れた沖合であれば「体に感じない地震(無感地震)」として地震情報にも掲載されないことがあります。
しかし、マグニチュードが7以上になると、大きな揺れや津波のリスクが伴います。
海溝型地震の場合は、直下型地震と違って初期微動が先に到達してから主要動が届きますので、初期微動の段階で体に揺れを感じるようであれば主要動は極めて大きなものになると予想できます。
その他、詳しいメカニズム的な部分は今回は割愛しますが、直下型地震と比べて海溝型地震はマグニチュードが極めて大きくなる傾向にあります。
近代の直下型地震で極めてマグニチュードが大きかったと推定されたものとしては、以下のケースが挙げられます。
例)マグニチュードが大きかった地震
・1923年 関東大震災:マグニチュード7.9
・1995年 阪神淡路大震災:マグニチュード7.2
その前に発生した1891年(明治24年)の濃尾地震は、マグニチュード8.0と記録されています。
しかし近年の地震では、直下型のマグニチュードは大きなものでも最大7.2程度となります。その一方で、海溝型地震の場合はマグニチュードが最大9.0に到達するものもあるなど、そのエネルギーは莫大なものがあります。
海溝型地震の例
海溝型地震のうち、特に大きな地震をもたらした事例としては以下のようなものがあります。
例)特に被害の大きかった海溝型地震
・1993年 北海道南西沖地震
・2011年 東日本大震災
その他、日本政府も今後30年以内に極めて高い確率で発生すると予測している「南海トラフ地震」も海溝型地震の極めて大きなものの一つとなります。
海外に目を向ければ、スマトラ地震やチリ沖地震など、日本まで津波や潮位変動が襲来したケースもあるなど、極めてマグニチュードが大きいものもあります。
家屋の被害が起こりやすいのはどっち?
大原則として、どちらのタイプでも家屋の被害は十分に起こりえます。
そのため、海から離れている地域にお住まいの方も、直下型地震に備えて、家屋の保険や火災保険などは完全に見直しておく必要があるでしょう。
まとめ
海溝型地震のタイプによって被害も影響も異なりますが、どちらにしても自宅や家屋に被害が及ぶケースも十分に考えられます。
いつ襲ってくるか分かりませんので日頃から防災意識を高め、また地震による家屋の被害がある場合には、早めに修繕しておくことも重要と言えそうです。
参照:外壁塗装の調査を行うサイトの例
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
