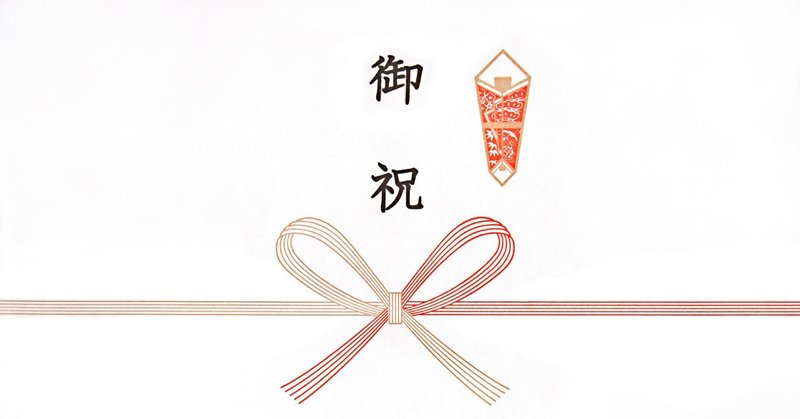
「君と私 志賀直哉をめぐる作品集」解説補遺②
■「君と私と」をもっと理解するために
「君と私」での里見の焦りを、もうすこし掘り下げてみましょう。
創作・環境・放蕩の3点に分けてみます。
① 創作の焦り
このころ、里見はまだ「これだ」と手応えを感じる創作ができていません。
しかし、5つ年上の志賀は着々と前進していました。
このあたりをざっと時系列順で並べると、
明治36年 志賀21歳:学生。小説家を志す。翌年、処女作「菜の花と小娘」
里見16歳:学習院の学生。
明治40年 志賀25歳:作品を里見に聞かせる。未定稿が多い。
里見20歳:スケッチのような小品を書き始める。
明治41年 志賀26歳:『望野』を始める。「或る朝」で手ごたえを得る
里見21歳:『麦』を始める。
明治43年 志賀28歳:白樺を始める
里見23歳:白樺を始める
明治45年 志賀30歳:滝田樗陰に認められ、中央公論で商業デビュー
里見25歳:「腐合いと蝉脱」を書く。最初の対立
大正2年 里見26歳:「君と私と」を書き始める
時系列で並べてみると、里見はちょうど志賀の数年あとを歩いているような感じですね。
明治45年(大正元年)、大正2年に着目してみてください。
このとき、里見は25,6歳。
志賀が手応えを得て、自分の文学を感得したのは、その5年前。里見と同じ26歳です。
そして明治45年、あの滝田樗陰がひきいる中央公論で商業デビュー。
そう、前回の記事でもご紹介した名編集長、滝田樗陰が、志賀を認めたのです。
でも里見はどうだったでしょうか。
彼にはまだ、志賀の「或る朝」にあたるような作品がありませんでした。つまり、まだ自分の目指すべき文学さえつかめていないのです。
志賀が「或る朝」を書いた年になっているのに、なにを書けば自分の文学と言えるのか、わからない。
里見が焦り、ここをひとつのタイミングと感じたとしても無理はありません。
早く自分の文学を得たい。そのために、志賀から自立したい。
自分をいつまでも支配下に置こうとする志賀の腕から逃れたい。
年齢というタイミングも、里見の焦燥をかきたて、志賀との対立につながっていったと言えるのではないでしょうか。
なおこの年の暮れ、里見は白樺に掲載した「河豚」(原題「実川延童の死」)で、ついに創作の手ごたえを得ます。
そして翌年には夏目漱石から声をかけられ、朝日新聞の連載企画に参加。ここから、彼の作家としての道が広がってゆくのです。
② 放蕩への疲れ
明治45年(大正元年)、志賀と里見は放蕩の日々に飽いていました。
遊びに行けば酒も飲みます。
昼夜も逆転します。
そんな日々を繰返せば体調がすぐれないのも当然です。精神的にも「神経衰弱」におちいっていきます。
神経衰弱というのは、特になにかの診断がされているわけではないものの気分が優れない状態を総称してこう呼んでいたようです。
一時期「ノイローゼ」と言われていたような状態でしょうか。
ところで、放蕩と気軽に言いますが、これはいったいどういうものだったのでしょうか。
娼妓は今では存在せず、芸妓も遠い存在になりました。当時の感覚としてはどういうものだったのか、分かりづらいところです。
当時の吉原での遊びは、現代で「風俗」と言って思い浮かべるようなものとは違いました。
また、「性」は当時の文学においては重要なコンテンツで、彼らには一種の文学的な冒険という気分もありました。
大臣クラスが遊ぶ超高級店にも出入りしており、金持ちのお坊ちゃんにしかできない遊びという面もあります。
当時、地元香川から上京して第一高等学校に通っていた菊池寛は、「君と私と」の大ファンだったと言います。
私は里見君の『君と私』などを、
どんなに愛読したか。
それは芸術的に感心したなど云うよりも、
田舎の中学生である私には、
学習院の学生生活など云うものが、
不思議な魅力を持つていたのかも知れないが、
里見君の初期の作品を
私がむさぼるように読んだのは事実である。
ここからは、当時の同世代の学生にとって、里見の描く放蕩の日々が、魅力的でかっこいいものに見えていたことがうかがえます。
現代の若者で言うならば、六本木のシャレオツなクラブの超高級VIP席に夜な夜な出入りし、かと思えばウユニ湖のような海外おしゃれスポットにも気楽に出かけ、帰ってきたら著名な芸能人や文化人などのインフルエンサーと一緒に写った写真をインスタにあげ……というような感じなのでしょうか。
ちょっとよくわかりませんが、ともかく、そんな日々は確実に志賀と里見を疲れさせていました。
なんにせよ、ふたりとも根が真面目だったものと思われます。
実は志賀も、放蕩から抜け出そうと悩んでいました。
明治45年あたりの志賀日記には、「里見や三浦たち放蕩仲間と距離を置いて、武者や柳たち真面目なグループと付き合うようにしなければ」という記述がみられます。
にもかかわらず、志賀にはそれができなかったのです。
そう思いながらも里見と会い、飲みに出、何時間もぶっ通しで町をさまよい続けてしまう。そんな日々が続いていました。
里見と離れようと思いながら離れられない心境を、志賀はこう描写しています。
信行(※志賀)は一刻も早く
坂口(※里見)と別れたかった。
(略)
左う思いながら、彼には何故か
「別れよう」と云い出す気がしなかった。
これ程の気分でいて、又それを
カナリ露骨に現わして居ながら
何よりも早い「別れる」という事が
何故こうも困難なのか自分でも解らなかった。
彼はこれまでも坂口との関係で
殊にこういうことの
多かった事を想い浮かべた。
腐縁と二人はそれを云っていた
ことなどを想った。
つまりはこの時期、現状を変える必要性を感じていたのは里見だけではなかったのです。
とりあえず「もうやめよう」と話し合えばよかったような気もしますが、そんなに単純なしがらみではなかったのかもしれません。
結局は志賀は「腐縁」を手放すことができませんでした。
捨てても構わないと行動を起こしたのは里見のほうで、それが「腐合いと蝉脱」から「君と私と」へつながっていった……と言えるのです。
③ 町のエネルギー
ふたりがさまよい歩く町にも目を向けてみましょう。
「君と私と」では、日本橋についての記述に「仮橋」という言葉が見られます。
実は、麒麟像で有名な現在の日本橋の完成は明治44年(1911年)。
作中の時点ではまだ工事中だったため、ふたりは、仮の橋をわたっているというわけです。時代を感じるとともに、急につながりが見えてきて親近感がわくところでもあります。
また、「月島の渡し」から月島にわたっている様子も見られます。
東京都中央区にある月島は、もとは明治期に埋め立てられた人工島で、渡し船を利用しないと渡れませんでした。月島の渡しは、そのなかでも今の聖路加ガーデンあたりにあった渡し場だといいます。
明治時代の人々は、渡し船に乗って、できたばかりの島、月島の明かりを目指していたのでしょう。
このように、「君と私と」にはタイムカプセルのように明治の東京が閉じ込められています。
町の記述を追っていくと浮かんでくるのは、江戸の名残を残しながら目覚ましく近代へ生まれ変わろうとするエネルギーに満ちた帝都・東京です。
そのエネルギーは路上にも充満しています。
夜な夜なさ迷い歩く志賀と里見は、まさにそのエネルギーを受け取り、古い殻を脱ぎ捨てて生まれ変わろうとあがいていくのです。
④ 世代のエネルギー
作中には森鴎外、北原白秋、永井荷風、小山内薫、上田敏など、当時の文壇の華やかなメンツが登場します。
彼らもまた、明治の文学を大正の文学へと変えていこうとするエネルギーに満ちています。
ここに本名が出ていない作家が二人います。なぜか。
おそらく志賀を怒らせたからでしょう。
それは谷崎潤一郎と吉井勇。
志賀が若手作家にからかわれ、立腹する場面がありますが、あれが谷崎潤一郎と吉井勇なのです。
明治期末、自分たちの新しい文学を作り上げようとする若者たちの熱気が、カフェやレストランには溢れていたでしょう。里見も志賀も、その若者たちの一人だったのです。
このような時代の空気も、「君と私と」には閉じ込められ、今にその熱気を伝えてくれているのです。
■ 連載の中断
大正2年、「君と私と」は「白樺」4月号から連載が始まりました。
4,5、と順調に進んで、6月号で志賀が怒り出します。
志賀は怒りのあまり抗議文を一度書き、足りずに二度書き、さらに足りずにもう一度書きます。
このうち二度目のものが「「君と私と」の私に」、三度目のものが「モデルの不服」と名付けられ、いずれも志賀全集で読むことができます。
「モデルの不服」ではかろうじて余裕ある先輩の顔をたもっている志賀ですが、「「君と私と」の私に」は、裏切られたという怒りに満ちています。なるほどこれはそのまま発表できないだろう、と納得も行きます。
それだけではなく志賀は電話をかけたり、里見に会ったりして抗議を続けます。すさまじい怒りです。正直、どうした?と聞きたくなります。
初めは跳ね返していた里見も、しだいに疲れてしまったのか、体調を崩して寝込んでしまいます。
そこで志賀宛に書かれたのが、「解説」でもご紹介した手紙なのです。
この手紙で里見は絶縁をにおわせますが、志賀はことわります。
志賀が望んだのは、距離を置くことなくともにありながら成長を目指す、という道でした。志賀は、今の里見が精神的に不安定な状況であることを指摘し、自分に見切りを付けるなと説得。その説得に里見も納得します。
こうしてひとまず激しい対立はおさまりましたが、「君と私と」の連載は中断してしまいます。
志賀のもとに原稿を持参してチェックを受けていたようすが、「失われた原稿」からもうかがえます。
遠い札幌の地でこの話を知ったのが、里見の長兄である有島武郎でした。
有島武郎は、現在の北海道大学の前身である札幌農学校で教鞭をとっていたため、すぐには東京の情報が入らなかったのでしょう。
しかし弟の窮状を知った有島武郎は筆を執り、志賀にこう書き送りました。
里見の「君と私」は
続けさして頂きたいと思います
私はあれを読んで苦しむことを好みます
穏やかですがきっぱりとした牽制です。
札幌の地で、弟の苦痛を読むたび心を痛めながらも、里見の覚悟を見守っていたのでしょう。
このようなところに、作家たちの人間性や関係がうかがいしれるのではないでしょうか。
ちょっとここまでで長くなってしまいました。
後は駆け足でご紹介していきましょう。
■「善心悪心」
里見初期のスマッシュ・ヒットとでも言ったような作品で、代表作の一つに挙げられることも少なくありません。
この冒頭では、「或る年上の女との関係」の清算が「案外にも容易く成就された」とちらりと触れられています。この「年上の女」が「いち」だと思われます。
別のくだりでうっすらと匂わせられていますが、「いち」はどうやら里見以外にも、里見の父やもう一人の兄とも関係を持っていたということで、有島家にはいられなくなったのかもしれません。
「いち」は地方の住職の後妻となり、有島家を永遠に去ったといいます。
ところで、里見50歳時の作品に「土産話」という短編があります。
架空の設定ですが、おそらく「いち」との関係を50代になってから振り返って書かれたものです。
そのラストで、主人公は女中との関係から受けた傷を、遠く過ぎ去った出来事として振り返ります。そこには当時の自分の未熟さを、若さゆえの純粋さとして懐かしむ気持ちすらあり、生々しい痛みはありません。
このころには、里見はもう「いち」との件からうけた心の傷を乗り越えることができていたのでしょう。
さらにこの作品には、彼女とのあいだに授かったらしき娘が出て来ます。
現実とは違い、無事に産まれて幸せになっているらしい娘。主人公は胸をつかれるような想いで見守るのです。
「いち」のことは吹っ切れても、罪悪感は里見の胸を去らなかったのかもしれません。
■「世界一」
「君と私と」に劣らずマイナーな作品と言えるでしょう。
この作品で、我々は、志賀と里見の関係のちがう側面を見ることになります。
「君と私と」でも、嵐の湖にボートを出した話や、
「君と私との心がピッタリと合って、鼓動を共にするような瞬間」
について触れられてはいますが、里見はそれ以上深く掘り下げてみせることはありませんでした。
しかし「世界一」では、「君と私との心がピッタリと合って、鼓動を共にするような瞬間」が思うさま描かれています。
まさに一つの心臓を共有しているかのような共鳴と言えます。
ここに至って初めて我々は、その言葉の意味と、なぜ志賀と里見の関係があれほどまでに断ち難かったかを知るのです。
鳥取砂丘で大仏の絵を描いた一連のいきさつについては、里見が「証言里見弴」で語っているので、事実であることが確認できます。
大仏の絵は、ふたりがともにあった青春の日に夢見た仕事の象徴ともいえるでしょう。
離れても互いを見、動きをうつしあい、時には手を取り大きく跳ぶ。
これほど理解し合い、喜びを得られる友が、手放しがたい相手となるのもうなずけます。そしてまた、ふたりがのちに復縁したことも理解できます。
たしかに、ふたりの間には、強いきずなが存在していたのです。
この作の発表は志賀との絶縁の終わり近くのことでした。
里見の感情が落ち着き、志賀との関係を客観的に見る余裕が出てきた、と言えるのかもしれません。
この作品があることで、「或る年の初夏に」のクライマックスは、さらに深い味わいを持ちえます。
その日々は松江で終わりを告げることがわかっているからです。
■「或る年の初夏に」
われわれは、深い共鳴と激しい対立とともにあった青春が、とうとう終わりを告げる瞬間を見届けることになります。
実際に松江で暮らした日々をモデルにした小説ですが、注目したいのは二人が違う下宿に入っていることです。
実はこれは、里見の希望でした。
違う下宿に入るか、もし同じ下宿であっても、家の一番遠い端どうしがいい、と書かれた手紙が今も残っています。
一緒に松江に行きながら、同じ下宿は嫌だという。
矛盾のようですが、このときもなお正しい距離を模索していたのでしょう。
振り返ってみると、この人たちは最初からこんなところがあります。
たとえば最初にもめた明治45年(大正元年)の「腐合いと蝉脱」のあとには、一か月ほど絶縁しましたが、復縁後、志賀は尾道に向かいます。
このとき、志賀は東京の出版社で第一短編集の準備中でした。
志賀が装丁を依頼した相手がふたり。一人が、白樺ではよく本の装丁を担当していたメンバー三浦直介。
もう一人が、先日まで絶縁していた里見でした。
志賀は尾道から里見とひんぱんに連絡を取ります。
このころ武者小路実篤が尾道へ送った手紙には、「そろそろ志賀が最初の長い手紙を里見に送っているころだと思って、みんなで有島家に集まった」と記されており、志賀が最初に手紙を送る相手は里見だ、と白樺内で認識されていたことがうかがえます。
また、志賀が一度帰京して尾道へ戻った際は、里見は「毎日のように会っていたので寂しい、明日にでもまた会いたいところなのに」と甘えるような手紙を出しています。
それからしばらくあとの手紙には、志賀の手紙に返事を出さないので志賀から文句を言われたらしいことが、文面からうかがえます。絶交していたとはとても思えません。
離れようという気持ちと、つながっていたい気持ち。
その相反する感情の間で、ふたりの言葉も行動も、揺れつづけていたのかもしれません。
振り子のように行ったり来たりするなかで、ゆっくりと、あるべき形を模索していった。二人は、そういう状態だったのかもしれませんね。
ついに志賀の腕を振り払う瞬間については、これ以上述べる必要はないでしょう。
ラストの里見の涙がすべてを物語っていると言えるのです。
■ 絶縁、そして
こうやって振り返ってみると、結局は、ただしい距離を知るために、二人はいちど離れなければならなかったのかもしれません。
そのために必要な時間が足かけ8年だった。それだけ経過して、それぞれ自分の人生をもった大人になったとき再会することができた。
そう考えると、志賀が「正誤」で「(復縁後は)安全で完全な友になれた」と語っていることも理解できます。
そうはいっても、すっかり落ち着くのではなく、やはり時々感情的になって喧嘩したりするのも、ふたりの人間味が感じられてほほえましいところです。
まだまだ、ふたりには面白いエピソードが沢山あります。
「幸福人」は、当時原稿に追われて旅館に缶詰めになり、フルスピードで書いたという作品です。
一晩で原稿80枚を書いたとか。
400字詰めなら手書きで3万2千字を書いたということになります。
原稿新記録だったそうです。
しかしこのようにひとつひとつあげていくと、この記事が終わらなくなってしまいます。
ちょっとあげてみますと、
・志賀の後輩が志賀家に泊まりに行くと、志賀から寝る前に「これ里見の新作」と押し付けられ、翌朝顔を合わせるなり挨拶もなしに「どうだった!?」と聞かれた
・復縁後、志賀の家で里見が夕食を作っていたが、あまりに遅いため志賀が「これ以上待たせるなら革命を起こすぞ」と台所に乗り込んできたので、里見がからすみのきれっぱしを食べさせると急におとなしくなってもごもごしながら帰っていった
など、愉快なエピソードがてんこ盛りです。
よかったらぜひ、いろいろな本を手にとって探してみられてくださいね。
「君と私 志賀直哉をめぐる作品集」を呼び水として、ゆっくりとでも二人の読者が増えて行ってくれることを願って、この記事を終えたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
