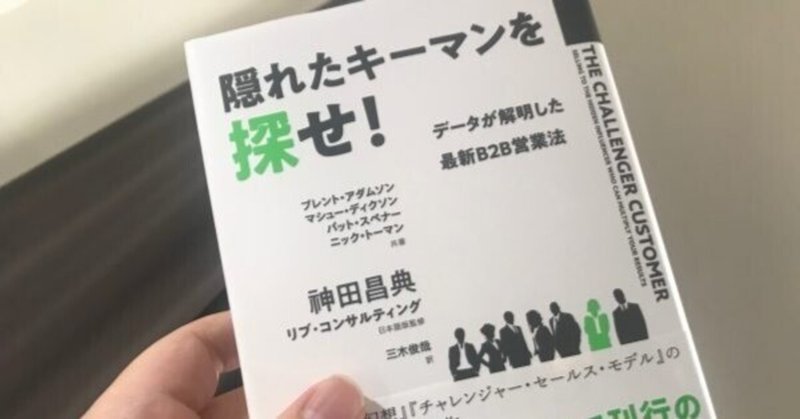
隠れたキーマンを探せ! データが解明した 最新B2B営業法
※私が読んだ本の書き出しとざっくりした内容を書き留める読書記録です
はじめの一行
監修者まえがき デジタル時代の営業についての、不都合な真実
まずは、TVコマーシャルのように、あなたの関心を引くクイズから始めよう。
次の問いに〇か×で、お答えいただきたい。
□購買決定にかかわる全員を追跡・説得できれば、良質の契約が取れる
□専門家としての知識を活かした提案は、利益率が高い契約につながる
□顧客ニーズに合わせた商品カスタマイズは、より良い条件での取引に至る
□製品ベネフィットを分かりやすく伝えれば、成約率は高まる
□魅力的コンテンツを提供するナーチャリングは、需要を創り出す
多くの人が信じている常識的なことを羅列して、しかし、それは間違いである、という事を言うまえがきは多い。
これをクイズ形式にすると、さらに食いつきがよくなりそうですね。
本書の内容
全体像
本書の主な内容は、B2B営業を個人的な経験則ではなく、データから解明した内容となります。
その内容はけっこう衝撃的です。
私自身、法人営業においては、トップを落とせばOKという事を先輩から習った記憶があります。
しかし、データから検証すると、購買決定にかかわる平均人数は、5.4人。
で、この人たち一人一人を説得し、同意させたとすると、ありきたりな提案内容となり、利益が薄くなると言います。
なるほど、肌感覚としても感じられるのは、顧客の中で誰一人「責任を取りたくない」と考えていることは透けて見えます。
たとえば、自分はとてもいいと思う式に行ったのだけど、他の部署がなんというか・・・
内容は素晴らしいと思うけど、複数社の合い見積もりを取らないと、あと後問題になる・・・
まあそんな声が聞こえてくるわけです。
そこで本書はいくつかの事例を引いて、その壁を突破する方法を伝授してくれます。
それは顧客側にある本当の悩みにフォーカスし、その悩みと製品を関連付けるというもの。
単にライバルとの比較の提案(程度の差)から、差別化を創り出す提案をすべき、と指南しています。
3分の1問題と5.4人の興亡
近年法人営業となると、基本的に「三者の合い見積もり」が必須になってきています。
どんなに素晴らしい提案をしたところで、「じゃあ同業他社三社に見積もりを」という事になる。
提案が価値として認められることは少なく、常に3社のうちの1社という立場となります。
それはつまり、し烈な価格競争にさらされており、せっかくの提案もここでほとんど無力化される。
一方、様々なソリューションの購買決定は、一つの部署で住む話でないことが多くなってきています。
組織やビジネスは複雑化し、複数の部門のOKが出て初めて購買に至ります。
そこに際して、5.4人の意思を統一する必要があります。
そしてこの5.4人を追跡するのですが、最終的な決定賢者を探しても、見当たらない。
みんな「〇〇部が良いと言えば検討する」とか、「自分のところでは決められない」とか雲をつかむような話になってしまいます。
ならば、とこの5.4人を追跡して追いかけて、一人一人の言質をとってもなんとも購買への確約には至らない。
つまり、購買を決定するのは、企業のなかでの誰か、ではなく組織そのものであると言えるかもしれません。
ある意味、営業パースンは見えない敵と対峙していると言えそうです。
意思決定権者はどこにいる?
法人営業に関して言えば、営業のこれまでの鉄則は上位の意思決定権者にあい、その人を説得することが重要と思われてきました。
これは言ってみれば、社内に一人、買いたいと言ってくれる人がいるときに、彼らとの協力関係が大事だと言います。
つまり、顧客の会社の中に賛同者を見つけた場合、その方の敵は社内にあります。
その社内の人間を説得し、合意を取り付けるステップについての戦略が必要と言えそうです。
本書では顧客の関係者を7つのタイプに分けています。
ゴー・ゲッター
他者の良いアイデアを支持する。
常に求められる以上の成果を出す
ミスから学び、進歩する
スケプティイク
不透明なプロジェクトを危険と見なす
影響力の強い関係者を破壊的なアイデアに備えさせる
変革にはまず小さな成功が必要だと考える。
フレンド
接触しやすく販売員との会話を楽しむ
販売員と同量のネットワークを築く
販売員に惜しみなく時間を割いてくれる
ティーチャー
新しい知見を教える
同僚や幹部から意見を求められる
他者の説得がうまい
ガイド
ベンダーには手に入りにくい情報を提供する
ベンダーと話すときは真実を述べる
情報を公平に分配する
クライマー
プロジェクトから個人的利益を得る
リスクを取ったことに対する個人的報酬を望む
成功談を話したがる
ブロッカー
安定その物が目標だと考える
改善プロジェクトは気が散ると考える
めったにベンダーを助けない
このうち、パフォーマンスの高い販売員は、ゴー・ゲッター、ティーチャー、スケプティックとの関係作りを重視し、兵員的な販売員はガイド、フレンド、クライマーをターゲットにする傾向があるようです。
営業の役割は「忘れさせること」!?
営業におけるセールスパースンの役割は何かというと、目標はソリューションを買わせることではなく、顧客の行動を変えさせること。
フェーズ1に顧客の現状があるとすると、
フェーズ2には「新たな行動に挑戦しようとする個人の動向」がある。
そしてフェーズ3で「質の高い取引のための集団コンセンサス」が必要となる。
ところで購買側は、販売員にコンタクトを取るのは購買プロセスが57%進んだ段階である、という事がわかっています。
販売側はもっと早く顧客と出会うマーケティングプランが必要ですが、実はこの時にも販売者と顧客の動向にはズレがあるようです。
たとえば、販売者は「専門家の視点/スマートな視点を示す」ということを意識していることが多いと思われます。
しかし、それはあまり顧客を動かす結果にはないようです。
むしろ必要なのは次の二つ。
①顧客のビジネスについて新しい魅力的な情報を教える。
②なぜ行動を起こすべきかについて、説得力ある理由を顧客に提示する。
自分達自身のビジネスに関する意外な情報に接した時に、自分たちの購買基準をリセットすることが多いようです。
そして顧客を動かすのに必要な情報を引き出すのに、こんな自問自答が必要となりそうです。
問い①われわれならではの持続可能な強みは何か?
問い②そんな独自の強みの中で、顧客に良く認識されていないものはどれだ?
問い③顧客が、彼ら自身のビジネスについて十分理解していない点(そのせいで我々独自の持続可能な強みに気付いていない点)は何か?
問い④顧客のビジネスについて何を教えてあげれば、彼らの現在の認識を変えられるか?
法人営業の役割は、古い考えを「忘れさせる」ことのようです。
デンツプライの事例とそれを作り出すチェックリスト
ここで歯科医療機器のデンツプライとう会社の事例が紹介されています。
彼らは、コードレスの画期的な地下治療器具を作り出しました。形状も重さも、人間工学に基づいて作られており、非常に使いやすい。実際に歯科医にモニターを依頼すると、好評です。
しかし、良いけど売れない。
歯科医は今の機械も十分使えるので、変化を起こすほどのインパクトがなかったと考えられそうです。
そこで様々な調査を行った結果、歯科医院においては歯科衛生士が休みがちなことを突き止めました。
実は、不自然な形で歯科医療機器を固定したりして使ったりするので手首痛に悩まされる歯科衛生士が多いのです。
そこで、デンツプライはまずは歯科衛生士の休業が多いことの原因が手首痛であり、その原因は歯科医療機器の重さや形状にあることを証明しました。歯科医師にとっては、歯科衛生士の休みがち問題は結構大きな悩みだったので、それを解消できるなら、とデンツプライの製品を真剣に検討するようになったといいます。
こういった展開を作るためのステップは以下の通り。
ステップ1 自社の差別化要因を洗い出す
ステップ2 顧客が最も関心を持つ結果の一覧を作る
ステップ3 結果に優先順位をつけ、起点となるものを選ぶ
ステップ4 結果のドライバーに関する顧客の認識をマップ化する
ステップ5 自社の差別化要因と顧客の結果とのつながりを想定する。
ステップ6 つながりを検証・確認する
コンテンツマーケティングの問題?
コンテンツマーケティングにおけるポイントは3つと言われています。
①スマートであれ
②役に立て
③存在感を出せ
とされているが、これが効果を表さない、という考えに基づいています。
そこで必要なコンテンツの在り方として、
・型破りなアイデアの探求を刺激する(Spark)
・型破りなアイデアを導入する(Introduce)
・型破りなアイデアに直面する(Confront)
という流れを設計する必要があると言います。
このコンテンツの進展プロセスをSICコンテンツ戦略と名付けています。
これは私の感覚的な表現ですが、思いっきり刺さるフックがなければ意味がない、という事でしょうか。
そのためには顧客が日頃悩んでいることにフォーカスし続ける必要がありそうです。
この先のステップ
さて、ここまで読み進めた(上記内容は全10章のうち第6しょぅあたりまでの内容の一部)だけでも、従来の常識的な営業パターンとはずいぶんと異なった印象を受けます。
その印象を根本から覆すような法人営業の真実はどこにあるのか。
この後はぜひ本書で解き明かしていただきたいと思います。
どちらかといえばマーケティング寄りだった話が、徐々に営業寄りになっていきます。
いやー、読書って素晴らしいですね。
Amazonでのご購入はこちら

頂いたサポートは、日本の二代目経営者のこれからの活躍を支援するために使わせていただきます。
