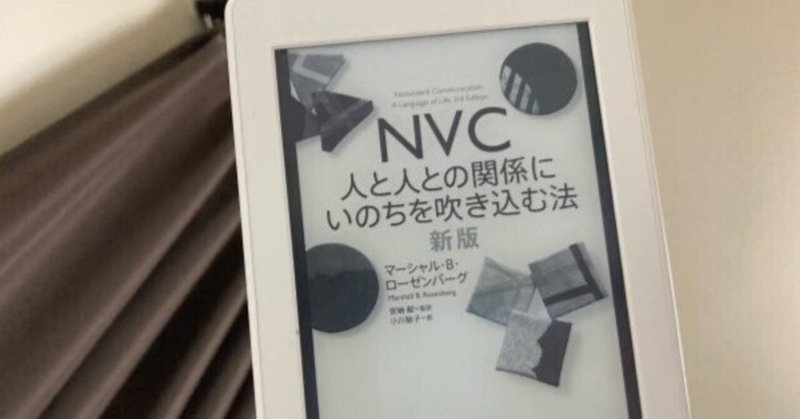
NVC 人と人との関係にいのちを吹き込む法 新版
※私が読んだ本の書き出しとざっくりした内容を書き留める読書記録です
はじめの一行
はじめに
人は生まれながらにして自分以外の人を思いやり、与えたり与えられたりすることを楽しむ。そう信じる私にとって、長年、頭から離れないふたつの疑問があった。人を思いやろうとする気持ちが一体どういうわけでかみあわなくなってしまうのか、そしてそのあげく、暴力的になったり相手から搾取したりするようなふるまいに出てしまうのか。逆に、どれほど過酷な状況に置かれてもなお、人を思いやる気持ちを失わずにいられるのはなぜなのだろうか。
人って面白い。ここにあるように過酷な状況にあっても人を思いやれるというのに、逆に私利私欲に走ってた人を害することもある。そんな人間のつかみどころのない本質から始まる本書。その間を埋めるものがあるのかないのか。あるとしたらそれは何なのか。その研究テーマこそが本書の中心にあるように思います。
本書の内容
NVC
本書のタイトルにあるNVCってなんだろう。
その内容は実はけっこうシンプルです。Amazonの紹介文によると、以下の4つのステップ。
1. 評価をまじえず、行動を「観察」する
2. 観察したことに対して抱いている「感情」を突きとめる
3. そうした感情を生み出している要因、「何を必要としているのか」を明らかにする
4. それを具体的な行動として「要求」する
本書を読み進めると多くが、事例をもとにしたこの4ステップの再現であることに気付きます。いろんなシチュエーションはあるものの、取り上げられた人間関係の問題のほとんどはこのステップで解決しています。
このステップを見ると、そのほとんどが「問題の本質を見抜く」ことに集中しているように思われます。
たとえば、親子の対話を考えてみましょう。
親は、子どもに勉強させたいと思って、早く宿題をしなさいと言ったとします。
子どもはどう対応するかというと、嫌だとか、ぐずぐずするとか、とにかく親の主張に抵抗します。ここで大事なのは、親に抵抗はしているけれど子供は何を満たしたいのかが明確になっていない点です。
そのニーズが明確ではないけど、親の提案は受け入れられない。
これをやりあっているうちは話は堂々巡り。
だから大事なのは、お互いのニーズを明確にすることと強調されているように思います。
本当は何をどうしたいのでしょうか。
場合によっては、子どもは宿題をするのではなく、今のシチュエーションの中で何が満たされれば満足なのかを明確にしたいところ。しかし大抵の会話の中では、したくないことは明確だけど、何を満たしたいかが不明瞭。そうすると話し合いは話し合いではなくなってしまう。こういった部分に配慮することで、人と人の対立の多くは解決できるのではないか。それが本書の提案です。
少し面倒くさいというか、常に冷静にいる必要があるのと、多少の訓練は必要ですがこのNVCという手法を学ぶことで、私たちは無用な争いを避けることができるのかもしれません。
いやーーー、読書って素晴らしいですね。

ちなみに私はこんな本書いてる人です。
頂いたサポートは、日本の二代目経営者のこれからの活躍を支援するために使わせていただきます。
