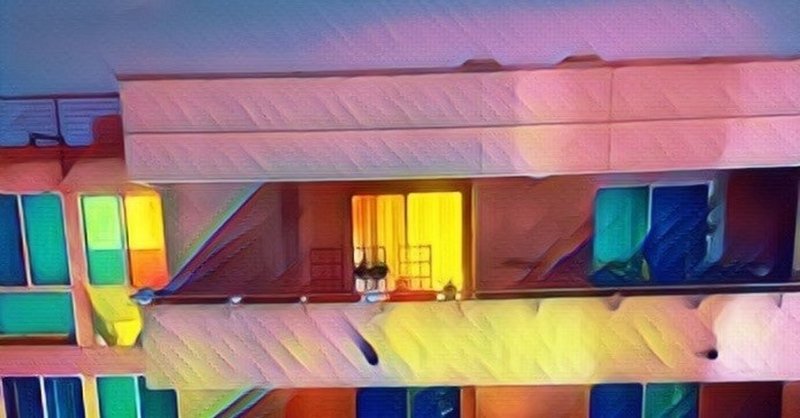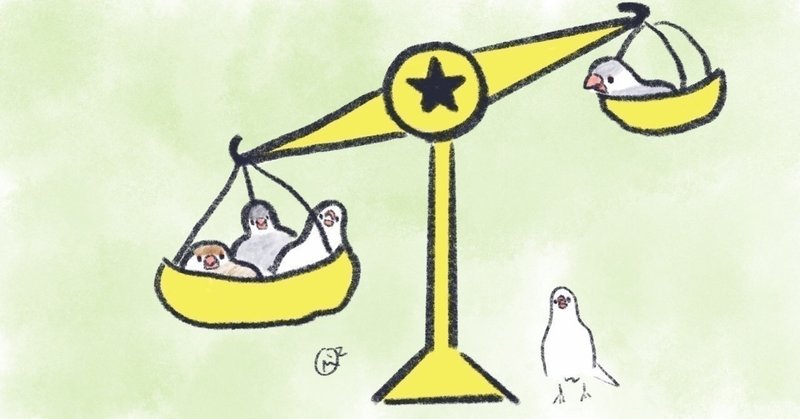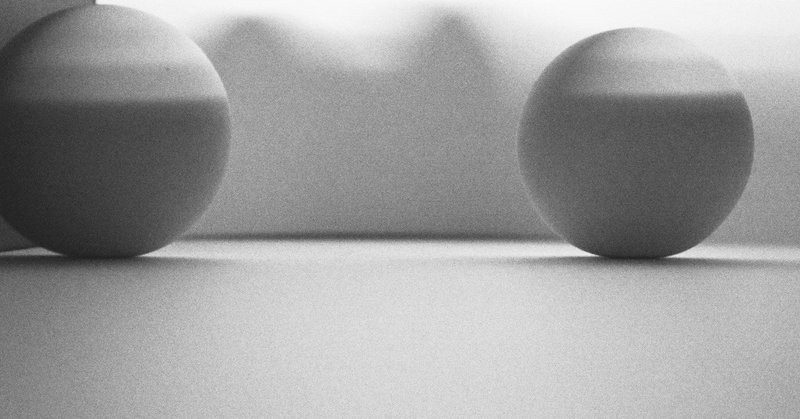記事一覧
相手に言葉を伝えるには
この文章は、自分の言葉が相手に伝わるようにしたい人に、読んでほしい。
さて普段、僕らは相手と言葉を使って、暮らしている。それは対面の会話、LINE、職場の文書、チャットなど、さまざまな場面やデバイスやツールで、使用されている。しかしながら、その内容の精度について、語られることは少ない。実際には多くの言葉が、相手に意味不明な状態で、伝わっている。
たとえば、きのうの友人とのチャットや、ネットに流
なにをつくっているのか
おはようございます。今週も書いていきます。
情報の伝達と、感情の伝達というのは異なる。最近YouTubeを編集しているなかで、そのことに気がついた。いま多くの人は情報の伝達を求めている。それは「ながら」で観られることで、すぐに分かることで、真似がしやすいことである。情報の伝達には、まず「どうやるのか」を伝える必要がある。
たとえば、この記事のタイトルを「noteの記事のPV数を増やすには」とか