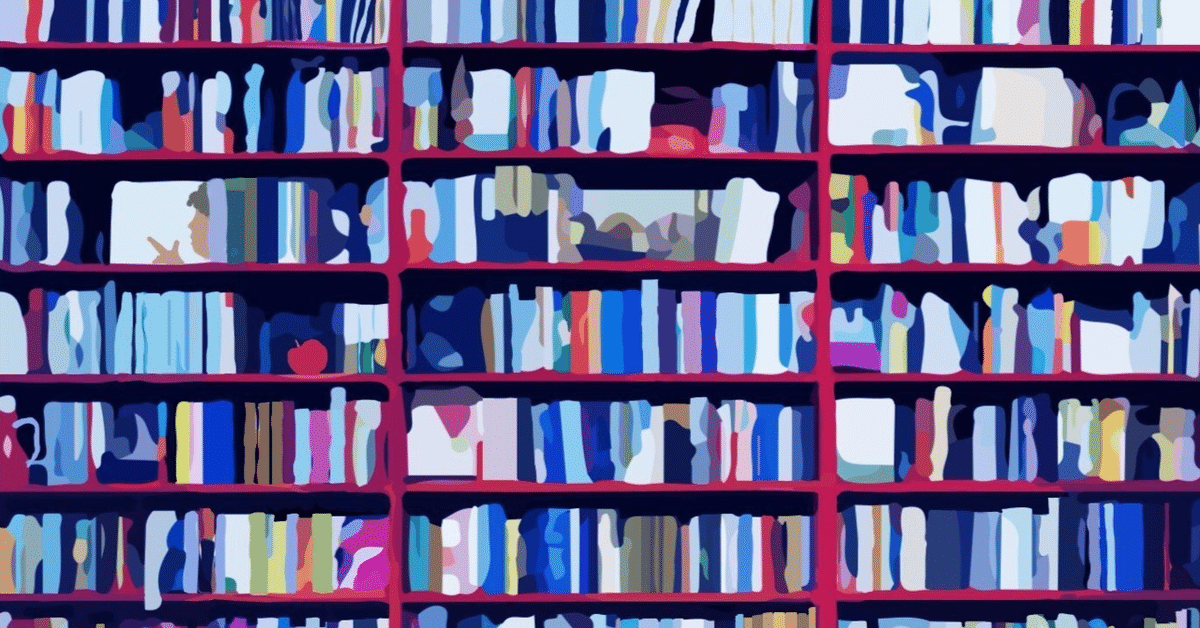
【エッセイ】言葉は本能か、それとも発明か?
話言葉は本能ではあるけれど、文字は発明である、深く考えもせず、なんとなくそう思ってきた。たとえば、漢字は中国で発明されて、日本に輸入されたという風に。文字のない文化ならいくらでもあるけれど、どれほど隔絶した集団であっても、口語コミュニケーションの全くない民族というのは考えにくい。
もっとも本能という概念を、最近は生物学でもあまり使用しないそうである。動物は学習によって行動を変えることができるけれど、それにも限界があると。ここでいう本能とは、アプリオリな能力という程の意味で考えてほしい。
言語活動は人間に元々備わった能力である。そこまでは問題ないようだ。しかし一歩進めて、たとえば「蜘蛛が糸で巣をつくる方法を知っているように、ヒトは言葉を使用する方法を知っている」と言われると、ちょっと待ってくれと言いたくなってくる。
アメリカの認知心理学者スティーブン・ピンカーは、『言語を生みだす本能』で、正にそのように主張している。たしかに、蜘蛛が糸で巣をつくるのは、元々蜘蛛に備わった能力であるからして、そういう意味では、ヒトに元々備わった言語使用の能力と同様であると言えないこともないような気がしないでもない。しかし、このようにたとえてしまうと、言葉の様々な側面(文化的、歴史的、伝統的、教育的、自己同一的……etc)が抜け落ちてしまうのではないだろうか。
ピンカーは、サピア=ウォーフ仮説などの言語的相対論に反対して、普遍的で心的な文法が存在するという立場をとっている。
言語的相対論とは、簡単に言えば、言葉が思考を限界づけているというような言語決定論である。たとえばイヌイットの言葉に雪に関するボキャブラリーが多いというような例があるし、極端な話、時間に関する単語を持たないどこかの先住民は、時間に関する概念を持たないというような馬鹿げた仮説まであったようだ。言葉がなければ思考は成立せず、思考はその言葉によって規定されているというわけである。
言語的相対論に反論してピンカーが挙げる例は、知的障害を伴わない言語障害や、言語障害を伴わない知的障害、さらにはイメージ思考などである。しかし、言語がなくても思考が成立するのは、たとえば道具を使用して課題をクリアする類人猿を見ればわかることだ。ただそのクリアした方法を言語を使って仲間に伝える術を持たないというだけである。
音声を使ってコミュニケートする動物を観察してみれば、人間の言語が本能由来で、進化的連続性があると言われても違和感はない。言語活動の根っこにあるものが文化や発明ではなく、先験的なものであるならば、あらゆる言語に通底する普遍的な文法が心的に推定されることになる。これがチョムスキーの生成文法の「原理とパラメータ理論」である。
様々な言語に共通する特徴は、単一の原言語から受け継がれてきたものではなく、又単なる影響関係にあるからでもない。そもそも本能に由来する言語は適応的なものであり、普遍的な文法が心的に存在し、それが様々な言語の統語ルールに反映する、という仮説である(もっとも、チョムスキー自身は言語を進化的獲得と見做していないようだ)。現実にヒトは言語を操っているのだから、脳の神経回路に文法モジュール(何と呼ぶかは問題だが)を想定するのは全く荒唐無稽ではない。
荒唐無稽ではないけれど、チョムスキーの生成文法は、人工的に抽出された仮構物のように見えなくもない。本能論者は、当然ながら諸言語間の差異にではなく、構造に目がゆくようだ。統語ルールによって無限に文を生み出せることに着目する。しかし、ルールは変化する。どの国語にも歴史があり、その変化をある程度は辿ることができる。同じような意味でinstinctに歴史があると言えるだろうか。
たとえば、食欲はinstinctであるが、料理は文化といえる。言葉の使用はヒトに固有の能力であり、さらに歴史・伝統的に独自の文化となり得る。これをinstinctと表現して良いものなのか。
ワグ・テストという例を、ピンカーは挙げている。「wag(意味のない言葉)が一つあります。今度は二つあります。これは二つの……」と子どもに語りかけると、決まって彼らはwagsと答えるというのだ。この実験から、名詞の複数形にはsを付けるという心的ルールがあると結論づけるのである。しかし、同じ実験を日本の子どもにしてみれば、名詞の複数形にsを付けるのは、文化的慣習的なルールであって、生得的なものではないことがわかるであろう。いや、実験するまでもない。
更に言うと、文に主語があり、動詞があり、目的語があるからといって、文法モジュールが脳にあるというわけにもいかない。ヒトに特有の認知の仕組みを反映しているだけかもしれないからである。
ところで、本書にはウォーターゲート事件で失脚したニクソンが、無罪証明のため提出したホワイトハウスでの録音テープの会話内容が長々と引用されている。これが第三者からしたら支離滅裂で意味不明なのである。それはつまり、文法ルールを無視して喋っているからだが、同じ状況にあって共通の話題で互いに意味を補い合うから、会話が成立しているのである。実はこれは、著者の主張に反して、明確な統語ルールに縛られずに言語コミュニケーションが成立する例と言えるのではないのだろうか。ひょっとすると厳密な文法は、生得的なものではなく、文字の発明と共に生まれたのでないのか、などと妄想が膨らむ。仮にそうなら、文字を持たない文化の口語コミュニケーションは、比較的ゆるやかな統語ルールしか持たないということになるだろう。
たとえば、
「ハンパねえな」
「パネえ、パネえ」
とか、
「うちら、マジやばくね?」
「やべえ、やべえ」
とか、
「いい人って、いいね」
「うん、いいね」
など。
チョムスキーの生成文法の批判者として有名なのが、マイケル・トマセロである。
トマセロは、遺伝子が99%一致しているヒト(言葉あり)とチンパンジー(言葉なし)の認知の根本的な差異を実験から読み取ってゆく。煩雑になるのでここでは詳細に取り上げてないが(というか、あまり覚えていない)、先ずこの認知力の差異により言語の使用が可能になると主張する。
この遺伝に基づく適応としての認知力(系統発生)、次に言語や文化の伝承・改変(歴史)、最後に受け継がれてきた歴史的文化環境での学習(個別発生)、以上の三段階で言語を分析することになる。比較してみると、ピンカーのような言語本能説が、一般向けの本であっても、いかにも素朴なものに見えてくる。言語を媒介とするものを含めて様々なコミュニケーションへの欲求は、生得的と言えるかもしれないが。
ヒトの子の模倣は目的と手段を分けて考えた上での行為であり、文字どおり猿真似ではない。周囲に言葉を話す人がいなければ、子が言語を学習することができないのは、模倣学習してコミュニケーションをとる相手がいないからであろう。そういう意味で、言語活動は食や睡眠と同列の本能とは言えない。
子どもの言語学習の発達段階でも、普遍的な文法は想定されないという。動詞の島仮説といって、新しい動詞を学習する度に異なる表現を覚えるが、最初のうちはその背後にある統語ルールを意識しているわけではなく、動詞それぞれは島のように隔たって関連づけられていない(たしかこんな説だったような……)。
子どもは先験的に存在している文法を再発明している(ピンカー)のではなく、先ず繰り返しや固まりとして言葉を覚え、それによって逆に世界をカテゴリー化・スキーマ化することが可能になるというのである。これは言語的相対論の立場に近いと言えるかもしれない。
幼児が「Let-me-see-it!」(み・せ・て!)と言うとき、letは使役動詞で、meとitは目的格……などと理解しているわけでないのは当たり前である。模倣学習の結果、脳内でコーパスをつくりあげて、シンプルな決まり文句を状況に適用していると考えられる。
私の考え(無責任な憶測)を述べると、コミュニケーションへの欲求は本能と言えるし、シンプルな音声を媒介としたコミュニケーションは生得的であろう。しかし、心的な統語ルールが先験的に存在するとは言えない。諸語の文法に見られる基本的な一致点は、普遍的なヒトの認知能力に基づくものであり、それにより翻訳可能性が成り立つ。しかし、それは常にその不可能性と表裏一体である。なぜなら、言語には歴史や文化があるからである。厳密な統語ルールは、文字の発明と共に生まれた。
だから、言葉は本能か、発明かというような単純な二項対立的な捉え方は、あまり意味がないような気がするのである。
(了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
