
【中国の思想と文化】「明哲保身」~中国古代知識人の処世術
要旨
「明哲保身」の語は、『詩経』の詩篇に由来し、「事理に明るく知恵の優れた者が、身に危難の及ぶ事態を避けて賢く行動すること」をいう。元来は、君主を輔佐して国を治める臣下の賢明な身の処し方を称える言葉であった。
儒家思想においては、『中庸』の章句中に引かれ、知識人が、世の状況を見極めて、出処進退を正しく判断する処世態度として重んじられた。
一方、道家思想においても、老子の「曲全」「知足」、荘子の「無用の用」などと志向を同じくするものであり、「明哲保身」は、儒道を問わず、中国古代の知識人が標榜する処世術の典型であった。
のちに、無原則に利己的に保身を図るという貶義の用例も見られるようになり、褒貶相俟って用いられるようになる。
明・王心斎の「明哲保身論」は、陽明学の立場から「保身」をすべてに優先させる哲学として注目に値する。
また、「明哲保身」は「狂」の思想とも関連する。険難な政治環境の下、歴史上多くの知識人が難を逃れるために「狂」を演じており、古代から近代に至るまで「明哲保身」の精神が、中国の政治風土に深く根付いていることを示している。
はじめに
「明哲保身」の語は、『漢語大詞典』の語釈に、その原義として、「明智的人不參與可能給自己帶來危險的事」とある。
優れた知恵を持つ人間は、我が身に危険をもたらす可能性がある事柄には関与しない、という意味である。
派生義として、「生怕有損於自己、回避原則闘爭的處世態度」とある。
我が身に損失を被ることを恐れ、原則上の争い(政治理念や思想的立場などをめぐる衝突や抗争)を避ける処世態度をいう。
従来は、知恵のある人間の行動規範として、好ましい意味に用いていた。しかし、今日では、我が身の安全のみを考える、損をしないように要領よく立ち回る、という利己的、功利的な保身の処世術として、好ましくない語気を帯びて用いられることが多い。
「明哲保身」という四字成語は、『詩経』に由来するものであり、元来、儒家思想において、君主を輔佐して世を治めるに足る賢哲の徳を称える言葉であった。
また、儒家のみならず、道家系の思想においてしばしば説かれる「曲全」「知足」「柔順」「韜晦」などの概念とも志向が合致するものであった。
「明哲保身」は、思想の流派を問わず、古代の知識人の間で、最も賢明な生き方として標榜されてきた処世術を表す言葉なのである。
一 儒家における「明哲保身」
「明哲保身」は、『詩経』大雅「烝民」篇に見える詩句に由来する言葉である。
肅肅王命 粛粛たる王命
仲山甫將之 仲山甫 之を将(おこな)う
邦國若否 邦国 若(したが)うや否や
仲山甫明之 仲山甫 之を明らかにす
旣明且哲 既に明にして且つ哲
以保其身 以て其の身を保つ
夙夜匪解 夙夜(しゅくや) 解(おこた)るに匪(あら)ず
以事一人 以て一人に事(つか)う
樊侯の仲山甫は、周の宣王をよく輔佐し、王命を正しく執り行い、諸侯の国々によく対処したとされる。尹吉甫が、そのことを讃えて仲山甫に贈ったという詩篇が、これである。
篇中の二句「旣明且哲、以保其身」は、仲山甫が「明」(物事の判断に明るいこと)である上に、かつ「哲」(知恵が優れていること)であり、それゆえに、自らの身を無事安泰に保ったことを褒め称えるものであり、これを四文字に縮めたものが「明哲保身」である。

この言葉は、『中庸』に引用されたことによって、後世、儒家の説く処世の法として広く知られるようになる。
君子の心得を述べた『中庸』第二十七章の中に、次のようにある。
君子は徳性を尊びて問学に道(よ)り、広大を致して精微を尽くし、高明を極めて中庸に道り、故きを温めて新しきを知り、厚きを敦(あつ)くして以て礼を崇(たっと)ぶ。
是の故に上に居りて驕らず、下と為りて倍(そむ)かず。国に道有れば、其の言、以て興るに足り、国に道無ければ、其の默、以て容るるに足る。
詩に曰く、「既に明らかにして且つ哲、以て其の身を保つ」とは、其れ此の謂(いい)か。
国に正しい道が行われていれば、賢明なる言説を尽くして政治に従事し、国に道が行われていなければ、沈黙を守って自己の身を全うする。そうした生き方を「明哲保身」として標榜している。
同じ主旨の言説は、孔子の教えにもあり、『論語』「泰伯」篇に、
危邦には入らず、乱邦には居らず。天下に道有れば則ち見(あら)われ、道無ければ則ち隠る。
邦に道有るに、貧しくして且つ賤しきは恥なり。邦に道無きに、富みて且つ貴きは恥なり。
とある。また「衛霊公」篇にも、
直なるかな史魚、邦に道有れば矢の如く、邦に道無きも矢の如し。
君子なるかな蘧伯玉、邦に道有れば則ち仕え、邦に道無ければ則ち巻きて之を懐にすべし。
とあり、孔子は史魚と蘧伯玉を並べて、双方共に褒め称えながらも、矢の如く真っ直ぐな史魚に比べて、出処進退に融通を効かすことのできる、つまり「明哲保身」を心得ている蘧伯玉の方をより高く評価している。

また、『孟子』「尽心上」にも、次のような一節がある。
古の人は志を得れば、沢、民に加わり、志を得ざれば、身を修めて世に見(あら)わる。窮すれば則ち独り其の身を善くし、達すれば則ち兼ねて天下を善くす。
志を得て立身出世すれば天下の政治に携わり、志を得ずに困窮すれば独り我が身を正しく保つこと、それが古の賢者の生き方であるとしている。

これらの言葉から窺えるのは、世の中が正しければ出て仕える、そうでなければ隠れて自己修養に努める、という儒家の処世観である。
これは、風見鶏の如く定見を持たない無節操な言動をいうものではない。世の中の状況を見極める判断力と、それに従って臨機応変に出処進退を切り替える行動力をいうものであり、真の賢明さを示す人徳の一つとされるものである。
二 道家における「明哲保身」
「明哲保身」は、儒家の経典を語源とする言葉であるが、また災禍を避けてしなやかに生きることを良しとする道家的志向に合致した言葉でもある。
『老子』に披瀝されている処世観は、生命を維持すること自体が困難な時代において、なにはともあれ生きながらえることに最大の価値を置いたものであった。
儒家においては、最高の徳目である「仁」「義」を貫くためには、生命の犠牲さえも厭わないとしている。『論語』「衛霊公」篇に、
志士仁人は、生を求めて以て仁を害する無く、身を殺して以て仁を成す有り。
とあり、『孟子』「告子上」にも、次のようにある。
魚は我が欲する所なり、熊掌も亦た我が欲する所なり。二者兼ぬるを得べからずんば、魚を舎(す)てて熊掌を取る者なり。
生も亦た我が欲する所なり、義も亦た我が欲する所なり。二者兼ぬるを得べからずんば、生を舎てて義を取る者なり。
これは「明哲保身」を説く姿勢とは矛盾するものである。「仁」と「義」が、決して譲れない徳目であることを示すレトリックとして誇張している面もあろうが、少なくとも、文言通りに解すれば、「仁」と「義」を「生」や「身」に優先させている。
こうした考え方は、道家思想にはまったくない。『老子』第二十二章に、
曲ぐれば則ち全く、枉(ま)ぐれば則ち直し。
とあるように、道家は、柔軟に己を曲げて身を全うすることを説き、教義や理念を生命に優先させることはない。
また、第四十四章に、
名と身と孰(いず)れか親しき。身と貨と孰れか多(まさ)る。
とあるように、儒家が重んじる名声や、世俗が追い求める財貨を無意味で有害なものとして退け、自分の身を安泰に保つことこそが何よりも大切であるとしている。
そして、「明哲保身」の生き方として、老子が具体的に唱えたものが、「知足」と「寡欲」であった。同じく第四十四章に、
足るを知れば辱められず、止まるを知れば殆うからず、以て長久なるべし。
とあり、また第四十六章に、次のようにある。
罪は欲すべきより大なるは莫く、禍は足るを知らざるより大なるは莫く、咎(とが)は得んと欲するより大なるは莫し。
老子が欲望を否定し、知足を唱えるのは、一にも二にも身の安全のためであり、その究極の目的は、天寿を全うすることにほかならない。
このように、危うい状況を避けて老獪に立ち回り、物に執着することなく恬淡として生きながらえるのが、老子流の「明哲保身」なのである。

また、『荘子』の中では、「役に立たないために木樵に伐られず、巨大に成長した神木の話」や「不具のため徴兵や労役を免れて、天寿を全うした支離疏の話」など、さまざまな喩えを駆使して、繰り返し「無用の用」が説かれている。
危難を避けて身を保全することを第一とする意味において、これもやはり「明哲保身」の志向を示すものである。

『楚辞』の「漁父」篇は、従来屈原の作とされてきたが、実際には、後世の道家系の思想を持つ者の手によるものである。
楚の朝廷から放逐され、世の混濁と自らの清廉を訴える屈原に対して、漁師がこう語りかける。
聖人は物に凝滞せずして、能く世と推移す。世人皆濁らば、何ぞ其の泥を淈(にご)して、其の波を揚げざる。衆人皆酔わば、何ぞ其の糟を餔(くら)いて、其の釃を歠(すす)らざる。
世俗の塵埃にまみれることを潔しとしない屈原をあとに残し、漁師は莞爾として笑い、次のように歌いながら去って行く。
滄浪の水清(す)まば、以て吾が纓を濯うべし。滄浪の水濁らば、以て吾が足を濯うべし。
両者の対話を通して、屈原と漁師の処世観の違いが浮き彫りにされる。
物に拘泥しない漁師の言辞は、老荘的な「明哲保身」の思想を最も文学的に体現したものと言ってよいであろう。
三 褒義から貶義へ
「明哲保身」は、儒家的見地からも、道家的見地からも、古代中国知識人の賢い生き方の典型であった。
歴代の文献から「明哲保身」の用例をいくつか拾ってみよう。
北宋・司馬光は、『資治通鑑』「漢紀」高帝五年の論讃の中で、漢の高祖劉邦に仕えた功臣について、次のように述べている。
夫れ功名の際は、人臣の処し難き所なり。高帝の称する所の如き者は、三傑のみ。
淮陰は誅夷せられ、蕭何は獄に繋(つな)がる、盛満を履(ふ)みて止まざるを以てに非ずや。
故に子房は神仙に托し、人間(じんかん)を遺棄し、功名を外物に等しくし、栄利を置きて顧みず、所謂明哲にして身を保つ者は、子房有り。
「漢初三傑」と並び称される張良・蕭何・韓信ら三人の功臣の中で、とりわけ張良が「三傑之首」として尊ばれるのは、「功成りて身退く」を実践した彼の「明哲保身」のゆえにほかならない。

「明哲保身」は、中国歴代の賢臣に与えられる賛辞であり、その経歴においてこれを欠いて禍を招いた者は、歴史的評価もまた引き下げられてきたのである。
唐・白居易の「杜佑致仕制」(『白氏文集』巻三十八)に、
尽悴して国に事(つか)え、明哲にして身を保ち、進退始終、其の道を失わず。自ずから賢達に非ざれば、孰か能く之を兼ねん。
とあり、また、北宋・欧陽脩の「晏元獻公輓辭」(其三)に、
富貴優游五十年 富貴 優游すること 五十年
始終明哲保身全 始終 明哲にして 身を保つこと全し
とあるように、「明哲保身」は、政界において賢明な身の処し方を実践した者を褒め称える常套句であった。
このように、元来は褒義で用いられていた「明哲保身」の語が、いつの頃から貶義で用いられるようになったのか、その時期を特定することは困難であるが、『詩集傳』で「保身」の語に記した朱熹の注に、次のようにいう。
保身は、蓋し理に順(したが)い以て身を守るなり。利に趨(おもむ)き害を避け、偸(ぬす)みて以て躯(み)を全うするの謂に非ざるなり。
ここでは、「保身」とは、利害損得に従って行動し、無節操に身を保全するという意味ではない、としている。貶義ではないことをことさら注として記す必要があったということは、逆に言えば、当時(宋代)、すでに慣用としては貶義で用いられていたことを物語るものである。
近現代に至ると、「明哲保身」は、利己的に我が身を優先させる、節義を欠いた生き方、という否定的な含意で用いられる場合が多くなる。
林語堂が「中国的国民性」と題する文章の中で、中国人が伝統的にあえて国事を語ろうとしない体質を論じて、
要中国人民變散慢爲團結、化消極爲積極、必先改此明哲保身的態度。
(中国の人民を締まりのないさまから団結させ、消極的から積極的に志向を変えさせるには、まずこの明哲保身の態度を改めなくてはならない。)
と語り、また、毛沢東が「反對自由主義」(『毛澤東選集』巻2所収)の中で、自由主義に内在する無原則な態度について、
事不關己、高高挂起。明知不對、少說爲佳。明哲保身、但求無過。
(自分と関わりのないことには全く無関心で、明らかに誤りと知っても発言を控え、明哲保身にして、ただ過ちを犯さないよう努める。)
と痛罵しているように、「明哲保身」は、世の事に関わろうとしない消極的な姿勢、過ちを犯さなければそれで良しとする事なかれ主義的な態度を専ら指すようになった。
次第に、賢さは、小賢しさや狡賢さを意味するようになり、四字句の意義は、「明哲」よりも「保身」の方に重点が置かれるようになった。
四 王心斎の「明哲保身論」
「明哲保身」の語は、こうして褒義と貶義の二面性を伴いながら、古来、知識人の処世態度を示す言葉として、しばしば詩詞文章に引用されてきた。
その中で、「明哲保身」を自らの思想の中核をなす概念の一つとして取り上げ、正面から論じた文章として注目に値するのが、明代の思想家、王心斎の「明哲保身論」である。
王心斎は、明代後期、王陽明の門下で致良知説を継承し、のちに泰州学派を形成して活躍した人物である。
王心斎の思想を特徴付ける学説の一つに「身本論」がある。これは、経世の学を唱える儒家がつねに抱える出処進退の問題を巡って展開された独自の処世哲学である。
「明哲保身論」と題する文章の冒頭に次のように言う。
明哲とは、良知なり。明哲保身とは、良知良能なり。所謂慮らずして知り、学ばずして能くする者なり。人皆之有り、聖人と我と同じきなり。
身を保つを知る者は、則ち必ず身を愛すること宝の如し。能く身を愛すれば、則ち敢えて人を愛さざることあらず。能く人を愛すれば、則ち人必ず我を愛す。人我を愛すれば、則ち吾が身は保たれり。
ここでは、「明哲保身」が、陽明学の基幹となる概念である「良知良能」と同じものであると説き起こす。そして、「保身」が自己と他者の間の双方向的な敬愛に繋がり、結局は自己の「保身」を担保することになる、という循環的な人間社会の法則を説いている。
そして、さらに論を展開し、「保身」はそのまま「仁」であり「万物一体之道」であり、忠孝の道を行い、天下国家を治める上での基盤であるとしている。
我が身が保たれてはじめて一家を保ち、一国を保ち、天下を平らかにするという論旨であり、儒家の理念である「修身・斉家・治国・平天下」を実践する上での必要前提条件として「保身」を据えている。
当時、陽明学左派の泰州学派は、反封建的な急進思想であったため、しばしば朝廷から弾圧を受けており、官途にある同門の士たちが、罪を得て死を賜ったり、流刑に処されたりしていた。
「明哲保身論」の背景には、そうした不条理な犠牲を強いられていた同志たちに対する王心斎の思いがあったことも考え合わせなくてはならない。
五 「明哲保身」と「佯狂」
中国の政治的環境の下では、多くの場合は役人である知識人たちが、平穏無事に生涯を終えること自体が、古来、そもそも極めて難しい。
それこそが「明哲保身」が臣下たる者の徳として称揚された所以であるが、その「明哲保身」を貫くために、彼らがしばしば採った方策が「佯狂」であった。
「佯狂」とは、狂気を装うこと、病理学的な意味での狂気を持たない者があたかもそうであるかのように偽装することをいう。
官界に身を置く者が困難な状況に陥った際に、韜晦的な所作によって難を逃れる方策であるが、命に関わる危急の事態においては、それを回避するための最終手段である。
中国の精神文化史の上で、「佯狂」の系譜の最初に位置するのが、箕子と接輿である。
孔子は、殷王朝の末、紂王の暴政下にあって、それぞれ異なる道を選んだ微子・箕子・比干らを「三仁」と称えた。
この三人の仁者について、『史記』「殷本紀」は、こう記している。
紂愈々(いよいよ)淫乱して止まず。微子数々(しばしば)諫むれども聴かず、乃ち太師・少師と謀り、遂に去る。
比干曰く、「人臣為る者は、死を以て争わざるを得ず」と。廼(すなわ)ち紂を強諫す。紂怒りて曰く、「吾聞く、聖人の心(むね)には七竅有り」と。比干を剖(さ)きて其の心を観る。
箕子懼れ、乃ち狂を詳(いつわ)りて奴と為る。
微子は、王の暴虐無道を何度も諫めたが、聞き入れられず、国外へ亡命した。比干は、自らの命を賭して王を強く諫めた結果、王の怒りを買い、ついに胸を割かれて死んだ。そして箕子は、比干の末路を見るや、髪を振り乱して狂人の真似をし、奴隷となって身を隠したという。
一方、接輿は、春秋時代の楚の人で、乱世を避けて狂人の如く振る舞っていた隠者である。『論語』「微子」篇に、次のような逸話がある。
楚の狂接輿、歌いて孔子を過ぎて曰く、「鳳よ鳳よ、何ぞ徳の衰えたる。往く者は諫むべからず、来る者は猶お追うべし。已(や)みなん、已みなん、今の政に従う者は殆し」と。孔子下り、之と言わんと欲す。趨(はし)りて之を辟(さ)け、之と言うを得ず。
乱世に道を説いて回る孔子の前を歌いながら通り過ぎ、今の世の中で政治に関わるのは危ないことだと諭している。
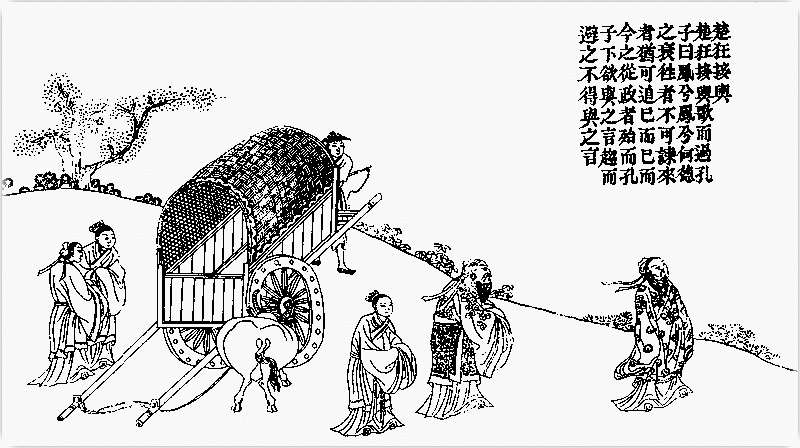
狂人を装って世を避ける、という箕子や接輿の生き方は、乱世における「明哲保身」の処世術にほかならない。
世の大勢に逆らわず、賢明に物事を処理して我が身を災禍から守る、という生き方は、古来、政治に携わる者がしばしば選んだ道であった。
中国人の伝統的な処世観からすると、こうした生き方は、時勢を顧みず、頑なに自己の主張を貫く生き方よりも、高く評価される傾向にある。古来、比干よりも箕子の方が、多く称賛を得ている所以である。
『論語』「公冶長」篇では、孔子が衛国の大夫甯武子について、
甯武子は邦に道有れば則ち知、邦に道無ければ則ち愚。
其の知は及ぶべきも、其の愚は及ぶべからざるなり。
と語り、乱世においては「愚」を装う「明哲保身」の生き方を讃えている。
甯武子の「愚」については、漢・荀悦「王商論」の中で、接輿の「狂」と並べて、次のように言及されている。
口を閉ざすとも誹謗を獲る、況や敢て直言するをや。身を隠し深く蔵ると雖も、猶お免るを得ず。
是を以て甯武子は愚を佯り、接輿は狂と為る。困の至りなり。
黙って身を隠しても禍が及ぶ世にあっては、「狂」や「愚」を装うほかはない。そうした窮極の選択が、危難を逃れるための典型的な方策として継承されていったのである。
中国の歴史の中で、とりわけ魏晋や明末清初など、政情の不安定な動乱の時期において、知識人たちは、自らの身を守るために、しばしば「佯狂」を演じてきた。
例えば、魏の阮籍は、反礼教的な韜晦の処世態度を物語る逸話が多いが、彼の奇行や狂態は、「佯狂」によって政治の風波を避けるカモフラージュでもあった。

「狂」は、時として免罪符のような効力を発揮することがある。
元来、「狂」は疾病の一種であり、これを患う者は、通常の人間社会の枠から弾き出される。そして、それによって、正常な人間に適用される倫理的準則や法的罰則が適用されなくなるのである。
「佯狂」は、決して消極的な生き方ではなく、険難な時代を生き抜くために、知識人たちが経験的に学び得た知恵である。
理念や道義を振りかざしてぽっきり折れてしまうよりも、風に靡いて逆らわず、「狂」であれ「愚」であれ、そう呼ばれることで身を保つことができるのであれば、その方が賢いとする考え方である。
おわりに
「明哲保身」は、古代中国の大地に生きた知識人たちが培ってきた、骨太で、したたかな、頗る大陸的な精神文化を投影させた言葉である。
中国の知識人が「明哲保身」を処世の指針としたのは、古い時代に限ったことではない。
近くに例をとれば、文化大革命を背景とした映画『芙蓉鎮』(1987年)に登場した秦書田の生き方は、まさに伝統的な「佯狂」による「明哲保身」の生き方であった。
秦書田は、町で唯一の知識人でありながら「瘋癲」として描かれている。彼の一見愚かしい言動は、乱世を生き延びるための知恵にほかならない。
狂気の時代を生き抜くために、「狂」を装い、「愚」を演じ、政治の嵐が過ぎ去るのを待つことを選択したのである。

天寿を全うすることに最大の価値を置くとすれば、無用であるがゆえに生き延びた者は、その無用性こそが真の有用性ということになる。
とにかく死なずに生き抜くことが何よりも大事という「生」に対する執着の強さは、中国の民族性において際立った特質である。
儒家は、現世のみを問題にする倫理道徳思想であり、死後のことは語らない。不老長生を説く道教は、いわば現世を永遠に引き延ばそうという発想であるから、「生」に対する執着の度合いで言えば、その最たるものである。
「生」を全うすることができさえすれば、あとはなりふり構わず、虐げられても、辱められても、死なずに済めばよい、というのであるから、極めて単純明快な哲学なのである。
古来、中国において「明哲保身」が重んじられてきたのも、根源的には、こうした「生」に対する執着の強さに由来するものであるように思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
