
出版企画書と言うものを提出してみました。
1 原稿を読もうとしない出版社はカスだ
noteに投稿されるユーザーは、自らの著作の書籍化意欲が高いと聞いております。
私も幼少の頃より作家になるのが夢だったので、はてなブログで書いた著作が同ブログの製本サービスで完成度の高い書籍として送ってこられた時は、何とか巷に販売したいと望んだものです。
まずは、ネット上でよく広告が出ている書籍化を支援する出版社にアプローチをかけました。しかしどの出版社も、私の原稿を全く読まないで、「自費出版」を進めるばかりで、その手数料を取りたがるクソ出版社ばかりでした。
皆さんご存知でしょうか?大ヒットする曲と言うものは、作詞家や作曲家、そして歌手だけでは成り立ちません。その間には「編曲者」と言う立役者が存在するのです。
私のようなど素人の書いた文章は、いかに内容が優れていたとしても、てにをはがおかしかったり、日本語が成り立っていなかったり、漢字が間違っていたり、他人の言葉を勝手に引用していたり、様々なハードルを乗り越えなければならないのです。これらの審査をしてくれるのがプロの編集者と言うものです。
皆さんもたくさんのブロガーの作品を読んでいて経験したことがるでしょう。言っていることはとても立派なのに、小骨が刺さるような日本語の誤りを。
どんなに素晴らしいアイディアもどんなに面白いストーリーも、プロの編集者が居て初めて良い作品になるのです。それなくして、たまたま売れたとしても、それはガキの落書きです。
それを、原稿を全く見ずに、とりあえず、「電子書籍の広告サイトに掲載させておきましょう。」と言って、掲載料をふんだくる連中は、出版社として恥を知るべきです。
確かに、市井のブログに比べれば、チャンスは広がるでしょうが、私が欲するのは、自分の作品の正当な評価と、的確なアドバイスです。
2 出版企画書
そんなこんなで、無駄な時間と労力を費やしていたところ、ある大手の編集者から耳よりの情報を入手しました。
「こういう場合は、本の「奥付け」(最終頁や裏表紙)に書いてある出版社所在地宛に「出版企画書」と言うものを送って、審査を受けるのが、正式な手続きである。この審査を受けなければ、出版社の編集者は決して本文を読む事はない」と言うのです。
私は、嘘っぱちの出版社にたくさんの原稿を送らされたが、結局奴らは何も読んでいなかったのだということです。
私は急いで、方向転換し、出版企画書の作成に乗り出しました。
しかし、残念ながら、この時期、私はとある事情で、自己主張を抑える薬を飲み始めていました。このため、著しく表現力や文章力が低下してきていました。そんな中で、何とかまとめたのが、以下の「出版企画書」です。
一応一通りの体裁は勉強しましたが、上記の都合で、文章には、あまり自信はありません。しかし、体裁としては、後任の役に立てるものを作れたと自負しております。
これから、出版企画書の作成に挑戦する方は、是非参考にしてください。
なお、めちゃくちゃ長いようにみえますが、これが標準です。
1 書籍タイトル
説難 (下線=作品冒頭にリンクしています)
2 コンセプト(主目的)
「説難」は、古代中国の思想家、韓非子の言葉で、「いかなる良いアイディアも、それを実現する主権者つまり君主に説くことの方が最も難しい」という意味です。
民主国家における主権者は、有権者である私たちであり、それが故に、私たちには、意識していなければならない問題や、備えていなければならない見識が多々有ります。
しかし、これらを有権者に説くことの難しさについて、政治家の地を這うような活動やマスメディアの創意工夫の軌跡を辿ると感涙する思いです。
本作品は、この課題に対し、ブログとういうツールの特性を活かして、これまで有権者が対峙し得なかった問題や見識に対して、むしろ貪るような興味と好奇心を創出することを目論むものです。
3 企画(主戦略)
⑴ 無秩序な展開で主題に正対させない
読者と著書との不幸の始まりは、主題との早すぎる正対です。まず本棚の表題と読者の興味、何とか手にしても、序盤で起こる著者の主張との残念な不整合。頑張って奥に読み進めば、共感や感動、人生を変える出会いも有ったかもしれないのに。
これに対し、多くのブログは、一話完結で連続性は無く、無秩序・無責任の記事の集合体であり、通常、主題や主張は存在しません。読者は、例え一つのブログに手をかけたとしても、一つの本屋で気に入った記事を探索しているだけのことが多いです。
本作品には、主題もストーリーも存在します。しかし、このブログの特性を活かすべく、後述の計画詳細で示すとおり、記事を細分化し、一見、無秩序・無責任に配信することにより、読者と主題との正対を遅らせ、私の本屋の滞在期間を延ばします。
⑵ 読者の知的好奇心を掻き立てる
こちらの本屋でしばらく立ち読みを続けてもらっていても良いのですが、今度はこの本屋から出られなくする戦略が必要になります。
それが好奇心を掻き立てる記事の提供です。それも、「知的」好奇心です。
多くの情報発信者は、話題を分かりやすく説明しようとしたり、わかりやすいもののように見せかけたりしようとしますが、私は、むしろ「攻め」に転じます。
大衆は意外に、少し難しいくらいの方が好奇心を掻き立てられると考えます。そこで、ギリギリ聞いたことは有る程度のやや高レベルな記事を紛れ込ませます。
さらに後述しますが、ここでも、一話完結と言うブログの特性を生かして、単純なおもしろ記事・豆知識の混ぜ込みでない手法を取ります。
4 企画詳細(戦術)
⑴ テーマ・・・三つのテーマを設定します。
イ 中国の思想家韓非子を紹介します。韓非子を知っているという方も、 誤解を持っている方が多いので、その誤解を解きたいと考えています。
ロ 主権の在り方。特に、民主主義国家における主権の本質と義務等を説き、最終的には、「良き有権者を育てる」ことを目的とします。
ハ 世界平和について、現在の感情的な訴えではなく、科学的な解析からアプローチする「平和学」の創設を訴えます。
いずれも、のけぞるようなテーマで、常人であれば距離を置くところでしょうが、コンセプトは「説難」。この難解な主張をいかに有権者に届けることができるかなのです。
つまり、ここからが、私の作品のアピールポイントです。
⑵ 戦術1・・・カオスの中の旋律
本作品は、無秩序無責任な記事の羅列でありながら、上記のようなテーマが設けられており、それらは、それぞれ、例えば、最初は、稚拙な思い付きが徐々に醸成され、最終的に成熟した提言にまとめられて行くといったストーリーを持ちます。
しかし、何度も言うようにこれを悟られないように、敢えて秩序を乱しつつも、小さなシリーズが盛り込まれていたり、布石と回収が差し込んであったりして、ランダムな配信のようで、結構有機的に結びついています。
私はこれを「曼荼羅」と名付けて、実はExcelで管理しています。
そして、一見無関係に見える三つのテーマを含め、複数の経糸が徐々に縒れて、最後には太い一本になるようなサーガの演出を心掛けています。
なお、中盤以降は、これらの仕掛けの一部を読者にも解説していきます。
カオスの中の旋律(曼荼羅)の存在を楽しんでほしいという配慮です。
⑶ 戦術2・・・旋律と無秩序の雑学
小松左京氏の「雑学おもしろ百科」に夢中になった事が有ります。
本作品でも、読者の興味を持続させるために多くの雑学を盛り込んでいます。
ただし、「雑学おもしろ百科」と違い、一本経糸を設けました。
ブログは、原則一話完結です。そこで、本作品では、一記事ごとに、関連をこじつけた芸術作品を紹介し、ミニ知識を紹介します。これが旋律(シリーズ)として意識されます。気に入った人がいたら、こっちを追い始める者も現れるでしょう。
さらに、前掲の3つの主題とは別に、まったく無関係の雑学路線を走らせますが、ここは無秩序の配信を行います。ブログと言うカオスをふんだんに活用します。
イメージとしては、定期的に表れるパンくずを追わせながら、時折、驚きと感動を与え、森の中へ引き込んでいくという作戦です。
韓非子は、その著書「韓非子55篇」で、ランダムに国策を語り、多くの興味深い説話を残し、そこから多くの故事成語が生まれています。
私は、この手法をSNSと言うツールを使い、現代用にアップデートしたわけです。
5 著者紹介(プロフィール)
ペンネーム:Kanpishi
職業はとある国家機関に勤めるしがない木端役人です。
若い頃は、就職後も夜間大学を卒業するくらいの情熱が有ったため、組織内では、合格すればエリートコース間違いなしと言われる士官学校に合格し、しばらくは幹部候補生として、特殊な育成を受けました。
「これから君たちを育成するために国家は膨大な税金をつぎ込むことになる。」の言葉に感激を受け、立派な指揮官を目指して、法学を主軸に、行政の在り方・国の在り方・国民の在り方についてはずいぶん学ばせていただきました。
当然、組織人としての処世術も十分学んだのですが、実践が苦手で、30半ばで幹部候補生の路線は辞退しました。
50前になって、今でも親交の有る当時の同期生と語り合っていて気づきました。
すでに、副署長クラスにもなろうかという彼らと、未だ部下一人居ない私が、組織運営や国家のビジョンについて、高い見識で苦も無く普通に語り合っていることに。
中退したとはいえ、一応将来必要になるものは授けて頂いていたようです。
しかし、もっと気になったことは、それらの見識は、私達役人だけでなく、むしろ有権者こそが備えなければならないものだと感じたことでした。
同期の連中は、仕事に活用するのに精一杯のようだし、私の方は未活用のまま廃棄処分を待っているだけです。
私は、市立保育園以来、一貫して公立に通い、国費に育てられました。
随分国費を投じて頂いた「お高い見識」とやらを、もう少し何かの形で残せないか?そんな思いからブログを書くことになりました。
どの程度の人に届くのかわかりませんが、このままドブに捨てるよりはましでしょう。
「はてなブログ」は製本サービスが提携しているというのが魅力的でした。
著者来歴
1969年 ○○生まれ 現住○○市内
1988年 ○○行政官庁入庁
1994年 某公立大学 経済学部卒業
6 読者ターゲット
15歳~35歳
法理に基づく主権を理解した「良き有権者」を育てることが目的です。
7 著者としての販促案
1案 コンセプトの通り宣伝。「我々は知るべき事を知らず、著者はそれが「説難」がためと思うものであり、これを排し世に必要な見識の流布を目論むものである。」
2案 本作品は、電子媒体のブログと紙媒体の製本とを両方読んだとき、双方の弱点が補足され、より、その細工と曼荼羅と言うパズルを楽しむことができます。ただ、それを実現する販促案は私には浮かびません。
8 書籍体裁
「はてなブログ」提携のMybooks.jpと言う製本化サービスでサンプルを作りました。
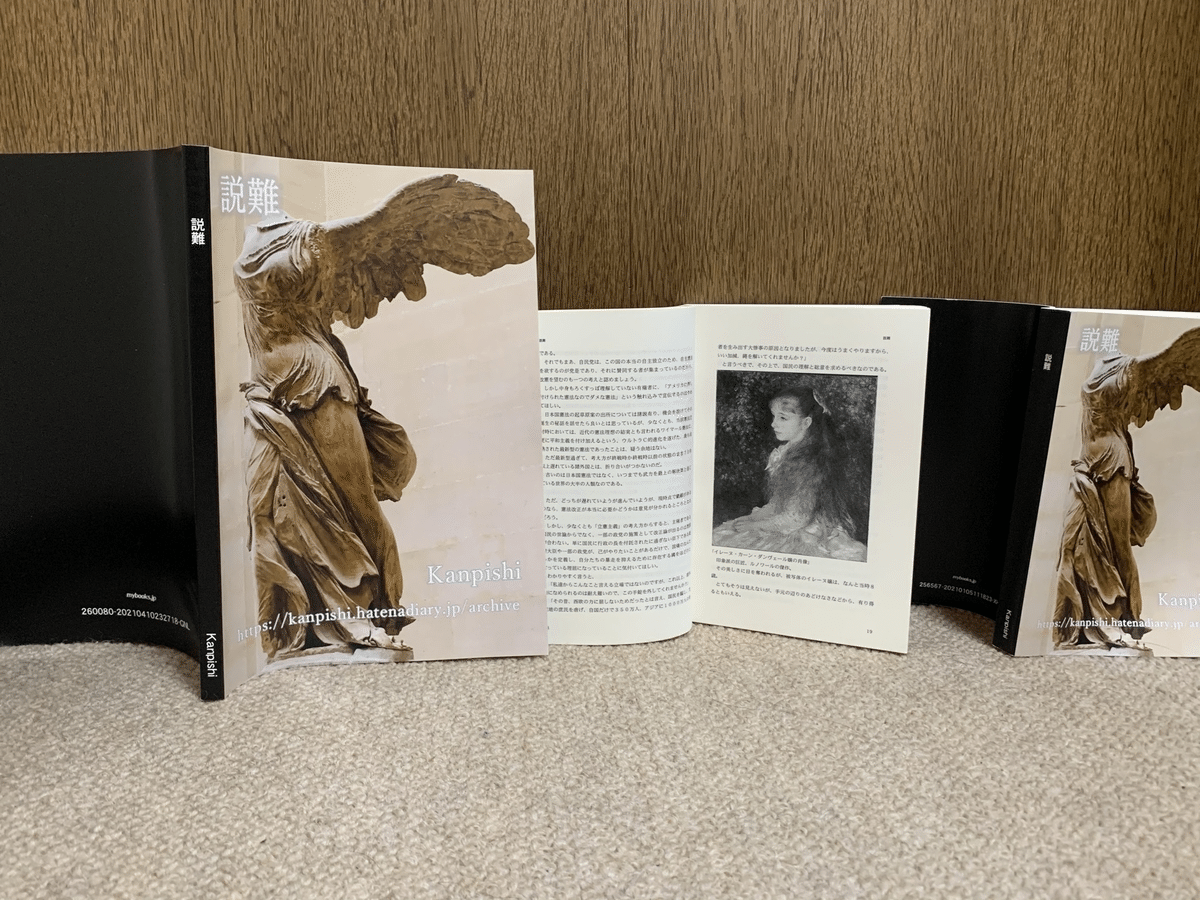
左のB5版は、普通文字で読みやすいのですが、挿絵が白黒だと不細工です。しかし、カラーにすると費用も掛かるし、さすがに本題が霞みます。
真ん中のB6版は、普通文字にすると、挿絵とのバランスが悪いです。
小文字にすると高齢者には厳しいのですが、330頁というちょうどよいサイズに収まります。字の小ささは、ターゲットを考えると、問題ないかと存じます。
9 目次・構成案 日付_ Title Page
Movement1 Inflation ←アルバムにリンクしています。以下同様。
20180101_C/2 説難 1
20180118_C/2 教育は国家百年の大計1:租税 6
20180204_C/4 想像 11
20180325_C/3 マグナ・カルタ 16
20180527_C/1 善く吏たる者は徳を樹う 21
20180603_C/2 教育は国家百年の大計2 選挙権 26
20180708_C/1 巧詐(こうさ)は拙誠に如かず 30
20180715_C/4 上杉鷹山 35
20180815_C/3 世界平和という和氏の璧 39
20180907_C/3 歴史の勝利 44
20181006_C/1 形名参同 48
20181027_C/4 複眼でモノを見る 53
Movement2 Sonata
20181111_C/3 ブレイクアウト〜非合理的な選択 58
20181126_C/4 Bravo! Ueno Park 63
20181211_C/2 教育は国家百年の大計3 自由 70
20181224_C/4 銀婚式 74
20190101_C/1 Legal mind 《法的思考》 79
20190122_C/3 ブレイクアウトⅱ~自衛という名の加害 84
20190218_C/4 情操教育 89
20190302_C/3 金持ちと喧嘩しよう 95
20190324_C/2 象徴(シンボル (symbol)) 102
20190411_C/2 教育は国家百年の大計4 勤労 107
Movement3 Metamorphose
20190526_C/4 道祖神 112
20190609_C/3 余桃を喰らわす 119
20190806_C/4 ネット長者達の黄昏 125
20190815_C/3 ブレイクアウトⅲ~命が深刻な問題でなくなる時 131
20190826_C/2 権利の行使は野卑であってはならない 136
20190901_C/4 君死にたもうことなかれ 141
20190911_C/2 寸法書を取りに戻るマヌケ 147
20191002_C/3 醜さを愛せ 152
20191015_C/2 教育は国家百年の大計5 教育 158
20191103_C/4 Bushido 163
20191124_C/2 大卒 168
20191201_C/1 三人市に虎を成す~2200年前のフェイク 175
20191216_C/4 人生万事塞翁が馬 181
20200101_C/3 平和を画するのであれば、利を用いるのが上策であり、情を用いるとあらばその涙を数えず笑顔を摘むべきである 187
20200111_C/1 良薬は口に苦し忠言は耳に逆らう 193
20200127_C/4 フェミニズムの帰結_前編《本性》 198
20200209_C/3 ブレイクダウンⅰ守られない約束 204
Movement4 Protocol
20200222_C/3 教育は国家百年の大計 最終回《平和》 209
20200305_C/1 象箸玉杯 215
20200311_C/1 合理主義 221
20200328_C/4 フェミニズムの帰結_後編《本能》 227
20200411_C/4 新型コロナウィルス 232
20200417_C/3 ブレイクダウンⅱ平和が不都合な人たち 237
20200425_C/1 夫れ火は形厳なり、故に人灼(や)かれること鮮(すくな)し。水は形懦(だ)なり、故に人溺るること多し。 243
20200503_C/2 碩学の砦 249
20200513_C/4 Borderline 255
20200527_C/3 ブレイクダウンⅲ勝者の配当 262
20200607_C/2 役人の矜持 267
20200620_C/1 五蠢 273
20200701_C/2 アルカディアにも税は有り 278
20200711_C/3 ブレイクスルー 283
20200723_C/4 普通 290
20200815_C/3 平和の理 297
20200905_C/2 主権の鼎 309
20200919_C/4 片雲の風 317
20201003_C/1 韓非の空 323
3 休筆
最初に、この企画書をの事を教えてくれた大手出版社にこれを送りました。タイトルに表記しているように、応募封筒にも細工を加え、散々感想を求めるコメントを差し込んだのですが、なしのつぶてでした。
まあ日本を代表する出版社なのでいた仕方ありません。
その後アドバイス通り、本の奥行きを見て、小さな出版社まで絨毯爆撃を加えるつもりでした。また、一作にとどまらず、続編の構想も練り始めていました。
しかし、薬品の効果で、理解力・読解力・文章力が低下し、何も書けなくなっていきました。別に変な薬を飲んでいるわけではない。むしろ、私の歪んだ性格を矯正するために必要な処置なのですが。
執筆は楽しいが、しばらくは納得の行くものは書けそうになさそうです。もしかしたらこの投稿が絶筆になるかもしれません。
私の経験は、所詮浅いものかもしれないが、少しでも明日の作家を目指す人のお役に立てらえば本望です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
