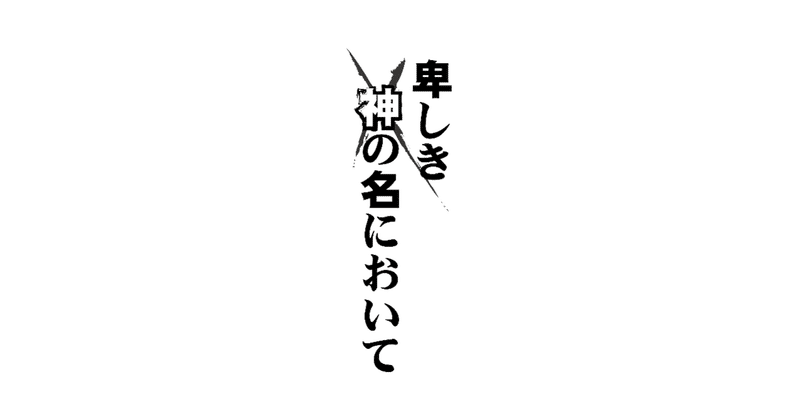
卑しき神の名において 第二章⑦
今まで数多くの卑神を見てきた。人の形をしたものも、それを逸脱したものも。――殺したのも、そうでないのも。だが少なくともクロウには、今目の前に現れた《殻烏》は、そのいずれとも一線を画しているように感じられた。
鎧を纏ってはいるものの、シルエットには女性らしい柔軟さが表れている。それでいて随所に持つ鋭利は、卑神自体が一本の刃であるかのように見えた。そして全身に黒い羽根の意匠と、左手に備えた鏡のような円盾。その装いには北欧の神話に登場するという戦場を駆ける戦乙女――ワルキューレを想起した。
(あれは本当に卑神なのか……?)
泰然と佇む姿を見て、クロウは独り言つ。卑神の姿はそれぞれだ、一つとして同じものはない。彼らはそのどこかに、"卑しき神"の名に相応しい暴力性や凶悪性が見て取れた。だが《殻烏》にはいずれも見て取れない、これではまるで――
(まるで、本当に神だとでも言うのか)
呆然とするクロウの傍らを、赤い風が駆け抜ける。アカネ――《咬羅》が《殻烏》に向けて躍りかかった。
●
カナエは初めての卑神としての知覚を、まるで夢現を漂うかのように得ていた。目が覚める直前の錯覚にも似た万能感。己の体が全く違う存在に置き換わったというのに、その心は満ち足りていた。
体が今まで知り得なかった理に沿って動き、赤い色の刃――《咬羅》の刃を受け流す。続く《咬羅》の追撃――恩頼「流血公女」によって様々な形に変化した血液を手に、《殻烏》へと追いすがった。
対象を血液に絞るという制約はあるものの、その操作性も再現性も《凄門》の「冰刀《水槌》」を上回る。剣、短剣、長剣、片刃、斧、手斧、槍、戦斧、鎖鎌、鉤、槌、鏢、戦輪、鈷杵――一つとして同じ姿はなく、一つとして同じ軌道をなぞらない。斬る、打つ、突く、薙ぐ、撃つ、払う、穿つ――嵐のように吹き荒れる鮮血の凶器を、しかし《殻烏》は紙一重で躱し続けて流水のように肉薄した。そのまま《咬羅》の胴へ正拳を放つ構えを取り、だが一拍置いて盾を用いた当身へ切り替える。
直撃した盾は甲高い音と共に阻まれる。《咬羅》の胴は血液が無数に変化した小札が棘を為し、一撃を阻んでいた。そのまま正拳を放っていればおろし金のように《殻烏》の手を抉っていただろう。
「殺しなさい、アカネ。貴方に負けるようなら、その卑神も不要よ」
《咬羅》の耳に届くのは慈母の如きヤクモの声。
「それとも――私も失望させるつもり? 母親にしたように」
その声に嘲りの色が混じる。武器を持つ手が軋んだ。
(違う、私はもう変わったんだ。私だけが手に入れた、私だけの特別な力。なのに――)
目の前の卑神に顔が重なる。自分を哀れむカナエの顔、家庭を顧みない父親の顔、弟の死を受け入れられない母親の顔。
「見下してんじゃ、ないわよ!」
両手の武器を接続、更に血液を加える。赤黒い渦は鋳型に流されたかのように、身の丈を超える巨大な鎌へと姿を変えた。
地を抉り、局所的な竜巻の如き猛威と共に迫る大鎌。《殻烏》の「兆し」は最早黒い羽根を経ることなく、カナエに明確な軌道を伝える。横薙ぎに振るわれた刃を屈むように回避し、がら空きになった《咬羅》目掛け踏み込む。体の勢いを殺さず地に手を付て縦回転、そのまま踵を当てる所謂「浴びせ蹴り」の構え。だが音を置き去りにする速度で落とされた踵は、《咬羅》に触れることなく空を切った。
《咬羅》は大鎌を振り抜く前に血液へ戻して後退。それが誘いだったとカナエが気付くより先に、準備は整っていた。
「早贄にしてやるわ」
地面を血液が走り、《殻烏》を中心に球体を為す。
「『流血公女・葬輪華』!」
鮮血の華が咲き乱れ、刃と化して《殻烏》へと殺到した。
上下前後左右から殺到する無数の刃を、カナエはまるで駒が並ぶ盤面を睥睨する如く見ていた。一切の死角なし、ただそれを実現するために《咬羅》は持ち得る全ての血液を注ぎ込んでいる。
今ならば"通る"。《殻烏》は盾で身を隠しつつ、自身を投擲するかのように跳躍する。
(殺った!)
血液を操作し、勝利を確信する《咬羅》。全ての血液を注ぎ込んだ"棘"の一本一本は生中な力で折れるものではない。アカネの意志を体現するかのように迸る赤黒い"棘"は、しかし《殻烏》の盾に触れて砂のように砕けた。
●
「まさかとは思ったけれど、やはり――」
《咬羅》の赤い檻を突破する《殻烏》を見、ヤクモは誰にも聞こえない声で独り言ちる。
「"御鏡"か!」
●
必殺を期して放った大技が回避とも呼べぬ芸当で無効化され、アカネの思考に空隙が生じる。その内に《咬羅》の鳩尾へと手を添えた。反応して全身を強張らせてしまった《咬羅》は、虎口の内に居ると悟るも逃げることはできない。
(――ここだ)
《殻烏》の踏み込みに耐えられず、両足を据えた地面のアスファルトが粉砕される。踵、爪先、脛、膝、腿、腰、腹、胸、肩。全身を回転させて生み出され、バネと緻密な重心移動によって増幅された力は、正中を経て伝達され零距離に触れていた拳から放出された。
寸打、あるいは寸勁。人の身であれば単なる一撃にしかならない技術。しかし卑神から放たれたそれは、必殺の一手となって《咬羅》の身を打ち砕いた。
同時にカナエは悟る。今自分を動かしているこの技術は、《殻烏》を通して誰かから伝えられたものだと。それは《殻烏》に自分を託した、あの女性以外に考えられなかった。
鮮血を巻き上げながら《咬羅》が吹き飛んだ。寸打が威力を発揮する直前、自身を流れる血液を操作して体内に壁を形成することで瀕死は免れていた。だがこれ以上の戦闘は続けられず、蹲って《殻烏》を睨め付ける。
踏み出した《殻烏》の足元を斬撃が走る。ひゅう、と風切り音を立てながらヤクモが糸を引き戻し、ぱんと柏手を打った。
「そこまでにしておきなさい、貴方の実力はよく分かったわ」
「……私はまだやれますが」
構えを解かないまま向き直る《殻烏》を、ヤクモは一笑に付す。
「死にかけの卑神憑き一人と、その人形を守りながら?」
「――勝手に戦力外に入れるな」
声のした方へ眼をやると、ボロボロのクロウが立ち上がるのが見えた。ただ仮面を保持する指は力なく、それが虚勢であることは明らかだった。
「その意志があれば、いつか私にも刃が届くかしらね。――それにしても」
ヤクモが《咬羅》を一瞥する。未だ卑神の体を保っているものの、既に戦う力は失われている。
「お前には失望したわ、まさか初めて顕装した相手に醜態を晒すとは。死にたくなければ、私の勘気を被る前に失せなさい」
その体を震わせたのは、怯えか怒りか。「あ、アカネちゃん」と声を掛けた《殻烏》に目もくれず、《咬羅》は翼を広げて飛び立った。
「じゃあね、クロウ。次はもう少しマシなのを用意しておくわ」
「クソ、待て!」
制止するクロウに目もくれず、ヤクモの姿が霧消する。静寂に残された三人のうち、最初に口を開いたのはミツキだった。
「流石に今回はまずかったわね、死ぬかと思ったわ」
未だ傷は残るものの、声色から深刻さは伺えない。胸を撫で下ろしたカナエ――《殻烏》に、クロウが向き直る。
「いや、まだだ」
仮面を捧げ持ち、顕装の構えを取った。
卑しき神の名において 第二章「飛鉄心 殻烏」〈了〉
※今回の後書きは後日ライナーノーツとして公開します。
甲冑積立金にします。
