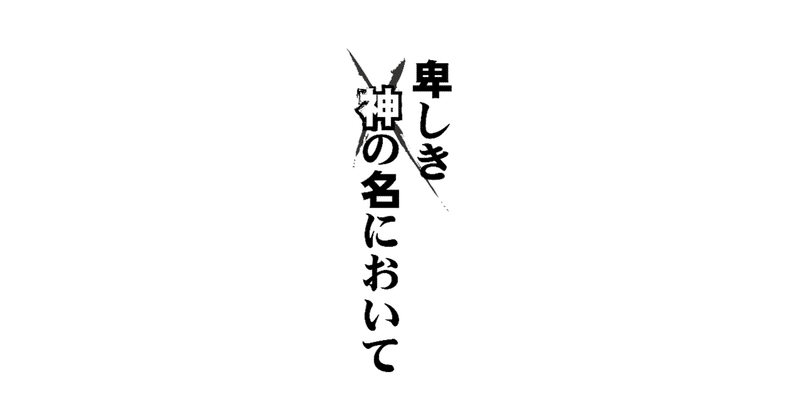
卑しき神の名において 第二章⑥
一説に依れば、走馬灯とは死に瀕した脳が過去の記憶から九死に一生を得る術を探すために見るものだという。仇敵の必死拳が迫るなか、クロウの脳裏には今まで殺めてきた者たちの記憶が浮かび上がる。
始めて殺めた卑神《禍槌》は、天をも焦がすほどの炎で山一つを紅蓮に染めた。
その後に殺めた卑神《忌世姫》は、大樹のような氷塊を降らせ村落一つを氷山に変えた。
クロウは試行する、彼らから奪い取った恩頼が矮小なのはそれを御するだけの力がないからだ。
(ならば、恩頼を以て恩頼を御すればいい)
丹田に内燃機関を仮想する。選択するのは「灼刀《鑪羅》」と「冰刀《水槌》」。通常と異なるのは、それが並列して存在するということだ。炎熱と氷結という真逆の異能は、互いの発現には干渉し合わず、かつ効果のみは打ち消し合う。
(これは術理ではなく、曲芸だ)
両手で互いに打ち消し合う色の絵筆を持ち、無暗に振り回しながらも画布の白さを保ち続けるような芸当。己の脳髄を焼き切らんばかりに過負荷が吹き荒れる中、加速する体感時間のなかで「それ」を為し遂げた。
疾走するヤクモの拳が触れ、刺突の型に構えた刃の切っ先が飴細工のように砕けた。
――もどかしい。
発現する"空"の想定位置を、刀から掌へ変える。一瞬でも持てばいい、今は刹那でも長く時を稼ぎたかった。
刀から手を放す。予想外の行動にヤクモが嗤うのを見た。人間ではなく、まるで虎の如き猛獣の面構え。それでも拳の軌道は変えず、一直線にこちらの眉間を狙ってくる。
暴走する一歩手前で荒れ狂っている丹田の両機関が保つ均衡を、ほんの一瞬崩す。押し留められていた炎熱が出口を求めて殺到し、炎は紅を超えて白く輝き、ここに秘剣が完成した。
「《結》――絶刀《不知火》」
白い軌跡を残し、手刀が疾走した。
●
「――あら」
ヤクモが驚きの声を上げる。頬に触れると一筋、赤い色が滲んでいた。指で拭うと傷がどこかも分からなくなるほどの、ささやかな傷。
「何年ぶりかしらね、傷を負うなんて。あの都からきた忌々しい武者共に負けて磐座に封じられて以来だから、一千年ほどかしら」
知ったことか、と吐き捨てようとしたクロウの体が崩れ落ちた。ヤクモの凶拳は直撃はしなかったものの、掠った箇所を中心にその衝撃だけで《凄門》の骨格は破壊されている。加えて恩頼の並列稼働《結》による負担は想像を絶し、人の形を保っていられることすら不思議なほどだった。
「いいわ。無様な姿を見せられたらここで殺すつもりだったけれど、今日は見逃してあげる。――貴方はね」
どさ、と這いつくばるクロウの眼前に何かが落とされる。
「ミツキ!」
名前を呼ばれて身じろぎをしたが、傷だらけの体は力なく横たわったままだ。
「ごめん、できれば逃がしてあげたかったんだけど――」
ミツキに続いて空から巨大な影が舞い降りる。赤茶けた、鳥というよりコウモリやムササビのような有翼の獣を思わせるそれ――アカネの卑神《咬羅》は、片足にカナエを掴むようにして抱いていた。
「さぁ、これで役者は揃ったわ。次の曲目を始めましょう」
本当に観劇に来たかのようにはしゃぐヤクモは、袂から瓶子を取り出した。中身を盃に注ぐとカナエへと突き出す。
「カナエさん、これを貴方に呑んで欲しいの」
彼女の視界の端で黒い羽根が翻るが、それが無くともろくな結果にならないことは分かる。ヤクモは虚空を見ながら、慈母の如き笑みを浮かべた。
「そう、それよ。あなたにしか見えない兆し。私にすら感知することしかできないその兆しが何なのか、私は知りたいの」
言葉通りなら見えていないのだろう羽根を、ヤクモは指さした。その指にすら羽根は反応したが、それだけだ。これには決して今のカナエを助ける力はない。
「呑まないならそれでいいわ、あなただけは見逃してあげる。でもここに這いつくばったクロウも、人形も殺す」
「やめろ、呑むな……!」
掠れた声で呻く《凄門》の背を、《咬羅》が足蹴にする。だめ押しの一撃で《凄門》の体は消え去り、クロウの姿だけが残った。跳ね除けようとするも、《咬羅》の足は微動だにしない。
「彼らを救えるのは貴方しかいないわ。大丈夫、クロウから何か言われたでしょうけど、卑神憑きになってもそれに溺れなければ何も臆することはないのよ」
ヤクモから受け取った盃には、薄暗い夜空を映す無色透明の液体が揺れていた。
「ごめんなさい、クロウさん」
視線を盃に落としたまま、カナエが呟く。
「……お願いだ、やめてくれ」
止める訳がないと分かっているのに、クロウは口にせずにはいられなかった。
「私はもう、この世界の部外者でいたくないんです」
本当に申し訳ないと思う、彼らは傷だらけになってまで自分を助けようとしてくれた。それでも知りたかった、自分にしか見えないこの羽根が何なのか。黒い翼に抱かれて見えた、炎に薙がれて消えた世界がどうなったのか。
(ここではないどこか、今ではないいつか、私ではない何かへ――)
その手掛かりに触れられるなら、今は何もかも惜しくはなかった。
喉を滑り落ちるように水が通り、自分の体に行き渡っていく。劇的に何かが変わりはしなかったが、背後に何かの存在を感じた。それが不快に思わなかったのは、ずっと見守っていてくれたことを知っているからだろう。
(あの時から、一緒にいてくれたんだね)
気付けば手には仮面が握られていた。黒曜石から削り出したような、鋭利で黒い猛禽類を思い起こさせる光沢の仮面。
クロウはカナエの周囲に黒い羽根が噴出するのを見た。「――よもや」とヤクモが喜びとも怒りとも取れる破顔で声を上げる。
カナエが仮面を掲げる。何を言うべきか、何を呼ぶべきなのかは理解していた。
「顕装――《殻烏》!」
(お願い、殻烏。その子を守ってあげて――)
どうして今まで忘れていたのか。それは五年前の平成二十七年、元いた世界が父母諸共燃える大蛇に焼き尽くされる寸前に見た、名前も知らない女性の最期の言葉だった。
●あとがき
《殻烏》でそのまんま「からがらす」と読みます。十年前に大学の文芸部の部室で思いついたのを憶えているんですが、当時は何に使うかは全く考えていませんでした。こうして世に出るとはまぁまぁ感慨深いものがありますね。
想定していた以上に後の展開のことを盛って書いた章になりましたが、それをどうやって書くのか全く考えていない。とりあえず第二章は次回で終了です、今週中に書き上げられればいいですね(万事が他人事)。
甲冑積立金にします。
