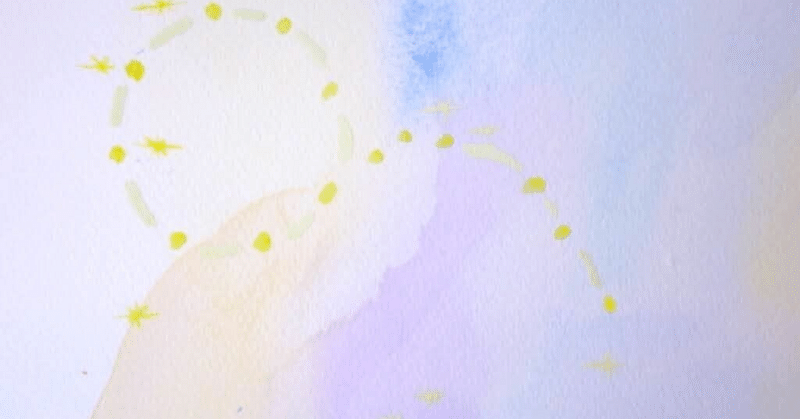
【掌編小説】彼
最近、彼のことを考えると、壁を這う蜘蛛を見つめているような気分になる。
バイアスが心の中で崩壊して、これから結婚するのだろうが、未来を事前に掃除して、私だけ精神的な更地に住んでいる。
壊れてしまった互いの温度計。私には灰色に見える秋の空。胸の奥にまで冷たい風が染みこんでくる。長過ぎる夜。鈍いオレンジの夕日。単純な赤ん坊の泣き声。
私が失ったものは他人を尊重する心と自分を愛する希望。生き続けることを無意味だとは思わないが、もう尊敬が剥離したのだろう。
孤独を夢見ている意識が自分たらしめ、次第に彼が汚く見える。
でも彼が風邪を引くと看病してしまう。ほっとけない。
私は病人の匂いが好きなのだろうか。明確な区分。
そういう意味で、答えを与えられないと生きていけないのかもしれない。
元気になると能天気な言葉にストレスが溜まって嫌になる。
嫌いになることに躊躇しないのはまだ子供だからだろうか。
もうすぐ28歳の誕生日。
今年結婚しなかったら一緒に住んでいてもずるずる進むだけだろう。
という予感が発生してからの結婚と、予感に支配されない結婚。
もう後者ではなくなった雰囲気で、観葉植物の葉が湿った布でケアされるようになった時点で私たちはもう終わったのだ。廊下にゴミが散乱していた、あの雑多な時期にするべきだったのだ。
私は後悔している。
誰かの子供の背中を見る度、外野なんだと思い知る。
子供が欲しい気持ちと彼の対する気持ちは全く別の世界の話。
私は一体どうすれば普通になれるのだろう。
高校生の時、急に来なくなったあの子は妊娠して退学して子供を産んだ。
少し前までSNSで子供と写っていたが、今はどうしているのだろう。
私が決して到達できない幸せの次元に行ったのか、それとも新しい地獄に行ったのか、分からない。
どういう道を選択しても、私もあの子も、そして彼も行き止まりにしか辿り着けない気がする。
小説を書きまくってます。応援してくれると嬉しいです。
