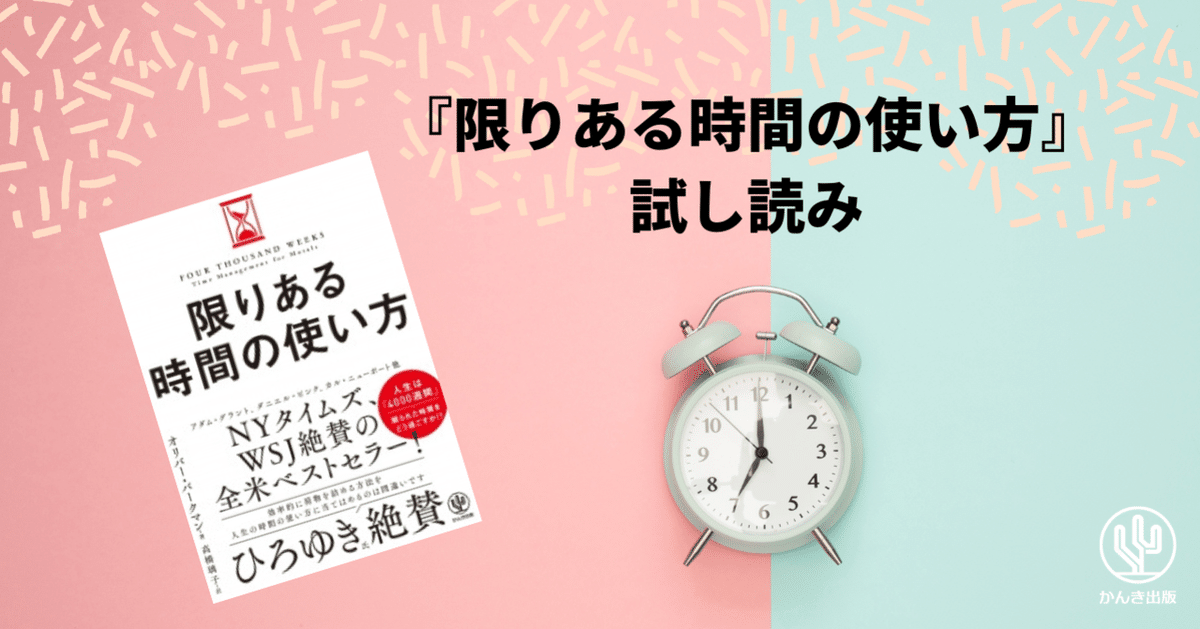
『限りある時間の使い方』試し読み
かんき出版から発売した『限りある時間の使い方』(オリバー・バークマン /著 高橋璃子/訳)の冒頭、イントロダクションを公開します。人生はたった4000週間。5分あれば読めますので、ぜひ立ち読みしてみてください。気になった方は最後に購入先もご紹介してますので、ぜひ御覧ください。
イントロダクション
長い目で見れば、僕たちはみんな死んでいる。
人の平均寿命は短い。ものすごく、バカみたいに短い。
ちょっと考えてみてほしい。人類が最初にアフリカ大陸に登場したのが今から20万年以上前。そして科学者の見積もりによると、太陽の熱で地球上の生命が絶滅するのは今から15億年以上先の話だ。
それで、自分の人生は?
80歳くらいまで生きるとして、あなたの人生は、たった4000週間だ。
まあ運が良ければ90歳まで生きて、4700週間くらいになる可能性はある。
もっとめちゃくちゃ運が良くて、人類でもっとも長生きだったフランス人女性ジャンヌ・カルマンと同じ122歳まで生きたとしよう。彼女は19世紀の画家ヴィンセント・ヴァン・ゴッホに会ったことがあり(とにかく酒臭い男だったらしい)、クローン羊のドリーが生まれた1996年にもまだ生きていた。科学が進歩すればそれくらいの寿命は一般的になるかもしれない。だがそれでも、あなたの生きられる時間は、ほんの6400週間ほどだ。
そんなふうに考えてみれば、古代ギリシャから現代に至るまで、多くの哲学者が人生の短さを延々と論じてきたのもうなずける話だ。人はどこまでも壮大な計画を考える頭脳を持ちながら、それを実行に移すだけの時間がない。古代ローマの哲学者セネカは『人生の短さについて』という文章のなかで、こう語る。
「われわれに与えられたこの時間はあまりの速さで過ぎてゆくため、ようやく生きようかと思った頃には、人生が終わってしまうのが常である」
4000週間という数字を最初に計算したとき、僕はあまりの短さに目の前が暗くなった。それから気を取り直して、友達みんなに聞いてまわった。「頭にパッと浮かんだ数字で答えてほしい。人は平均で何週間生きると思う?」ある人は数十万と答えたので、僕は僭越ながら、彼女にそっと教えた。メソポタミアのシュメール文明から現在まで、人類の文明全体の時間をあわせても、31万週間にしかならないんだよと。
「我々はみんなもうすぐ死ぬ」と言った現代の哲学者トマス・ネーゲルは正しい。
そうだとすると、時間をうまく使うことが人の最重要課題になるはずだ。人生とは時間の使い方そのものだといってもいい。
ところが現代の、いわゆるタイムマネジメントというやつは、あまりにも偏狭すぎて役に立たない。タイムマネジメントの指南書が教えることといえば、いかに少ない時間で大量のタスクをこなすかだったり、いかに毎朝早起きして規則正しく過ごすかだったり、あるいは日曜日に1週間分の食事をまとめてつくりましょうということだったりする。いや、もちろんそれも大事だと思う。けれど、それだけでは話にならない。
世界は未知のものごとであふれているというのに、タイムマネジメントの先生たちときたら、目の前のつまらないタスクをこなすことばかり考えている。
世界は全速力で破滅に向かおうとしているのに――文明はおかしな方向に突き進み、パンデミックが世界中を襲い、地球はどんどん熱くなっているというのに――タイムマネジメントの先生は誰も世の中を良くしたり、社会の危機に立ち向かったり、地球環境を守ったりすることについて語ろうとしない。
それどころか、世の中にあふれるタイムマネジメント本のほとんどは、人生がものすごく短いという事実さえも認めようとしない。タイムマネジメントさえすれば何でもこなせるという幻想を振りまいているだけだ。
僕は、世の中のそんな風潮に物申したいと思う。狂ってしまったバランスを取り戻したい。そして、時間をもっと現実的に見つめてみたい。ものすごく短くて、きらきらと光る可能性に満ちた、4000週間という僕たちの時間を。
人生のベルトコンベア
「時間が足りない」なんて、何を今さらと思うかもしれない。
いっぱいになった受信トレイに、長すぎるやることリスト。もっとやるべきことがあるのではないか、なにか別のことができるのではないか、いやどっちもやるべきなのではないか。現代人は誰でも、そんな焦りを抱えている(人が忙しいかどうかを判断する方法?誰かが菜食主義者かどうかを判断するのと同じだ。心配しなくても、向こうから教えてくれるさ)。
しかし2013年に、オランダの研究者たちがおもしろい可能性を示唆している。そもそも本気で忙しい人は忙しさの調査に参加する暇さえないため、忙しさに関するデータはかなりの暇人から集めた結果なのではないかという説だ。
最近では低賃金で不安定なギグワーク(訳注:ウーバーイーツなどに代表される、空いた時間で単発の仕事を請け負う働き方)が流行し、忙しさが「ハッスル」と言い換えられるようにもなった。あれこれの仕事で忙しいのは悪いことじゃない、活気に満ちた働き方だ。ソーシャルメディアでハッスル自慢しようぜ、というわけだ。
だけど実際に起こっていることは、そんなおしゃれなものじゃない。昔ながらの問題が激化しているだけだ。増えつづける仕事量を、限られた1日の長さになんとか押し込めるべく、みんな必死になっている。
忙しさは、問題の入り口にすぎない。よく考えてみると、問題の根っこにあるのは「時間が限られている」という事実だ。たとえば、インターネット上のいろんな気晴らしをやるうちに、集中力がなくなってしまったという嘆き。子どもの頃は本の虫だったのに、今では段落ひとつを読み終える前にスマホに手を伸ばしてしまう。なぜそれが問題になるかというと、限られた時間を有効に活用できていないからだ(もしも時間が無限にあるなら、フェイスブックで午前中を無駄にしても自己嫌悪に陥ることはない)。
自分は忙しすぎるわけじゃなく、むしろ暇で困っているんだ、という人もいるかもしれない。何の意味もない退屈な仕事にうんざりしていたり、そもそも仕事にあぶれているかもしれない。そうだとしても、状況を苦しくしているのは、やはり限られた時間を思うように活用できていないという感覚だ。
現代の深刻な問題ーー社会の政治的分断や、YouTubeの動画で過激化したテロリストなどーーも、結局は人生の短さという事実に行きつくかもしれない。人の時間と注意力には限りがあるため、テック企業はあの手この手で無理やり僕たちの関心を引こうとする。その結果が、正確さを犠牲にしてユーザーの感情を煽り立てる悪質なコンテンツだ。
結婚や出産、キャリアの選択といった普遍的な悩みも、限られた時間のジレンマだといえるだろう。仮に何千年も生きられるなら、そもそも悩む必要はない。ゆっくり時間をかけて、全部試してみればいいからだ。
そしてさらに悩ましいのが、歳をとると時間が早く過ぎるという憂慮すべき現象だ。30歳以上の人なら実感していると思う。ただでさえ4000週間は短いのに、残り時間が減れば減るほど、時間が経つスピードまで加速してしまう。
限られた時間との戦いは古くからあったかもしれないが、最近の状況は問題をさらに深刻にしている。
2020年、新型コロナウイルスのパンデミックが発生し、僕たちの日常は停止した。時間の感覚が壊れてしまった、と感じている人も多い。時が過ぎるのが速すぎるような、しかし同時に延々と停滞しているような感覚だ。
僕たちの時間は分断された。家で仕事をしながら子どもの面倒を見る人にとっては時間が足りないし、休業になったり失業した人にとっては時間が多すぎる。昼夜のサイクルがおかしくなり、真っ暗な部屋でノートパソコンの光に照らされている人たちがいる。危険と知りながら休むわけにいかず、病院や通販業者の倉庫で命をかけて働いている人たちもいる。
そして僕たちの未来は、奇妙な保留状態に置かれた。ある精神科医はそれを「新たな終わりなき現在」と呼ぶ。宙ぶらりんの不安のなかで、ひたすらSNSの画面をスクロールし、Zoomでなんとなく会話をし、不眠症に悩む日々。未来の計画を立てるどころか、来週以降の生活がどうなっているかもわからない。
こんな状況では、時間管理の難しさはいっそう大きなストレスになる。なんとか時間を有効に使おうとしても、うまくいくどころか、かえって事態が悪化する。世の中にはタイムマネジメントの指南書があふれているし、日々の雑務を効率化するための「ライフハック」を紹介するウェブサイトもうんざりするほどある(ライフハックという言葉が示唆するのは、人生が機械のプログラムのようなものであり、アルゴリズムを直してやれば最適なパフォーマンスが得られるという奇妙な考え方だ)。
仕事やエクササイズ、さらには睡眠から得られる利益を最大化するためのアプリやウェアラブル端末も増えた。食べる時間を節約するための食事代替ドリンクまである。台所用品からオンラインバンキングまで、ほとんどの製品やサービスは効率化を最大の売りにしている。問題は、そうした製品やテクニックが機能しないことではない。それらを活用すれば、もっと仕事をこなして、もっと多くの会議に出席し、もっと多くの習いごとに子どもを連れていき、もっと多くの利益を会社にもたらすことができるかもしれない。ところが皮肉なことに、それに成功したところで、ストレスは減らない。以前よりもっと忙しく、もっと不安で、もっと空虚な気分になるだけだ。
アメリカの文化人類学者エドワード・T・ホールはかつて、現代社会の生活をベルトコンベアにたとえた。古い仕事を片づければ、同じ速さで新しい仕事が運ばれてくる。「より生産的に」行動すると、ベルトの速度がどんどん上がる。あるいは加速しすぎて、壊れてしまう。
最近、とくに若い世代で、日常生活が送れないほど深刻なバーンアウト(燃え尽き症候群)になる人たちが増えている。ミレニアル世代の社会評論家であるマルコム・ハリスの言葉を借りれば、彼らは「胎児のときからリーンで無駄のない生産機械として製造され、最適化された道具の世代」である。
とてつもない無力感を覚えるのも無理はない。
タイムマネジメントやライフハックの技術は、大事な真実を見落としている。「時間を思い通りにコントロールしようとすればするほど、時間のコントロールが利かなくなる」という真実だ。手に負えない幼児と同じで、抑えつけてもだめなのだ。
食器洗い機や電子レンジやジェット機は、僕らの使える時間を増やして、より豊かな生活を可能にするはずだった。それなのに、実際は誰も時間が増えたと感じていない。むしろ生活が加速したせいで、みんな以前よりもイライラしている。電子レンジで2時間待たされるのは、オーブンで2時間待つよりもずっと腹立たしい。郵送で3日待つのは我慢できても、重いウェブサイトで10秒待たされるのは我慢できない。
仕事の生産性アップも、やはり同じ矛盾にぶつかる。数年前、メールが増えすぎて困った僕は「インボックス・ゼロ」という効率化ツールを導入した。ところがメール返信を効率化しても、結局はやってくるメールの数がいっそう増えるだけだった。
ますます忙しくなった僕は、タイムマネジメントで有名なデビッド・アレンの『仕事を成し遂げる技術』を読んでみた。「どんなにやることが多くても、頭をクリアにして生産的な仕事ができ る」「武道でいうところの『水のような心』を手に入れる」という謳い文句に惹かれたからだ。
でも、どうやら僕はアレンの真意を読みちがえていたらしい。どんなに心を研ぎ澄ませたところで、やるべきことが減るわけではなかったのだ。
僕はやることリストを超速でこなせるようになったけれど、その結果、ありえないほど大量の仕事が舞い込んでくることになった(なぜそうなるのかは、心理学および資本主義のしくみから理解できる。詳しくは後で説明したい)。
何かがおかしい。未来はこんなものじゃなかったはずだ。
1930年、経済学者のジョン・メイナード・ケインズは「孫たちの経済的可能性(Economic Possibilities for Our Grandchildren)」と題したスピーチのなかで、ある有名な予言をした。100年後には、富の増加と技術の進歩のおかげで、みんな週に15時間しか働かなくなるだろう。人の悩みは忙しいことではなく、ありあまる余暇をいかにうまく過ごすかということになるだろう、という予言だ。
「創造以来初めて、人類は真の、永続的な問題に直面する。経済の悩みから解き放たれた自由を、いかに使うかという問題である」とケインズは言った。
しかし残念ながら、ケインズはまちがっていた。
必要なだけのお金が手に入っても、人は満足しない。欲しいものや真似したいライフスタイルがどんどん増えていくだけだ。もっとお金を稼ごうと頑張り、忙しさを何かの勲章のように自慢する。
まったく不思議な現象だ。そもそもお金持ちというのは、お金のためにあくせく働かなくてもいい立場ではなかったのか?
忙しいのは、もちろんお金持ちだけじゃない。トップの人たちがさらにお金を稼ごうとするなら、手っ取り早い方法は所有する会社や業界のコストを削減することだ。下々の労働者は効率化に追い立てられ、切り捨てられる不安におびえながら働いている。ただ生き延びるためだけに、もっともっと働かなくてはならないのだ。
やり遂げよう。でも、何を?
こうして問題の核心に近づいていくと、さらに深いところに、なんとも言いがたい感覚が居座っていることに気づく。どんなに大量の仕事をこなしても、どんなに成功しても、自分は本当にやるべきことをやっていないのではないか、という感覚だ。
本当はもっと重要で充実した時間の過ごし方があるんじゃないか。
今こうやって黙々とこなしている仕事は、本来やるべきこととは違うんじゃないか。この感覚はさまざまな形でやってくる。何か大きな目的のために自分を捧げたい。危機と苦しみに満ちたこの時代に、自分の力を労働や消費とは違うことに使いたい。こんな無意味な仕事を辞めて、自分の好きな仕事をしたい。限られた人生なのだから、もっと子どもと一緒に過ごしたい。自然のなかで過ごしたい。とにかく通勤から解放されたい。環境保護活動家のチャールズ・アイゼンスタインは、物質的豊かさのなかで育った子ども時代に、これに似た感覚を初めて覚えたという。
人生はもっと楽しく、もっとリアルで、もっと意味があるはずだ。世界はもっと美しいはずだ。子どもながらに、そう思った。月曜日が嫌いで、週末や祝日を待ちわびるなんてまちがっている。おしっこをさせてもらうために手をあげなければならないなんてまちがっている。よく晴れた日に、毎日毎日、室内に閉じ込められるなんて何かがおかしい。
生産性を高めようとするたびに、違和感は増していく。本当に大事なことが、なぜかどんどん遠ざかってしまう。
僕たちの日常は、どうでもいいタスクをひたすら片づける日々だ。いつか邪魔な仕事をすべて終えたら、そのときこそ大事なことができるはずだ。そう思って頑張るけれど、本当にそこに近づけるのだろうかという不安もある。自分の能力が足りないんじゃないか。
時代のスピードに取り残されはしないだろうか。「私たちの時代を支配するのは、喜びを欠いた切迫感である」と、エッセイストのマリリン・ロビンソンは言う。彼女によると、ほとんどの人は「自分とまったく関係のない不可解な目的の手段となるために、自分や子どもたちをせっせと準備している」。
人に言われたことを必死で頑張れば、誰かの役には立つかもしれない。毎日毎日残業して、その残業代でたくさん買い物をすれば、経済のよりよい歯車にはなれるかもしれない。だけど、そんなことで心の安らぎは得られない。限られた時間を、大切な人や物のために使うこともできやしない。
本書は、時間をできるだけ有効に使うための本だ。
ただし、いわゆるタイムマネジメントの本ではない。
これまでのタイムマネジメント術は失敗だらけだった。そろそろ見切りをつけたほうがいい。時間がぽっかりと宙に浮いたような今こそ、時間との関係を再考する絶好の機会かもしれない。先人たちが直面してきた問題を現代に当てはめてみると、ある真実が明らかになる。
生産性とは、罠なのだ。
効率を上げれば上げるほど、ますます忙しくなる。タスクをすばやく片づければ片づけるほど、ますます多くのタスクが積み上がる。
人類の歴史上、いわゆる「ワークライフバランス」を実現した人なんか誰もいない。「うまくいく人が朝7時までにやっている6つのこと」を真似したって無駄だ。
メールの洪水が収まり、やることリストの増殖が止まり、仕事でも家庭でもみんなの期待に応え、締め切りに追われたり怒られたりせず、完璧に効率化された自分が、ついに人生で本当にやるべきことをやりはじめるーー。
そろそろ認めよう。そんな日は、いつまで待っても、やってこない。
でも悲しまないでほしい。それは実際、とてもいい知らせなのだから。
==============================
イントロダクションはここまでです。気になった方はぜひお手に取ってみてください。目次はこちら。
目次
PART 1 現実を直視する
第1章 なぜ、いつも時間に追われるのか
第2章 効率化ツールが逆効果になる理由
第3章 「時間がある」という前提を疑う
第4章 可能性を狭めると、自由になれる
第5章 注意力を自分の手に取り戻す
第6章 本当の敵は自分の内側にいる
PART 2 幻想を手放す
第7章 時間と戦っても勝ち目はない
第8章 人生には「今」しか存在しない
第9章 失われた余暇を取り戻す
第10章 忙しさへの依存を手放す
第11章 留まることで見えてくるもの
第12章 時間をシェアすると豊かになれる
第13章 ちっぽけな自分を受け入れる
第14章 暗闇のなかで一歩を踏みだす
エピローグ 僕たちに希望は必要ない
付録 有限性を受け入れるための10のツール
ご購入はこちら
プレスリリースはこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
