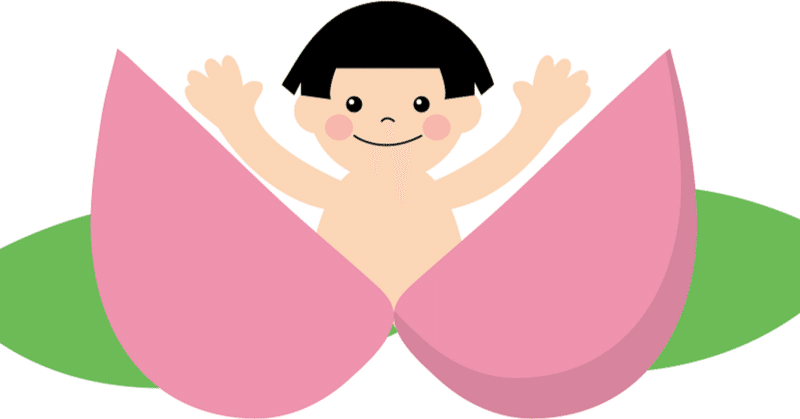
桃太郎のモモ
桃太郎は、桃から生まれて、おばあさんに作ってもらったきびだんごを持って、犬、猿、雉をお供に鬼退治に行く。
子どもの頃に見た絵本の桃は、先っぽがとんがっていた。
今の絵本では、丸い桃から桃太郎が生まれてくる。先っぽがとんがっていない。だって、今の子どもは先っぽがとんがった桃なんて見たことがない。桃といえば丸いものしか知らない。
魚といえば切り身で泳いでいて、肉も初めから人工培養された塊のように思っている。生きている牛や豚や鶏が殺され、その命をいただいているとは想像できない。鶏の首を切り、羽をむしって料理する場面なんて見ないし、牛や豚の死体の塊がつるされている屠殺場なんて知らない。
そんな残酷な話は別の機会においといて、今回は桃だ。
昔の桃は、先っぽがとんがっていた。
桃のまんじゅうを看板にしたバーミアンのマークは先がとんがった桃だ。
中華料理の桃まんじゅうは、まん丸ではなく、先っぽがとんがっている。
今のように、日本で丸い桃が作られるようになったのは明治かららしい。それまでは先のとんがったものが「桃」だった。昭和の時代でも、まだ先のとがった桃が知られていたから、桃太郎の絵本でも先のとがった桃が使われた。ところが現代では、先のとがった桃なんて見ることもない。
昭和の昔、田舎の私の家には桃畑があった。今と同じ丸い桃を作っていたが、1本だけ、先のとがった桃の木があった。
「水蜜桃」の木だと聞いていた。
先のとがった水蜜桃は、中身が真っ赤な色をしている。かじると酸っぱい。むちゃくちゃ酸っぱいけど、食べられないわけではない。子どもだった自分でも食べられた。まあ、1個が限度だけれど、独特の味わいがあって、ある意味おいしかった。
田舎の家はもうなくなったし、他の畑を見ても、水蜜桃を作っている家はなかった。
大人になって、水蜜桃がなつかしくて調べてみると、一部特産品として作っている地域があるが、全国的にはもう作っているところがないらしい。
それに、「水蜜桃」という言葉を調べると、「今の白桃のもとになった」と書いてある。あれっ。私の知っている水蜜桃は赤い実をしている。缶詰の桃は黄色のものがある。これは黄桃といわれる種類で、実が固いので缶詰に使われるそうだ。白桃はご存知の通り、ピンクがかった白い色をしている。桃の実には赤・白・黄色の三種がある。
私が知っている「水蜜桃」は、実は「天津水蜜桃」という種類で、赤い実をしている。これとは別の「上海水蜜桃」という桃も、明治期に日本に伝わり、これが今の白桃になったそうだ。同じ「水蜜桃」といっても「天津」と「上海」では違った種類の桃だった。
「水蜜」なんていう甘そうな名前がつけられるということは、それまでの桃は、もっと甘くなかったということだろう。天津水蜜桃は酸っぱかったけど、それが甘く感じられるほど昔の桃は甘くなかったのだろう。
そんな桃が、桃太郎の物語になり、バーミアンのマークになるということは、それだけ桃は大切にされていた。
桃源郷という言葉があるが、これは人里離れたユートピアのような別世界。そこには桃の木がある。桃の実は長寿の薬としても珍重されていた。薬としてなら昔から桃の木が植えてあっても不思議ではない。
桃太郎伝説の中には、川から流れてきた桃を食べたおじいさんとおばあさんが精力もりもりになって夜の営みをして生まれたのが桃太郎だという話もある。
ああ、桃が食べたい。
自分が正しいと思っていることも、見方を変えると全く別の物になる。ひとつの意見、ひとつの考えだけにしばられると、頭が固まってしまう。
まだまだ桃についてはいろんなことが書けるだろうが、今回はここまで。
タイトル画像はパブリックドメインQさんからお借りしました。御伽草子の挿絵があれば使いたかったのですが、そこまで探せませんでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
