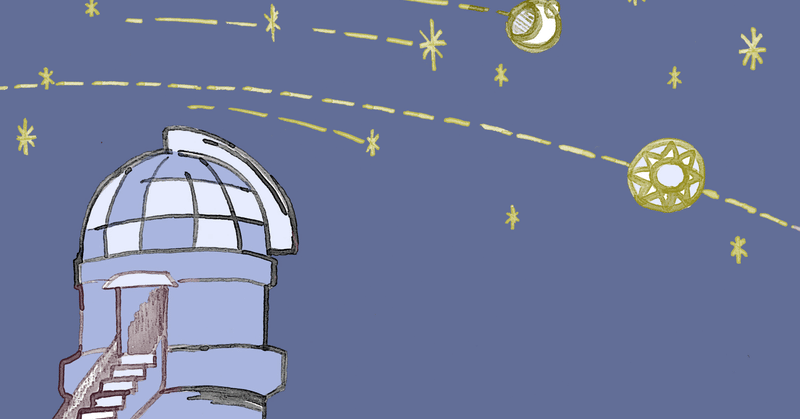
【小説】スピカ
目が覚めたとき、自分が何者で、今どこにいるのかを思い出せなかった。よほど深く眠っていたのだろう。足のつかない水の中にいるような不安な気持で、辺りを見回す。ここは列車の中だった。窓の外には、まだ水の張られていない田んぼが広がり、空は透明な水色で、日差しがきらきらとまぶしかった。それらが通り過ぎて、あっという間にわたしの視界から消えた。トンネルに入ると、窓はわたしの顔を映した。美しくも醜くもない。どこにでもいそうな容姿の、特徴のない一人の若い女。間もなく岡山です、というアナウンスで、そうだ、岡山に来たのだ、とわたしは、寝ぼけた自分に言い聞かせるように、つぶやいた。
予定より二時間も早く、待ち合わせ場所の駅に到着してしまった。一人で遠出することに慣れていないから、乗り遅れてもいいように早め早めに行動したせいだ。東京から新幹線で三時間半。岡山駅でのぞみからこだまに乗り換え、新倉敷から在来線で三十分。目指した場所は、拍子抜けするほど近かった。でも、ここに来るまで何年もかかった気がした。体は到着しているけれど、まだ心が追いついていない。
わたしは駅舎を出て、ロータリーに待機しているタクシーを覗きこむ。
「あの、天文台に行きたいんですけど」
どうぞ、と気軽に請け負う運転手に不安を覚えて、
「国立天文台岡山天体物理観測所、です」
と、言い直した。大丈夫だというように運転手が大きくうなずいた。運転手は、迷う様子を少しも見せず、車を発進させる。道を説明する必要がなかったことにほっとして、シートに体を沈めて息を吐いた。
車しか交通手段がないから、わたしが到着する時間に合わせて車で降りてきて、駅まで迎えに行く、と、瀬良敏和はメールに書いてくれた。でも、取材に押しかけて仕事の時間を取らせるだけでも迷惑なのに、わざわざ迎えに来させるのは気が引けた。タクシーで行けるのなら、そのほうがいい。天文台には、天文博物館という一般の人向けの施設も隣接されていたから、上がってしまえば時間は十分つぶせるし、心の準備もできるだろう。
車は、鬱蒼としげる木々の中に入っていき、急な山道をくねくねと登りはじめた。車酔いしないように、わたしは運転手の肩越しに道の先を見つめる。
「どこから来られたんですか?」
「東京です」
「遠いところから、よう、おいでんさったな」
方言で運転手は言った。孫を迎える祖父母のような親しい響きだった。
「ドアのところに、うちの会社の電話番号書いてあるでしょう。帰るときはそこに電話してください」
カバンから手帳を取り出そうとした途端、体が大きく右に揺さぶられた。酔わないように気を付けていたのに、さっそく胸がむかむかしていた。文字を書くどころじゃない。番号をメモするのはあきらめる。帰りはきっと何とかなる。瀬良敏和に会えさえすれば、山の上に取り残されて途方に暮れるということはないはずだ。たとえ送ってくれなくても、タクシーの電話番号くらいは教えてくれるだろう。
「あ、失礼。お客さん、もしかして、研究者の方でしたか」
と、運転手は笑った。
「お若いから、てっきり一般の見学者かと思いました。じゃあ、これから数日間は山籠もりですね。天気もいいし、いいデータが取れるといいですね」
わたしがメモを取らないので、運転手は勘違いしたのだろう。でも、車酔いがいよいよひどくなって訂正する元気がなかった。許可を取って、そっと窓を開ける。
「この天文台ができた時、私はまだ子供でよく分からなかったんですが、親父や大人たちはずいぶん自慢そうでしたよ。岡山は天体観測に適しているから選ばれて、東洋一の望遠鏡が設置されたんだって、何度も聞かされました」
「晴れの国、岡山ですね」
岡山や天文台について調べていたときに、何度も目にした岡山県のキャッチフレーズだ。
「そう。晴れる日の割合が高いらしいですね。ずっとここに住んでたら、そんなこと言われてもぴんときませんけどね」
国立天文台岡山天体物理観測所と刻まれたゲートが見えた。でもまだ天文台らしきものは見えない。車はさらに山道を登っていく。
「でも、東洋一だったのは五十年前の話で、今はもっとすごいのがハワイにできて、みんなそっちに行っちゃうんでしょう」
「そうとも限らないですよ。確かに、望遠鏡の規模としては、日本一というわけではなくなってしまいましたが、国内にある望遠鏡として、まだまだ果たすべき役割があります。それに、岡山で長年培われてきた技術や経験というものもありますから」
するすると言葉が出てきた。岡山天文台に勤める研究員の瀬良が新聞のインタビュー記事で語っていた言葉の受け売りだった。
「そんなもんですかね」
まるで自分がほめられたみたいに運転手は笑った。
車が上がりきると、視界が開けた。コンクリートの駐車場には、数台の車がぽつぽつと止まっている。
「ここが一般の見学者用の駐車場で、研究者用のゲートは、まだ上になります」
「あ、ここでいいです」
上に上がろうとする運転手を慌てて止めた。
「まだ時間が早いので、博物館のほうも見学していきます」
「そうですか」
料金を払うと運転手は、慣れた様子で領収書を発行してくれた。そして、観測、がんばってくださいねと言うと、ドアを閉めた。
眼下には町が広がって、緑の山々が見えた。ずいぶん高いところまで登ってきたんだと思いながら、深呼吸をする。体の中に、新鮮な空気が入ってきて、むかむかしていた胸が少し楽になる。
博物館に続く階段を上がっていく。上の方にカップケーキみたいな形の建物が見えた。あの丸い屋根の中に巨大な望遠鏡がおさまっているのだ。そして、この望遠鏡を使って瀬良敏和――自分と血のつながった本当の父親――は研究をしているのだ。
一緒に暮らしている父とわたしが、血のつながりがないということを知らされたのは十七歳、高校二年生のときだった。修学旅行でオーストラリアに行くことになり、パスポートを取得する必要があった。
「こせきとうほんってのがいるんだって」
「そう、じゃあ、お母さんが取ってきてあげる」
と、母は気軽に請け負ってくれた。でも、しばらくしてそわそわするようになり、ある日の晩御飯のあとに難しい顔をして、一枚の紙をうやうやしくわたしに差し出しながら、今まで隠していてごめん、と告白したのだ。
戸籍謄本というものを、わたしのそのとき初めて見た。一枚の紙切れに真珠(しんじゅ)というわたしの名前があり、母・井上沙織、養父・井上隆、そして、父のところには瀬良敏和というわたしの知らない名前が書いてあった。
冗談でしょ、と、わたしは思った。
わたしの父は同級生のお父さんたちと比べたら少々年を取っていて、髪が薄くて太っていて、容姿の面ではあんまり自慢できるところがなかったけれど、誰もが名前を知っている会社の重役を務めていて、部下からの人望も厚く、社会的にはできる男であるらしかった。母は母で、そんな父にべったり甘えていて、ふたりは喧嘩をすることもなく、いつも仲睦まじかった。本当のお父さんが別にいるなんて、そんなこと、一度も考えたこともなかった。
紙から視線を上げると、父も母もわたしの様子を真剣な様子でうかがっていた。泣き出しても暴れだしても、覚悟はできているという顔だった。そんなふうに待たれると、反応する気も失せてしまう。何より現実味がなかった。そもそも、わたしは、自分がショックなのかどうかもよく分からなかった。
ふたりの熱い視線に気圧され、何かこの件について言わねばと焦る気持になって、
「この人、どんな人?」
と、紙を指さしてきいた。そんなぶっきらぼうな言い方になったのは、父の前で、ほかの人をお父さんと呼ぶのはためらわれたからだ。
「天文学者」
と、母は言った。予想外の返答で、思考が停止した。
「で、今、どこにいるの?」
「それが分からないのよ。どこか海外の研究所だと思うけれど」
母は途方にくれたように大きなため息をついた。わたしがじっと見つめていると、
「やだ、真珠。疑ってるの? 別に隠しているわけじゃなくて、本当に分からなくなっちゃったのよ」
と、付け加えて大きく首を振った。ふうん、と、わたしは言った。母のリアクションが演技かかっていて、いかにも嘘くさかった。
「じゃあ、いいや」
わたしはそれで話を打ち切った。十七歳のわたしにとって、世界のどこかにいて会うこともできない天文学者の本当のお父さんよりも、修学旅行のグループ分けや、部活のレギュラー争いや、大学受験のほうが大事だった。それに、父と母がふたりで息をつめて見守っている中で、取り乱したりするのは何だかしゃくだった。
それでわたしは決定的に永久的に、本当の父が別にいることについて、ショックを表明するタイミングを逸してしまったのだった。
修学旅行先のオーストラリアで、夜空を見上げているときにふいに思い出し、本当のお父さんは別の人だった事件を真由に話してみたら、
「天文学者だなんて、かっこいいじゃん」
と、真由はひとりで盛り上がった。
「えー、そうかな」
「かっこいいよ。巨大なアンテナ操作して宇宙と交信してるんでしょう。あ、真珠が数学とか物理とか得意なのってお父さんの遺伝じゃないの? いいなあ。本当のお父さん。なんかピンチのときに助けてくれそうじゃん」
「ピンチってどんな? 」
「エイリアンにさらわれそうになったときとか」
映画の見過ぎだ。他人事だと思って勝手なことを言う。けれど、わたしもどこか他人事だった。紙切れに書かれた活字の名前を見ただけで、実感なんて湧かない。写真一枚残っていないのだ。それに、異国の地で夜空を見上げて話しているものだから、現実感がないのはなおさらだった。
「真珠は、本当のお父さんに会いたい?」
「分かんない」
「分かんない、か。相変わらずクールだよね」
わたしはクールなのだろうか。ほかの多くの女の子は、こんなとき、どんなふうに振る舞うのだろうか。ぐれたり非行に走ったり、育ててくれた父に、本当のお父さんじゃないくせに、と泣き叫んだりするのだろうか。真由ならどうする、ときいてみたかったのに、いつの間にか、昨夜誰かが誰かに告白したらしいという話が始まって、自分はいつ告白するかという真由にとっての重大問題に移っていた。わたしはその話に相槌を打ったり、適当にたきつけたりなだめたりしながら、分かんない、という自分の発言について考え続けていた。わたしは本当のお父さんに会いたいのだろうか。会いたくないのだろうか。
もし、向こうがわたしに会いたいと思っていたら会いたいけれど、そうじゃなかったら会いたくない。そんな結論にたどりついた途端、内臓がぎゅうと締め付けられるような苦しさに襲われた。圧倒的な星の中に、自分の体が浮かび上がって飲まれるような気がした。地面がなくなって、自分の体の一部が切り離されて消えてしまいそうな感覚。
「南十字星分かりましたか? 分からない人は手をあげて呼んでくださいね」
理科教師の甲高い声が、わたしを現実に引き戻した。
あれから八年が経った。今、目の前に広がっているのは南半球の夜空ではなく、人工的に作られた日本の春の夜空だ。博物館に入ってみたら、プラネタリウムが始まりますと案内されて、中に入ったのだ。
――ひしゃくの形をした北斗七星の柄の部分を延長した先にあるオレンジ色の星がアルクトゥルス、さらに同じだけ延長したところにある白い星がスピカです。
この曲線を春の大曲線といいます、とアナウンスが続ける。へえ、とわたしは素直に感心する。夏の大三角形という言葉はおぼろげに覚えている。あと、冬のオリオン座は見て分かる。でも、春の大曲線という言葉は初めて聞いた。
プラネタリウムなんて小学生のとき以来だ。たまにはこういうのもいいかもしれない、と思ったところまでは覚えている。新幹線の中であれだけ寝たはずなのに、わたしはまたしてもぐっすりと眠りに落ちていた。
マナーモードにしていた携帯電話を見ると、何件か着信が入っていた。あらかじめ登録しておいた瀬良敏和の番号だ。慌てて天文博物館の外に出て、電話をかけなおす。せっかく早めに来たというのに、待ち合わせ時間はとっくに過ぎていた。
「すみません。プラネタリウムを見ていました」
わたしが言うと、電話の向こうで瀬良敏和は、あれ、と言った。笑いを含んだような親しみのこもった声だった。
「じゃあ、もう上まで来てるんですね」
「早く着いたので、タクシーで来てしまいました」
じゃあ、博物館の前で待っていてください、と言われて電話を切る。わたしは深呼吸をして、乱れていた髪の毛を手で直した。
数分後、瀬良敏和が現れた。綿のパンツに白いポロシャツという格好で、すらりと足が長く、体も引き締まっている。五十歳近いはずなのに、四十代初めにしか見えない。研究者特有の偏屈な感じがしない。魅力的な人であることにほっとした反面、わたしは軽く失望もしていた。会った瞬間に、雷に打たれたように本当の親子であるという確信が体を走る、とか、そんな非科学的なことを心のどこかで期待していた。でも、そんな気持は湧いてこなかった。目の前にいるのは、感じのいい知的そうなひとりの男性研究者だ。
「あの、伊藤真理です」
言いながら、慣れない手つきで名刺を差し出す。普段は実験室にこもっているから、名刺の扱いが分からない。
瀬良は、ライター・伊藤真理と書かれた偽物の名刺をじっと見つめている。
「このたびはお忙しい中、取材を引き受けてくださってありがとうございました」
怪しまれているんじゃないかと思いながら、わたしは慌てて言葉を続けた。
「こちらこそ、わざわざ岡山まで来ていただいて、すみません」
瀬良はわたしに向かって微笑むと、名刺をポケットにしまった。
「望遠鏡、もう見ました?」
「いえ、まだです」
「今は一般公開用の時間だから、ガラス越しにしか見ることができませんが、一緒に見に行きましょうか?」
瀬良が背中を見せて歩き始めて、わたしはようやく緊張が解けて、力が抜けた。ライターであるということを信じてもらえた。いきなり追い返されなくてよかった。
山のてっぺんに見えていた丸い建物を目指して歩いていく。かなり急な斜面だった。日差しがきつかったけれど、風は冷たくて気持いい。ウグイスの声があちこちから聞こえた。
瀬良が、わたしのほうを振り向いて立ち止まった。
「足もと気を付けて」
斜面が急だからという意味だと思って、大丈夫です、と元気よく答える。
「いや、そうじゃなくて」
指差されて自分の足もとを見ると、そこにはうねうねと体を波打たせながら道を横切っていく派手な黄色の毛虫がいた。思わず、わ、と声が出た。よく見ると、道のあちこちに同じような毛虫がいて、右へ左へせっせと移動している。中には踏みつぶされてぺったんこになっているものもいた。
ひきつったわたしの顔を見て、瀬良敏和は笑った。
「自然がいっぱいでしょう」
ドームの中に入ると、大きなアブやハエが窓の隅を這っていた。それらを見ないようにして薄暗い階段を登っていく。虫は苦手だ。ひとりだったら、こんなに虫がいる建物には絶対に足を踏み入れないだろう。でも、階段を登り切って、巨大な望遠鏡を目にした途端、わたしは虫のことなんて忘れてしまった。それは望遠鏡と聞いて想像する形とはまるで違っていた。天に向けられた青い筒は、巨大な記念碑のように見えた。
「もうこの望遠鏡も五十歳を越えてますから、最前線というわけにはいきませんが。まだまだ現役です」
と、瀬良は言った。
「観測の時にはドームが開きます。外から見たら丸い屋根みたいになってたあの部分ごと、ぐりぐりと回転して、夜空のどの方向を見るかを決めるんです」
わたしがいつまでも望遠鏡に見とれていると、写真撮らないんですか? と、瀬良が言った。わたしははっとして、デジタルカメラを取り出す。
「あと、メモとか追いつかなかったら遠慮なく話を止めてください」
そうだ、取材なのだからメモを取らなくては、と、わたしは慌てる。
「あ、じゃあ、録音させてもらっていいですか?」
「構いませんよ」
買ったばかりのICレコーダーを取り出して、録音スイッチを入れ、カバンのポケットにしまう。これで取材の格好はつく。
「すみません。まだ新米ライターで、慣れていないんです」
わたしは下手な言い訳をした。
「じゃあ、前は別のお仕事をされていたんですか?」
「研究開発の仕事をしていましたが、先月辞めました」
とっさに、本当のことを言ってしまった。
「研究って、何の分野ですか?」
「物性化学です」
「そう。じゃあ、物理用語を使っても問題ないですね」
瀬良は波長の違いによる観測方法について説明を始めた。楽しそうに研究内容を話し続ける「父」を見ていると、わたしはだんだんさみしくなってきた。こんなふうに自分の好きなことを職業としてやり続けられたら、どんなに幸せだろう。もともとわたしは獣医になりたかった。でも、第一志望の獣医学科に落ちてしまい、物理が得意だったから、とりあえず後期試験で理学部物理学科に入学した。そこで仮面浪人をして獣医を目指すつもりだったけれど、物理の勉強が思いのほか楽しく、夢中になった。それで院に進み、企業で研究開発の職を得た。でも、その仕事も結婚をするために辞めてしまい、その結婚相手には逃げられた。何もかもが中途半端だった。中途半端なだけじゃない。今のわたしには何も残っていなかった。
もし、彼が母と別れなかったら、わたしは、この父のもとでどんな人間に育っていただろうか。でも、もしわたしが一緒にいたら、彼は今のように研究を続けられていなかったかもしれない。瀬良に会う前に、わたしは天文学者について少し調べた。物理系の院に進んだから、知り合いの知り合いをたどっていけば、天文学を専攻している人間にコンタクトを取ることはできた。電波望遠鏡のような、昼でも観測できる研究もあるが、この岡山天文台にあるような光学望遠鏡では夜の観測がメインになる。いったん観測が始まれば昼夜逆転の生活になり、何日も観測所に泊まりこむらしい。きっとその間は地上のことなど忘れているだろう。さみしがりやの母はそのことに耐えられなかったのかもしれない。それに子供がいたら、自由に海外に移動したりできないし、収入の面でも制約がある。
こんなふうに、もしも、のことを考えても仕方がないということが分かるくらい、わたしはもう大人になっていた。別れた恋人と二度と元の関係に戻らないのと同様、父と母も結婚し、わたしが生まれた時の関係には戻らない。なのに、目の前にいるもう一人の父を見ていると、そんな妄想が止まらなかった。
「研究内容よりも、人物に焦点を当てた企画ということでしたっけ?」
建物の外に出たときに、瀬良がたずねた。わたしは自分が出した取材依頼メールを思い出しながら、うなずく。
「岡山は初めてですか?」
唐突な質問だった。はい、と答えると、
「せっかくだから、僕の好きな場所に案内します。日が暮れる前に行きましょう」
「いいんですか?」
思わぬ提案に、わたしの心は浮き立った。
「研究所の中を案内してもいいんですけれど、研究開発の仕事をされていたんだったら、研究室がどんな感じかはもうご存知でしょう? 夜間観測の人たちが寝ているからあまり大きな声は出せないし、外に出たほうがいろいろと話しやすいかもしれません」
車回してきますので、下で待っていてください、と瀬良は言って、研究所の方へ歩いていった。わたしは、足もとの毛虫を避けながら、ひとりでゆっくりと坂を下っていった。
初めて本当の父の存在を知った十七歳のとき、インターネットというものはよほどのコンピューターオタクでない限り、触れたこともないというのが普通だった。でも、時代は変わった。インターネットで検索してみることを思いついたのは、大学院生のときだった。天文学者、瀬良敏和と入力して検索すると、あっさりとそれらしき人物が浮かび上がった。研究者としての詳細なプロフィールも載っていて、それを見ると、東京の大学院を出て研究員として岡山の国立天文台に所属し、そのあとアメリカに留学して、ハワイの天文台に在籍し、それから数年前にこちらに戻ってきて、ふたたび岡山の国立天文台所属の研究者となっているということが分かった。
わたしはとても混乱した。海外にいて連絡を取ることもできないと思っていた本当の父が、こんなにもあっさり見つかってしまった。研究所に電話をかけることもできるし、会いに行くこともできる。メールアドレスも載っているから、メールを出すこともできる。連絡を取れるということは、わたしは父に会うか会わないか選択できるということだ。
そのときは会わないという選択をした。でも、それ以来、わたしの心の一部は常に岡山にあって、何か重大な忘れ物をしてしまったような気持だった。いつか取りに行かなくてはいけない。そう思っていた。
その「いつか」は、婚約者に逃げられたときに訪れた。婚姻届を出す予定にしていた二日前に連絡が取れなくなった。あとで知ったことだけど、そいつは二股をかけていて、相手の女の子が妊娠したことが発覚して、わたしと結婚するのをやめて姿をくらましたらしかった。大学を卒業して以来、ずっと遠距離で付き合ってきたから、結婚を機に一緒に暮らすつもりだった。仕事をやめ、結婚相手を失ったわたしのもとに残ったのは、婚姻届に添えて出す予定だった一枚の戸籍謄本だけだった。
何もやる気がしなかった。その中で唯一、思いついた行動が、本当の父親に会いに行くということだった。ただし、娘だとは名乗らず、名前を偽って、取材という名目で。
「そんな面倒くさいことしないで、あなたの娘ですって会いにいけばいいじゃん」
高校時代からずっと縁が続いている真由は、わたしの案を聞くと、きっぱりと否定した。わたしが黙ると、言い過ぎたと思ったのか、
「まあ、いろいろ家庭の事情というものがあるんだろうけれど」
と、付け加えた。わたしはますます返す言葉がなくなってしまった。いろいろな家庭の事情なんてなかった。父も母も、もう大人なのだから会うか会わないかは真珠が判断したらいいと言っていたし、そもそも母は瀬良敏和に娘と会うことを禁止したわけではなかった。会えない事情があるとしたら、向こうの方だ。だからわたしは娘だと名乗るのが怖かった。名乗ったせいで会うのを拒絶されたら、もう、手詰まりだ。自分の父親がどういう人なのかを知るチャンスがなくなる。
「取材依頼メールの下書き見てくれた?」
真由の職業は編集者だ。わたしが「取材」という手段を思いついたのは、真由の影響だ。
「ああ、あれ? 全然ダメだった」
一生懸命書いたのに、ひどい言いようだ。
「まず、天文学者を取材したいっていう理由だったら、わざわざ岡山まで来なくても東京の研究者を紹介しますって言われるのがオチでしょう? なぜ、その人じゃないと駄目なのかってことが分かるように書かなくちゃ。あと、嘘の出版社や雑誌名を出すのもアウト。今はネットで何でも調べられるんだから。フリーランスでライターをやっていて、持ち込みの記事で、まだ企画段階で形になるかどうか分からない、くらいに書いておけば、実際に記事にならなくても言い訳はつくでしょう。あと、真珠が知りたいのは研究内容じゃなくて、お父さんの人生のことなんだから、天文学について知りたいなんて書いたら、延々と研究の話をされて、下手したら、ほかの研究者の話も聞いてみたらって、あちこち連れまわされるかもよ。人物に焦点を当てたドキュメントを作りたいって説明したほうがいいと思う」
確かに、とわたしはうなった。さすがプロは違う。
「あと、国立天文台って国の機関でしょう? 取材するなら許可がいるかもしれないし、そうなると面倒だから、もし差支えがあれば名前を出さないフィクション形式のドラマにするとか、実在の名前や機関を出すときは、事前に必ず記事をチェックしてもらって勝手なことは書かないとか約束すると、取材に応じてくれやすいかも」
なるほど、と言って、わたしはさらにうなった。
「で、どう書けばいいの?」
「もういい。説明するの面倒くさいから、わたしが書く」
しびれを切らして、真由はそう宣言した。
「それより、大丈夫?」
何が、と答えたけれど、真由が婚約破棄の件について言っていることは分かっていた。
「真珠さ、慰謝料請求できるよ」
「相手がお金持ってなければ請求できないよ。わたし知らなかったんだけど、あいつ、借金抱えていたみたい」
「最悪。ほんと、結婚しなくてよかったね」
たとえ請求できるとしても、争う気力がなかった。何年も付き合って信頼していた男がそんな人間だったことと、自分がそれを見抜けなかったことに失望していた。
「しかし、やっぱり真珠はクールだね」
と、真由は言った。
「そうかな。一応落ち込んでいるんだけど」
控えめに反論したけれど、わたしなら包丁持って相手の実家に押しかけるね、という真由の言葉に苦笑いした。真由に比べたら誰だってクールな部類に入るだろう。
電話を切って一時間も経たないうちに、真由から完璧な取材依頼メールの見本が届いた。わたしは伊藤真理という仮名を使って、瀬良にメールを出した。
瀬良からの返事はすぐに来た。取材を受けていいという文を見て、あまりにもあっさりと進んでいくことが恐ろしくなった。でも、ここまで来たら途中でやめるわけにはいかない。何度かメールのやりとりをして、取材に行く日を決め、わたしはライター・伊藤真理という名刺を作って、この岡山にやってきた。そして今、瀬良の運転する車の助手席に座っている。
運転しながら、瀬良は、いろいろな話をしてくれた。ハワイにいた時の話、岡山で過ごした思い出、アメリカで出会った困った教授の話。車で一時間ほど走ると、鷲羽山という看板が見えた。
「わしはねやま?」
わたしが尋ねると、
「わしゅうざん」
と、瀬良は言った。どこかで聞いたことがあるような地名だった。ここから山道になるから、酔わないように気を付けて、と瀬良は言った。でも、カーブの多い山道も、不思議と気分が悪くならなかった。瀬良の運転がうまいのかもしれない。あっという間に目的地に到着した。
「あれを登ったところに展望台があるから」
広々とした駐車場の先に長い階段があった。今日は登らせてばかりだけど、と瀬良は笑う。日頃の運動不足を見破られないように、わたしは息が切れるのを我慢して階段を登っていく。登り切ったら、目の前に半透明の布を広げたような海が広がっていた。瀬戸内の海は穏やかだと話に聞いたことはあったけれど、こんな静かで美しい海を初めて見た。湖のような、透明のゼリーのような水面だった。その中に緑の島々が顔を出し、船がゆっくりと横切っていく。船が進んだあとに柔らかなしわが寄り、広がって消えていく。優しいという言葉が一番ぴったりとくる穏やかで美しい光景だった。
「あの橋が瀬戸大橋ですか?」
島と島を結んでいる白くて優雅な橋を指さしてたずねると、瀬良はうなずいた。橋の先に見えているのは四国だった。
「ここからの眺めも充分きれいだけど、あと十分ほど歩けば山頂にも行けますよ。三六〇度、すべての景色を見渡すことができますけど、どうしますか?」
「絶対に行きます」
力強く答えたら、瀬良が苦笑した。息が切れても、筋肉痛になっても、そんな素敵な場所があるのならぜひとも行きたかった。
坂を上っていく。木々の間からさっきの場所からは見えなかった島々が見えた。乱れた息を隠していたつもりだったのに、結構しんどいでしょう、と瀬良に言われた。
「そんなことないです」
と、わたしは強がった。瀬良のほうは毎日展望台に続く道を行き来しているからだろうか。軽い足取りで歩いていく。道を上がっていくと、最後にこじんまりとした岩山が見えてきた。
「この上です」
まずは瀬良が手本を見せるように、よじのぼった。差し伸べられた手を握るのが恥ずかしくて、ひとりで大丈夫です、と答える。足場に注意しながら、岩によじのぼる。体を引き上げたとたん、絶景が目の前に広がっていた。橋も海も島も海岸沿いの家々もすべて見える。傾きかけた夕日がきらきらと水面を光らせて、空がピンク色に染まっていた。その光景に、わたしはすっかり心を奪われてしまった。
黙って見とれているわたしの隣で、瀬良も黙っていた。わたしはもう最初の目的も、自分がライターで取材だと偽っていたこともどうでもよくなっていた。この景色をこの人と一緒に見たことを、一生覚えていようと思った。それだけで十分だった。
「プラネタリウムを見たのなら、春の星座の見つけ方を解説してたでしょう?」
瀬良は岩に腰をかけて夕暮れの空を見上げていた。
「北斗七星があって、その柄を伸ばした先にアルクトゥルスとスピカがあるってやつ」
「はい、見ました」
わたしは、自信を持って答えた。その部分だけは眠らずにしっかりと見ていたから、よく覚えている。
「あれ、便利だから覚えていてください。ちなみに今、スピカはあの辺りにあります」
瀬良は夕日と反対側の海に近い位置を指さした。見えるのだろうか、と目を凝らしたら、見えませんよ、と瀬良は笑った。
「今の季節、夜になったら見えます。たぶん、明るい星だから、東京でも見えるでしょう」
夕日を背にして、瀬良は空を見上げていた。斜めに差す日が彼の顔に陰翳をつけて、最初に会った時よりも年を取って見えた。でも、穏やかで優しい顔だった。
「僕は自分の娘が生まれた瞬間、岡山の天文台にいました。どうしてもやらなくてはいけない観測があって、病院に駆けつけることはできなかった。でも電話で生まれたという知らせを聞いて嬉しくなって、外に飛び出した。そのとき見た夜空は人生で一番きれいだった。降るような星空だった。その中で、スピカが白く気高い光を発して輝いていた。その光景は今でも忘れられません。スピカの和名は真珠星といいます。あなたの名前はそこから取りました」
わたしは言葉を失ったまま、瀬良敏和を見つめた。
「名前は違ったけれど、メールアドレスにshinjuという語が入っていたから、もしかしてと思ったんです。いや、もしかしてというよりも、このメールがあなただったらいいなと思いました。別人がやってきて、がっかりさせられてもいい。可能性があるのなら会おうと思った。そして、今日、一目見て、自分の娘だと確信しました」
ここ、よく来ていたんですよ、と瀬良は言って立ち上がった。
「まだ幼かったから、覚えてなくて当然です。小さかったあなたは、何回来ても、この山頂にのぼりたがりました。そしてこの岩に座って、いつまでも景色を眺めていた。もう行こうと言っても、もう少しと言い張って、びくとも動かなかった。今日のあなたを見ていたら、昨日のことのように思い出しました。二十年以上経っても、同じ行動をするんだと思って、おかしかった」
目の前にいる瀬良敏和が、わたしの知らないわたしの話をするのを聞いて、涙があふれて止まらなくなった。悲しいのか、つらいのか、嬉しいのか分からなかった。さみしいのかもしれない、と思った。決して取り戻せない時間があることを知ってしまったことが、さみしいのかもしれなかった。
「スピカは春の星座を構成する星ですが、一年中、どこかの時間にどこかの空にいます。ほかの季節は太陽があるから見えないだけなんです。僕はどんな場所にいても、どんな季節でも、スピカの位置は分かります。スピカを見てはあなたのことを思い出していたつもりだった。でも、それは間違っていた。今、目の前にいる真珠と、僕の記憶の中にいる真珠の間にいたはずの真珠を一度も見なかったことを、僕は一生悔やむかもしれない」
一度だけ、母が、わたしと瀬良敏和が似ていると言ったことがある。本当の父親を知ってもまるで取り乱さなかった真珠を見ていたら、何だか、あの人を思い出した。真珠のドライなところ、あの人にそっくりだ、と。
母の言わんとしていることはよく分かった。この人とわたしはよく似ている。似ているから、よく分かる。ドライでもクールなわけでもない。臆病なのだ。自分のせいで誰かが迷惑がかかるのが怖くて、自分の感情をぶつけて拒絶されるくらいなら、自分から去ったほうがいい。そんなふうに生きてきた。
「会いに来てくれてありがとう」
わたしは目をつむった。今まで感じたことのない穏やかで安心した気持だった。それはわたしの体の記憶だった。わたしの体はきっと覚えている。この土地も、わたしとよく似たこの人と過ごした時間のことも。
〈了〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
