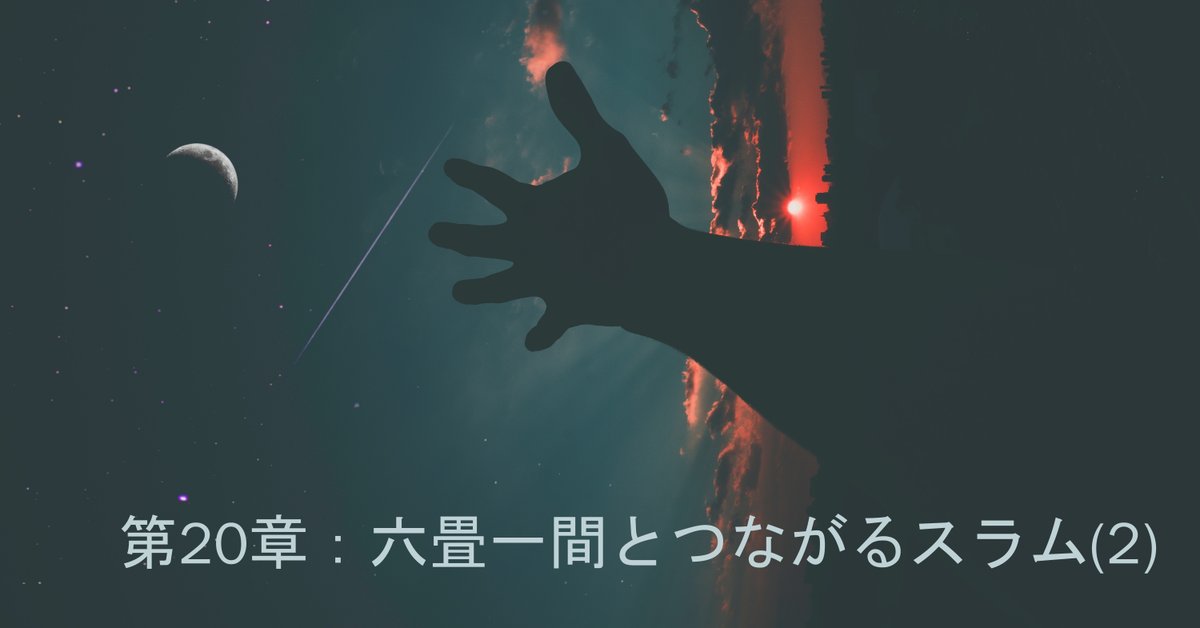
月面ラジオ { 20: "六畳一間とつながるスラム(2)" }
あらすじ:(1)30代のおばさんが、宇宙飛行士になった初恋の人を追いかけて月までストーカーに行きます。(2) 失恋した月美はダメな大人になりました。
◇
◇
白い壁にたくさんの花が咲いたようだった。
立ちならぶ家の壁の落書きが、オレンジ色の街灯の下で花畑のようなのだ。
壁紙スクリーンに夜の街が映しだされていた。
ブラジルの街、ファベーラ・サンタ・マルタだ。
サンタ・マルタは、南米に無数ある巨大スラムの代表格だ。
丘の麓から頂きまで、三歳の子どもが散らかした積み木のように、無造作に家をならべて作った街だ。
「家の上に家を建てていけば、こうなるんだ」と、我々に知らしめてくれる景観で有名である。
そのすべてが無許可のうちに建てられたという。
ここには行政から許可されたものはなに一つない。
中に入ればさながら迷宮で、素人が入り込んだら最後、急な坂道とせまい階段につまずきながら、無数の曲がり角を探索しなければならない。
もちろん月美はスラムに行ったことはないのだけれど、街角の風景を見ただけでそれが想像できた。
数万人もの人間が、この大きな迷宮でフェジョアダを食べ、服を着替え、ぐっすり眠る毎日を送っているそうだ。
壁紙スクリーンに映し出されたその光景は、さながら一枚のパノラマ写真だった。
六畳一間とつながるスラムというわけだ。
スプレー缶で描かれた落書きだらけの家壁の間に、エアコンの室外機と、盗電用の電気ケーブルが並ぶ手狭な階段があった。
手前の道はオレンジの街灯で明るいのに、階段の上は暗くてよく見えない。
そんな階段のいちばん下に、若い男が腰をおろしていた。
芽衣の友人のファビニャンだった。
「こんばんは、ファビニャン。相変わらず、夜ふかしなのね。」
芽衣は英語で話しかけた。
月美も芽衣も、電脳秘書の通訳の世話にならないくらいには英語を話せる。
ファビニャンというのはあだ名かなんかで、きっとほんとうの名はファビオだと月美は推測した。
年齢は芽衣と同じくらいで、きっと学生だろう。
あたりがうす暗いせいもあって、月美にはファビニャンの人種がよくわからなかった。
ヨーロッパ系とアフリカ系の混血なのだろうけど、よくよく見ればアジア系か先住民にも思えるので、不思議な印象だ。
洗濯したばかりの白いシャツを着ていた。
襟元までボタンを締めている。
青いチノクロス・スラックスを履いていたが、きっといいブランドのものだ。
スラムでは、あまりお目にかかれない出で立ちだった。
若者はいかにも「散歩中に電話をとった」というような雰囲気を醸してはいるが、どちらかと言えば「ホーム・パーティーのホストとして玄関で出迎えてくれた」ように見える。
短く整えられた茶系の髪と、黒い縁の大きな眼鏡がその若者をいっそう知的に見せていた。
「夜のスラムを散歩しながら……」
ファビニャンが口を開いた。
「ロボットを動かす新しいアルゴリズムを作っていたんだ。」
「そんなことができるのか?」
月美は驚いて言った。
「このスラムは街そのものがデジタル化されているからな。ブラジル政府による貧困層の生活改善の一旦で、デジタル化がはじまった。俺たちがうまれるより前の頃の話さ。いまじゃ、誰でも無料でネットが使えるし、街中が壁紙スクリーンであふれている。」
しばらくすると、壁の落書きが消えた。
原色の落書きの代わりに、モノトーン調の絵画がいきなり現れた。
牛と馬、それに嘆き悲しむ人たち……
ピカソのゲルニカだった。
「街中がこんな感じなのさ。落書き対策で始めた壁のデジタル化だけど、落書きがないとスラムらしくないといって、いまでは落書きを再現している始末だ。こんなこともできる。」
ファビニャンがわきに置いてあったものを手にあった。
それは少し大きめのキーボードデバイスだった。
ファビニャンはキーボードを膝の上に置き、キーを打ちこんだ。
ゲルニカが消え、今度はコンピューター・プログラムの文字の羅列に置き換わった。
ファビニャンの指が踊るたびに、壁の上の文字が淡々と置き換わっていく。
すると、芽衣の腕の中から粗茶一号が飛びだし、クルクルと回転しながら「こんにちは、世界のみなさん」と電子合成音でアイサツをした。
「手に馴染んだインターフェースさえ持ち歩けば、好きな時に好きな場所で仕事ができる。」
「トランペット奏者が街角で演奏するみたいだね。」
芽衣が言った。
「街そのものがコンピューターだし、そこらじゅうに電脳秘書が潜んでいるんだ。世界中とつながっているから、芽衣のスラムとも気軽に通信できる。」
「あのね、ファビニャン、ここは私の家じゃなくて、親戚の家なの。それに部屋は汚いけどスラムじゃない。」
自分の部屋をスラム扱いされて呆然とする月美を横目に芽衣が説明した。
「スラムの街そのものがデバイスだなんて。」
芽衣が感心した。
「技術が進んでるのね。おどろいちゃった。」
「そのうち、サッカーをしながらでもプログラムができるようになるよ。」
ファビニャンが答えた。
「ところで何かようかい? 俺たちの息子のことか?」
「そう!」
芽衣は、本題を思い出して手を叩いた。
「粗茶一号に改良を加えたいの。」
お手製のロボットを膝に抱えながら言った。
「せっかく電磁浮揚をさせるなら、せめてカップを三つ同時に持てるくらいにしたいと思わない? 制御システムの改造ってすごく難しいけど、あなたの神業のようなコーディングならなんとかなるわ。」
「なるほど、挑戦のしがいがある。」
ファビニャンは唸った。
「けど、カップの数は足りるのかい? 前にテストした時は、君の叔母のティーカップをさんざん割ってしまったじゃないか。」
「まだいくつか残っているから大丈夫だと思う。」
「いまなんて?」
月美がおどろいて言った。
「そうなると、あとはスケジュールの問題だな。なんとかコンテストに間に合うようにタスクを組み替えないと……」
「ねぇ、前から気になってたことがあるんだけど……」
芽衣がもったいぶった調子で言った。
「ブラジルに住んでるくせになんでスケジュールのことばかり気にしてるの?」
「とんだ偏見だ。」
ファビニャンは憤慨した。
「ラテン系がみんな時間に対して無神経なわけじゃない。神経質なブラジル人や、サッカーが嫌いなブラジル人だっているさ。とにかく機能の拡張となると時間が惜しい。明日までにプロトタイプを実装してみるから、そちらで一度テストしてほしい。」
「そう。よろしくね愛してるわ。」
「俺もさ。じゃあな。」
映像がぷつりと途切れた。
六畳一間の一角は、ただの白い壁紙に戻った。
壁紙の一角でトム猫さんがベッドに潜って眠りこけていた。
「つまり、そいつが例のロボットか?」
月美が口を開いた。
「そう。今度クアラルンプールであるコンテストに出品するロボット。災害現場の補助ロボット部門で金獅子賞をとるつもり。やっと動くようになってきたから、月美ちゃんにお披露目したてわけ。」
「チームは何人だ?」
「三人。ハードウェアは私。ソフトウェアはファビニャン。操縦者はマレーシア人の高校生が担当するの。誰とも直接会ったことはないけど、みんな仲良しよ。ちなみに私、いまファビニャンと付き合っているわ。」
「会ったこともないのに?」
「初めて合う場所は月の上って決めてるの。ベッタリとよりそうことだけが愛のカタチじゃないしね。」
「気の長い話だな。」
月美は肩をすくめた。
「ところで月美ちゃん。仕事はもう終わり?」
「うんにゃ。論文を書かなくちゃいけない。次の学会ではぜったいに採択されたいんだ。」
「原稿はほとんど完成してるんでしょ? さきにご飯を食べようよ。」
「いいよ。」
月美は言った。
◇
マグロが残っていたので、夕食は「漬けマグロのドンブリ」になった。
マグロの切り身を醤油と味醂とごま油のタレで漬けこんで、ご飯にのせるだけの料理だ。
マグロを切り身にして、調味料を用意して、漬け込んで、ご飯を炊くのは芽衣の役目で、炊いたばかりのご飯をたらふくドンブリによそえるよう炊飯器の前で待機するのが月美の役目だった。
「月美ちゃん!」
ソウメンを茹でている最中に芽衣が大声で指示した。
「他にやることがないなら、シソの葉っぱとってきてよ!」
「シソ? 裏庭の雑草のことか?」
「そんなわけないでしょ。鉢植えで栽培してるから、それをとってきてほしいの。洗ってちぎってご飯に乗せるだけだから! あ、待って。やっぱり先に八方だしを取ってきてよ。月美ちゃんの冷蔵庫に入ってるから。ついでにお味噌汁も持ってきてね。そろそろソウメンも茹で上がるよ。」
「あいよ!」
月美はきっぷよく返事して、芽衣の部屋を出た。
自分の部屋に戻ると、月美は鍋をおいたコンロに火を入れた。
貧乏アパートなので、コンロは部屋にひとつしかない。
芽衣の部屋ではソウメンを茹でて、月美の部屋では味噌汁をわかしているのだ。
夏の太陽が月美たちを激励しているかのようで、湧いた鍋はあっという間に月美を蒸しあげた。
それでも暑い日に熱い味噌汁を、クーラーの効いた部屋でのむのはたまらなく幸せなのだ。
月美は、暑さから一時的に避難するために冷蔵庫を開けた。
八方だしは芽衣が勝手に月美の冷蔵に入れていたようだけど、他にも醤油や黒酢やサワークリームなどの見知らぬ調味料がたくさんあった。
ふと思い立って冷凍庫を開けてみると、肉と鮭の切り身、それにアイスクリームの山がそこにあった。
「おい、なんだこれは!」
月美は隣の部屋に向かって叫んだ。
「私の冷蔵庫だぞ! 勝手に使いすぎだ!」
「べつにいいでしょ! 月美ちゃん、どうせ缶ビールしか入れないんだから。」
すぐに芽衣が怒鳴り返してきた。
「こっちの準備はもう終わるから、さっさと八方だし持ってきてよ!」
さっきまで地球の裏の人間と話していたのに、いまは壁越しにどなりあっている。
「芽衣のやつ……」
月美はブツクサ言いながら芽衣の部屋に味噌汁を運んだ。
「どんどん陽子に似てくるな。」
◇
「ねぇ、月美ちゃんはなんでその人に恋をしたの?」
芽衣が布団の中で尋ねた。
月美はゆっくりと、珍しく言葉を選びながら答えた。
「気がついたら好きになっていた。たぶん出会った瞬間に好きになったんだと思う。」
月美と芽衣は別々の部屋に住んで入るけれど、夜は布団を並べて一緒に寝ることも多かった。
今夜は月美の部屋で寝ている。
布団の中から見上げると、古びた窓の上に満月があった。
灯りを消した六畳一間は、いつもより明るかった。
夜の畳の匂いがやけに強く感じる。
となりで寝る芽衣は、子どものように見えた。
「もう結婚しているんじゃないの?」
芽衣は静かな声で言った。
「子供もいるかもしれない。『月生まれ』だって珍しくない時代だし。」
「そうかもしれない。いや、きっとそうだろうな。でも会いたいんだ。」
月美は言った。
「うっとうしいと思われそうで怖いな。なんだろう……どんどん自信がなくなっていくよ。」
「大丈夫だよ。人に好きって言われてイヤな人なんていないから。」
「だといいんだけど……」
月美は天井を見上げたままつぶやいた。
ひとりの男を思いつづける自分が信じられなかった。
青野彦丸とはもう二十三年も会っていないというのに。
月美は芽衣と寝る時によく自分の思いの丈を語る。
中学生の時に大失恋をしたこと。
高校のきびしい入学試験を乗り越え、それがきっかけで勉強を好きになったこと。
そのまま大学に入って、ついには物理工学の研究者になったこと。
自分を捨てたあの男を見返してやるために、月に行って、月で偉大な研究をしたいと思うようになったこと。
一時は挫折したけど、芽衣と出会い、ふたたび月を目指すようになったこと。
彦丸と出会って月美は月を目指すようになった。
彼がいなければ研究者になることも絶対になかっただろうし、人生はつまらないものだったかもしれない。
でも月への道のりはあまりに遠かった。
芽衣と知り合って十年が経つけれど、いまだに月行きの足がかりすらつかめない。
「自分は月に行けないかもしれない。そんなふうに心の底で思いながら、いつもそれをふり払うのに必死なんだ。」
月美は小さな声で続けた。
「画期的だと思っていた考えが、実はだれでも思いつけるような平凡なものだった。自分はその程度でしかないという真実を突きつけられるようで怖いんだ。なぁ、芽衣、お前もやっぱり不安になるのか? ちかごろお前はなんだか焦っているような気がする。」
「次が最後のチャンスかもしれないの……」
芽衣は言った。
「最後のチャンス? 月面大学なら何歳になったって入学できるチャンスはあるだろ?」
「木土往還計画って知ってるでしょ?」
「もちろん。木星と土星がほぼ同時期に地球に接近する奇跡のようなイベントが間もなく起こる。そのタイミングを見計らって木星と土星の両方いっぺんに行っちまおうっていう壮大な計画だ。いま月では特大宇宙船が開発中で……ってまさか、芽衣?」
月美は驚いて布団から起き上がった。
「うん。」
月美を見つめたまま口のあたりまで布団に潜りこんで芽衣は答えた。
「木土往還宇宙船のクルーになりたいの。三年以内に募集が始まるから、その時まで月に立っていなければ話にならない。」
「最近、ロボット操縦技師の免許をとったり、フルマラソンの大会に出ていたけど、それと関係あるのか?」
「ほんとはエンジニア職だけで応募したいけど、すでに実績のある人たちには勝てないから……」
布団の中からくぐもった芽衣の声が聞こえた。
「だから色々なことができるようになりたくて……宇宙船のクルーになるなら体力も要るし……」
木土往還計画には莫大な資金が投資されている。
古臭い表現だけど「国家予算に匹敵するほど」なのだ。
二惑星同時最接近の機会を逃したら、人類は向こう百年は外惑星に行けないかもしれない。
だから芽衣は焦っているのだ。
外惑星の開発に成功すれば、無限のエネルギーを人類は手に入れる。
無限ではないが、どうせ使い切れないほどだから無限と同じだ。
エネルギーさえ足りていれば、これまでやりたくてもできなかったことがすべて実現できる。
戦争をこの世からなくせると言う人もいるくらいだ。
「冗談だろ……」
月美は言った。
「芽衣、お前にとって月は踏み台か?」
「まさか。」
芽衣は首をふった。
「月に行くだけでも、すごく大変なことだよ。でも行くことだけを目標にしちゃだめなの。そこで何かを成し遂げなくちゃ。そこでしかできないことを……私しかできないことを。月美ちゃんもそうでしょ?」
「あぁ……」
月美は寝たままうなずいた。
「だから私は月を目指すの。月よりも遠い場所まで行くために。」
「芽衣……お前はやっぱすごいやつだよ。」
月美は心の底から感心した。
やがて寝静まった芽衣を横目に月美は彦丸のことを思った。
あいつはいま地球を見上げているのだろうか?
それとも木星や土星、あるいはもっと遠くの星を見つめているのだろうか?
風のまったくない夜で、芽衣の静かな寝息だけが聞こえた。
あとは冷蔵庫のモーター音がたまに聞こえるくらいだ。
私たちは、こんなにも狭い部屋で寝ながら宇宙を目指している。
ほんとうにあそこまで行けるのだろうか?
月を見ると切なくなる。
遠すぎて。
月美は幻想的な眠りについた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
