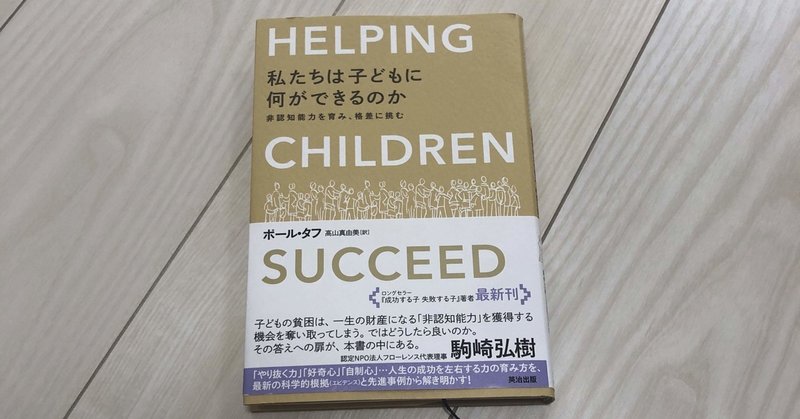
お勧め本【私たちは子どもに何ができるのか:Helping children succeed】
子育て、教育に関わる全ての人に読んで欲しい。
個人的には、前作の「成長する子・・」よりも少し内容も進んでおり、具体的で読みやすかった。
親子間の負のスパイラルはよく言われるけど
貧困・家庭内不破など、家庭環境が悪くても、
育ての母が子供の感情に敏感であれば、子供のストレス耐性・記憶力などに影響はない
という著者の主張が何より新鮮だった。
もちろん環境が整っているのは発育上ベターではあるものの、
そうじゃない場合にも精神的ケアで担保できる。というのは救いになる。
参考になったポイントと私の解釈をまとめておく。
📗📕「学力」よりも「非認知能力」がその後の人生に影響を与える
「非認知能力」「ソフトスキル」
グリット(やり抜く力)、好奇心、自制心、楽観的なものの見方、誠実さ・・
といった気質を指す
自制心や楽観的なものの見方が育たず、
「キレやすい子供」と言われるのは「非認知能力が低い子供」とも捉えられる。
環境変化も目まぐるしく、正解がない昨今において
「計算ができる」「文章がうまくかける」など学力的なもの、知識やスキル
ではなく「非認知能力」の高さが重要視されている。
いくら学力向上のための施策を投入したり
語彙や読み書きスキルをインプットしたり
しつけとして厳しく指導したり
詰め込み教育をしてみても
「非認知能力」をしっかりと育てられないと
自律ができず結局は大人になってからつまづいてしまう。
📗📕非認知能力に影響をあたるもの
「非認知能力」はスキルとして教えることはできない。
子供を取り巻く環境の産物として、非認知能力が習得される。
つまり、「子供に何を教えるか、学ばせるか」ではなく
「子供にどのような環境を準備するか」
を大人は考える必要がある。
【ネガティブ要因】
・幼少期の慢性的なストレス
・家庭環境の機能不全
・ネグレクト
【ポジティブ要因】
・アタッチメント(愛着)
↑貧困・家庭内不破など、家庭環境が悪くても、
育ての母が子供の感情に敏感でアタッチメントがうまく形成されていれば、子供のストレス耐性・記憶力などに影響はないというデータも。
📗📕親や周囲はどのようにサポートが可能か(幼少期まで)
アタッチメント(愛着)を育むこと。
子供の言動に対して、関心を示し反応する。
「あら、痛かったねえ」「そうだね、わんわんだね」
子供が動揺、緊張しているときにストレス対処の手助けをする。
「これができなくてイライラしたのね、貸してごらん」
行政などの支援の場合は、親がそのような関わりをするよう
やり方を伝えるだけではなく、親自身への心理面、感情面の支援が重要。
📗📕親や周囲はどのようにサポートが可能か(それ以降)
幼少期以降は、生活における「学業」の締める割合が大きくなり
「学業へのスタンス、自信」そのものの影響が高くなる。
そのため、「人間関係」のみではなく「学習指導」も無視できない要素である。
デシとライアンの3つの内発的動機付け
「自立性」「有能感」「関係性」
学校であれば
・私はこの学校に所属している
・私の能力は努力によって伸びる
・私はこれを成功させることができる
・この勉強は私にとって価値がある
と生徒が思える支援をする。
例:「ポジティブな感情で」「高い期待をする」
教師と生徒、生徒同士の「人間関係」はここでも極めて重要。
人間関係の助けも借りながら、課題に粘り強く取り組み、
苦労してやり遂げる経験が「有能感」と「自立性」を生み出す。
#買ってよかったもの
#読書感想文
#推薦図書
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
