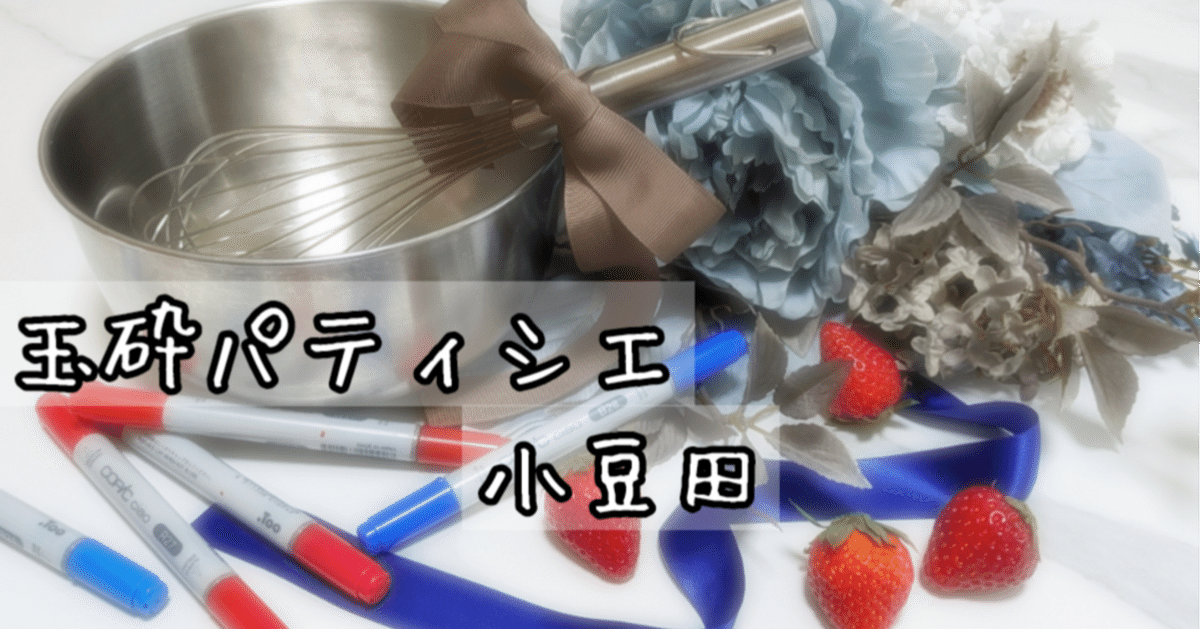
玉砕パティシエ小豆田⑨
五.カトルカールをまたいつか
『FUKUSHI』で働いていて一カ月が経とうとしている。が、それでもわからないことがある。
柏森さんが、なぜ離婚したのか、だ。
小豆田さんのように変た、ではなく、特殊な嗜好を持ち合わせているわけではなく、わらびさんのように情緒不安定な面があるわけではない。
どちらかといえば、いたって普通なのである。
真面目で、几帳面で、時に面倒見がいい。それは彼が作るケーキを見ても、商品出しの際の並べ方を見ても、私にマドレーヌをくれた時のラッピングを思い出してもわかるし、小豆田さんの躾とわらびさんの面倒を見ている姿からもわかる。
一般的に世間が結婚相手に求める、誠実さや真面目さは、完璧なほど備わっている。
裏を返せば几帳面過ぎたり気難しそうにも見えるが、果たして原因は何なのだろう。
定休日前の営業日、そのお客様はやってきた。
ハーフパンツから覗く膝小僧は、もう治っているが擦り傷の跡が残っている。黒いランドセルも、大分傷が入って皮が捲れている箇所がある。相当使い込んでいるようだ。高学年になるとリュックサックに変える人も珍しくないだろうに。一年生の頃から、ずっと使い続けているのだろう。小さな体、と表現するほどの体格ではないから高学年だろうか。
店に入って来たのは、小学生の男の子だった。
『FUKUSHI』に訪れるお客様としては、非常に珍しい。
少年はランドセルの両肩紐をそれぞれ手で握り締めて、一直線にレジにやって来た。
「カシワモリいますか?」
はきはきとした喋りだった。
このくらいになると、子供でもしっかり話せるのか。自分が小学生だった頃の記憶などもはや曖昧で、目の前にいるその少年を通してしか、判断ができなかった。
そんなことを考えていた所為か、少年の言ったことを、上手く処理できなかった。
「こんにちは。今呼んで参りますので、少々お待ちくださいませ」
聞き返そうとしていたところでわらびさんが少年に気付き、売り場を後にした。
数分後、彼女は柏森さんと一緒に戻ってきた。
「優光、一人で来たのか?」
「うん、お母さんが明日、仕事が入ったから、好きなの買って来ていいって」
「わざわざ伝えに来てくれたのか。ありがとな」
そう言いながら、柏森さんは少年の頭を撫でた。
普段気難しそうな顔をしている彼からは想像できないほど、顔を綻ばせて。
「どれにするか決まってるか?」
「長いケーキ!」
「長いケーキのどれにする?」
「チョコ!」
長いケーキ、とはパウンドケーキのことらしい。
バター、砂糖、卵、小麦粉の四つが基本の材料となっている。通年商品で、季節によっては栗やシトロンなどの限定商品を出す。今は抹茶が季節限定になっている。
他のケーキには目もくれず、パウンドケーキを即答した少年は、ランドセルから財布を取り出した。
「学校からそのまま来たのか?」
「家に帰って、財布取ってきた」
「荷物置いてきたらよかったのに。重くなかったのか?」
「中身は出してきた!」
ランドセルは鞄代わりらしい。少年は柏森さんに中を見せるようにランドセルを傾けた。その拍子に、私達にまで中身が見えた。わらびさんがくすりと笑う。それから思い出したようにショコラパウンドを包み始める。いつもよりゆっくりした手つきだ。
「鞄無いのか?」
「あるけど、なんかメンドかった」
「ランドセルの中身出す方が面倒じゃないか?」
「んー」
少年は時折体をくねらせながら、柏森さんの言葉に答えていく。落ち着かない様子だが、顔は笑っている。嬉しいとか恥ずかしいとか、そういう感情が見え隠れする。
会計が終わって、少年がおつりを財布にしまったところで、わらびさんは袋に入れたショコラパウンドを柏森さんに渡し、柏森さんから少年の手に渡る。
「気を付けて帰れよ」
「うん。あ、小豆田!」
少年は私達の後ろにある窓を見ながら叫んだ。
振り返ると、小豆田さんが片手にボールを抱えて、窓からこちらを覗き込むようにして少年に手を振っている。普段売り場で見せる接客用の整った笑顔ではなく、就業前や就業後に見るような、少し無邪気な笑顔だった。少年も同じような顔で手を振り返した。
「またねー!」
少年はそう言って手を振りながら店を去る。私もつられるようにして手を振った。
「柏森さん、明日の予定無くなったんなら、マティーニ奢ってくださいよ」
何事も無かったかのように話し始めたのは、わらびさんだった。
スッといつもの気難しそうな表情……の中に若干の哀愁を含んだ柏森さんが答える。
「このタイミングで言うな。こっちは楽しみにしていた予定が無くなったんだぞ」
「この前奢ってくれるって言ってたじゃないですか。そのついでに励ましてあげますよ」
どうやら、あれだけ大泣きしていたのに、その部分はしっかりと覚えているようだ。
あまりにも普通に雑談を交わしながら業務に戻ろうとしている二人を見て、思わずタイミングを逃してしまいそうになる。
「あの、さっきの子は……? 常連さんのお子さんでしょうか……?」
わらびさんはいつものふわりとした笑みを湛えて黙ってしまった。
彼女のこの笑みは、自分を守る鎧でもあるのだろう。なんとなくそう思った。
少し居心地悪そうに逡巡した後、柏森さんは、
「あー……、俺の子だ」
歯切れ悪く言った。
私の脳内で、特定の曜日に放送されていたサスペンスドラマのテーマ曲の冒頭が流れた。
なんだか、ショックだった。
私は別に柏森さんを恋愛的に好きだとか、そういう感情は一切無い。
だから例え彼が今離婚していなかったとしても、新しい恋人がいたとしても、別になんとも思わなかっただろうし、おめでたいとも思えただろう。
なのに、なぜかショックだった。
それは勿論、深層心理では柏森さんを恋愛対象として好いていたからでもない。
例えるなら、「清純派アイドルが熱愛報道を飛び越えて、妊娠したから結婚しました」報道を見たファンと、同じ気持ちかもしれない。
当然ながら、柏森さんはアイドルではないし、どちらかと言えば小豆田さんの方がアイドルに例えても納得できる。いや、これらは全く論点とは関係無い。自分が相当ショックを受けると同時に動揺しているのだと自覚した。
それでもミス無く仕事ができたのは、「燈架さーん、まだ今日のお仕事は終わってませんよ」と語尾にハートが付きそうなやさしーい声と笑顔で喝を入れられたからだ。
就業後、柏森さんに子供がいたと知って私が謎のショックを受けている、と知った小豆田さんは、面白そうに笑った。
「燈架ちゃんは柏森くんに何を夢見てたの? 彼だってどこにでもいる煩悩を抱えた普通の人間だよ?」
「ですが、そもそも何で離婚を……」
「それはですねぇ、柏森さんが浮気現場を奥さんとお子さんに目撃されたからです。今お二人は北海道に移住して、電気もガスも無い大自然の中で暮らしてるんですよ」
「わ~ら~び~! 嘘を吹聴するな! 甘樂は名前を呼んではいけないあの虫以下だと言いたげな目で見るな!」
「アッ、嘘なんですね……。失礼しました……」
その間にも「わらびちゃんそのドラマ世代じゃないよね?」「配信で観たんですよ。小豆田さんも世代じゃないですよね?」「親が観てたから少しくらいは」と二人は呑気に話している。テーマソングなのか、次第に「あ」と「ん」と「ら」しか歌詞がない曲を歌い始めた。
今日来た少年は、葛町優光君。小学五年生。
優光君は別れた奥さんと暮らしているらしい。
「燈架ちゃんいい加減立ち直ったら? 柏森くんを美化したところで、美化するだけ無駄だよ」
「それはわかってるんですけど……」
「おい甘樂、今小豆田に乗っかってさりげなく悪口言っただろ」
「そうですよ! 無駄な幻想なんて抱かない方がいいですよ!」
「わ~ら~び~!」
お前まで乗っかるな! という柏森さんの声が響いた。続いて小豆田さんとわらびさんの愉快な笑い声が聞こえる。
その声を聞いても、鬱々とした気持ちは治まらない。
そもそも、なぜ私はショックを受けているのだろう。
「……別に、私は柏森さんのご家庭のことなんて、どうでもいいんですよ」
自分の気持ちを整理するために、気持ちを口にしてみる。
小豆田さんは笑って、柏森さんの「オイオイ」という声が私に飛んできた。
「離婚してるのも、今の時代珍しいことじゃないし、むしろ普通なんだと思います」
「そーだ! そーだ!」とわらびさんが合いの手にも似た声を上げた。彼女はいかなる状況でも、離婚というものを強く推奨しているのだろう。
「でもお子さんがいるのに離婚するなんて……、ぁあ! そうですよ! お子さんがいるのに離婚されてることに、私はショックを受けているんです!」
脳に一気に酸素が回ったように、スッと血の巡りがよくなった気がした。
それと同時に体温も二度上がったように、体が熱くなる。その勢いで、つい聞いてしまう。
「柏森さん、なぜですか!」
柏森さんは顔半分を歪ませて、押し黙ってしまった。
「燈架ちゃん、そこは外野の僕達が口出しするところじゃないよ」
そんな彼を見かねたのか、先程まで野次馬に徹していたのに、小豆田さんが援護するように彼の側に回った。
「さっき自分でも言ってたじゃないか。柏森くんの家庭のことはどうでもいい、って。なのに、優光くんのことには口出しするの?」
「だって、お互い納得して別れた親はいいかもしれないけど、両親が別れる子供側の気持ちはどうなるんですか?」
「それは優光くんの気持ちであって、第三者が勝手に推し量るものじゃないよ。それに、優光くんの立場や感情を一番に想像して悩み苦しんだのは、優光くんのご両親だと思うよ」
それはわかっている。
今日会った優光君の表情は、とても明るかった。
もともとの性格なのかもしれないし、一緒に暮らしている母親と、とても関係が良好なのかもしれない。
それでも、血の繋がりしか関係性がなくなってしまった父親のことも大好きなのだと、十分に伝わった。
しかし、だからこそ、だ。
だからこそ、価値観の違いという、ありがちな理由で別れてしまったのが、納得できないのかもしれない。
シンと静まってしまったバックヤードは、なんだか気まずい空気が漂っていた。
「柏森さーん、やっぱり明日マティーニ奢ってくださいよー。約束したんですしー」
沈黙を破ったのはわらびさんだった。緊張感の無いふわっとした調子だ。返事も待たずに続ける。
「じゃあ明日の予定立てましょうね。なんならこれからでもいいんですよ? その辺もちゃんと決めましょう? というわけで、わたし達はもう少し残りますね」
「わらびちゃん、柏森くんが駄目って言ったら僕と、」
「さよーならー」
ふんわりとした笑顔でふりふり手を振っている。小豆田さんは満足した様子で「お疲れー」と手を振り返している。
「じゃあ柏森くん、今日は鍵よろしくね。燈架ちゃん、先に行こうか」
「反省しています。余計な口出しをしてしまいました」
外は六月に向けて夏を感じる湿った空気が漂っていた。吐いた言葉が湿気て沈んだ気がした。
「柏森くんは真面目で責任感の強い人だからなー。自分を責めて、明々後日は休んじゃうかもなー」
それを聞いて、溜め息にも似た声が漏れた。「今から謝りに、」と言ったところで、笑い声が聞こえた。
「冗談。逆だよ逆。真面目で責任感強いから、絶対来るよ。事故に遭っても来るし、刺されても救急より先に僕に遅れるって連絡してくると思うよ」
それを聞いて、ますます今すぐに引き返して謝った方がいい気がしてきた。今度は溜め息ではなく、「あぁあああぁあ」と声が漏れた。知らず知らずのうちに、頭も抱えていた。またも隣から、場違いな小さな笑い声が聞こえた。
「でもね、正直燈架ちゃんの言ったこと、僕もわからなくないし、柏森くんだってわかってる部分もあると思うよ」
「え?」
「親の気持ちは、親になった人にしかわからないけどさ。子供だった期間は平等にあるんだし、大人になっても自分は親の子供であることに変わりはないからね。子供の気持ちは、皆、何かしら想像できるし、共感だってできるんだよ。子供の気持ちがわかる分、燈架ちゃんに限らず、皆口出ししたくなるんだろうね。世の中にある問題を、そうやって自分事として考えられたら、もっと良くなっていくものも絶対にあると、僕は思うよ」
「……だけど、やっぱり、私が文句つけることでもなかったと思います」
「柏森くん、明日別れた奥さんと優光くんと、三人で会う予定だったんだ。その予定が無くなって落ち込んでるのもあるから、謝るならまた今度にしてあげて」
「えっ、別れた奥さんとも会う予定だったんですか?」
「月に最低一回は会ってるみたいだよ。まぁ奥さんも忙しい方だから、会ったとしても短い時間の時もあるけど。あ、燈架ちゃんが二回目にケーキ買いに来た時なんかも、まさにそうだよ。三十分だけ会うために、別の店でお茶してたんじゃないかな」
パティシエが二人しかいないのになぜあの時いなかったのだろうとは思っていたが、ようやく謎が解決した。
「まぁ今は、別れてからも会えるくらいには仲が良い、って考えとけばいいと思うよ」
就業後のバックヤードが妙に賑やかだったのも、わらびさんの遠慮が無いように聞こえた発言の数々も、全ては柏森さんを励まそうとしていたからなのかもしれない。街の灯りで照らされた蒼い夜空を見上げて、今さらながら気付いた。
定休日明けの出勤。パティシエ組は朝からその日に販売する商品の調理で忙しい。業務に関係ないことで声を掛けるタイミングは、無いに等しい。昼休みに謝ろうか、と考えながら開店前の準備をしていると、わらびさんが上機嫌に声を掛けてきた。
「燈架さん、お休み前はありがとうございました」
「……私、お礼を言われるようなことしましたっけ?」
「はい、おかげで美味しいお酒を飲めました」
どうやら本当にお酒を飲みに行ったらしい。
以前は泣き喚くわらびさんを柏森さんがあやしているような構図だったけれど、今回は落ち込む柏森さんをわらびさんが励ましたのだろうか。
「やっぱり人のお金で飲むお酒は最高に美味しいですね!」
どうやらそうでもないようだ。
いつも本当に素敵な笑顔のわらびさんが、パアァッという効果音が付きそうな最高の笑みを湛えている。
マティーニを奢ってもらうと言っていた気がするが、それ以外も、いや全額奢ってもらったのかもしれない。
末っ子気質というか、甘え上手というか、自分のそういう性質を活かす方法を、彼女は熟知しているようだ。もしかしたらそれは対柏森さんだけの可能性もあるけれど。
私は心の中で柏森さんに「すみませんでした」と先に謝っておいた。
その日、開店と共に入店したのは、女性のお客様だった。
三十代後半から四十代前半くらいの年齢だと思うのだが、三十五歳だと言われても納得してしまう雰囲気があった。
足首が見える細身のパンツに、装飾が少ないスッキリとしたシンプルなブラウス。
前髪は横髪と同じ長さまで伸ばされており、こめかみの辺りで緩くウェーブして、そのまま流れるように下に落ちている。顎の辺りで髪全体の長さが収まっていた。
額が見える分、キリッと上がった眉と、細い鼻筋がよく映える。目も大きいけれど、ぱっちりとか華やかという表現よりも、クールで引き締まった目元だ。
身長も平均より高い。一七〇センチあるかないかくらいだろうか。綺麗に伸びた背筋で、見た目よりもずっと高く見える。
肩幅よりも少し広いくらいの歩幅で、レジまでやって来た。自信と余裕を感じられる佇まいの所為か、目を奪われてしまう。
「こんにちは。お久し振りです」
わらびさんのその声で、現実に戻る。遅れて「いらっしゃいませ」と言うと、微笑みながら会釈を返された。思わずドキッとした。
「久し振りね、わらびちゃん。元気でやってる?」
「お陰様で。いつもお世話になっております」
「こちらこそ、迷惑掛けて」
「とんでもないですよ。このお時間にいらっしゃるの、珍しいですね。今日はお休みですか?」
「夜勤明け」
「それはお疲れ様でございます」
親しげな会話がなされている。常連さん、ということだけわかるが、わらびさんの知人だろうか。
「お呼びして来ましょうか?」
わらびさんのその問いかけに、女性は一瞬店の奥――厨房の窓を見た。
「いや、いいわ。お気遣いありがとう。ごめんなさい、とだけ伝えておいてもらえる?」
「承知しました」
一瞬わらびさんは寂しそうに微笑んだ。ように見えた。
その後わらびさんは、注文も聞かずにプレーンのパウンドケーキをショーケースから取り出した。
「貴女、新しく入った方?」
「は、はい!」
「いつここに?」
「四月の下旬からです」
「あら、じゃあまだ一カ月経ってないくらい? どう? 慣れた?」
「基本的な仕事はなんとか……。でも、商品のこととか意外と覚えることが多くて」
「わからないことは小豆田君にしっかり聞いてね。あと柏森もコキ使っちゃって」
「は、え、」
「あの人、人の世話焼くのが趣味特技みたいなものだから」
そう言って女性はおかしそうに笑った。大人びた綺麗な人だけど、無邪気に笑う。それがなんだか可愛らしかった。
困ったように曖昧に笑う私を見た彼女は、はたと笑うのをやめて、顔を覗き込むようにして首を傾げた。
「私のこと、柏森から聞いてない?」
少しだけ顔が近くなった。その拍子に、ふわりといい香りが漂ってきた。その香りにまたドキッとして、歯切れ悪く返事をしながら頷くことしかできなかった。
「元妻の、葛町朔乃です」
ニコリと笑いながら、彼女は言った。
あまりにも爽やかで直球の自己紹介に、こちらが動揺してしまう。
「し、新人の、甘樂燈架ですっ……!」
「やだやだ、緊張しないで」
気さくに笑う姿からは、柏森さんと夫婦だったということは想像できない。
いつの間にか包装を終えたわらびさんがやって来る。「わらびちゃん、今度また飲みに行きましょう?」「是非お願いします。あ、今五作目をお借りして読んでますよ」「今度また感想聞かせて」という親しげな会話が始まる。不意の「甘樂さんも今度食事でもどう?」という葛町さんの問いかけに、私はまたも「よ、よろしいのですか⁉」と、あわあわ答えたのだった。
「でもいつになるかわからないから、また時間ができたらわらびちゃんに連絡しておくわね」
「お仕事、何なさってるんですか?」
すぐにその場が設けられるのではないとわかって、少し心に余裕ができた。今度は言葉に詰まらずに言えた。
「麻酔科医してて。休みが不規則だからいつになるか。ついこの前も急にシフト変更することになって、予定を前日にドタキャンしたし」
最後の言葉は、苦しそうに笑いながら、それでも冗談めかして話していた。
会計を終えた葛町さんは、商品を受け取ると「またね」と私達に手を振った。入ってきた時と同じ歩調で扉に近付き、店を出て右に曲がる。
その扉が閉まると同時に、レジ横から人影が飛び出した。
それが誰なのか認識できたのは、扉の取っ手を握るために一瞬立ち止まって、扉を開けた反動で店を飛び出し、「朔乃!」と叫んだ声と横顔を見てからだ。
葛町さんが振り返る。横顔だからわからないけれど、少し驚いた様子だった。柏森さんは気にせず彼女に歩み寄る。二人の口元が動いているが、扉は完全に閉まり、何を喋っているのかはわからない。
「燈架さん、朔乃さんがご購入されるのはプレーンのパウンドケーキなので、覚えておいてください」
「プレーンの? 毎回ですか?」
「はい」
こんなにケーキの種類があるのに。なのに、パウンドケーキ。それも、プレーンとは。
「ところで、小豆田さんは何しに来たんですか?」
わらびさんの声につられて声が投げかけられた方向を見ると、小豆田さんまで売り場に顔を出している。
「柏森くんが急にサボり始めたので、僕もサボりに来ました」
「そんな理屈が通じると思いますか?」
「あっじゃあ人材育成に参りました」
わらびさんの顔を見て、慌てて訂正する。
「燈架ちゃん、パウンドケーキのパウンドとは、どういう意味でしょうか」
「それは聞いたことがあります。重さの単位のポンドですよね」
「では、なぜパウンドケーキはパウンドケーキと呼ばれているのでしょうか」
なんだか日本語がおかしい気がする。
が、きっとフォレノワールのように、何か由来があるケーキなのだろう。
なぜ「パウンドケーキ」と呼ばれているのかを問われているのだ。
先ほどのようにスラスラと言葉が出てこず、うーん、と考える私を見て、
「ヒントは、重さ」
と付け足した。
「……全ての材料を混ぜると、一ポンドになる?」
「あー、惜しい。逆だよ。一つずつの材料が一ポンドずつ、っていうのが由来になってるんだ。ちなみに一ポンドは、四捨五入して四五四グラム」
「四五四グラムずつ混ぜると、かなり大きくなりませんか?」
砂糖は入れすぎだ。卵も大量に使用している。
「最初は凄く大きなケーキだったんだろうね」
「ポンドって英語な気がするんですけど、パウンドはフランス語になるんですか?」
「いや、パウンドケーキって名前は英語だろうね。ポンドの発音に近い音が、パウンド。フランスではカトルカールって呼ばれてる」
「随分印象が変わりますね」
「でも意味はほぼ一緒かな。四分の一が四つ、って意味だよ」
「このお菓子は、四ということにこだわりがあるんですかね」
「四人で分けると、ちょうど四分の一ずつ幸せを分けられるかもね」
そう言って彼は視線を店の窓――柏森さん達に向けた。
何を話しているかはやはり聞こえない。
でも、険悪な様子なんて微塵も感じられない。
「……あれ? 柏森さん、もう一人お子さんがいらっしゃるんですか?」
訊ねると小豆田さんは「おぉっと」と呟いた。わらびさんも不思議そうに彼に視線を送っている。
「計算ミスだ」
「普通します? そんな単純な計算ミス」
わらびさんが至極不思議そうに小豆田さんを見つめながら言った。
「『FUKUSHI』の人数とダブったのかもしれない」
彼女は訝るように見つめ続ける。その視線から逃れるようにして彼は話を戻す。
「まぁ三人でも残りの四分の一を三等分すればいいし、何人で食べたとしても、長いケーキを端から切り取って食べていくのは、幸せな光景だと感じるよ。あと、二人は優光くんと朔乃さんがいつもパウンドケーキを買っていく理由は、知ってる?」
私は勿論、わらびさんも首を横に振った。
「これは優光くんから聞いたことなんだけど、家族三人で暮らしていた時、いつもお父さんが作ってくれていたお菓子らしいよ。お母さんは、プレーン味が好きだったそうだ。作り手の愚直さが一番よく表れてるから、だって」
わらびさんと二人で息を飲んだ。
「材料もだいたい家にあるものだろうし、混ぜる物次第で味にも変化が加えられる。マフィンみたいにカップもいらないし、生クリームを塗ったりもしないからそれほど急いで食べる必要もない。
これはしがないパティシエの妄想、いや、かなり現実に近いと思われる想像だけど、忙しい奥さんと家で一人になりがちなお子さんを想った結果、このお菓子を選んで作っていたのかもしれないね。お菓子よりも甘くて胸焼けがしそうだ」
わらびさんがこちらを向くのがわかった。私も彼女の方を向く。驚きと嬉々とした感情が混ざったような表情だった。
「あぁ、僕がこうして不用意にお客様の情報を喋ったことは、うちのスー・シェフには内緒にしててね。個人情報とプライバシーの保護はどうしたんだ、って怒られそうだから」
口元に人差し指を添えて、悪戯っぽく笑っていた。
わらびさんは真似するように口元に人差し指を立てて、楽しそうに「はい!」と言った。さすがに私はその仕草は真似できなかったので、同じように承知の旨を述べた。
「じゃあ僕はそろそろ仕事に戻りまーす」
そう言って厨房へ帰って行った。
同じ頃、柏森さんと葛町さんも、軽く手を上げて、葛町さんは歩を進める。その後ろ姿を少し名残惜しそうに眺めた後、彼は店内に戻ってきた。わらびさんはさりげなくショーケースの端をハタキで撫でるように掃除していた。私もレジ周りをタオルで拭いておく。
その日の昼休憩、バックヤードに全員が揃ったところで「柏森さん」と声をかけた。私は全員が居る前で彼を糾弾するような真似をしたのだ。今度は私が晒し者にならなければ、フェアじゃない気がした。
謝ろうとして口を開いたところで、遮られた。
「離婚の原因は、俺にある」
という柏森さんの言葉によって。
「アイツが体調悪いからって、珍しく仕事を休んだ日があったんだ。でも俺は仕事を休めなくて、いつも通りに家を出た」
なんだかありがちな展開なのかもしれない。小豆田さんが小さい声で「すみません」というのが聞こえた。
「帰ってみたら洗濯物もきっちり畳まれていて、部屋の掃除もされていて、夕食まで準備されていた。だから言ったんだ。『何をしている、馬鹿か!』って」
もう十分に理解した。けれど、誰も彼の独白を制することができない。
「体調が悪い時まで、家事なんかしなくていいと言いたかったんだ。洗濯も掃除も料理も、放っておいたって俺ができることを、アイツだって知ってたはずだ。だから、思わず怒鳴ってしまったんだ」
……思っていた展開とは違うのかもしれない。黙って続きと詳細を待つ。
「でも、あの時『ありがとう』と一言でも言えたら、結果は変わっていたのかもしれない。それに、体調不良の原因は…………」
そこで、言葉が途切れた。
しばらく考えるようにして黙っていたが、やがて。
「いや、何でもない」
と結んで、それ以上の話は聞けなかった。
「中途半端な惚気話聞くと気分悪いなー」
「ですねー」
変に静まり返った空気を打ち消すように、小豆田さんとわらびさんが言った。
「お前等……、人がせっかく黒歴史を打ち明けたというのに……!」
「黒ぉ?」
「青の間違いじゃないですかぁ? 初恋が実ったけど初恋人に上手く感情伝えきれなかったみたいなエピソードを黒歴史って言わないでくださいよー」
「わらび! いつも話を聞いてやってるのに、人の話は悪意を持って聞くとは何なんだ!」
「わたしと柏森さんは墓友なんですから、それらしい発言を心掛けてくださーい」
結婚は墓場友達、の略だろう。
「墓友と略すな! 意味が変わるだろうが!」
「毎回毎回中学生みたいなエピソード聞かされる身にもなってくださーい」
葛町さんの言う、柏森さんの趣味特技は人の世話を焼くことというのも、間違いではないのかもしれない。恐らくわらびさんは、葛町さん公認の、柏森さん世話焼かせ係だ。柏森さんもなんだかんだ誰かの面倒を見ているときの方が表情豊かだ。柏森さんがわらびさんに貸しているあのレンガ本は、パウンドケーキを購入していた時の会話からして、もともと葛町さんの好きな作品なのだろう。それを離婚した後に、柏森さんが葛町さんの代わりの存在として、買い揃えたのかもしれない。
私だけが事情を知らなかったというのは寂しいが、「普通」になっているとはいえ、「離婚」という言葉に、まだ良いイメージが無いのも事実だ。私も聞いた時は、彼に対して偏見を抱いたのも事実だ。それ以上に、彼のことだから、別れた葛町さんや優光君に対する偏見を恐れたのだとも考えられる。ならば、問われるまで伏せられていたのも仕方がない。
小豆田さんの言っていた『別れてからも会えるくらいには仲が良い』は、子供のためなら仲良くできるとかそういう意味ではなく、『別れてからも、好きな気持ちは変わらない』という意味なのだろう。
これ以上考えても無駄だろうけど、恐らく離婚の本当の原因は、「自分のことより相手を想いすぎる相手を気遣って」かもしれない。ではその気遣う事情は何なのかは……私は知らなくてもいい事だ。
夫婦とか家族とか、分かりやすい単位でそのままある関係よりも、別れても両親の仲が良い方が健全とも言える。優光君の笑顔を思い出して、そう思った。
柏森さんとわらびさんは、まだやいのやいの言い合っている。いつの間にか柏森さんイジりから抜けていた小豆田さんは、スマホを見ている。ふと画面が見えてしまった。女性の写真を眺めていた。
芸能人だろうかとも思ったが、そういう風には見えない。良く言えば清楚な雰囲気。しかしどちらかというと、素朴で地味だ。わらびさんの方がうんと可愛い。
「どなたですか?」
駆け出し中のアイドルや役者という可能性も捨てきれない。わらびさんのように、彼にも推しがいるのだろうか。世間話のつもりで聞いてみた。
「僕の妻だよ」
やけにシンプルで、それでいて意外性のある答えだった。
「可愛いでしょ? 燈架ちゃんも見る?」
見ると答えていないのに、画面を向けて写真を次々フリックしていく。見るというより、見せられている。小豆田さんには言えないが、毎日わらびさんを見て、今日は葛町さんも見ている身としては、彼の言葉を強く肯定できない。苦し紛れに出た言葉が、
「……お若いですね?」
次々フリックされていくから年齢が上手く掴めないが、まだ二十代後半から三十歳前半くらいだろうか。小豆田さんとは、十歳近く差があるように見える。
それにしても、何枚あるのだろうかと思うほど、次々と写真が表示されていく。
「この辺りは付き合い始めた頃のだからね。あ、ここから結婚後かな」
「私今アルバム見せられてるんですか? せめて一番新しいものだけにしてくれませんか?」
また新しい写真が表示されたと同時に聞き捨てならない言葉が聞こえてきたので、フリックを一度止めさせた。「んー」と言いながら最新まで、遡って遡って遡っている。止めなければ昼休憩中ずっと続いていたかもしれない。
「この辺りかな」
私よりニ、三歳年上だろうか。が、女性のお腹が膨らんでいる。そう言えば、彼もこれから父になる人だった。お腹が膨らんだ女性はどれも眼鏡を掛けていた。華やかさとは遠い印象を受ける。
「あー、やっぱりどの写真も可愛いな。都は最高に可愛い」
私に画面を見せるのをやめて両手でスマホを持ち顔の前に持ってきて、デレデレ――いや、でへでへとニヤけている。
勢い余って画面にキスし始めかねない様子だ。
こんなにも奥さんのことが好きなのに、変な病を患っているものだ。
というか逆に、奥さんはそんな人が夫でいいのだろうか。
「……そういえば、葛町さんには玉砕しに行かなくてよかったんですか?」
葛町さんは柏森さんが好きなのだから、フラれる結果しか見えない。
小豆田さんはサッと表情を強張らせた。
「そんなことしたら、僕は柏森くんに殺されちゃうよ」
大真面目な顔して続ける。
「柏森くんが捕まるの嫌だし、『FUKUSHI』を任せるなら柏森くんがいいから、そういう居なくなり方されたら非常に困るんだよ」
「せめて殺されたくない、って言ってくださいよ。柏森さんが捕まる前提で話されるの、ちょっと生々しいです」
それを聞いて、彼はいつも通り楽しそうに笑った。そして――
「さ、早く食べようか。休憩時間にはしっかり栄養を摂らないと」
名残惜しそうにスマホの画面を見つめてから、しまった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
