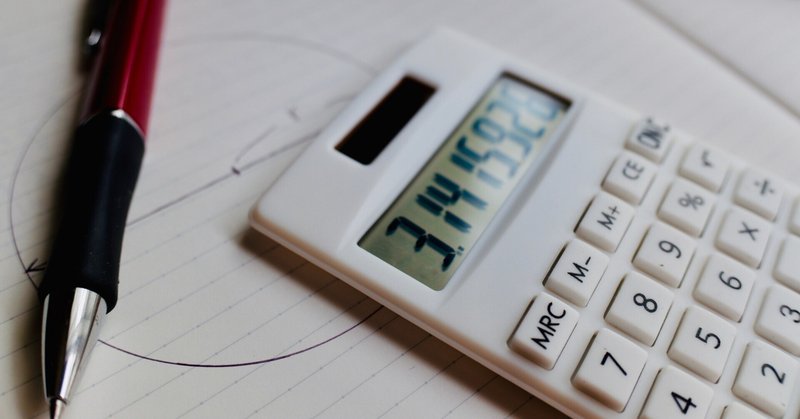
【降灰記file.04】ぬばたまのひとよひとよにひとみごろアポロ計画、人を円かに(巣々木盥)
ぬばたまのひとよひとよにひとみごろアポロ計画、人を円かに
数学はできないです。
とあらかじめ言い訳したうえで、「ひとよひとよにひとみごろ」は2の根号の語呂合わせ、つまり、√2=1.41421356……のことを言っている。そして、枕詞には通常直後にかかる言葉が必要なのだが、たぶん「ひと」ではない。ここでは、「アポロ計画」から連想される宇宙にかかると考えるのが良いだろう。となると、√2は無理数だから(合ってますよね?)、枕詞とそれがかかる言葉の間には無限の隔たりが生じることになる。そして、だめ押しのように結句の「円」だ。πも無理数だから(合ってることにしますよ)、歌の中に二つの無限小の世界が生まれている。
『佐々木』は榊隆太と巣々木盥によるネットプリントである。名前の読み方が合っているのか自信はないが、榊も巣々木も「佐々木」に限りなく接近してずっと接することのできない漸近線のように思う。二人の名前を足して割っても無理そうなのは、「さ」の音が一つ足りないからだろう。このもどかしさは、両者の連作にもつ印象と似ているが、巣々木の場合、時おりあらわれる胡散臭い文語もあいまって顕著だ。
だいたい語呂合わせというものも、数字に近いようでいて怪しい。1を「ひと」、6を「ろ」と読む慣習だとか。語呂合わせにしたところで、意味も分からない。どういう状況? そもそも語呂合わせの「ひと」は人間のことなのか? 円についても「真円は存在しない」とかそういう話を歌に吸着させたくなる。なにかに近いようで、なにかにはならないものを連想させつづける。
個人の感想ですって言って、そうしてしっかりまず踏み込むよ
面白い歌だと思う。同時に、この人は個人になれないのだとも思う。個人というものが常に公共に晒されていると了解しているから、このようなエクスキューズが発生する。あるいは、組織の意向や社会の無意識を単に再生産する際にもこのエクスキューズを用いることがある。個人になれないものの、できるだけ個人に近づくための動作が、「踏み込む」なのだろう。
双子は一つの図鑑を読んで想像される二人の子ども
警鐘を鳴らしたければご自由に 違う展覧会に同じ絵
(榊の歌は漸近線と曲線の存在をしっかり見せていて、特にこの2首にはなんだか釘をさされた気持ちだった。タイトルが「指南」なのもすごい。)
(文・景川神威)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
