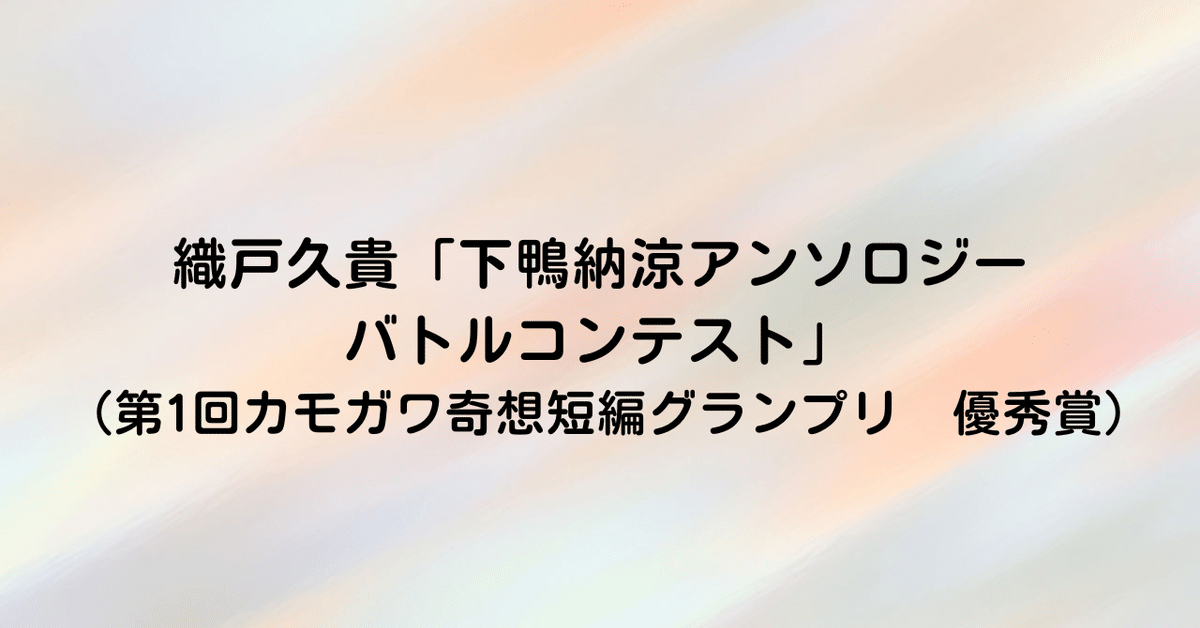
織戸久貴「下鴨納涼アンソロジーバトルコンテスト」(第1回カモガワ奇想短編グランプリ 優秀賞受賞作)
第2回カモガワ奇想短編グランプリの開催を記念して、前回大会の受賞作品をnote上で順次公開します。前回の選評はこちら。
作者紹介
織戸久貴(おりと・ひさき)
第9回創元SF短編賞大森望賞受賞。『京都SFアンソロジー:ここに浮かぶ景色』(社会評論社)に「春と灰」を掲載。『百合小説コレクションwiz』(河出文庫)著者紹介テキスト作成協力。
ブックキュレーションが競技化されたのは二〇三〇年代のことだ。
当時、小説という文化圏はあまりにも肥大化していた。AI技術の革新に伴い、現存する文字の総数は雪だるま式に増えつづけ、だれひとりとしてそのすべてを把握できていなかった。〈一億総クリエイター時代〉とまで呼ばれ、ウェブ発の小説がメディアミックスをくり返し、小説投稿プラットフォームが乱立しては廃れていった。しかし、いつしか子供も大人も、本を選ぶという行為への興味を失っていた。
総人口の数パーセントとされる読書好きの人々でさえ、自分が好む傾向の作品をAIのレコメンドに従って読むような時代だった。つまり、だれもが自ら努力し、自分だけのお気に入りの作品を求めようとはしなかった。
なぜならすでに平均寿命や生涯年収、余暇時間が簡単に算出できる時代であり、わざわざつまらない・むずかしい・わからない作品を読むのはリソースの無駄でしかなかったからだ。それゆえ、読書の多様性が急速に萎んだ時代でもあった。
これを懸念した日本文学振興会と日本図書館協会、そして全国の古書組合が立ち上がった。諸団体は利害を合致させ、優れたキュレーターを市井から発掘し、選書行為をエンターテインメントに昇華できないかと考えた。
そこで生まれたのが〈ブックキュレーションコンテスト〉だった。
のちに〈アンソロジーバトル〉と呼ばれる知的競技である。その全国大会が京都の下鴨納涼古本まつりで開かれるようになったのは、二〇三四年夏のことだった。第一回、最高気温四十二度を記録した糺の森では、十一名の参加者が熱中症のために救急搬送された。のちに一名が死亡した。
しかしこの事実は京都市を含むその他の団体によって隠蔽された。翌年には何事もなかったかのように第二回大会が開催され、協賛企業からの賞金も用意された。こうしてエンタメとしての読書はにわかに復活した。
アンソロジスタたちの熱い夏は、以後二十年にわたってつづく。
*
〈アンソロジーバトル〉とは、五つの短篇小説を並べる対戦型競技である。
プレイヤーは予算一万円(自費)の範囲で、制限時間内に古本まつりの出品物を自由に購入する。これらを〈カードプール〉とし、そこから最終的に五つの短篇を選ぶ。つまり〈アンソロジーデッキ〉を構築し、その組み合わせの面白さで優劣を競う。
評価軸は五つ。
文学性、テーマ性、オリジナリティ、リーダビリティ、ある視点。
このすべてを総合し、勝敗が決する。大会は予選とトーナメントによる勝ち抜き性であり、〈デッキ〉の構成は一試合ごとに変えることもできる。
また、バトルには相性がある。対戦相手と収録作が被ってしまえば、オリジナリティは低いものとみなされ、編者が意図した効果も発揮できない。なにより目的となる書籍が先にだれかに購入される可能性もある。海外作品を組み込む場合は、原語であるかどうか、どの訳が選択されたのかも評価の対象となる。
よってただ面白い作品を五つ並べただけでは意味がない。時間や金銭のリソース管理、知識量、フィジカル、集中力、気候、時の運、あらゆる複雑なパラメータを前提としたうえで、高度なブックキュレーティングが要求される。
ではその構築例を示そう。
■テーマデッキ
いわゆるジャンル小説のみによって構成されるデッキ。たとえばSFであれば〈タイムトラベルデッキ〉などで収録作の色を統一しやすく、テーマを演出できる。しかし前例も多く、オリジナリティを追究することがむずかしい。大会初期ではよく見られたが、定石が整った第五回以降では評価が低くなった。
■ストーリーデッキ
作品を順に読み進めることで、〈大きな物語〉を印象づけるデッキ。掴みの一作目と落ちの五作目が重要とされる。比較的構築が容易だが、アンソロジスタの狙いがうまく伝わらないと減点されるデメリットもある。それでも五作すべてのコンボがつながった場合の爆発力は大きい。〈円環デッキ〉、〈地獄巡りデッキ〉、〈バベル崩壊デッキ〉、〈輪廻転生デッキ〉など、過去大会での優勝例が挙げられる。
■文学全集デッキ
作家別、言語別、時代別など、切り口がさまざまで、『テーマデッキ』の応用編ともいわれる。かつて〈五作品ルール〉がなかった第二回大会では、古本まつり恒例の「三冊まとめて五百円コーナー」に全額をつぎ込み、安価で大量の海外古典を仕入れた〈世界文学全集デッキ〉や〈マジックリアリズムデッキ〉が猛威をふるった。しかし翌年よりルールが改訂され、ブームは一瞬で過ぎ去った。
■マルジナリアデッキ
書籍の余白部分、つまり〈マージン〉に文章が書き込まれた短篇を収録することで、かつての持ち主の気配を感じさせるというメタデッキ。しかしそもそも書き込みのある名作を揃えることが難しく、再現性がまったくない。統計的には、七年に一度のペースで登場するデッキであるといわれている。
このように〈アンソロジーバトル〉は概念の破壊と再生という名の発展をくり返していたが、その深奥は二十年経ってもなお未知の領域であった。
しかし、二〇五四年に事件は起きた。
*
二〇五四年大会は、奇跡の年と呼ばれる。
勝率の低かった〈テーマデッキ〉が復活を遂げたからだ。
ハリイ・ケメルマン「九マイルは遠すぎる」から連綿とつづく純粋推論のミステリのみを揃えた〈九マイルデッキ〉をはじめ、イタロ・カルヴィーノによる幻想文学『見えない都市』に触発されたケン・カルファス「見えないショッピング・モール」など、マルコ・ポーロの架空の語りだけを集めた〈インビジブルデッキ〉、五篇分の文章のほとんどをマジックで塗りつぶし、まったく新しい短篇小説を生み出した〈墨塗りデッキ〉などが現われ、そのどれもが高水準の得点をたたき出した(ただし墨塗りデッキはのちに失格扱いとなった)。
しかし、これら過去大会であれば優勝するであろうレベルのアンソロジーたちは、すべてひとりのダークホースの前に敗北した。
そのアンソロジーを編んだのはアルゼンチンからの留学生だった。かれの提出したデッキには、収録順という概念がなかった。しかし同時に、あらゆる順序で読むことができた。つまり順列によって理論上一二〇通りの読みが成立するのだった。おそらくはフリオ・コルタサルの作品から連想した戦術であり、かれはトーナメントの対戦相手をこのデッキのみで圧倒し、破竹の勢いで決勝戦まで駆け上がった。
通称〈石蹴り遊び〉革命である。
当初はデッキの成立じたいが疑われたが、たしかにどの順で読んでも瑕疵がなく、かつビビッドな読書体験であることを審査員たちは否定できなかった。とはいえ、これはアンソロジーなのだろうか? わたしたちはなにかを間違えているのでは?
その疑念は拭えないまま、ついに決勝戦がはじまった。
*
決勝戦に現われたもうひとりの編者は甲冑騎士だった。
空調服を改良し、熱中症を防ぐことに特化したデザイン。〈アンソロジーバトル〉は二十年のあいだに興行として認知され、コスプレでの参加は珍しくなかった。
しかしその見た目に比べ、騎士はひどく地味な編者だった。
予選もトーナメントでの試合も、相手よりほんのすこしだけ得点の高いデッキで勝つだけで、面白みがなかった。つまり運だけの、三文アンソロジスタだった。にもかかわらず、決勝でその騎士は前代未聞のアンソロジーを提出した。
それは古地図、カセットテープ、フロッピーディスク、CD-R、USBメモリから構成され、そのどれもが書籍ではなかった。広義の記憶媒体ではあったが。
ただ、決勝の場で騎士は告げたのだった。
「これらはすべて、物故作家の未発表原稿である」
途端、観戦者全員が唖然と口を開けた。
急遽、近くのジャンク屋から読み取り用の機材が持ち込まれた。古地図の裏には落書きめいたくずし字があったが、会場にいた高名な古美術鑑定家が、とある戯作者の真作と認めた。カセットテープには声が吹き込まれており、文字起こしアプリでテキストデータ化し、その場で形態素解析にかけられた。それは口述筆記を得意とした昭和作家の文体と一致した。CD、USBの中身もそれぞれ平成、令和に活躍した作家のもので間違いなかった。こうして〈石蹴り遊び〉革命は一晩も待たずに終わった。
試合後、どうすれば、と留学生は問いかけた。
「あなたのようなアンソロジーを編めるのですか。どんな経験を積めば」
甲冑騎士は答えた。
「人生とはどうせそんなものさ。長篇の恰好をした、短篇の寄せ集めだ」
そういって、はるか遠くを指さした。すると木々に隠れていた蝉たちが鳴きはじめ、いっせいに飛び立った。なにが起きたのか、だれも理解できなかった。
森が一瞬でしずかになった。
遅れて、がしゃん、と大きな金属音が響いた。
あたかも操り糸が切れたかのように、騎士の甲冑はバラバラになって地面に転がっていた。鎧の中はまったくのからっぽだった。
まるで『不在の騎士』だった。
のちの調査で、騎士は糺の森に設置されていたKYOTO Wi-Fiを通じて遠隔操作されていたことが突き止められた。IPアドレスも追跡できたが、発信元は京都市内のマンションの空き部屋であり、一年以上借りられていなかった。
唯一わかったのは、京都大学の英米文学研究者による指摘で、騎士の最後の言葉が、エリック・マコーマック『パラダイス・モーテル』からの引用であったことだけだった。ただ違法に回線を使用していたため、その犯行をわざわざ名乗り出る者もいなかった。
〈騎士〉の正体はだれも知らない。
そのあとはつまらない風説だけが流れては消えていった。
正体は第一回大会で死んだアンソロジスタの子供であった説、京大教授説、政府の陰謀説、AIの暴走説、カルヴィーノの幽霊説、宇宙人説。
しかし翌年以降、下鴨納涼古本まつりには大量の偽書が出品されるようになり、大会は事実上の存続が不可能になった。こうして〈下鴨納涼アンソロジーバトルコンテスト〉はおよそ二十年の歴史に幕を下ろす。
こうして人間による能動的読書の時代は終わった。
いまではこの物語を憶えているのも、あなたとわたしだけである。
「第2回カモガワ奇想短編グランプリ」応募要項はこちら。
