
【昔は獣害なんてなかった?4】
【万葉の時代から】
よくある誤解ですが、
昔は獣害なんてなかったから、
今は増えすぎだ、
獣害のなかった頃ぐらいまで、
数を減らそう、
…この場合の「昔」は、
歴史的にみて、
とても限定的な「昔」です。
じつはこれ、
明治以降の、
わずか100年ちょっとの間だけのコトです。
農業が始まって以降の、
二千年ほどの時間、
そう、江戸時代までは、
獣害はあたり前にあり、
先人たちは、
野生動物と闘い続け、関わり続けてきました。
では、いつ頃から
「獣害があった」のでしょうか?
これまで、
獣害について記載された
江戸時代の文献などを見てきました。
(吉野林業全書も発行は明治時代ながら、それに記載されたノウハウは、江戸時代から紡がれたもの)
とすると、
獣害の歴史はどのくらいまで遡れるでしょうか。
そのヒントは、
余りにも身近なところにありました。。。
小倉百人一首は、もちろんご存知ですよね。
中でも、
第一番、天智天皇が詠み人となっている
この歌は、有名です。
「秋の田の かりほの庵の
苫をあらみ
我が衣手は露にぬれつつ」
しかし、
その意味は?と尋ねられると
どうでしょうか。
この歌の意味をご存知でしょうか。
そう、この歌こそが、
獣害防除の歌なのです!
以下、意味を追っていきましょう。
秋の実り多い田んぼで、
(夜になると、
シカやイノシシがやってくるので)
(追い払うために夜通し寝ずの番、
通称:シシ番をしていると、)
粗末な見張り小屋、シシ小屋なので、
小屋の、壁のムシロの目が粗く、
夜露が降りてきても、それをしのげず、
わたしの着物の袖を濡らすのだよ。
(ナントも疲れをさそうなぁ。)
という、
獣害対策の役割の一旦を担う農民の、
悲哀の情景を詠んだ歌なのです。
この歌の元歌は万葉集で、
詠み人知らずといいますから、
もともとは農民の労働歌だったんですね。
また万葉集には、この歌だけでなく、
見張りのための小屋の、「仮廬(かりほ)」
が出てくる歌がこの他にもあり、
また、
シカやイノシシがよく出没する田、
「鹿猪田(ししだ)」
が出てくる歌も多数あるそうです。
これらのことから、
1500年近く前から獣害が「異常」ではなく、
「日常」だったことがわかります。
日本列島で、農業を行うということは、
人工的な草原を造成するということであり、
しかもそこに実る栄養価の高い作物は、
野生動物にとっても
魅力的なエサ資源であることに他なりません。
ましてや、
草原をエサ場としていた
シカやイノシシにとっては、
人工的な草原と自然草原との区別など、
付くはずもありません。
よって、
農業の始まりとともに
野生動物との闘いは必然的に始まり、
獣害との向き合わざるを得ない選択の始まりだったのでしょう。
さて一方で、
現代の農山村やワタシたちは、
「見張り」や「追い払い」にキチンと向き合い、
これ程までに
獣害対策を実践しているでしょうか。
現代のワタシたちは、
野生動物の鼻先に、
エサを突き出しているにもかかわらず、
覚悟なく無防備でいることが、
「正常」な「日常」だとカン違いしていないでしょうか。
かもしかの会関西は、
失われた防除の技術と意識、を取り戻し、
現代にあった資材、方法で
新しくつくっていくコトを実践してゆきます。
参考:
上野誠(2016) 万葉手帳 東京書籍 235pp.
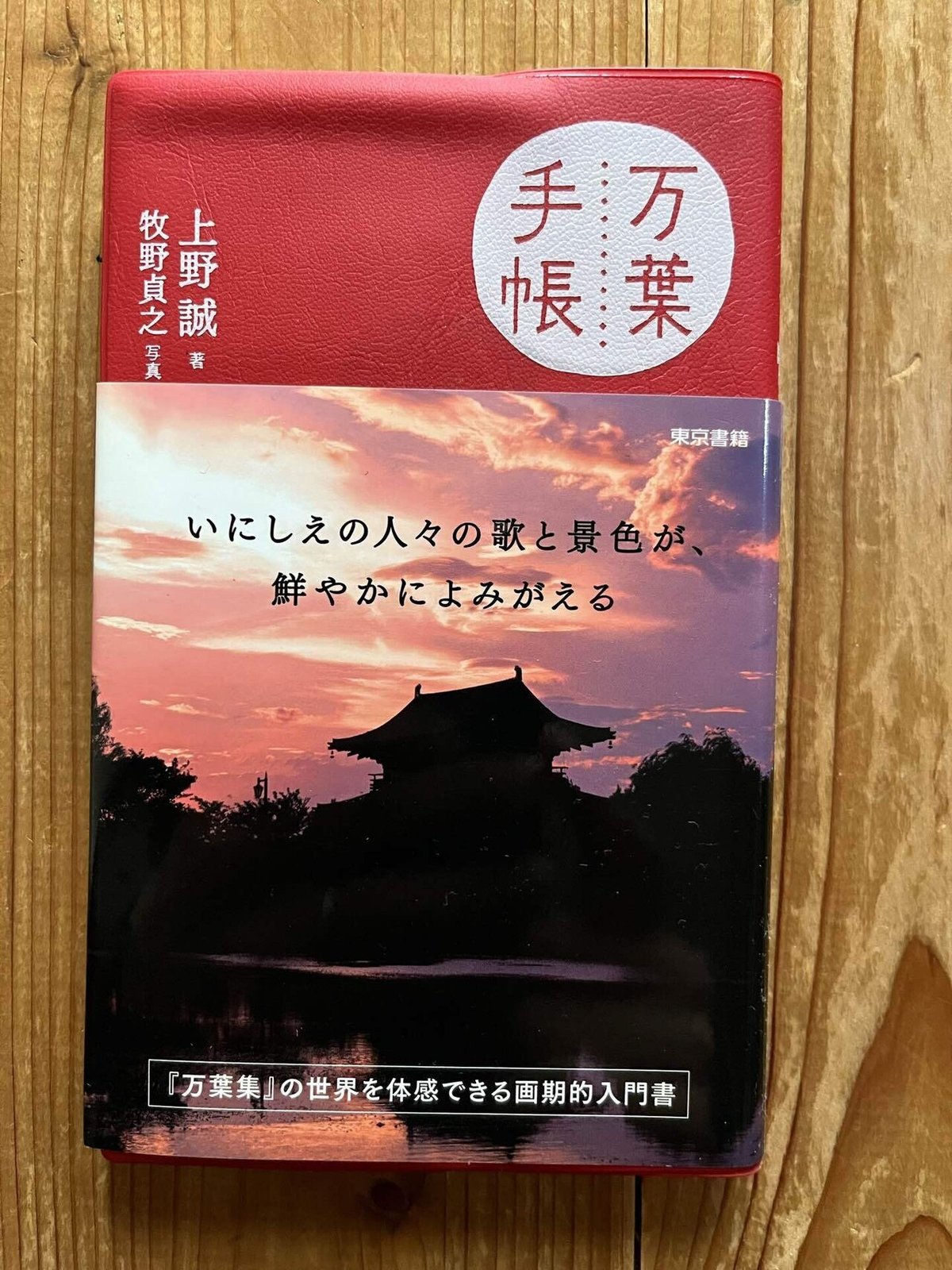



写真ものがたり 昭和の暮らし 2山村
農山漁村文化協会 640pp
