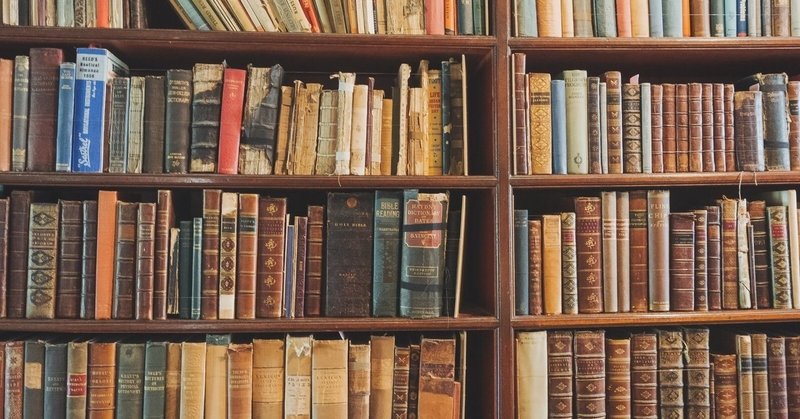
読書の感想をネットで発信してみよう
おはようございます、神島竜です。
みなさんはブログやSNS、あるいはYoutubeやニコニコ動画などをやっていますか?
やってなかったら、ぜひオススメです。
インプットをしているなら、アウトプットもしたほうがいい、ネットで発信している人はみんな言っていることですが、僕もそれには賛成です。
しかし、今回は発信することでインフルエンサーになれとか、お金を稼げるとかいう話ではありません。あくまで発信すること自体のメリットについて語ります。
じつは僕もいくつかネットに発信する手段を持っています。
はてなブログ、Twitter、読書メーター、そして1週間前にはじめたnote。後、バーチャルユーチューバーに興味があってですね。神島竜とは関係のない形ではじめる予定です。
読書だけじゃないんですけどね、こういうふうにいろんな人にわかる形でネットに流すことは、お金とか評価以外でもインプットする点で役に立つんですよ。
本を読んだり、勉強したり、サロンやらセミナーとかでインプットするって時に注意したいのがですね。詰め込むだけ詰め込んで、整理できているのかってことなんですよ。
知識は使えないと意味がないんです。この使えるというのは役に立つか立たないかよりも、人に説明できるかどうかが大事なんです。どんなものでも、人に説明できるくらい理解できていれば、いざって時に使えます。どんどん本を読んで俺は頭がいいんだぞって状態にすると、このいざって時に使えないんです。
例えば、頭の中を一つの部屋だとします。部屋の中ではつねにプリンターが動いていて、キミの目に映るあらゆる事象が次々と印刷される。脳のどっかの部位はそのプリンターの紙を拾い集めては、書き足したり、ファイルに保管する。んで、彼らはキミがその知識を人に話そうとするときに、ドタバタと走り回っていろんなとこに保管した資料を集める。んで、何度か集めていくうちにこれは一か所に集めておいたほうがいいぞと彼らは思いだすため、じょじょにその資料はまとまったフォルダに保存され、いつでも取り出せるようになる。
記憶の定着ってのはさ。たぶんそういう仕組みなんですよ。
いろんな人に発信することの大事さってこのへんだと思うんですよね。
最初はTwitterでもいいんです。やっていくと、自分の知っていることを人に伝えるのって難しいな、と思うはずです。この感覚を持つことが大事です。
その経験を重ねていくと、本の読み方や勉強の仕方も変わります。
とにかく覚えるんだって考えから、使うためにどうやって覚えるのがいいかって考えに変わっていくんですよ。
ぜひ、Twitterからでもいいのではじめてみてください。
頂いたサポートは本に使います。
