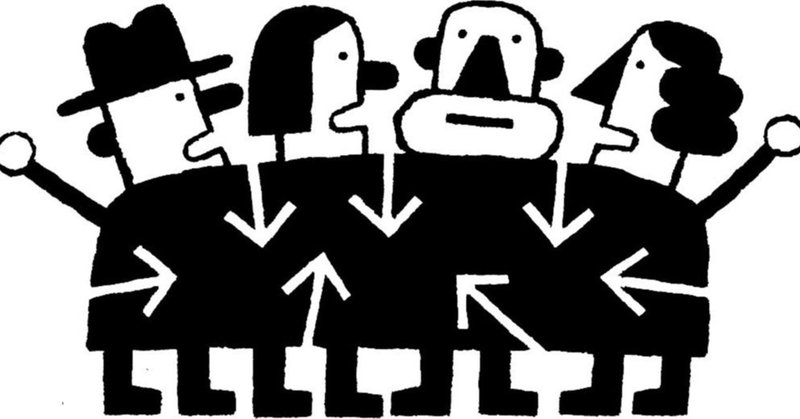
手紙を書きましょう
(20180512記)
慶應文学部の名物教授だった池田弥三郎さんは、『手紙のたのしみ』(文春文庫キンドル版)の中で、個人の主体性を尊重する戦後の民主教育は、個性的であることを重視するあまり「紋切り型」を悪しき慣習として切り捨ててしまい、そのせいでみんな気軽に手紙を書けなくなった、と嘆いています。
たしかに。手紙の冒頭で相手に語りかけるバリエーションと言われても、数には限りがあるでしょう。目新しい言いまわしを求め、「紋切り型」を避けようとするから書き出せない。だから手紙は衰退の途をたどったのだ、と池田さんの憤懣は尽きぬご様子。
そこで、このところすっかり縁遠くなっている、手紙の味わいや風合いを思い出していただこうという魂胆です。本の手触り、持ち重り、物質性を求める愛書家のみなさんには、いくらかご賛同いただけるのではないでしょうか。
まず、手紙の持つ温かさ、肌触りのようなものを思い出していただくために、『須賀敦子への手紙』(つるとはな:二八五〇円)を手に取ってみましょう。イタリア文学者、翻訳家、エッセイストとして幅広く活躍していた須賀さんが亡くなられてもう二〇年。
心許した友人に宛てられた五五通におよぶ書簡の写真を収録した本書は、便箋やはがきの風合い、筆跡やインクの色味も相俟って、ご当人のエッセイなどとはまた違ったかたちで須賀さんの人となりや心の動きを浮かびあがらせます。
宛名の入った封筒の写真も収め、細かい文字は活字化したり、英字部分は翻訳するなど、丁寧な編集も好ましく、あぁ、自分がこんな手紙をもらったら嬉しいだろうな、と思わず口元が緩みます。
でも、いざ手紙を書き出そうとすると、それを誰に宛てるかが最初の悩みどころになるかも知れません。そんなとき、家族や友人の名前を数えつつ、高森美由紀さんの『お手がみください』(産業編集センター:一二〇〇円)を読むと、スッとある人の顔が心に浮かんでくるような気がします。
児童文学の気鋭の手になる本作は、小学校二年生の眞子と八六歳になる曾祖母のかずという、二人の心の交流を軸に、眞子を取り巻く家族や世界を描いた佳作です。
大好きなひいばあちゃんに手紙を書いて返事を心待ちにする眞子ですが、返事は一向に戻りません。その謎が解けるには、その後、二〇年以上の歳月が必要でした。穏やかな心のやりとりが、きっと手紙を書くことへのハードルを下げてくれるでしょう。
さて、みんなはどんな手紙を書いているのかしら、もっといろいろな手紙を読んでみたい。そんな心境にたどり着いたらしめたもの。『手紙読本』(講談社文芸文庫:一五〇〇円)をどうぞ。
洒脱なエッセイで知られた江國滋さんが、日本を代表する文士たちの手紙から九〇通余りを選び抜き、コメントを付したアンソロジーで、お祝いにお詫び、催促にラブレター、果ては遺書に至るまで、文士の生態を活写し余すところがありません。
私は個人的に、本書は近頃話題の『〆切本』シリーズ(左右社)のマクラになっているのではないかと思っています。
続いて、手紙とは何か、という到底答えが出そうにもない大問題に、図らずも迫ってしまった感のある名著が、ガーフィールドの『手紙 その消えゆく世界をたどる旅』(柏書房:二八〇〇円)です。なぜシェイクスピアの手紙が残っていないのか、なぜジェイン・オースティンの手紙はつまらないのか、ルイス・キャロルによる手紙の書き方指南等々、古今の手紙をめぐる興味深いエピソードが通史的に紹介されています。
もうひとつ、アッシャーの『注目すべき125通の手紙』(創元社:三〇〇〇円)もお薦めします。本書の魅力は、収録された手紙の差出人と宛先をいくつか紹介するだけで充分に伝わるはずです。切り裂きジャック→自警団長(!)、レイモンド・チャンドラー→編集者、NASA→修道女(!!)、ヒトラーの甥→ルーズベルト、エリザベス二世→アイゼンハワー、ミック・ジャガー→アンディ・ウォーホル。なんだか、おもしろそうでしょう?
有名な作品ですから多くは語りませんが、『レター教室』(ちくま文庫:五二〇円)は、五人の登場人物たちがやりとりする手紙だけでストーリーが展開してゆく、言わずと知れた三島由紀夫さんの名品で、タイトル通り各パートが手紙の文例になっている心憎い仕掛け。未読の方はこの機会に是非どうぞ。
物語の展開に手紙が重要な役割を果たす作品としては、他にも東野圭吾さんの『手紙』(文春文庫:六九〇円)や喜多川泰さんの『「手紙屋」』(ディスカバー:一五〇〇円)、井上ひさしさんの『十三人の手紙』(中公文庫:七〇五円)などがあります。どれも著者の個性が存分に発揮されたストーリーテリングとなっているので、読み比べも一興でしょう。
一九八七年の大ベストセラーながら、最近では忘れられてしまった感のあるウォードの名作『ビジネスマンの父より息子への30通の手紙』(新潮文庫:五九〇円)は、手紙の相手にふと息子が浮んだビジネスマン必読です。
おおよそ父親と息子というのは微妙な関係で、ビジネスで成功した著者がそのノウハウを息子に伝えるために書いた三〇通の手紙は、非常に普遍的な教訓を含むものの、果たして息子はこれをどう読むのだろう、などと考えてしまいます。
それでも、息子の成長を望まない親はいないわけで、その複雑な情感をビジネス小説の名手・城山三郎さんが見事に翻訳しています。
『夢をかなえるゾウ』シリーズ(飛鳥新社)や『ウケる技術』(オーエス出版社)で知られる水野敬也さんの『たった一通の手紙が、人生を変える』(文響社)も合わせて読んでみてください。
大河ドラマの時代考証などで知られる小和田哲男さんの『戦国武将の手紙を読む』(中公新書:八四〇円)は、二〇人の戦国武将が出した手紙(それは時に遺書だったりもします)の原文と訳文から、彼らの人間像や心情に迫ります。
連絡に書状を使うしかなかった時代らしい、相手に自分の思いを伝えたいという欲求が率直に感じられ、手紙を書く上でもヒントとなってくれそうです。
夏目漱石の膨大な書簡から、家族や弟子たち、読者などに送った手紙を選んで紹介するのが、小山慶太さんの『漱石先生の手紙が教えてくれたこと』(岩波ジュニア新書:八八〇円)で、とても漱石らしい手紙がある一方、いくつかの手紙からは、日頃のイメージとは少し異なる漱石像が浮かびあがり、そのギャップも興味深いところです。
詩人リルケの『若き詩人への手紙・若き女性への手紙』(新潮文庫)の読後感が本書に近く、それは漱石とリルケが共に教育者としても非常に優れていたことの証であるように思いました。
パートナーへ手紙を書いてみようと思ったかたには、三つの愛のカタチを示した以下の三冊をご紹介します。『島尾敏雄・ミホ 愛の往復書簡』(中公選書:二四〇〇円)はひたすらロマンティックな印象ですが、生きては帰れぬ特攻隊の隊長と沖縄の島の娘という、二人の置かれている状況を客観的に見つめ直した瞬間、世界は一転し、異様な切迫感が胸に迫ります。自身『百年の手紙――日本人が遺したことば』(岩波新書)という名著を持つ梯久美子さんの解説も必読です。
プロレタリアート詩人の壺井繁治は、昭和五年、共産主義者として逮捕され、『二十四の瞳』(角川文庫)で知られる妻・栄に獄中から手紙を送ります。
『二人の手紙 獄中往復書簡集』(編集室屋上:一八〇〇円)には、暇を持てあまし妻からの手紙が遅いと憤懣をぶつける夫と、体調不良で手紙を書く暇もないと切り返す妻のやりとりが収められています。行き交う言葉は乱暴で、言い草はどこか自分勝手。にもかかわらず見え隠れする伴侶への甘えと相手を思いやる優しさが、なんだか良い感じです。
『鍵』と共に谷崎潤一郎晩年の代表作とされる『瘋癲老人日記』(新潮文庫・中公文庫)。その作中、谷崎自身がモチーフと思しき「老人」を惑わす長男の嫁・颯子のモデルとなったのが渡辺千萬子です。
この二人の間で交わされた三〇〇通近い書簡を収めた『谷崎潤一郎=渡辺千萬子往復書簡』(中公文庫)は、未読の谷崎ファンはもちろん、『瘋癲老人日記』を読んで深淵かつ隠微な愛の世界を覗き見た読者には、究極のラブレター指南としてお薦めしたい奇書です。
さて、私は、言葉を紡ぐことは考えることと同義であり、手紙を書くことは思考の道筋を明らかにしていく過程だと考えています。
哲学や宗教学にも造詣の深い評論家の若松英輔さんと、福島で東日本大震災を被災した詩人の和合亮一さんの間で交わされた書簡を編んだ『往復書簡 悲しみが言葉をつむぐとき』(岩波書店:一七〇〇円)を、読んだとき、改めてその思いを強くしました。東日本大震災、ひいては人の死というものを眼前に、高ぶることも激することもない静謐な筆致を支える官能と思索に深く胸を打たれます。
今回ご紹介する作品には、いずれも手紙の受け手への強い思いと、形式に拘らない、自由な表現が込められており、それはメールやSNSの時代に、私たちが失いつつあるもののように感じます。
かつて池田弥三郎さんが憤った、そして気がつかないうちに私たちが囚われている「紋切り型」や、デジタルの制約を超えて、さぁ、あなたなりの言葉と筆致で手紙を書いてみませんか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
