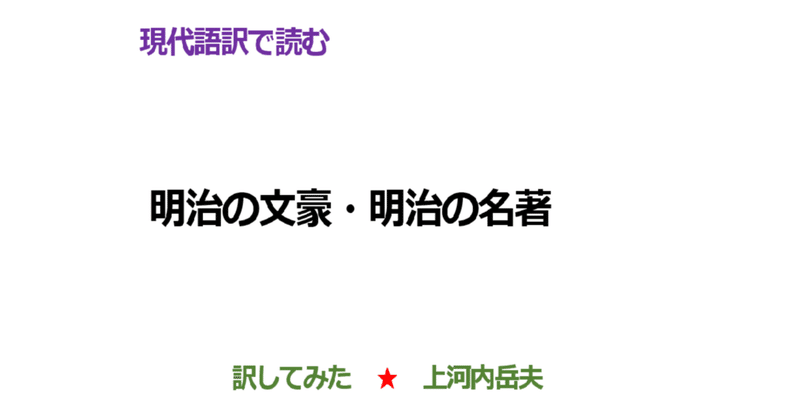
二葉亭四迷「小説総論」現代語訳
二葉亭四迷が、明治19年4月に刊行された「中央学術雑誌」に冷々亭主人杏雨の名前で発表した「小説総論」の現代語訳である。当時四迷は23歳であり、最初に発表された文学論であった。「小説総論」は単独の評論ではなく、坪内逍遙の『当世書生気質』に関する連作評論の序論として位置づけられていた。こうしたこともあって発表当初はほとんど注目されなかったが、昭和3年に『明治文化全集』(日本評論社刊行)に収録されたことによって、その存在が広く知られることになった。現在では、「小説総論」は本格的な写実文学論として極めて高い評価が与えられ、言文一致体による写実主義小説『浮雲』は、その理論の実践であるとされている。
この現代語訳の底本としては、『二葉亭四迷全集 第5巻』(岩波書店、1965年)を用いた。あわせて『日本の文学1 坪内逍遙、二葉亭四迷、幸田露伴』(中央公論社、1969年)を参照し、十川信介先生による注解を現代語訳に利用させていただきました。記して感謝を表わします。
小説総論
二葉亭四迷 著、上河内岳夫 現代語訳
人物の善悪を定めるには自分に理想がなくてはならない。小説の是非を批評するには、自分に定義がなくてはならない。そうであるから今、『当世書生気質』の批評をするにも、あらかじめ本人の小説の本義を吹聴して置かなければならない。本義などというものは、到底面白いものではないので、お読みになる方にも退屈であれば、書く本人にも迷惑千万で、結局はない方がましかも知れないが、これもことの順序なので、全く省く訳にもゆかない。よってなるべく端折って記すので、しばしのご辛抱をお願いします。
およそ形(フォーム)があれば、ここに意(アイディア)がある。意は形によって現れ、形は意によって存在する。物の生存の上から言うと、意があっての形、形があっての意であるので、いずれを重いともいずれを軽いともなしがたいだろう。しかしその本分の上から言うと、意こそが大切である。意が内に存在すればこそ外形に現れもするが、意は形がなくてもなお存在するであろう。しかし形は意なしには片時も存在するべきものではない。意は己のために存在するものなので、厳しく言えば形の意ではなく、意の形を言うべきである。あのベリンスキー(ロシアの批評家)が、「世の中には、ただ意匠のみが存在する」と言われたのも、強ちに出任せでもないと思われる。
形とは物である。物が動いて事を生じる。それゆえ事もまた形である。意の物に現れたもの、これを物の本分という。物質の調和である。意が事に現れたもの、これを事の本分というが、事の本分はちょうど物の本分のように、これまた形をなす所以のものである。火の形に熱の意があれば水の形にも冷の意がある。それゆえ火を見ては熱を思い、水を見ては冷を思う。梅の枝にさえずる鶯の声を聞いたときは長閑になり、秋の葉末に集く虫の音を聞くときは哀れを催す。もしこのように自分が感じる所を物に負わせれば、どうして天下に意のない事物があるだろうか。
こう言ったからと言って、強ちに実際にある某の事や某の物の中に、某の意が完全に現れていると思ってはいけない。某の事物には各々その特有の形状が備わっているので、某の意もこのために隠蔽される所があって、明白には現れがたい。これを例えると、張三も人である、李四もまた人である。[訳注:「張三李四」は、中国ではありふれた姓である張家の三男と李家の四男の意で、平凡な人物のことを言う]。人に二種はないので、差別があるべきはずはない。しかるにこの二人の者を見て、私が感じる所に差別があるのはなぜか。人の意が尽く張三に現れていると言うと、かの李四はどうだろうか。もし李四に現れていると言うと、かの張三はどうであろうか。そうしてみると張三も李四も人は人に相違がないが、これは人の一種であって、真の人ではない。それゆえいまだ完全に人の意を現すのには十分ではない。思うに人の意は、私の頭の中の人において現れるものであるが、実際の個々の人において完全に現れるものではない。その理由はなぜかと尋ねると、実際の個々の人においては各々自然に備わる特有の形があって、かの人の意もこのために妨げられて、ついに完全には現れがたいことによるのである。ゆえに言う、「形は偶然のもので変更は常ならず[一定しない]、意は自然のもので万古易らず」と。易らないものは当てにできるが、常ならざるものはどうして当てにできるだろうか。
偶然の中に自然を詮索し種々の中に一致を詮索するのは、天性の需要として人間にはなくてはならないものである。詮索と言ってもそのやり方には二つの様式がある。一つは知識をもって理解する学問上の詮索、一つは感情をもって感得する芸術上の詮索である。
知識はもともと感情の変形で、俗にいわゆる知識と感情とは、古参の感情と新参の感情ということだなどと論じ出すと面倒臭く、結局は当惑の種を蒔くようなものである。そこで使いなれた知識と感情という用語で言うと、おおよそ世の中の万端のことは、知識ばかりでもうまくいかなければ、また感情ばかりでも埒が明かない。「二二んが四」[掛け算の九九]ということは、知識では合点するだろうが、よく人の言うことであるが「[浄瑠璃節の]清元節は粋で、常磐津節は身がある」ということは、感情でなくては了解できないことである。知識の眼から見るときは、清元節でも常磐津節でも、およそ「声楽」[ここでは三味線伴奏による語り物音楽]というものは、みな人間の声に調子を付けたもので、その調子に身のあるものは常磐津節となり、粋なものは清元節となると、まずこのように言わなければならないはず。しかしもし「その身のある調子とか、粋な調子とか言うものは、どのようなものでございますか、拙者はいまだ食べたことはございません」と、剽軽者がいて問いを起したならば、たとえ富楼那[弁舌第一といわれた釈迦の弟子]の弁舌があって1年360日しゃべり続けにしゃべったとしても、この返答はしきれないであろう。そんな無駄口に暇を潰すよりも、手っ取り早く清元節と常磐津節とを語り比べて聞かせるのがよい。その人の耳が悪いのでなければ、手を打ち合わせて「なるほど」と言われるのは必定である。これは結局のところ、清元節や常磐津節は直接に聞き手の感情の下に働き、その人の感動(インスピレーション)を喚起し、こうして人の扶助を待たずに、自らよく説明するからである。これを某学士[有賀長雄『文学論』]の言葉を借りて言えば、これは物の意が保合[意と形の統一]の中に現れたものと言うべきか。
ところで粋や身という意は、天下の意であって、一つ二つの声楽曲が私有するものではない。ただ声楽は天下の意を採ってこれに声の形を付し、それによって一個の現象とならしめたまでである。それゆえ意がいまだ声楽に現れない前には、宇宙間の森羅万象の中にあるには相違がないが、あるいは偶然の形に妨げられて、あるいは他の意と混淆していて、容易には了解できるものではなかった。こんなに了解できない無形の意を、ただ一つの感動(インスピレーション)によって感得できるように、これに声楽という形を付して普通の人にも容易に感得できるようにしたのは、芸術の功績である。ゆえに「芸術は感情をもって意を詮索するものである」と言うのである。
「小説には勧懲[勧善懲悪]と模写の二つがあるが、しかじかの理由で模写こそが小説の真面目である。そうであるのに今の作者は無知蒙昧で古人の出任せに誤って、痔持ちの治療でもするように、むやみやたらに『勧懲、勧懲』と言うのは何事だ」と、近ごろ二、三人の学者先生が歯ぎしりをしてもどかしがられたことは、ごもっとも千万と思われる。お読みいただいている本人の芸術の定義を拡充して、これを小説に及ぼしたとしても同じことである。そもそも小説は浮世に現れた種々雑多な現象(すなわち形(フォーム))の中で、その自然の情態(すなわち意(アイディア))を直接に感得するものであるので、その感得を人に伝えるのにも直接でなければ適わない。直接になろうとするには模写でなくては適わない。それゆえ模写が小説の真面目であることは明白である。かの勧懲小説とはどのようなものであるのか。写実主義(リアリズム)を軽んじて二神教(デュアリズム)[二元論]を奉じ、善は悪に勝つものという当て推量を規範として世の中の現象を説明しようとする。これは仏の教えの提灯持ちで、小説めいた説教にすぎない。どうしてそれを呼んで真の小説とすることができるだろうか。とは言え「模写、模写」とだけ言って、どのようなものかを論定しておかなければ、こちらにも胡乱な所があるというもの。よって試みにその大略を述べると「模写ということは実相[すなわち形]を借りて、虚相[すなわち意]を写し出すということ」である。前述のように、実相界にある諸現象には自然の意がない訳ではないが、偶然の形に覆われて判然とは了解できないものである。小説に模写した現象も、もちろん偶然のものには相違はないが、言葉の言い回し、脚色の模様によって、この偶然の形の中に明白に自然の意を写し出すこと、これが模写小説の目的とする所である。そもそも文章は活きている必要があり、文章が活きていなければ意があっても明白になりがたい。脚色は意に適切である必要があり、適切でなければ意は十分に発達することができない。意は実相界の諸現象にあっては自然の法則にしたがって発達するものであるが、小説の現象の中にはその発達も得てして論理に適わないものがある。例えば恋情の切実なものはしばしば人を殺すということを意とする小説があるとして、そのご本尊の男女の者がともに浮気な性質で、「末の松山浪越さじ」[絶対に心変わりするまい]との起請文もすっかり目前の空言、一時の戯れであるとすると、結末に至り他に仔細もないけれど、ただ親父の不承知によって、手に手をとって川の中に身を投げるという段になると、これではどうやら洒落で命を棄ててみるように聞こえて、話の筋道がわからないといった類いは、これではいわゆる意の発達が論理に適わないもので、意があるといってもないのと同じである。これを出来損い中の出来損いであるとする。[訳注:「末の松山浪越さじ」は「君をおきてあだし心をわが持たば末の松山浪も越えなん」(『古今集』読人しらず)による]
そもそも一口に模写と言っても、どうして容易なことになるだろうか。王羲之[中国の書家]の書を「あれでも」書家が真似したとしても、その筆が意をとることは難しく、巨勢金岡[平安の宮廷画家]の絵を三文絵師が引き写しにしたとしても、その神髄を伝えることは難しい。小説を編むのも同じことである。浮世の形を写すことさえ容易なことではないのに、ましてその意を写すことができるだろうか。浮世の形のみを写してその意を写さないものは下手の作である。意と形を写して完全に備えるものは上手の作である。意と形を完全に備えて活きたようなものは名人の作である。思うに意の有無とその発達の巧拙とを考察し、これを論理的に考え、これを事実に徴して、それによって小説の価値を定めるのは、批評家がまさに努めるべき所である。
(明治19年4月「中央学術雑誌」)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
