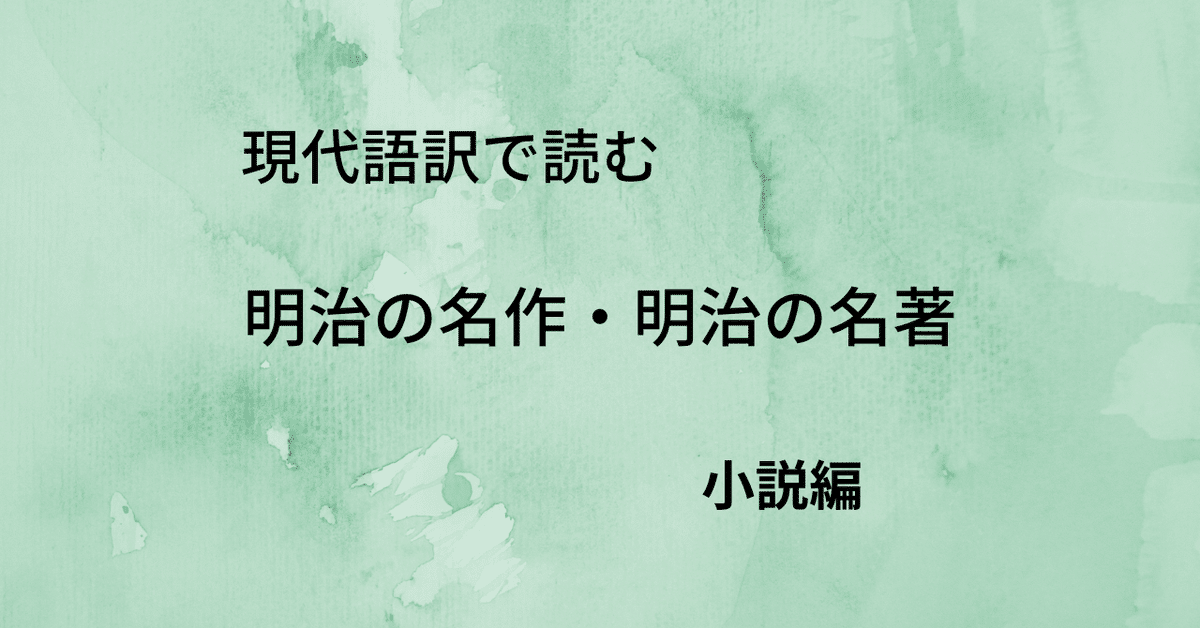
仮名垣魯文「安愚楽鍋」現代語訳
明治4~5年に5分冊として誠至堂から刊行された仮名垣魯文の代表作『安愚楽鍋』の現代語訳である。
幕末から活動していた戯作者の中で、明治の新時代にいち早く対応したのが仮名垣魯文であった。明治3年に『西洋道中膝栗毛』の刊行を初め、明治9年に全15編30冊として完成させた。ただし、第12編以降は友人の総生寛に譲る形であるが。この作品は十返舎一九の『東海道中膝栗毛』をもとに、弥次郎兵衛と喜多八の孫がロンドン万博に出かけると言う設定で、福沢諭吉の著書や旅行者からの聞き取りに基づいて書かれたものである。当時は大いに人気を博したものの、人種差別的な笑いを含んでいることもあり、現代人にはあまり楽しめるものではないだろう。
これと並行して刊行をはじめたのが『安愚楽鍋』で、式亭三馬の『浮世風呂』をもとに、舞台を銭湯から文明開化の新風俗である牛鍋屋に移して、そこに集まるさまざまな客の会話を描いたものである。魯文が飲食店の広告ビラを制作するコピーライターとして活動していたこともあって内容は写実的であり、文明開化に対する庶民の反応をありありと描いている。この作品は開化期の風俗をうかがう資料、あるいは明治初期の口語を研究するための素材としても使用されている。ドナルド・キーンは、「『安愚楽鍋』は小さな傑作で、明治の小説の中で、今日でも楽しんで読める最初の作品となった」(『日本文学散歩』)と評価している。
『安愚楽鍋』は江戸の伝統の形式によって刊行され、全体は3編からなり、初編、2編(上、下)、3編(上、下)の5分冊として刊行された。3編の最後には、4、5編の続刊が予告されているが、実際には刊行されなかった。いくつかの序文などに加えて、全部で18話からなる。各話に共通する登場人物はおらず、各話が完全に独立した短編集であると考えることができる。現代語訳に当たっては読みやすさを優先して、古い形式を残すよりも現代的な形に変更することを選んだ。全体の18話に番号を付した。各話は、最初に小さな文字で人物の紹介があり、その後に会話が続くという、江戸の戯作によくみられる形式で書かれているが、文字の大きさではなく両者の間を線で区切って表示することにした。会話については全体が一人語りの場合には、会話を示す「 」を除くなど、現代的な表記に直した。また、原本では段落が設定されていないので、これも読みやすさを考えて訳者が設定した。原本には各章に挿絵が付いており、服装などを理解する上で大いに役に立つものである。挿絵については、原本を「古典籍総合データベース」(早稲田大学)や「国会図書館デジタルコレクション」などで見ることができるので、ここでは掲載しなかった。
さらに、江戸の戯作本では末尾以外に広告が入ることがある。現代の読者は本来読みとばすべき広告を、小説の一部と誤読してしまうことがある。このため、あえて以下の部分を訳から除外することにした。
① 初編の「標目従初編至弐編」:標目とは目次のこと。初編について目次だが、二編については予告になっている。実際の二編はこの予告通りにはなっていない。
② 二編の「西洋料理通跋」:魯文の近刊の料理本『西洋料理通』(明治5年刊)の広告として、その跋文(後書き)を掲載している。この料理本は「横浜に居留するイギリス人が日本人の使用人に料理を指示したメモ」を入手して執筆した実用書である。
③ 三編の「告條」:告條とは広告のこと。特に「飲食店のビラ」の製作で大きな評価を得ていた魯文が、コピーライターとしての仕事を求める広告であって、この部分自体が一種のサンプルになるという手の込んだものになっている。
現代語訳の底本としては、『明治開化期文学集』(「日本近代文学大系 1」、1970年、角川書店刊)に所収のものを用いました。興津要先生の注釈から多くを学び、それに大きく依拠して現代語訳に取り組みました。深く感謝を表します。あわせて坪内祐三他編集『仮名垣魯文』(「明治の文学 第1巻」、2002年、筑摩書房刊)に所収のものを参照し、脚注の一部を現代語訳に利用させて頂きました。深く感謝を表します。
現代語訳「牛店雑談:安愚楽鍋 一名・奴論建」
ー 牛鍋屋の雑談 気楽に胡座をかいて食べる鍋 一名・酔っ払い ー
仮名垣魯文 著 上河内岳夫 現代語訳
Ⅰ 安愚楽鍋 初編全
初編自序
世界各国の諺に「フランスの着倒れ、イギリスの食い倒れ」と食卓のメニューのように並べるが、衣料は肌を覆う入れ物で、食料こそが命を繋ぐ鎖である。奔馬や野猿が騒ぐように抑えがたい煩悩を止めて、咲いた桜の花より団子。色即是「食う」。色気よりは食い気が先で、佳美肉食。牛に惹かれて「膳好(お膳を好む)方便」。[牛に引かれて善光寺参りと仏教の「善巧方便」をかける]。仏教徒の五戒はサランパア[放っておいて]。虚実の内外を西洋風味に和え混ぜて、世間によくなれた甘口が、作者の例の手前味噌ですが、その家言[加減をかける]が悪くてはかどらず、あの牛の小便が18町も続くようにだらだら。急案に即席で調理しました[急にアイデアを思いついて執筆しました]。[牛鍋に入れる]刻み葱の五分ほども透きがない積もりで、あれこれタレを按排しました。生肉のお代りは後にして、一鍋に箸をつけてください[まずこの本の覆いをとってください]。文明開化の開店の広告文めかして申し上げます。
明治4年辛未の卯月初めの5日
東京[日本橋]本石町萬笈閣[版元名]の隠居において
牛の煉薬「黒牡丹」の製造主 仮名垣魯文題する
開場
天地は万物の父母であり、人は万物の霊長である。それゆえに五穀草木、鳥獣魚肉、これらが食となるのは自然の理であって、これを食べることは人の本性である。昔々の俚諺に、ももん爺の狸汁に、因果応報で穢れを浄める、かちかち山の切火打がある。[「かちかち山」の昔話として、お爺さんがつかまえた狸に、お婆さんが殺されてかわりに狸汁にされ、その敵討ちにうさぎが、狸の背負った柴に火打石で火をつける話がある]。
あらたまの[月にかかる枕詞、月の]うさぎも吸物で味をしめ、この食い初めによって、そろそろと開化した西洋料理。その効能も深見草[牡丹の別名]。牡丹[猪肉]や紅葉[鹿肉]は時季を選ばず、猪より先へはだらだら歩きで、たとえ遅くても怠らず、往来が絶えない浅草通り。蔵前の定店の名高いフラグ(のぼり旗)には「牛肉鍋」。十人寄れば十種の注文。昨晩人気の味噌を挙げて、タレを利かせるのは、朝帰り。生肉のお代りをする粋がり連中に、西洋書生や漢学者流、劉訓に似た儒者があれば、肖柏[室町の連歌師]めかす僧もある。士農工商・老若男女・賢愚貧福がおしなべて、「牛鍋を食べなければ開化が進まない奴である」と、鳥なき郷の蝙蝠傘[を持つ者が言う]。鳶合羽の翼をひろげて、遠くから来る者は人力車で、近くの者は銭湯帰り。
[牛店は、牛鍋のほかに、販売もしていて]薬食い[牛肉]、牛乳はミルク、乾酪は洋名チーズ、乳油は洋名バター。牛陽[牛の陰茎、強精剤]は、ことに潔く「あの肉陣の兵糧に」と、土産に買う者も非常に多い。人の出入りが賑やかで、混み合いの節には、「[順番の]前後に御容赦を」、「御懐中物には御用心を」。「銚子のお代り」、「お会計」、「お帰んなさい、いらっしゃい」と声がかかる。実に流行は昼夜を置かず、繁昌ぶりはこの通りである。されば「牛は牛連れ」と仲間を求める肉食の群集が、席を区別する様子を、個々別々に穿って言えば、ざっとした所がまずこんなものになろうか。
1 西洋好きの聞き取り
年の頃は34、5歳の男。色は浅黒いけれど、石けんを朝夕使うと見えて、あか抜けて色艶がよい。頭は撫でつけか総髪にでもなるところが、百日このかた生やしたのを右の方へ撫でつけ、もっともオーデコロンという香水を使うとみえて髪の毛のつやはよく、髷は格別に大きくはない。絹衣の道行[和服用外套]ぶったものに、唐糸双子の綿入れまがいを身につけている。更紗の下着[和服の重ね着で内側に着る衣服]は、裏は張り返しの額裏であるにちがいない。金巾で張ったこうもり傘をかたわらへ置き、苦しい算段で買い求めた袖時計の安物を襟から外して、時々時を見るのはそっちのけで、実は他の者への見せかけ[時間はどうでもよく、時計を自慢したいの]である。ただし鎖は金のてんぷら[金めっき]と見えた。隣で牛を食べている客に話をしかける。
―――――――――――――
もし、あなた。牛は至極よい味ですね。この肉が開けると、牡丹[猪肉]や紅葉[鹿肉]は食えはしない。こんな清潔なものをなぜ今まで食わなかったのでございましょう。西洋では1620、30年前から、もっぱら食うようになりましたが、その前は牛や羊はその国の王か全権と言って家老のような人でなければ、普通の人の口へは入りませんのさ。おいおい我が国も文明開化と言って開けてきましたから、我々までが食うようになったのは、実にありがたいわけでございます。それをいまだに「野蛮の弊習」と言ってね、開けない奴らが、「肉食をすれば、神仏へ手が合わされねえ」の、「やれ穢れる」のと、分からない野暮を言うのは、究理学[哲学]を弁えないからのことでございます。そんな田舎者に、福澤諭吉の書いた「肉食の説」でも読ませたいね。
もし西洋にはそんなことはございません。(この人は「ございません」を「ごうせん」などと言う癖がある[この現代語訳では「ございません」を採用])。彼方はすべて理で押して行く国柄だから、蒸気の船や車の仕掛けなどは恐れいったものだね。すでにご覧なさい、伝信機(テレグラフ)の針の先で新聞紙の銅板を彫ったり、風船で空から風を持ってくる工夫は妙ではございませんか。あれはね、もし、こういう訳でございます。地球の図の中に「熱帯」と出ている国があるがね。あそこが「赤道」と言って日の照りが近い土地だから、暑いことはたまらない。そこで国の人が日に焼けて、みんな色が黒くなる。それだから、その国の王がいろいろ工夫をして、風船というものを造って、大きな円い袋の中へ風をはらませて、空から下ろすとその袋の口を開きます。すると、大きな袋へ一杯にはらませてきた風だから、四方八方へ広がって国内が涼しくなるという工夫でございます。
まだ奇妙なことがあります。ロシアなどという極寒い国へ行くと、寒中はもちろん夏でも雪が降ったり、氷が張るので往来ができません。そこで彼の蒸気車というものを工夫しましたが、感心なものだね。一体に蒸気車と言うものは、「地獄の火の車」から考え出したのだそうだが、大勢を車へ乗せて、車の下へ火筒をつけて、その中で石炭をどんどん焚くから、車の上に乗っている大勢は、寒気を忘れて、遠道の通行ができましょう。なんと考えたものだね。何さ、このくらいの工夫はあっちの手合いは朝飯前です。
この大千世界の形象さえ、混沌として毬のようであると考えたわさ。それ以前は、釈迦如来が須弥山と名づけたところが、西洋人はまんまんとした海上を渡って、世界の果てから果てまでを見極めたのだから、釈迦坊も後悔したそうさ。そこで海を渡る工夫を、西洋では「後悔術」[航海術のしゃれ]と言いますわな。・・・おや、もうお帰りか。はい、さようなら。・・・おいおい、ねえさん、生肉で1合、五分葱も一緒に、頼む、頼む。
2 怠け者の廓話
年は24、5歳で、色が生白く、頭の髪はたくさんで銀杏に結い、噺家の円朝まがい。お召の藍微塵の小袖一つ、胴着は定めし女物を直したものと思われる。2、3日も遊里に居続けて、ぼんやりした姿で、少しやつれを見せるたちである。銀鎖が16本の煙草入れは、本物か怪しいもので、7度焼きの如心張りの煙管、根付は象牙の鏡蓋で、これも仕入れ物と見えた。時々腕をまくって、腕守りの金の金具をひけらかし、連れと二人、差しつ押さえつ[他人の杯に酒をついだり、他人からの酌を押しとどめたりしながら]飲みかけ、目のふちを赤くして、黄色い声の高調子である。
―――――――――――――
[訳者注:吉原遊廓ではまず引手茶屋に寄り、そこから気に入った遊女の部屋へ案内される方式をとる。遊女と初めて会うのが初会、次が二会、そうして3回通って初めて馴染みとしての親密な関係になる。その際には祝儀金が必要であり、かつ他の遊女との関係が制約される]
半ちゃん、夕べの世界は、おいらは実にふさいだよ。あの楼へは、3、4度登楼したことがあるのだから剣呑だと言うのに、竹坊がむやみに「あがろう」と言うから。お前は一件[馴染みの遊女]の所へ脱走してしまうし、おいら一人で他へあがるのも面白くないから、平気な顔であがりこんだ所が、あいにくと二会までいった遊女が、おいらに出っくわしたろうではないか。こいつは甘かったと思ったけれど、引き付け[引き合わせ]の時にごまかして脇を向いていたから、お茶屋が気をきかして『へい、お召しかえ』と、早く切り上げたので、その場は切り抜けたが、番新[番頭新造、おいらんの世話女郎]めが、おいらの顔を見おぼえていやがって、遊女の部屋へひけて座敷へ入ると、すぐに『もしえ、主やあよくきなました。人が悪うざんすよ。これさ、お茶屋の人、この客人は先月の3日に、田町の弁天平野から三人一座で二会に来なましたお客だますよ』と敵[相手のおいらん]に声をかけられたから、後ろを見せるのも外聞が悪いとは思ったが、馴染金の散財には代えられない。これを聞くやいなや小便に行って、その帰り足で階段をトントン。『履き物を』と自ら声をかけて、茶屋の女を「置き去りまいねん、さっさとござれや」[年末の門付の囃し文句]という身で飛び出して、茶屋まですたすた帰った所が、女中が後から追いかけて来て、『何かお気にさわったことでもございましたか』は、ええこう、いいじゃあないか。
だがな、おいらのように年がら年中吉原へばかり入り込んでいては、顔が悪くなって、先がこわがって相手にしないから、嶋原[築地新富町の新島原遊廓、本章末の訳注参照]へでも巣を替えようと思っているのさ。なんだっても丸3年というもの、ひと晩も欠かしたことがあるめえじゃあねえか。それだから宝槌楼の言葉の「こうなんし、ああなんし」から、鶴泉の「くされている」「だしきっている」、平泉では客を古風に「主」と言ってさ、「なんだます」「じれってえ」と言うことから、松田屋のつの字ことば[語尾の「す」が「つ」に聞こえる]。角海老の早や言[言葉を速く話すこと]に、岡本屋の「くるわよ」「ゆくわよ」、金瓶大黒では「ああやだよ」という言葉が禁じられたし、尾彦の朝の迎えの早いことや、大文字屋の気の軽いこと。伊勢六の[見識張っているといわれるのだが、実は]「大見識の内ゆるみ」までを知っているし。岡田屋の花魁[最上級の遊女]たちは『傾城水滸伝』[馬琴の作]の種本で、甲子屋の新造衆が客が来るか来ないかを茶屋に念をおすことまで承知しては、楽屋が見通しで、客になっても面白い遊びはできないから、ずっと世界を見やぶって新造買いもして見たが、「次の間遊び」[新造には自分の部屋がないので、仕えるおいらんの隣の間を使う]は、甚だ気骨の折れるものだし、いまの壮年で、あんまり老人じみるから、それも廃して芸者の所へ出かけたが、組で[銀で]80匁は続かない。
裏茶屋入りの汐待[裏通りの茶屋で機会を待つこと]も大儀だから、ぐっと色気を去って幇間[太鼓持ち]を買って遊んでもみたが、彼奴らはどうも友を呼んでならないよ。この間も新孝を誘って、金子[吉原の有名な料理屋]へ夕飯を食いに行くと、後から喜代寿に正孝、序作、露八などという流行っ子が、どかどかと押し込んで来て、かけがえのない大札をとうとう一枚こすらせられたぜ。もうもう吉原はごめんごめん。しかし今夜は廓の名残に、かの一件[馴染みの遊女]の所へ出かけるつもりだが、もう一晩つき合うべしさ。なに『また株[お得意の決まり文句]だ』。いやさ、実に今夜で、根っきり、葉っ切り、本当にこれぎり、これぎり。さて、お銚子も御積り[これでおしまい]だ。
[訳注:「嶋原」とある新島原遊廓は、築地の外国人居留地近くに外国人を当て込んで作られた遊廓で、明治2年に明治新政府の最初の事業の一つとして完成した。名前は京都の島原遊廓にちなんだもので、遊女の数が1700人という大規模なものであったが、居留地の外国人はそう多くはなく、しかも宣教師が大多数だったので、見物には押しかけたけれど実際に登楼する者はほとんどいなかった。また、士族はここに近寄らず町人しか来なかったことから全く繁昌せず、明治4年には廃止された。サイデンステッカー『東京 下町山の手 1867-1923』(安西徹雄訳、講談社学術文庫、2013年)による]
3 田舎武士の独り飲み
年の頃は30歳ばかり。色はあくまで黒く、頭は自鬢[自分で髪を結うこと]の草束ね、もっとも総髪は火のつきそうな乱れ髪で、黒木綿の紋付と鈍付布子に小倉の汚れ腐った袴である。短い一本刀の柄が汚れることを厭うのか、あるいは柄糸のほつれを隠すためか、白木綿でぐるぐると巻きつけ、つんつるてんの着物を腕まくりして斜に構え、よほど酔いが回ったと見えて、割り箸の先にタレのついたのを二本つかんで、手拍子を打ちながら、どすのきいた大声で詩を吟じる。
―――――――――――――
〽 衣は骭に至り~い、袖は腕に至る~う。
腰間秋水、鉄を断るべし~い。
人触れば人を斬り。馬触れば馬を斬る~う。
十八 交わりを結ぶ、健児の社あ―――
[訳注:当時流行した頼山陽作「前兵児の謡」の前半。山陽が薩摩を訪問した時に薩摩隼人をたたえて作ったもの。大意:衣服は足のすねまで、袖は腕までの短いものであるが、腰の刀は鉄を斬るほどである。触れる物は人でも馬でも斬り、18歳になれば健児の団体に入る]
「これこれ女子、酒を持って来ないか。これこれ、そしてな生肉の柔らかいのをいま一皿くれんか。ああ、愉快じゃ愉快じゃ・・・」
とあたりをきょろきょろ見回して、隣にいた侍をじろりと見やり、崩した膝を立て直して、「はあ、失敬ごめん。・・・これこれ女子。何をまごまごしておるか。勉めて速やかにせい」
と言いながら、またこちらの侍にうち向かって
「君、牛肉は至極ご好物と推察仕るが、僕なぞも誠実に賞味いたすでござる。いや、このような物価沸騰の時勢に及んで、割烹店などへ罷り越すなどという義は、いわゆる「激発の徒」でござる。この牛肉という物は、美味極まるのみならず、開化滋養の食料でござるて。いや何かと申して失敬ごめん」
「これこれ女子。ちょっと来んか。これ、あのうな、生肉をな、一斤ばかり持参いたす[土産にする]ので、至極の正味を周旋いたしてくれい。ああ酩酊極まった。・・・おお生肉か、ええわええわ。会計はなんぼか」
甚句 〽 愉快きわまる陣屋の酒宴、中に益荒男美少年――
と鼻歌を歌いながら、荒々しく刀を下げ、竹皮の包みを柄にかけて
「女子、また来るぞ」
と朴歯の履き物をがらがらさせて、表へ立ち出て
〽 敷島の大和心を人問わばあああああ、
朝日にい、匂うう、山桜花あああ―――
4 野太鼓のおべっか
[訳注:野太鼓あるいは野幇間とは、芸もなくただ客の座をとりもつだけの太鼓持ち、素人の太鼓持ちのこと]
年の頃は32、3歳で、顔は細長く、背のひょろりとした男[野図八]。藍微塵の御召縮緬、唐更紗は縁ばかりの下着[和服の重ね着で内側に着る衣服]に、揃え絹縮の栗梅に染めた羽織へ小さく五ツ所紋を付け、上州博多の船格子、糊の強い帯を締め、まがい珊瑚樹の緒締めを付けた黒桟の一つ下げ、根付は角にて唐獅子を作った古風な細工。煙管は石州張りのてんぷら[メッキ]である。時々眉毛を上げ下げし、口をつぼめて物を言う癖がある。連れの若旦那[浮さん]は、かねて得意の客と覚しく、浅草の地内あたりで行き会い、取り巻いて離れない様子である。
―――――――――――――
「もし、若旦那どうでげす。この節はだいぶ柳橋の辺りでお浮かれ筋ではございませんか。ええ、もしあまり迷わせすぎると罪になりますぜ。柳橋の筋は誰でございますか。白状、白状。・・・おっと忘れた、忘れた。2、3日前に嶋原の晩花楼から、飛札到来、種はここに有馬の人形筆。[急な手紙が来ました、それはここにあります]」
と、懐中の紙入れから、うやうやしく手紙を出して見せかけて
「えもし、あの娼妓は、あなたに対しては仕事を離れた扱いですぜ。いえさ、油をかける[おだてる]などというのは、一通りのお客です。あなたと拙者のその仲は、昨日や今日のことではない。まあ、お聞きなさい。この間、晩花楼の主人の千臆さん(俳名である)へ甘海宗匠からの伝言を頼まれましたから、ちょっと顔を出したついでに、楼上[2階]へ行った所が、私を見ると、おいらんが
『野図八さん、浮さんと一緒かえ』
と次の間に駆け出して来たから、私がひとつだまくらかして
『ヘい、浮さんは、今、「さめや」(清元の栄喜の宅、引手茶屋)に寄っておいでなさるから、すぐに後から・・・。おいらん、ご愉快。何か、おごりなさい』
と十八番の鉄をきめると、
『ああ、待ってくんなよ』
と何かそわそわしながら新造衆に耳打ちさ。私が、[遊女の] 尾車さんや連山さんの所を回ってくるうちに、金花楼の珍味たっぷりの手形[おごったという印]のビールが1本現れました。ところで、しゃあしゃあとご馳走を頂戴する間が、およそ西洋時計で1時間3ミニウット[1時間3分]ばかりの時間だから、娼妓から
『野図八さん、浮さんはどうされたのでしょう、あまりに時間がかかることだよ』
と言われてはっと胸に釘。露見しないうちに、こっちから切り上げ、揚貝、ちょんちょん幕[拍子木を打って幕を閉めたという洒落]。
『ちょっくら、私がお迎えに、行きます、さいづち、たばねのし[語呂合わせ]』
と、廊下とんびも[廊下に出て]羽を伸ばして、すたすた逃げて来たのさっさ。もし、今度はあなたとでもお供でないと、見つかればどんな目に会うかしれませんよ。ああ、あんまりしゃべって喉がひっつくようになりました。息継ぎに茶碗で一杯頂き、「[おかざき]女郎衆はよい女郎衆」、ちっと時代だが、おっと、おっとととととと、ごぜえす、ごぜえす」
と、ぐっと飲んで頭を叩き、鍋の牛をむしゃむしゃと食べる。また箸を下へ置いて
「若旦那、若旦那。ちょっとご覧なさいまし。隣の年増は、ちょっとあか抜けた身なりだが、牛を平気の平左で食べる達者さは、あれはただ者ではございませんぜ。なんでも吉原のお茶屋の妻君か、さもなければ山谷堀[隅田川から吉原に向かう堀]辺りの船宿の女房かしらん。堀では見かけない顔だが、どうも分からない。・・・おっと、堀と言えば紫玉[巴月庵紫玉、狂画師]の所へ絵短冊を客先から頼まれましたから、今戸[現、浅草]の弁次郎の所へ風炉[茶の湯用の湯沸かしの炉]の注文に行くついでに、一昨日ちょっと寄りましたら、外を有明楼へ行く芸者が、2組ほど通ります。誰だと見れば、あにはからん。もし、それの一件のお猫[芸者]さ。そら、いつか大七[向島の料理屋]から、くすねて浜中屋へ連れ出した芸者さ。本当にお前さんほど罪作りな、冥利の悪いお方はございませんぜ。彼奴は、私を見ると、紫玉の家の敷居をまたいで、
『若旦那はどうなさいました。あれっきりではあんまりですから、もう一ぺん、後生でございますよ』
とあたりに気兼ねをして、手を合わせて別れました。ねえもし、あなたはどういう腕を出して、ご婦人をお殺しになるのでげす。実に不思議、妙でございます。ああ、恐ろしい、恐ろしい」
5 職人のむかっ腹
年の頃は40歳位。大工か左官らしい身なりである。印半纏、股引に腹掛け。三尺帯は汚れているけれど、白生地の算盤染め、淀橋まがいの煙草入れ[革の煙草入れ]に厚張りの真鍮煙管。髪は、篠を束ねたようである。連れも同じく職人ながら、この人物は年嵩といい、ことに兄弟子であろうかと思われる話ぶりである。よほど酔いが回ったと見えて、巻き舌の高い声で威張ってみせる癖がある。
―――――――――――――
ええこれ、松や聞いてくれ。あの勘次の野郎ほど付き合いのねえ間抜けは、西東の神田界隈には、俺はあるまいと思うぜ。まあこういう訳だ、聞いてくれ。夕べ仕事のことで八右衛門さんの所へ顔を出すと、ちょうど棟梁が来ていて、酒が始まっているのだろう。手前の前だけれど、おらだって世話焼きだとか、犬のくそだとか[なんとかかんとか]言われている体だから、酒を見かけては逃げられないだろう。仕方がないから仲間に入って一杯やっつけたが、なんぼ先が棟梁大工でもご馳走にばかりなっては外聞がみっともないから、盃を受けておいて、小便をたれに行く振りで表へ飛び出して、横町の魚政の所へ行ってキハダマグロの刺身をまず1分あつらえこんで、内田[駒形の酒問屋]へはしけて[するりと抜けて]一升とおごったが、おれが「知らん顔の半兵衛」で帰ってくると、間もなく酒と肴がきた所から、棟梁も浮かれ出して、『新道の小美代を呼んで来い』とかなんとか言ったからたまらねえ。
芸妓が一枚飛び込むと、八右衛門頭まで浮気になってがなりだすと、勘次の野郎がいい芸人のふりをしやがって、二上りだとか湯あがりだとか、蛸坊主が湯気にあがったような面をしあがって、狼の遠吠えで散々ぱら騒ぎ散らしやがって、その挙句が人力車[掛け声からこう呼ぶ]で小塚原[千住宿(現、南千住)の女郎屋]へ押し出そうとなると、勘次のしみったれめ、「おさらば随徳寺を決めた」もんだから[逃げたから]、棟梁も八さんもそれっきりになってしまったが、ええこう、面白くもない「細工貧乏人宝」だ[小細工ばかりするやつだ]。あの野郎のように銭金を惜しみやがって、仲間付き合いを外すしみったれた了簡なら、職人をすっかり止めて人力車の車力にでもなりやがればいい。
人を馬鹿にして、こちとらあ四十面を下げて色気もそっけもないけれど、付き合いとくれば、夜が夜中、槍が降ろうとも、唐天竺からアメリカのばったん国[韃靼国の誤り]までも行くつもりだ。あいつらとは職人の質が違わあ。口幅ったい言い分だが、うちには70歳になる婆に、嬶とガキで、以上7人暮らしで、1升の米は1日ないし、夜が明けて鴉がガアと啼けば、2分の札がなければ貧乏揺すりもできない体で、年中、「十の字の尻を右へぴん曲る[七の字のこと]」のが半商売[質屋通いが商売のよう]だけれど、南京米と「かての飯」[米以外を混ぜた飯]は食ったことがない男だ。あいつらのように嬶に人仕事[裁縫などの内職]をさせやがって、自分は仕事から帰って来ると並木通り[雷門の門前通り]へ出て、仕事の休みに内職で作っておいた塵取なんかを並べて売りあがるのとは、「すっぽんにお月さま」「下駄に焼き味噌」ほど違うお職人様だ。ぐずぐずしやがると素脳天[頭のてっぺん]を叩き割って、西瓜の立売りにくれてやらあ。はばかりながら、本気のことだが、「矢でも鉄砲でも持って来い、恐れるのではねいわい」と言い掛かりは言いたくなるだろう。のう松、手前にしたところがそうじゃあないか。・・・おいおい、姉さん。熱くして、もう2合、そして生肉も代りだ。早くしろ、ええ。
6 生文人の会談
近頃流行の書画会の連中、年の頃は31、2歳位。野暮なこしらえで、身なりもそれほど悪いわけではないが、世間を見破ったつもりで着物も上下不揃いなのを意気地もなく着なし、黒の羽織、紫の太紐を胸高に結んで、見識は鼻柱とともに高く、傍らに唐紙を巻いたものと扇子を束ねたものをアメリカ更紗の風呂敷に包んでかけ置いている。下地によほど酒の匂いがあるのは、中村屋か万八[柳橋の料理屋]辺りの会くずれ[二次会]と見え、連れの者は誘って連れて行った、ただの人物と見えた。もっとも折々受け答えがあるようである。
―――――――――――――
ああ今日の会は弱った、弱った。あのように唐紙や扇面の攻め道具で取り巻かれては、さすがの僕もがっくりだ。これだから、近頃はどんなに招かれても謝礼ばかり持たせて書画会へは出ないことと決めたが、今日は南溟老人[春木南溟、画家]の喜寿の宴で、ことに南湖翁[南溟の父、江戸の画家]の三十三回の追善だから、「先生に出て貰わなければ枕山、松塘、蘆洲、雪江、東寧、帆雨、柳圃、随庵、桂洲、波山[人名は章末の訳者注を参照]の諸先生たちが不承知じゃから、ぜひに出席を願う」と、わざわざ扇面亭の善公[幇間]と広小路の一庭[画家]が使者に来たので、やむを得ず出かけたところが、肴札5枚掛けの一局[配布された酒肴券が5枚の場所]へ合併して一杯飲むが否や、『どうか先生お後で願います』と左右から扇面の鎗襖さ。「さても、うるさいことだ」とぎょっととしたが、予期していたことで「ああ、これも会主への義理だ」と観念して、書画の注文でも「扇面が2百疋、唐紙なら5百疋」と極札がついている[揮筆料の相場が決まっている]腕を、一言の礼のみで、まず4、5本に書かせられたと思いなさい。僕の体の回りを雲霞のように取り巻いて、『お後で一筆どうか、諸先生の合作でござりますから、ちょっと願います』だの、やれ『遠国から頼まれました書画帖です』だのと、たちまち扇紙が山をなしたのは実にうるさい。
早く切り上げて脱出しようと身支度をしている最中に、隣の方で酔っぱらった者が喧嘩を始めるという騒ぎで、人々が奔走する間に早々と下の階に来ると、台所で琴雅[文人]や乙彦[人情本作家]などいう風流人が内食をきめている[隠れて食事をとっている]。向こうの隅では、諏訪町[現、台東区駒形]の松本が、ええ何さ、楓湖先生[松本楓湖、日本美術院幹事の画家]が、芸者の房八を相手に大いに酔っ払って『これから船で上手[隅田川の上流]へ出かけるから、ぜひ付き合え』と困らせるので、ここにも足を止めることができない。それはたまの付き合いだから止むを得ないが、明日は大藩の知事公から召されて、お席で絹地の三幅対の山水画の掛け軸を即席でしたためなければならないから、『ちょっと付き合いは外すが、後日に』と言って、貴君の袖を引いて抜け出したが、なにか呑み足りないようだから牛店に行くと決めたのは、中村[駒形の蒲焼き屋]のような騒々しい所より落ちついて呑めるから好都合だ。
さて、まず春木氏の義理も済んだが、ええ、また来月の一日は、万八で虚堂[書家]の展覧会、二日が、ええと、寺島町の梅隣亭で席画[宴会の席で依頼に応じて即席で絵を書くこと]の約束だ。ああ、うるさい、うるさい。実に有名人に誰がした。もうもう名聞[世間の評判]は廃すべし、廃すべし。・・・おっとととと、こぼれる、こぼれる。
[訳者注:大沼枕山[漢詩人]、鈴木松塘[漢詩人]、植村蘆洲[漢詩人]、関雪江[書家]、猪瀬東寧[画家]、尾崎帆雨[画家]、福島柳圃[画家]、服部随庵[書家]、荒木桂洲[画家]、服部波山[画家]]
Ⅱ 安愚楽鍋 二編上
二編換序
牛の喘ぐわけを問う宰相もいない[漢の宰相が、気候のため牛が喘ぐのを見て、陰陽の不調を憂えた故事]。牛を羊に代えるように言う王もいない[鐘に血を塗るため引かれていく牛を見た王が羊に代えるよう指示した故事]。大牢の滋味[大牢とは天子が社稷を祭るための生け贄として牛を用いたことを言う]。煮焼いて一鍋が300銅。角を抜かれ、皮を晒され、肝を乾される。各国との交際[開国]は、汝[牛]を殺すためではない。魯酒淡くして、邯鄲が囲まれる[思いがけない災難を受けることのたとえ]。さらに災を移されたこと[食用に供されるようになったこと]を哀れむ。ああ天か時か[運命だ]。
芬兮成孚[不詳、架空の中国人名か] 題する
[前口上]
[海外で牛疫が出たという]伝染病の新聞[ニュース]に、売り広めた牛肉の効能も空しくなるかと、牛肉屋の主人は角を折り、肉を減らし、力を落とす。まるでリンデルペスト[ドイツ語、牛疫]を病んだように。予防の手立てもなかったので。
他国のことは知らず、言葉に出すのも恐れ多いが、我が国は八百万の神達と親類一家のよしみがあるので、たちまち例の神風に吹き払われて青天白日、再び栄える牛店は繁昌。わけてもこの頃は吉原と新島原の立ち退きで[吉原は火災、新島原は廃止のため]、「物を言う花」[遊女]は花川戸に、賑わう人は山の宿[山は浅草の奥山のこと]に。ふられる宵も厭わずに、泥に踏み込む田町の素見[浅草の田町は旧名が泥町であった]。
行きも帰りも流行の牛肉で一杯酒をのみ、ぱくつくのは腹組。牛の小便は18党、結ぶ交わりは健児の社中。文明開化の散切り頭に、王政復古の総髪頭に、そして因循姑息な半髪額。芸者は、箱持ちの案内に付き従って、娼妓は引手茶屋の女中に引かれて。老若男女の差別なく、ここに一群れ、かしこに二組。三人寄れば、呼び出しの揚代は36匁(当時45匁に改定)。失う知恵の割前勘定[割り勘]。腎薬[強精剤]を用いた経験は、「これから直ぐに人力車で、地元が悪ければ花川戸へ」と、浮いた駄洒落の口車で「ちょんきなほい」と押し出す。あとはお酒と生肉の鍋。まず先様は一度きりで、代わる代わるにという人心は、いわゆる覗きからくりではないか。作者の口調は、三馬三馬[式亭三馬から]。さてこれからは、本物の芝居で言えば、序幕でございます。そのための口上は、
チョンチョンチョンチョンチョンチョン、チョチョチョチョチョチョン
7 娼妓の秘密の肉食
年の頃は24、5歳。シャコとか言う髷を頭に結んで、前髪から一寸ほど上の方は、簪ずれで禿げ、眉毛は逆立って、美しいけれど、何となく恐ろしそうに見えるが、もっとも厳めしく見えるのは生まれつきである。藍微塵の御召縮緬一つで、襦袢は何やら分からないけれど、襟は絹縮の薄鼠に雁金の模様がある。帯は男物で、茶色の博多織の一本独鈷をぐるぐる巻いて、格好の悪い所を隠すため、茶縞の御召縮緬、着物と袖口の合わない袢纏を意気地なく引っかけ、よほど酔いが回ったと見えて、目を据え、腕まくりをして、茶碗で酒をあおる風体はただ者ではない。
作者が考えるに、この女は吉原から田町辺りに移転した「交じり見世」[大籬につぐ格式の店。半籬]の娼妓に違いない。『吉原細見』[ガイドブック]の位付けは、「山形にうろこ」[中流のマーク]、仲の町の呼び出し[吉原のメイン・ストリートの引手茶屋から声がかかる]ではあるが、浮気者のいなせ好き[いなせな若者好き]で、とかく町抱えの鳶の者[火消しの人足]や番屋者[番所の番人]に思いを寄せるたちで、年明き近い[年季奉公の契約期間の終了に近い]年の功で、客の扱いも巧者ながら、悪足[遊女などを食い物にする情夫]に入れあげて、座敷着は言うに及ばず、客から貰った道具をはじめ、銀の袴を履いた[銀が張ってある]象牙の箸まで、みな伊勢屋や辻屋などという質屋へ質入れして、単衣物一枚で夜具にくるまり、遣り繰り算段で「升屋」[酒屋]から一升借り込んで、茶碗酒を呷って、「脱走しようか、住み替えに出ようか」と考えの最中に、赤い風が吹いたの[吉原火事]を幸いに、田町の引手茶屋へ転がり込み、無理矢理に茶屋の女房の着物と袢纏を借り込み、茶屋の女中を連れ出して、因縁のある客の所へ押しかけていき、中宿[出会い宿]に一晩泊まって、なにがしかの小遣いをいたぶった帰り道、かの女中と二人連れで牛店に入って、夕べからの窮屈袋を開いた気まま酒と見えた。
―――――――――――――
「ねえ、おはねどん。お前の前だが、伊賀はんという人もあんまり卑怯な人ではないか。この節、上方から芸子とか舞子とかが訪ねて来たので、私の所へはぱったり足が止ったから、そのはずではあるけれど、切々と来る時分には、やれ『身請けをしよう』の、『親元へ掛け合って、もらい引きをする』のと、無理往生に私の体へ傷を付けたり、証文を書かせたりしたくせに、「樽づけ[深い仲の女]ができたから、もう用はない」というふうで、イタチが道を切ったようでさ。今度[明治5年の吉原の火事で]焼け出されたから、訪ねて行くと留守をつかって、中宿の二階に上げっぱなしの客人なんかのように、散々ぱら待たせた挙げ句が、『取り込んでいて会われないから、いずれ茶屋まで訪ねるから』とさ。
私が、あんなふざけた奴をこれまで取り留めた[客として取ってきた]のは、音ちゃんの一件から。[吉原の]仲の町中の評判も悪くなったし、馴染みの客は離れてしまったし、自分が後々のことを考えてこうと定めて、とっておきにしておいた作さんも、誰かにしゃくられた[すくい取られた]と見えて来なくなってしまうし。着物が無服で、初会にも出られない始末の所へ、『[あなたには]初会だが、[茶屋には]馴染みだから出てくれ』とお前の所のおかみさんが言ってきてくれたから、[午後12時に張り店を]退けてから床へ回ってみると、「やぁ、とこせ」[かっぽれの掛け声]の初坊が熱病を患ったような[酒に酔って赤い面]客人で、散切りの中の選りっ枯らしで、しみじみ辛うざんしたけれど、お前の家のお客だし、ことに初馴染みだからと思って、目をつむってつとめると、肌しつっこく、始終、手悪戯をしたり、力尽くで帯を解いたり、実にたまらなかったよ。
もうもう、あんな小うるさい客はつとまらないから、断わろうかと思った途端へ音ちゃんの所から、『お金を5両ばかり、貸してくれ。駐春亭で頭取出会いとの一座だから、金が足りないで、ひょっとして恥をかくといけないから、ぜひぜひ頼む』と、使いを寄越されたけれど、あの人にもこれまでたびたび入れあげて、質にやるものは小の町さん(新造の名前である)から「あなめどん」(禿[見習いの少女]の名)の着替えまで、置き尽くした所ざあますから、5両どころか1分の算段もできはしないね。しかし、あの人も肌合いな[特別の心意気を持った]商売をしているから、定めし顔尽にも関わるだろうし、「全く工面ができない」と言って、やたら働きのない女郎だと愛想をつかされるのは知れきっているから、じれったくて、小の町さんに相談をすると、あの人の言うには、『おいらん、丁度いい切れ目だから、できないと言って断わっておしまいなんし。年もいかない私の口から失礼ざますけれど、あの人と長く逢い引きをしなんしちゃあ、おいらんの身が詰まるばかりですから、どうぞこれを幸いに切れておくんなんし』と言ってくれたのざますから、私もあの人ゆえじゃあ、茶屋主には愛想をつかれるし、お客はしくじってしまうし、4年越しに「いい人」に取っていた作さんまでなくなして、素っ裸になったからには、例え住み替えに出て小格子[格下の小見世]へ下がっても、相遂げようと思い込んだ者を、今さらわずかの金銀づくで愛想をつかされるのは残念でならないし。と言って、他には算段の仕方もない。年季も急には入れられないし、どうしたらよかろうと、一時逃れに『後から持たせてあげるから』と使いを帰して、梅が枝のこと[歌舞伎の場面で、遊女の梅が枝が、手水鉢を無間の鐘(その鐘をつくと金持ちになるが、来世は無間地獄に落ちるという鐘)になぞらえてつくところ]を思い出してさ。ほんに馬鹿らしいわけざますが、広間の手水鉢で無間の鐘をつこうかと階段を慌てて駆け下りる途端に、伊賀はんが来なんしたから、ふと思い出して、お前の家へは済まないが、相対無心を言って[直接掛け合って無理にねだって]、5両もらったのを、直ぐに大音寺前まで持たしてやった。急場の恩があるから、その晩は寝ずにつとめたものざますから、[伊賀は]いい色男の気になって、毎晩毎晩、せつせつにやってくるので、日々の小遣いにも困らないし、物日のしまいもしてもらうし、座敷着も質から請け出してもらったりして、仲の町へも遊びに出られるようになって、一件[好きな人]にもたまには会えるのは、伊賀はんのおかげだと思って、いやでいやでたまらないのを、情人のように取っていたのざんすよ。
お前の所の客人を悪く言うのではないが、どこの女郎衆だって、あんな甚助の[嫉妬深い]自惚れを取り留める者があったら、賭けですよ[賭けをしてもいい]。そして普段の様子と言えば、「麻の風呂敷に茄子」(ぎすぎすすること)で、言うことが「トンボにさの字」(キザという意味)でさ。俺の遊び方はどうだの、こうだのと通がっているざんすが、「田印の青竹」(田舎者の生聞きということ)は、「牛に花林糖」ざんすよ(「もう、コリゴリ」ということである)。ええ、いけしゃあしゃあとして「焼けたら尋ねて来い」と言い上がった口を、忘れやがってさ、しぶしぶ5両ばかりの目腐れ金を出しやがったから、癪に障ってたたきつけて帰ろうと思ったけれど、中宿の手前もあるから、不承不承に持っては来たが、こればかりの端金を持って帰っちゃ、叱られるんざんすよ。
何だえ、おはねどん、遅くなるとえ。いいじゃあないか。遅くなれば人力車があるから、びくびくおしでないよ。これから帰ったら、成田屋[料理屋]か住田川[蒲焼屋]へ行って、正孝はんか民中はん[両人とも太鼓持ち]を呼びにやって、飲み直しをしましょう。何だえ、平松か錦鶴[いずれも料亭]がいいとえ。私は平松や錦鶴は、堰かれて[堰き止められて]いるんざんす。おほほほほほほ(これは借りがあるので行かれないことと見える)。・・・さあ、もう一杯、この茶碗でおあがりよ。なに、飲めないとえ。嫌なら私が飲むからおよし。冷やでもいいからもう一本。そして生で食べるのざんすから、薄く切ったのを山葵醤油をつけて、さあ早く言いつけておくんなんし。ええ、じれったい。癪に障るようーーー」
8 半可通の世間話
年の頃は 34、5歳で、あか抜けした人物ながら、「とかく聞いた風」の悪い癖がなくならない。何でも4文の[かわら版から材料を取った]世間話を知ったかぶりでして、折々に辱められても、蛙の面に水である。服装のこしらえは一々うるさいので、画面[挿絵]に譲って詳しくは言わない。皆様よろしく察してください。これも一座は二人連れである。
―――――――――――――
「ええもし、友先生、当世の形勢はおいおい開けてきましたが、商売第一の世界になったから、私たちのような怠け者は廃されるわけだね。お互いに漢語通から因循家だとか、旧弊家だとか言われるのだから、大いに流行に後れてきましたが、にわかに散切頭にもなれず、洋服の算段もできないから、半髪頭を叩かれているのだが、実に往来を歩くにも肩身が狭いようだよ。何か物欲しそうに洋巾で張ったこうもり傘を突き立てて、メリヤスの筒袍を肌に着て、一六日[当時の休日]に、[吉原の]立ち退きを冷やかすのも、あまり拙なわけだから、昨日はぐっと大ひねりの酢豆腐[知ったかぶりの若旦那、落語から]で、誘った連れは誰かと言うと、諏訪町の炭俵よ。それ、浅草河岸の炭屋さ。彼は図南[画家の山崎雲仙]の門人で、書体もかなりにできます。俳諧も相応にやります。彼の人とともに薪炭を積み込んで浅草河岸へ引いてきた大八車へブランケット[毛布]を敷き設けて、これに相乗りを決めて、車力[荷車引き]両人を雇い込んで押し出すところは、蔵前通り。人力車の往来が目まぐるしい中へ「エンサカホイ」[掛け声]と引き出したら、世間の億万の俗物めらが、「驚き、桃の木、山椒の木」。嘲るやつらを耳目に触れず、大通りを馬喰町へかかって、魚店から左へ曲がり、横山町を真すっぐに本町、室町、からから渡るのが日本橋。それから高輪十八町、牛の小便だらだらで急に鉄道見物だ。お泊まりはぜひ南品[品川遊廓]と言う所を、連れに引かれて無事に帰宅さ。どうだ。これは近頃のヒネリだろう。
時に、こう牛豚が行われては、天麩羅の種に使う所がありそうなものだが、そこまでには至らないが、使ったらきっと面白いよ。天麩羅と言えば「出揚げの扇夫」[屋台料理であった天麩羅を座敷料理として始めた。通人として有名で下述のように様々の風雅に携わった]が故人になったそうだが、彼も東京の名物者だ。「惜しまれる時に、散ってこそ」とは言うけれど、彼などは惜しむにもあまりがある人物さ。三題噺は正行流[落語の題で「楠正行」を得て「まさという男の面」とした]で、ああ執心汝の馬鹿[「嗚呼忠臣楠子之墓」のもじり]と、田町の湊屋[山谷堀の船宿兼小料理屋]に美名を残し、狂言は鷺流で凹齋仁右衛門の直弟であること、これは「このあたりにかくれもなし」[狂言の決まり文句]。清元は、お玉が池の太兵衛の直伝。一中節に静太夫の名前があり、石切河岸の是真老人[漆芸家]を、胡麻の油の煙に巻き、久保町の多賀屋[天麩羅屋]から万年町の亀水子[料亭]までを、衣の粉でかき回した手際は、なかなかの腕前さね。
腕と言えば、喜三郎[松本喜三郎、浅草の奥山(観音堂の裏、見世物小屋が多い)で人形興行を行う]の活人形が、おいおい番数がそろうが、彼奴は当世の左甚五郎だね。人物を見るとごく真面目だが、細工にかけては、おそらく日本一だろう。日本一で思い出したが、『東京中の宝を集めて、浅草の奥山で博覧会をするつもりだから、その時に世話人になってくれ』と、小林椿岳先生[画家]と平瓶雷先生に頼まれたが、いや花屋敷の地続きも、あの手合いが住めば、おいおい開けて賑わうだろう。おや、お前、平瓶雷先生を知らないか。それは写真好きの北庭筑波という変わり者よ。人間も斑葉[ごましお頭]だと、豪勢面白みがあるのう。それ、お前も付き合ったろう、横山町の大又[日本橋横山町の薬種問屋大坂屋又兵衛]よ。彼奴が、道了薩埵[南足柄の大雄山最乗寺]の開帳[両国での出開帳]で、蹴鞠の見世物を周旋して、金方を蹴散らせた[金主なのに逃げた]滑稽があるよ。出方[案内係]の者が、弁当の手当もないから大又に催促したら、蹴鞠の沓をみんなの前へ放り出して脱走してしまったのは、「沓でも食らえ」[糞でも食らえ]という謎だと言ったのは、大笑いの話ではないか。
話と言えば、小さんが横浜で夢楽と改名した所から、青木の席亭で「青海原沖津白波」という外題を出して、遊女汀江と幻小僧新吉の伝を話した所が、5百、6百人ずつ毎晩の大入りで実入りがしっかり、太った腹が膨れた所から浮気になって、ある後家鞘へ所持の山刀をはめ込んで[ある後家と深い関係になって]、「面でばかりは色はしない。腕だ腕だ」[色事は顔でなく腕でするのだ]と、渡辺綱が羅生門から土産を持って帰ったように、東京へ来てほのめかしている後から、その後家殿が追っかけてきて、とっちり頓馬な目にあって、高い座料[高い手切れ金]で落ちになって、話の市が栄えたそうだが、いや、世の中を見渡すと様々な新聞[ニュース]があるものだね。だがね、おいらぐらい流行を穿てば、戯作者や狂言作者なら、たいそうな書き下ろしができるのだぜ。一昨日、[浅草の]地内の河竹[黙阿弥]が来て、「何か新狂言の種になる話はないか」と買出しに来ると思いなせえ。その後から諏訪町[現、駒形1丁目]の魯文が「『西洋栗毛』の種になる珍説があるなら聞かせてくれ」と言ってくるし、横浜の活版局から、毎日、新聞を催促に来るし、あまり世間を広く詮索だてをするとやれ博識だの、物知りだのと言われて、うるさくってならないぜ。
おいおい、友先生、これさ、俺にばかりしゃべらせて、猪口はどうするのだな。おやおや、居眠りか。酒は御積り[これでおしまい]にして、飯にしようぜ。これさ、ぼんやりせずに、もう一杯やらかしねえ。おい姉さん、酒と牛肉の代りだ、代りだ。
Ⅲ 安愚楽鍋 二編下
9 芸者の座敷話
年の頃は28、9歳の町芸者で、あか抜けした性格。以前は検番の下地っ子[内弟子]から出て、柳橋から山谷堀、金春[新橋]に数寄屋町を踏んできた戦場場数の達者者である。ある期間、東京に不見識なことができたことから、旅稼ぎに出かけて、中山道の熊谷から忍城のある行田を経巡り、上州[群馬県]回りをして桐生に止まり、それから一度東京に戻り、横浜で稼ぎ、深川の中流の遊女屋のかかえ芸者をも勤めた、海千山千の裏を経た獣である。この頃は浅草の広小路辺りへ出てお披露目をして、ちょっと老けたけれど長年の功で押し回す大莫連[すれっからし]。座敷帰りをこっそり抜けてきたと見えて、「何どん」[巳のどん]とか言う箱回し[箱に入れた三味線を持って行く男]を連れて、着替えのままでかねて好む牛肉を食いに来たのである。酒はもちろん大酒飲みで、飲めば飲むほど色が青ざめ、酔いが回るに従って、持ち前の伝法[女がいきがって男のような言動をすること]の尻尾が現れ、立て膝になって、色気もなくぐいぐいとあおるのである。
―――――――――――――
巳のどん、私は横浜にいた時分、たえず異人館へお座敷で行って、牛というものを食べつけたら、こっちへ帰ってきても、三日にあげず食べないと、何だか体の具合が悪いようだよ。ここの店の肉も随分いいけれども、横浜でしめたてを料理番が人参とごった煮にして湯煮をし、それから本当に煮たのを食べると、実にこんな旨いものはないと思うよ。私も初めは気味が悪いし、こんな物を食べちゃ、神仏へ手が合わされないことと一途に思っていたが、お通辞[通訳]などの話を聞くと、決してそんな訳ではないと事柄が分かったから食べ始めたのだわね。
この間、寿仙[未詳]へ私の知っているシャボンさんという異人さんが来て、芸者に『食べろ』と言うと、一座が――おたまさんに、ふく松さんに、小みつさんに、おらくさんさ――みんなが異人に慣れないものだから、嫌がって逃げて歩くのを、面白がって追っかけ散らして、おらくさんをつかまえて無理に口の端にもっていったものだから、おらくさんが大声を上げて泣き出したわね。そうすると、みんなが異人さんを止めて、牛肉をペケにさせようと思ってさ、よくよく見ると、牛ではなくて、牛皮のお菓子[白玉粉で作った和菓子]だろうじゃないか。大体、今の若い芸者衆はふざけているわね。ちょっとお客にからかわれると、泣き出したり、「座敷をもらって帰る[許可を得て中途で帰る]」の、「やれ、あのお座敷へは出られない」のとさ。どこを押せばそんな音が出るだろう。
芸と言えば、「座付き」[最初に祝儀で奏する曲]が済んで、「三下がり」から「二上がり」の都々逸に、「相撲甚句」から離れると、河童が岡にあがったようで、「梅は咲いたか」[初歩の曲である]も稽古中のくせに、客の選り嫌いをして、少し向こう面[器量]がいいと、自惚れきって、三味線の胴へ枕紙をあてがう算段[客と寝ること]ばかりをして、たまに渋い客の座敷へでも出て、三味線なしで世間話にでもなると、あくびをしたり、畳のちりをひねったり、子守の子が御斎に呼ばれたようで、ざまはないよ。お客が端唄を歌うとか、一中節を語らうとか言うと、「はるさめ」や「わがもの」も終いまで満足には弾けず、「夕霞」も『まだそのくせが』という掛りの所ばかりで、「くらべぼたん」も『いちばいしほのみちのべに、提灯あれど恋の闇』で、お終いさ。それで芸者もねえもんだわね。私なんざあ、13歳の時、北廓[吉原]で披露目をして、やかましい合衆に引き回されて、お座敷のたんびに、ばちじりでコツコツやられたり、ももをそっとつねられたり、いじめていじめていじめ抜かれたかわりには、[訳注:以下は当時の有名な師匠についたことの自慢]太鼓から二挺鼓と踊りは花柳流の出稽古と西川流へかけ持ちの稽古さ。清元は山谷堀の延津賀さんに通ってもらう。長唄は弥十さんに来てもらう。一中節は代地[裏門代地、吉原の地名]の序遊さんの弟子になる。義太夫は、岡太夫さんに教わって、14歳の春に金子でさらいのあったときに、太夫衆に頼まれて、三味線を弾いてやったよ。歌沢節は虎右衛門さんや芝金さんを呼ぶにはおっくうだからと、抱えられた家で言うから、それでも知らないじゃあ、くやしいと思うので、中尾屋の美佐吉さんの所へ行って、拝むようにして教わって、30番や40の端唄は、覚えたのさ。
それだから町へ出てから、柳橋でも堀[山谷堀]でも、下谷でも、金春[新橋]でも、芸者一通りのことはつとめたから、こんな場末へ流れてきて、ひいひい芸者と付き合っているのは、恐れるけど、ばばあ芸者になっては、気が引けて言いたいことも控えめにしていれば、いいかと思いやがって、鶏卵のからが取れもしない置屋芸者のくせをして、生意気な口を聞くから、おかしくってたまらないわね。しかし、芸者の沽券も下がったが、今ではお客も、不見識だよ。ようやく二本か三本の玉を買うと盗みばかり売らせたがって[2、3回芸者をあげる代金を払うと、金を払わず個人的に会おうとして]、「お座敷でなければ、普段着のままでいいから、ちょっと挨拶に出て来い」の、やれ「親類づきあいで、一日柴又の帝釈さまへ出かけよう」のと、いろいろな熱を吹いて、送り狼のように、転んだら食おうとばかり狙って、油断も隙もありはしないよ。
町人で通人ぶって、どこ町さんだとか、また俳名だとかを名乗る猪尾助(聞いた風のことを言う奴)よりも、いっそ散切頭で、甚句持ちきりのお客の方が始末がいいよ。渡り者も刻まないから[流れ者は遊びが大雑把だから]、芸者やお茶屋のためにはいいけれども、同じ散切りの中でも、書生さんは人が悪くて、唐人のお尻が多いね[空っ穴、つまり金がない]。1、6日のドンタク(休日、オランダ語の日曜日)に、5人が一座で芸者一組くらいを、柳半[浅草広小路の蒲焼き屋]か藤本[同所の菜飯屋]へ呼び上げて、乱暴に騒ぎ散らしてドロンケン[酔っ払い、オランダ語]の挙句が、向こうの写真屋(浅草広小路の三木与一郎)へみんなを連れて押し上がって、芸者とも7人一度に、ガラス一枚へ写させて[写真をとって]、お茶やお菓子を散々荒らしてさ。私たちが、後で先生へ言い訳をするのが、どんなにつらいか知れはしないわね。
もうもう芸者も先が見えてきては、あがったりだよ。ほんに因果な商売で、いつまでもうだつは上がらないと思うから、これまでたびたび見切って足を洗ったが、亭主を持って貧乏でもすると、「こんなしみったれな世帯を張るよりは、いっそ芸者がましだろう。もう2、3年うはうはして暮らしてみよう」と、引き眉をしたり、お歯黒を研き落としたりして、披露目直しをしたのもたびたびだが、何になっても濡れ手で粟をつかむようなことはないねえ。ほんにさ、芸は身を助けるほどの不幸せとやらで、「川だちは川で果てる」[その人の得意の技が、身を滅ぼすもとになる]わね。
おや、巳のどん、お前もう、御膳か。なんだね、まだいいじゃねえか。もう一杯、お飲みったら。・・・もし、姉さん、あの、ご面倒ながら、生で食べるのだから、精肉を薄切りにして、山葵醤油をつけて二人前おくれよ。そして、お銚子をごく熱くして、急いで持ってお出で。ついでに五分葱とお香の物をさ。おやおや、向こうにいる散切りは、きのう八百松[吉原の一流料理店]で呼ばれたお客だよ。間が悪いねえ。巳のどん、衝立をこっちへ寄せて、私のかげをかくしておくれ。どうしたらよかろう。ええ、かまわない。ちょっ、知られたら知られたときのことさ。ねえ、巳のどん。
10 物知らずの無茶論
年の頃は40歳くらいで、居職[自宅で仕事をする職人]の態の男である。他には道楽はないけれど、毎晩、軍団の席に攻めかけ、常連の内に入り、高座の際へ付いて、講釈師の息継ぎや中入りの間などに話などをしかけて、何も知らないくせにつべこべと口を出す癖がある。しかし、いろは47文字がようやく読めるほどの非識字なので、好きで和漢の戦や故事などを聞いても、耳から耳へ抜けるうちの楽しみである。そうではあるが、少しは聞きかじって、連れの男に話しかける。連れの人物も気の合った仲間を求める「読めぬ同志、書かぬ同志」ゆえ、よい話し相手である。
―――――――――――――
安さん、お前はとかく[麗々亭]柳橋や[三遊亭]円朝の続き話[連作落語]が好きだけれども、ちょっと講談の方を聞いてみなさい。それは「天下のご記録読み」だから、また落語なんかとは違って実があるね。今節は駒形の席へ昼は[松林]伯円、夜は[伊藤]燕尾が出るが、なかなか面白いぜ。落語もおかしくっていいけれど、根がこしらえ物だから、聞いてしまってからは夢を見たような心持ちだが、そこは実録のみっしりした徳には、太閤記でも三河後風土記[家康の物語]でも豪勢なものだよ。ちょっとした所が、太閤秀吉公の知謀などというものは、すばらしいね。生まれが尾州[尾張]愛知郡、中の中村の百姓、築網[正しくは「竹阿弥」]という網打ちの漁師の子で、お袋様は在郷中納言[正しくは「在五中将」]、ええ、何とか言う公家の娘、おお、それそれ藤原行平朝臣[正しくは「在原行平朝臣」]さ。この朝臣様がね、何かしくじりがあって須磨の浦へ流された、と思いなさい。その浦の汐を汲む海女となれそめて、その腹へできたのが太閤様のお袋さ。だから後に前の関白大名大尽[正しくは「太政大臣」]といわれるほどの子を産んだのだ。だが因縁というものは恐いものさね。それから、その公家の娘を、お袋の海女が手塩にかけて育てた所が、父無し子だもんだから、土地の者が馬鹿にして、『おめえのとっさんは何だ何だ』とからかわれると、その娘が『あまが子なれば父も定めず』という歌を詠んだもんだから、『なるほど公家の落し胤に相違ねえ』とみんなが感心したろうではないか。だが『歌というものは豪勢徳のあるものだ』と、この間、[伊藤]花清が講談の引き語[説明のため本編以外に引かれる話]に言ったが、違いないぜ。火傷をした時には、『猿沢の池の大蛇が水まして、いたまず火滅す、ひりつかず、あびらうんけんそはか』という歌を3べん唱えれば、即座に直るし、針がなくなった時には、それ、『清水の音羽の滝は尽きるとも、失せたる針の出でぬことなし』と、これも3べん唱えると、直ぐに針が出るというから、不思議ではないか。
不思議と言えば、道灌山[現、西日暮里]の螺抜けよ。[明治4年に道灌山で山崩れが発生して、螺貝が昇天したという噂が立った]。あそこを道灌山とつけたのは、昔、太田道灌という人が城を築いた場だからさ。そこでその人がつねに戦に用いた螺貝を天下太平になったから山に埋めてしまったのがだんだん育って、今度抜け出して天上したという評判だが、これはありそうなことだね。なに『道灌も歌を詠むか』だって、歌を詠むの候の権八じゃあねえ[歌を詠むなんて、そんなものではない]。その時分大日照りがあって、青天60日の間、雨というものは一粒も降らなかった時、相撲の太鼓を担ぎ出してドデフルドデフルと叩きながら、三囲の土手[向島の墨堤]をあっちこち雨乞いをする所へ、道灌様が行き会わせて、『いそがずば濡れまじものを夕立や田を見めぐりの神ならば神』[道灌の「急がずば濡れざらましを旅人の後より晴るる野辺の村雨」と其角の「夕立や田を見めぐりの神ならば」の混乱]と詠み上げて、三囲の稲荷のご神前へ納めると、今まで晴れ渡った空が一面に雲ってきて、たちまち大雨が降り出したものだから、道灌様も濡れしょぼたれて、関屋の里のある百姓家へ飛び込んで、『雨具を貸してくれ』と頼むと、内からきれいな娘が山吹の花を盆へのせて持って来て物も言わずに出すと、そこは物知りだから考えたね、万能集[万葉集の誤り]とかいう歌の本の中に、『何とやらして山吹みのひとつだになきぞかなしき』[七重八重花は咲けども山吹の実のひとつだになきぞ悲しき(兼明親王、後拾遺和歌集)]という句があるさ。それを引き語にして、簔一つもないと断わったのが、藪にも功の者[草深い所にも立派な者がいる]、百姓の娘でも馬鹿にはならないさ。山吹というものは花が咲いても実がならないからのことを引き出したのは、恐れ入ったものではないか。だから理詰めほど恐いものはないと思うよ。恐いと言えば、この牛はしめたてだと見えて、だいぶこわいぜ。これこれ、姉え、すき焼きにして、もう一鍋、早く早く。
11 人力車引きの語り
当時開けた人力車の車夫の二人連れ。昨日、近在へ行く長丁場でしっかりとせしめた骨休めで、体の養いに牛を食べに来たとみえて、単衣物の下着に、白い筒袖を着て、牛の精と酒の温もりで寒さを忘れ、両肌を脱ぎ、筒袖の肌着を現した態の図のようである。五郎八茶碗で、差しつ押さえつ[他人の杯に酒をついだり、他人からの酌を押しとどめたりしながら]、よほどのドロンケン[酔っ払い]である。
―――――――――――――
力や、俺は昨日ほど骨の折れた仕事はなかったよ。朝っぱら新橋まで急ぎの仕事で、浅草見附[現、浅草橋]から2朱と2百の立前[車代]で引いてくと、橋際で下りたから、帰りを乗せて来ようと呼びかけていると、俺が前に赤岩[大伝馬町の駕籠屋]で働いていた時分に馴染みの伝馬町の唐物屋[舶来の雑貨品店]の番頭が鳶合羽の脚絆掛けでやってくるのを見かけて、確かに横浜への買出しだと見受けたから、『もし旦那、お久しぶりでございます』と声をかけると、『おお、八公か、久しぶりだの。時に今から大急ぎで川端[六郷川の渡し場]まで、やらないか』と言うから、値も決めずに直ぐに乗せたわ。そこで腕と車の続くだけ急いだ所、昼前に川端まで着くと、『多きにご苦労。思いのほか早かった』と、2分の立前に酒代が2朱と来たので、半日の仕事で3分余りよ。
それから大森まで引き返して、山もと[飲食店]で、茶漬けを食べて、少しくたびれたから、ふらふら引き返すと、後から来た客人は、これも同じく浜[横浜]の帰りらしい身なりよ。足元の[草鞋の紐が]緩んだ所を、遣り違いに見つけたから、『旦那、浅草まで帰りの車にお召しなさいませんか』と勧めたら、『見附までいくらで行く』と言うから、『何さ、仕立ての帰り[客を送った帰り]でございますから、いくらでも思し召しで』とやっつけると、
『それなら、2分やるから、急ぎで田町[吉原近くの茶屋町]までやってくれ』と乗り移るやいなや、もめることなしに無事に送り届けることを心に決めて、七つ前[午後4時前]に田町の突き当たりから右に曲がった「口一」(中村屋をこう言う)という茶屋[遊女が格子を巡らせた店先に並ぶ張り店]へ送り込むと、約束と見えて、おいらんがしまって[化粧して]待っていて、店先に張り込んでいたものだから、酒手が1分さ。
もう1両の立前になったから、軽車で返ろうとすると、西の宮[田町から浅草へ向かう途中の小祠]の角で、帰りの客がかかって、2朱と4百で両国まで引いてきたが、家に帰って、湯に入って、酒を一合やるとがっくりして、床も敷かずに寝てしまったが、今日は腕先と足の裏が痛いようだぜ。いや、仕事がある時には、目まぐるしくあるけれど、あぶれる時には、朝っぱらから立て場[街道で人力車を止めて休息する場所]にまごついたり、相談のできかかった役がペケにされたり、たまに懸かった仕事も[人力車の]クサビが抜けて、乗り賃を踏まれたり[払ってもらえなかったり]、大勢でくじを引くと残りくじばかりになるし、実に渡世は車の回り合わせだぜ。
さあ、力、燗が直った。お代りだ。はさて、呑めと言ったら・・・。おっと、こぼれたか。こりゃあ、ご免なさい、ご免なさい。おいおい、姉さん、牛肉の代りを頼みますよ。
12 復古の今様話
掛合いの一人は、年の頃が40歳あまりの総髪。御召縮緬の小袖、黄八丈の下着、黒羅紗に白羅紗の紋所を置かせた割羽織。仙台平の裏付袴を着て、銀の地に純金の目貫[刀の柄の側面の飾り金物]のあまり長くはない大刀に、小刀をそえて差しているのは、いずれの旧藩かの公用方とおぼしい。連れの男は町人の態で、これも40歳あまり。縞の羽織、木綿の綿入れは花色木綿の裏付きで、額裏とは見えない。紺のメリヤスの股引に白足袋。ごく真面目な身なりである。以前に出入りしていた町人と見え、途中で行き会い同道した様子である。
―――――――――――――
町人 「旦那さまは、近頃牛肉をお用いでございますか」
士 「はい、僕などもやはり因循家のたちで、あまり肉食はしなかったが、一昨年の大病以来、西洋医者に治療を受けてから少しずつ用いてみたら、つい好きになって、現在は3日用いなければ具合がわるいようだから、当店から毎度取り寄せて常食同様にいたしています」
町人 「へへえ、それは結構なことでございます。私なども、よい年になりますまで、肉食は穢れるものと覚えまして、とんと用いずにおりましたが、ご時世に連れましてこの味を覚えました。忘れませんが、この夏の新聞に出ました「リーテルペスト」[牛疫]とやらの伝染病が恐ろしくて、昨今まで止めておりましたが、あの説は外国だけのことで、日本へは渡らずに済みましたと見えます」
士 「はい、家畜の伝染病とあるから、私も人とともに恐縮はいたしたものの、活きた牛をしめて食うのだから、当節とても過ちはないはずじゃが、いや、牛店は大いに困迫いたしたろうて。あははははは」
町人 「さようでございます。せっかく開けかかった牛肉も、伝染病の風聞で大いに景気を落としましたが、この節はおいおいそのような噂も薄らぎまして、このように繁盛いたしますが、物価が高値の時節柄ゆえ、食物屋なども商いにくいでございましょう」
士 「いやさ、物価が高値とは言うものの、よく思えば高いのではない。元来、近年までは金銀銅鉄の精密な割合[交換比率]も知らずに、鉄銭と銅銭を入れ交ぜて、大小の区別もなく、波形があれば4文で通用と心得、金銀貨幣も同じことで、銘さえあれば2分は2分、1分は1分、その形の大小に関係なく、軽重にも頓着なく、規定の印でありさえすれば同じことで、吹替え[改鋳]のたびに小さくなり、性質もおいおい悪くなったのを、文明の開化に従って人もだんだん利口になり、利口に過ぎて悪知恵を巡らす者が出るから、そのままには捨てておかれない所で、古金から4文や1文の銅銭まで、その割合ができたのだ。この割合を考えれば、高いとてどれほどのこともない。
今日の形勢を見ても分かるが、まずは朝廷のお救いや南京米のおかげとは言いながら、米が高いとしても餓死する者もなく、酒が高くても生酔いが多いだけだ。食ったり飲んだりできるからこそ、100文で1升の高い米を食った時も、やはり薦を着た者[乞食]もあったから、地獄[私娼]や夜鷹[街娼]をする奴は、全体おのれが淫乱ゆえ、我と我が身を苦しめるのだ。とかく東京は繁華に過ぎて豪奢が強いから、裏長屋に住む職人どもの妻や娘などが、紡績の技は少しも心得ず、歌・浄瑠璃や踊りなどの遊芸のみを好んで、貧乏隠しとは言いながら、ちょっと出かけるのにも、お召しの袢纏織物や博多の帯を締め、芝居・寄席・見世物が見たいまま、神仏の参詣にかこつけて、口に美食を好み、ついに夫の身上を食い潰すのだ。すべて衣食の奢りは、どうかひどく禁じたいものだ」
と、この話のうち、盃のやり取り、牛鍋を食うことがあったと知らなくてはならない。
町人 「仰ることは、実にさようでございます。先刻のお話の通り、金銀の割合を考えてみますれば、高いやら安いやら訳がわかりません。まず身近なところで愚案いたしますれば、元は8文の浴場銭[入浴代]が、現在は44文と申しながら、文久銭[文久に発行された4文の銅銭]と鐚[表面がすり減った悪銭]が混じれば、元の10銭でございますから、2文高い勘定になり、青四文銭[真鍮製の寛政通宝]ならば以前と同様、12文銭であれば、元の4文で4文の釣りを取るので、半分の値より安い割でございます。また、髪結賃もその割合で丁度半分の値、と言って天保銭で払えば6倍になりますが、米はおおよそ12倍、反物類は6、7倍ゆえ、同じ割には参りませんが、大工や諸職の手間賃もみなそれぞれに上がりましたゆえ、米が高いと言ってさほどに困るはずはござりません。割の悪いのは乞食ばかり、鉄銭より他にやるものがなく、文久銭をやれば釣りをとりますが、勘定に大雑把な人は青銭をやることがござりますから、どうやら埋め合わせになりましょう。はははははは。でございますが、東京もおいおい華族様方が増えて御永住になるという風聞でござりますゆえ、[徳川家が駿府に移って寂れた東京も]昔の繁昌に立ち返りましょうか、いかがでございましょう」
士 「されば一寸先は闇で、僕などが愚昧に分かることではないが、たとえ華族方が東京居住になられたとて、これまでのようにはなるまいと思われる。まずそれぞれの街道の大通りの分はそのままにして、それぞれの裏町の辺鄙な所は真ん中に一緒にまとめて、あとは開墾ができて茶畑・桑畑になったから、7、8年も過ぎたら、製茶・養蚕が盛んになって、老少・婦女子のよい職業さ。やがて人手が足らなくて困るようになるであろう。その時には百人、千人がする技もひとつの器械で用が足りるように開けることは疑いない。そうなってこそ真の繁昌さ。「国産多きは国の富」だ。僕も、もとは和漢の書物を少し読んだけれど、横文字ばかりは大嫌いで、鎖港攘夷の説を唱えたが、こうまで交易が盛んになっては、外国の実情を知らないのも不自由で、嫌ったことを悔やんでいるけれど、さりとて白髪を抱きながらエビシ[ABC]を学ぶのも恥ずかしいので、訳書だけを読んで彼の国の実情は少し分かったから、以前の説を反古にして、「開港交易にあらざれば、富国強兵の策なし」と思う心になったのだ。それに東京ばかりでなく諸国とも茶・蚕卵紙・絹糸などの産物が増えて、交易がますます盛んになれば、皇国の富となり、富は大砲や大艦も自由にできることは知れているから、地球の中の強国となると思えば、何と頼もしいことではないか。東京が不景気だとか寂しいとか、あれやこれやと言うのは、理に疎い連中の言うことだ」
町人 「仰せを伺いますと、実にそうでございます。私も老いの学問に翻訳書でも読みましょう。実に西洋流でなくては夜が明けません。おやおや、とかく申すうちに、パッタリと日が暮れました。もう一つ召し上がりまして、あとはご飯に致しましょう。・・・これこれ、姉さん、牛肉のお代りとお燗のよいのを。そしてな、鍋が煮えついたから取り替えてくれないか。・・・[盃を受けて]へいへい、これは恐れ入ります。おっとほほほほほ、へいでございます、ございます」
第2編下巻了
Ⅳ 安愚楽鍋 三編上
第三集の序
種痘は天下の仁術で、肉食は万民の滋養である。それ故に、牧牛が国家に益があることは、どうして他の獣と等しいことがあろうか。最近、開化がようやく進んで、市井の貧しい人々でも、牛痘や牛肉が世の中に功があることを知っているので、それによって治療を全うして、多くの人が長生きをするようになり、それによって食料を調達して、庶民が健康な体を保つようになった。今日、これに及ぶような僥倖が何かあるだろうか。この頃、魯文さんの著述になる小説、「安愚楽鍋三集」の稿を念入りに見て、笑い話の中に諷諫[遠回しにいさめること]のある筆使いに感心した。小道[ささいな道義]と言っても見るべきものがある。ああ、話をすることがどうして容易であるだろうか。そこで一言よけいなことを言って、それによって感心して読んだことを感謝するものである。
時に明治5年壬申の初春吉日、
東京浅草金龍山下の旅館、駿州屋の小部屋において
陸中国[岩手県]水沢の藪医
臥牛散人こと 小野凉亭 これを記す
当世牛馬問答
馬 「牛公、久しく会わないうち、手前はたいそう出世をして、ラシャのマントにズボンなんぞで、すっかり西洋風になってしまったぜ。うまくやるな」
牛 「お、馬か。手前こそ、この節はたいそう立派な車をひいて、1日と6日[当時の休日]には、賑やかな所へばかりドンタク[休日]に出かけるそうだが、うらやましいぜ。俺たちは、「牛、牛」と世間で持て囃されるようにはなったけれども、わずかに表面ばかりで、生まれて物心がつくかつかないうちに、鼻面をひかれて、築地や横浜[当時のと蓄場の所在地]へ身を売られた挙げ句が、四つ足を杭へ結わえ付けられて、ポンコツを決められてよ、人間の腹へ葬られて実に塞いでしまうわけさ。」
馬 「いや、そうでねえ。全体、手前の仲間は、高輪の船場や大津の芝山あたりで、車をひく身の上ではないよ。天道様から、人間の食物になるように、この世界へお産み付けになったのを、まだ人間が開けない所から、なりが大きくて角などが生えていて、力がありそうに見えたものだから、重荷でも背負わせようという思いつきで、これまで米俵を積み込んだり、祭礼の練り物なんかをひかせたのは、全く人間の心得違いだ。中国は開け損なった国だけれど、牛は物を積み運びをする獣ではなくって、人の食い物になるものだと心得ていたから、「大牢の滋味」だの、「伐冰の家[高貴な家]には、牛豚を飼わず」だのと言っておいた。当時、開化とやらの世の中では、人間はもちろん、鳥獣でも、すべて生あるものは、それぞれご奉公をしなくてはならないとある先生がおっしゃったのを、「馬の耳に風」にしないで聞きとめておいたが、手前の仲間は人間に食われて、万物の頭領の体を養うのが天への奉公だ。ポンコツを決められて人の腹へ入れば、手前達の役目が済んで、畜生の業が滅して、人間に生まれ変わる道理ではないか。人間で例えるなら、辛抱しとげて旦那から暖簾をもらって、出店を開くのだぜ。はてさ、年がら年中、藁や小豆の殻を食って寝て暮らすよりは、天への奉公を勤め上げて、畜生道の苦しみを去って、人間界へ生をかえる方がよかろうと思うぜ。こちとらは、人間の口へ入ろうと思っても、誰も食ってくれず、赤馬はまだしも梅毒にかかった者が薬に食うけれど[赤馬が梅毒に効くという俗説があった]、それはたまの事だから、業の滅する時はない。」
牛 「そう聞けば、なるほどもっともだ。もうもう、愚痴は言うまい。ああ、牛の音も出ない。[ぐうの音の洒落]」
13 商人の胸算用
年の頃は 31、2歳。あめ唐[あまり高級ではない和物の唐桟]は見かけばかりで洗い張りが効かないと、古着屋へ注文して、小梅模様の唐桟の二子織で乱立縞の洗い張りをした羽織に、上着は同じく古着屋へ注文して胡麻柄縞、それに紛い更紗の下着。帯は日本橋の小倉屋で3分ぐらいは弾んだと見え、目立たぬ風俗ながら、銀革の袖時計を襟に掛けたと見えて、鎖が折々ちらつくのは、1ミニウト[一分]を争う商法家[商人]であると見えた。連れの男も同じ年配で、鳶ごしらえ、こうもり傘を持参の態で、折々横浜へ往来する商人であるだろうと思われた。
―――――――――――――
「商兵衛さん、牛肉は横浜だということだが、この家のは随分食えるね。おいらは馴染みだけに亭主が並より気をつけて極新しいのを食わせるから、初めての牛店などへは滅多に入らないよ。この間、芝で昼の 12時過ぎになったから、腹が減ってたまらないので、ある牛店に入った所が、店の構えをみるといかにも今月の初めまで鰻の蒲焼き・骨抜き泥鰌柳川流の出来合い店を、牛肉に押されて牛は牛連れと出直したと見えて、いやこと慣れないので、下女なんかが全く気が利かなくて、「五分葱をくれ」と言うと「昆布はございません」だの、生肉を注文すると鶏卵を持って来たり、おまけに肉と言えば日向に乾した木片のように、カラカラして筋だらけで、いくら噛んでもちぎれない、古臭くなった老牛を食わせられたので、代りには手を付けないで勘定をして飛び出したが、実に牛肉ばかりは日増し[日数がたって古いもの]は真っ平さ。しかし福地先生[福地桜痴、政治評論家・「東京日日新聞」社長・作家]などは「古臭いのがいい」とおっしゃるが、素人口では、しめて2日目あたりが最上だね。
最上と言えば、今度、アメリカ 18番商館から引き取った羅紗は、綿なしの上物だが、10行李まとめて売りたいものだが、急に買手はないかね。なにさ、店で小売にさせれば、百円ぐらいは儲かる品物だけれど、おいらはちょっと神戸まで行って来たいから、ここで代物を札に引き換えないと都合が悪いからさ。ええ、商さん、南京米[輸入米]が築地のある商館へ千俵ばかり到着したが、どうだお前買わないか。なに、「まだ下落する」と。うう、そこだ。売主の異人も「日本がこれほどまで下がりはしまい」と思って、積み込んで来た所が、香港でしけを食って、久しく逗留していたうち、日本相場が下がったものだから、がっかりして、当面囲っておくつもりのだが、あいつらの目算で、まだ下がると踏んだから、損耗を承知で売ってしまう料簡だから、そこへ付け込んで精一杯値切りつけて買い落とす策があるよ。その代り斡旋業者が欲張りだから、1割の手数料では承知しまいが、そこは「読みと歌」[読みガルタと歌ガルタ、相手の出方次第]だ。おいらが半口のるから欲張りに斡旋させてはどうだ。
なに「油を買った」と。これこれ石油へ手を出す時ではないぜ。それよりは赤銅[銅]を買ってみないか。この間、函館から利助が帰ってきたが、あっちではたいそう異人が買い込むというから、ぱっとしないうちに買い込むのだぜ。おいらは神戸へ行かなければ、ここでいくらも買うのだけれどコンペイニ[仲間、company]が前に発っているから、どんな利益が降って湧こうとも、ここでは手を広げることができないから残念だ。なに神戸は格別の大商売というのではないが、ちょっとばかり目的があるのさ。上手くいけばひときわのお慰みだが、まず損はしないつもりさ。
それに今年はぜひ上海かジャワあたりまで航海して、みっしりと儲けるつもりさ。何でも大商売は、洋行しないのでは大利がないから、去年、アメリカのサンフランシスコの博覧会へ行くつもりだったが、吉原の立ち退きに引っかかって大散財したので、「とんちんかんとなりにけり」さ。どうか2、3年のうちに世界中の繁昌な港へおし渡って、大六[大黒屋六兵衛、日本橋の唐物店]や伊勢勝[西村勝三、横浜の鉄砲店]何ぞにも劣らない身上になって、浜の高嶋屋[高島嘉右衛門、横浜の貿易商]の上を越して、1年に 10万両ぐらいのお易[税金]を上納したいものだと心がけているのだよ。はて、人は大きなことを望まなければ、開化の人物ではないよ。酔ってほらを吹くのではないが、これまでおいらが見込んだ商売に五分も外れたことがないのは、そこが腕前と肝っ玉だ。はばかりながら一番ウンと踏んまえれば、5万や10万の金貨はたちまち手元へ積み上がらあ。
ええこれさ、商兵衛さん、しっかりしねえ。おや、こくこくと船を漕ぐのか。ははあ、果報は寝て待つつもりかの。おいおいそんな不勉強では儲からないよ。しっかりしてもう一杯、・・・ああ意気地のないお相手だ、お相手だ。
14 芝居者の身びいき
なりは紬の紺地へ「魚がし」と白抜きの大文字で染め抜き、もっとも白地へ薄ねずみをかけた上着。下着はかえって地味なもので、胴裏は揉みであることが分かる。赤い襦袢の袖をぴらぴらと出しかけ、得意の客と二人連れで、猿若町[浅草の芝居町]を退き、うるさく取り巻く仲間の者を遠ざけたのは、一人で潤うつもりに違いない。最前から牛鍋で差しつ押さえつ呑みかけて、よほど回った酔い加減である。
―――――――――――――
「えもし、旦那。この春の仕初め[初春芝居]に「腰越状」を一幕見せたのは、座元と地内の師匠(作者の河竹新七を指す)の工夫で、去年の仕始めに『勧進帳』を見せたやり方でございますが、いい思いつきではございませんか。当代の役者は今戸(河原崎権之助)に限りますね。(この客は総じて三升[代々の市川団十郎の俳名]びいきと見える。よってこのように言うのである)。年が若いにしては、隠居(七代目市川海老蔵をさしてこう言うのである)などよりも、また一段とこっているから、恐れ入ったものでございますぜ。とかく「役者は一文上がり」[一文でも多く給金をとる役者は演技が上]でございますから、仕種がよくなって人気が乗ってくれば、万事ひいき目が寄ってきますわね。それに私の方の太夫元さん[興行主]は、めっぽう腹が広いから、顔見世[11月]でも、仕始めでも、脇町[他の芝居町]よりは、一倍気を入れて、桜を植えてもしみったれた樹は植え込まないから、おのずから櫓に光が出て[芝居小屋が繁昌して]、景気がよくなるわけでございます。
お前さんの前だが、人間は腹がよくなければ[太っ腹でなければ]、人は使われません。去年の顔見世には、猿若町は3丁目までともに飾り物はしないなかで、私の方の太夫元の思いつきで、三好町[現、台東区蔵前]の玄老先生[魯文などと交流があった通人]に請け合わせて、茶屋ののれんに芳幾[落合芳幾、浮世絵師]に似顔を画かせて景気をとっておいて、直ぐに年末のうちに、河竹さんに脚色させて一幕書かせて、仕初めに見せるなどという趣向は、「お釈迦様でもご存知あるめい」。何とすごい大将ではございませんか。動きがとれません。実に去年の『忠臣蔵十二時』の趣向などは、見物客の腹をえぐりました[感動させた]では、ございませんか。それに役者が、山崎屋[河原崎権十郎]に高嶋屋[四代目市川小団次]、舞鶴屋[中村仲蔵]の老練で、勉強ぞろいでございますから、五分も透きはございません。今戸の小林平八郎[吉良家の付け人の役]は、身にしみじみとようございました。
(声色で)「湯茶はー、必ずー、熱いものー」。熱いと言えば豪勢煮え燗だ。おいおい、下女さん、あまり燗が熱すぎて、腹の中で羽目を叩いて三助をどつくぜ。[銭湯で湯が熱いと、羽目板を叩いて三助に苦情を出すことから]。杯洗[杯洗い]の水は鍋の塩辛いのを調合して水切れだ。代りをたっぷり持ってきな。「はて、水は安いもの、牛は高いもの、水はたっぷりお汲みなさい」、「あいあい、さようでござい」。あはははは・・・。
え、もし、旦那。さっき尾の丸[猿若町の芝居茶屋]をお出かけなさると、入れ替わって入り込んだのを、夜目遠目だが「何者なるか」と透かし見たらね、今の仲鶴[中村屋鶴蔵]むかしの雁八[道化方]に、喜知六・小半次[いずれも名脇役]の三人さね。剣呑、剣呑。もう一足のことで、あいつらに取り巻かれてごろうじろ。まさか私どもとは違って牛店へ連れ込む理屈には参りますまいから、必ず有明楼[浅草今戸の料理茶屋]か大七[同所の会席料亭]か、ないし利口を見せて親類づきあいごかしで、藪天[猿楽町(現、浅草6丁目)の天ぷら屋]とでも河岸を変えるかでございますが、それにしても謝って[安くしてもらって]一人前が2分宛てのご散財さ。ああ、危うし。
この間のように、お前さんと私といやな道行きだが、向こう越しで伸び上がらねば三囲神社を後に見て、平岩[須崎(現、東向島)の会席料亭]で内会ちゃぶちゃぶ[内緒の食事]を決めようと、座敷へ座ったばかりの所で、後ろの唐紙障子をすらりと開けて、『不義者見つけた、動きやがるな』と[芝居の口調で]声をかけたのを、誰かと思ったら杵屋の犬公と元役さね。そのあとから、客に取り残された山谷堀と猿若町の老芸妓が二組さね。私もギックリしたからお前さんの顔を見ると、そこは旦那は豪勢踏ん切りがいいて。おめずおくせず落ち着き払って『おや、みんなか。丁度いい所へ、よく来てくれた。留公とさしで、寂しくってならなかった』と仰ったのをいい潮にして、下っ端連中が総出で舞台へ並んで、犬公の犬の声色に、ミミズの鳴く声の古臭いものを辛抱して聞いてやって、大散財をなさったなんぞは、浮世の義理でお前さんのお顔だから[顔が広いから]、仕方もありませんが、この頃は助兵衛[女遊び]はありませんから、牛肉の効能が見えますまい。
ええ、今夜はおはしけなさる[ここはするりと抜ける]のですか。そりゃあすいぶんおかしい思いつきでございますが、一件[馴染みの遊女]の所までお送りした後、[私だけ]下宿へ引き下がるのはつらい訳だが、おいらんの向こう顎[食事の先方持ち]とは言わせませんぜ。今夜はしっかりと規模[なにかしくみ]がありそうなもんでございます。・・・えっ、なに、私の登楼できる妓家に付き合って下さる。えっ、そいつは、ありが対面曽我五郎[「ありがたい」と曾我の「対面」を掛けた]の台詞ではないが、花待ち得たる今宵の仰せ。はて珍しい、ばたばたばたばた[芝居の拍子木をまねた]、ばったり、まったり、あんまり浮かれて、また杯洗をひっくり返した。・・・おいおい、姉さんや、雑巾だ、雑巾だ。
15 藪医者の不養生
9尺の門口を張って[正面が約3mの構えで]、門札に「本道 外科」と割書にして、玄関はなく、すぐに靴脱ぎである。「頼みます」と言うと、先生自らが障子のうちから、「どうれ」と声をかける。按摩上がりの「でも医者」である。『傷寒論』[中国の医書、漢方医の聖典]の国字解も分かりかねる「野だい九郎」。医者は医者だが、「薬は風邪ひきの他は、おことわり」と札を出しておくなら罪はないけれども、そのくせに向こう見ずの大胆坊主で、薬種屋の「掃き寄せ」を買い込んでどんな病にも用いるので、毒にもならないが可もなく不可もない、開化には不用の人物である。
年の頃は50歳あまり。羊羹色の午後4時を過ぎた[質流れの古ぼけた(午後4時は、暮れ「七つ」なので、「4時過ぎ」は「質流れ」を意味する)]ぺらぺらした羽織に、まがい八丈の黄色に黒みのかかった小袖、下着なしの鼠色か浅黄色か、正体分明ではない織りのかかった襦袢一枚。角細工の山刀を傍らに雪駄とともに置いて、牛鍋一人前、酒は一合ずつ、生肉のお代りはあつらえず、五分葱と香の物ばかりを代えて、ぐびりちびりと呑みながらの独り言である。
―――――――――――――
ああ、今日は寒かった、寒かった。たまに病人の家から人が来たと思ったら、愚老[自分のことをこう呼んでいる]などには、なかなか手もつけられない難病の様子だから、切り抜けようとは思ったが、「ままよ、危うい橋も渡らなければ、まぐれ当たりということもない」と思案して診察している所へ、親類どもから立ち会わせるという散切り頭の西洋医者が出かけて来たので、その場を譲って直ぐに脱走するわけにもいかないから談合してみた所が、彼奴はなかなかの腕達者と見えて、愚老などが足元へも及びもつかないから、いい加減なごまかしを言って逃げ出してきたが、当節のように医道が盛んに開けては、一文不通[無学な]の愚老などが、医者の真似をしている所ではないぞ。
しかし、いくら物知らずの愚老らでも、これまで漢方が行われていた時には、葛根湯だとか、大柴胡湯だとか、あるいは薬名も大黄・人参・甘草・陳皮ぐらいは覚えておるが、漢方医は古医方も後世方もともに廃止同然の時世に及んだので、医業で生活を立てるには、西洋医薬の名前も初歩だけでも覚えなければならないが、髭を食い反らして[髭の先を偉そうに上に反らせて]今から学ぶこともできず、別に薬名だけ聞きに行く所もないから、病人の家に招かれて、今日のように西洋医と応接する段になってくると、蛇に会った蛙同様で、すくんでばかり居らなくてはならない。そのたびごとに半年ずつも寿命を縮めるのだから、どうしても廃業して、持ち前の野幇間に店を出し直す方が上策だ。
全体に医者は付けたりのつもりだが、商売冥利で、折り節にまぐれ当たりで全快させる病人もあるものだから、ひいきの引き倒しで、それらの人が愚老を「活き薬師如来」のように思って、他の病人に紹介してくれるのが、結句迷惑千万さ。そんな面倒なことより、浅草の十二軒か、両国の並び茶屋あたりの知り合いの所へ腰を掛けて、網を張っていさえすれば、どこかの出入り場の息子か、ないしは若い者なんかに出会うさ。そこで「いや、いずれへ」とか「どちらへ」とか、敵に声を掛けられて後ろを見せる敦盛はいないから、「これは先生」と入り込んでくるのをこじつけて、鉄面皮勿論で「ちょっと一杯いかがです」と、無理なこじつけでも割烹料理店へ連れ込んで、上戸でも下戸でも、選り好みすることなく口をかけてやった老妓と合併して散々に無理にすすめて、その客の財布をお為ごかして「御用心」で預かっておいた中から、店の会計とその日の立ち前[幇間としての賃金]をこちらへ着服して、あわよくば芸妓の尻尾を持ち上げて枕金の釣りをとるか、さもなければ人力車の二挺仕立てで吉原へでも引っ張って、知り合いの茶屋へ送り込んで、「伊勢六の5階見物」とか、「金瓶の異人館一覧」とか名前をつけて大興行[派手な遊び]をさせて、利得は茶屋と山分けだ。「遊興おんぶ」[客の懐を当てにして遊ぶこと]の先生株さ。このような仁術を施しつけているので、一服が3分や5分の薬の礼をあてに、爺むさい病人なんかを煮焼き返しにはしておれない。ああ、廃業、廃業。しかし完全に廃業したら、風邪薬の小遣い取りができないわい。いやいやどうでも医薬に関係していては、むこ嫁の媒酌や地面・家作の周旋の仕事の邪魔になるから、「本道 外科」と割書した表札を取り除いて、「武佐堀欲庵」とだけ書いておこう。それで坊主頭では、旧弊が一洗しないようだから、当世流に散切り頭に鬘を代えるのが名案だ。
いや、かれこれ言ううちに、もう7時だ。飯は宅で食うとして、鍋一枚に酒が2合。これこれ、女中、この勘定はいくらじゃ、いくらじゃ。
16 落語家の楽屋落ち
年の頃は22、3歳。色は生白く、大髻[男子の結髪で、たぶさを普通より大きく結ったもの]である。円朝か燕枝などを張っているつもりであるが、中入り前後に高座にあがる素人話の代物。去年の春あたりまで「若旦那株の金茶[お客]」と言われた変わり者が、鹿[噺家]に食い物にされ、噺家の仲間に引き込まれた大生聞きである。
甘い母親の仕送りで、お召縮緬の二段揃え。ぞろりとした身なりゆえ、押し出しは真打めかすが、技芸はお話にならないものと思われた。そのくせよい芸人ぶって、女客でも取り巻く料簡で、あご稼ぎ[客にご馳走になること]でたまたま客に連れられ、この牛屋へ来たことを知るべきである。
―――――――――――――
「姉さん、鍋は御膳の時として、スープの吸い下地で、葱を細かく削いで、鞍下[牛の背の鞍の下になる部位の肉、ヒレ]の極みという所を、そぼろに刻んで、パラパラと入れて、二人前もって来な。そしてお酒はいいのを2つ、極熱だよ。なにさ、おいらだと言えば、親方が知っているよ。気が利かないガキだ。じれったい」
「へへへへへへ。え、もし、若旦那どうでげす。あなたもとうとう西洋に巻き込まれて、牛を召し上がる様におなりになったのは、不思議でげすね。何でも牛をやらないのでは、健やかには行きません。前々は、私どもの連中でも、牛や豚の話をしても、恐ろしいという顔をした者がございましたが、「鹿[はなしかの洒落]が牛や豚を食うのは、共食いだから」という訳かと思いましたら、えもし、開けない手合いではございませんか。「なにか穢れる」とか、「不浄だ」とか、訳も知らずにただ恐れているのだから困りますが、近頃は連中もおいおい開けてきたと見えまして、夜席[夜間興行]の出がけなどには、牛で一杯しめた上で、掛け持ちなどをつとめると、高座でどんなにかしゃべりいいか知れません」
へい、おっとっととと。・・・ごぜえます、ごぜいます。そう立て続けに頂くと、夜席がつとまりません。普段ならぶっこ抜いても[寄席を休んでも]、一晩くらいでは客の頭数が減る気配はございませんが、初日から三晩目でございますから、ここが要でげす。へい、昼席は山二亭で、夜は並木亭でちょっと中入りの前をつとめまして、すぐに東橋亭の切り[最後の番組]を話しまして、それから吉原の新席がはね[終演]でございます。
へい、ありがとう。まあ、ごひいきのおかげで、昨晩などは百五十足ばかり参りましたから、並木も東橋もまず大丈夫、三四百足は、参るようになりましょうと存じます。並木は円朝の後で、東橋が小さん、夢楽の後というものでございますから、豪勢骨が折れますが。燕枝と私が一晩がわりに、中入り前と切りをつとめるのでございますから、まずありがたいことに赤首で前面が埋まります[かぶりつきが熱中して真っ赤な顔をした客で埋まる]。
それに燕枝が、この春の話初めに自作の「嵐の花おぼろの月影」という呼び物を話しますので、私が「吉原新聞今様姿」というものを新作しましたから、4、5晩の続き物で話しますが、どうか若旦那、一晩お聞きにお出でになって下さいまし。こう申しては自慢を言うようでございますが、私も噺家にならない以前は、有人[山々亭有人、戯作者]の弟分になりまして、創作の道も少しやりましたから、どうなりこうなりまとまっておりますが、話し初めから聞く客に耳の肥えたお方があれば、それを的として[その人を対象にして]話に実が入りますが、高座の前で分かりもしないくせに悪口をきいたり、混ぜっ返す田夫野人[田舎者]があるので、諸事恐れますよ。
へいへい、ももももも、おっと、おっと、こぼれます。どうかこれでお酒はちょんと区切りで、飯をしめるとしようじゃございませんか。若旦那も、あまりあがらない方だから、御積り御用心。おっと危ない。すんでに鍋がとんぼを返る[ひっくり返る]所でげした。・・・おいおい、姉さんや。あの親方にそう言って生肉の最上をすき焼きの種にして、4人前。炊きたての御膳は承知だろう。おいおい、そして脂身をたんとだよ。これこれ、面倒だろうが葱を小口からざくざくに切って、熱い湯をかけて持ってくんな。
えもし、これが異人のコックと言ったら、分かるはずないが、ちゃぶちゃぶ屋の直伝でございますぜ。すき焼きを食べた後で、葱の湯通しをあがってごろうじろ。極西洋でございますから。御膳の来るうちに、「お中入り」にもう一杯あがったらどうですかね。一番の景物がお燗直しのお徳利[一番風情をそそるのが、燗をつけ直した徳利だとふざけた]。・・・へい、ちょっとお酌。二番[の景物]が、お銚子を頂戴かね。あはははは。これじゃあ、とんと前座の者の言い草だね[気の利かない言い方だ]。いよいよ、打ち止め。お銚子は御積り、御積り。
Ⅴ 安愚楽鍋 三編巻之下
17 茶屋女の隠し食い
年の頃は18、9歳か、あるいは20歳を1つ、2つ越したか、定かではない。島田髷を潰しに結い、風織縮緬の張りかえし、上上着の晴れ着なしで、普段着も見世着も、この上へ、これも馬道か仲町の古着屋でお袋が安く買い落とした、御召縮緬の藍と鼠の荒い縞の袢纏をひっかけ、鯨帯の後先ばかり紫縮緬で、中は縮緬呉絽[ゴロフクレン、舶来の梳毛織物]で接ぎ合わせたと察せられた。この女は浅草の奥山へ雇われて、夜の内職[夜の密淫売]を書入れに、安い立ち前[賃金]で、10時頃から白粉をこてこて、そろそろ見世を開く茶屋女と思われた。
連れの女は50歳近く、入れ歯をお歯黒でごまかし、黒油で白髪をかくす「ばばあ実盛」[斎藤実盛は白髪を染めて木曽義仲と戦った]である。なりの拵えは、栗梅金巾の張りかえしの額裏、藍微塵の銘仙、前掛けだけは御召縮緬である。これはみなさんご存知の三途の川の渡し場に住む道案内の周旋か、其れ者の上がりと見えて、年はとっても嫌味たっぷり。「触れば落ちん風情である」と文句に書くべき、八百屋半兵衛の母と、遣り手のおよくと、仲居の萬野とを合併したような白化け婆[厚化粧の老婆]である。
彼の茶屋女の「間が悪いから一緒に行ってくれ」との頼みに、「下地は好きなり、御意はよし」で、この牛店の鍋酒盛り。両人ともよほど酔いが回ったので、古狸と野狐の尻尾を現し、あたりにはばからぬ平気な顔で、差しつ押さえつ、牛の肉を肴に、そろそろ木地のはげる話し口で、その楽屋を察するべきである。
―――――――――――――
ころ 「おひきさん、お前も『牛は食べない』などと、この間水月亭[浅草寺境内の料亭]でお言いだったが、嘘か騙しだね。随分いけるじゃないか。呆れもするよ。あれさ、お代り目だよ」
とお酌をする。婆は歯茎を現して笑いながら、
ひき 「あははははは、おころさん、お前も開けないことを言う子じゃないか。あの時は、それ客人が一座だから、いくらこんな婆になったからと言って、まだ孫に手を引かれて、杖にすがって鳩に豆をやる年でもないから、お客などのそばで『牛を食べるのが、大好きだ』と言っては、まだ馴染みもないお方だから、あんまり色気がなさ過ぎて、『この悪婆めが』と睨まれるだろうと思うから、ああは言ったようなものの、鋤だの鍬だのと言う段じゃあないよ[大変に大好きだ]。ぜんたい牛がまだ流行らない時分から、悪物食いで、その時分には両国の並び茶屋で、小川のおとくさんなどと肩を並べて見世を張っていた[張見世、すなわち店先に居並んで客を待っていた]時分で、組合の頭の連中が見世へ来ては、「山鯨[猪肉]が旨い」という話をするので、食べたくってならないから、雪が降って見世を早じまいにした晩方に、江戸屋にいた婆やを誘って、長い橋[両国橋]を越して向こう両国へ行って、ももんじい屋に入ろうとすると、灯りがかんかん点いていて、間が悪くて入られなかったわね。その時分は、年もぐっと若しめけていた時だから、なんぼおきゃんで、はねていても、そこは女だけで山鯨の店の前を行きつ戻りつしていた所へ、馬場の頭の子分の穴熊という若い衆が、丁度ももんじいを食べに来て、門口で出会ったろうじゃないか。そうするとさあ、何でも『一緒に入れ』と手を引っ張られたのをいい潮にして、入って食べたのが「御初会」さ。それから食いつきになって、霜月の声を聞くと、色気よりは食い気、見栄も飾りも瓢箪もさ[見栄も外聞もない]。その気でなければ、生物は食えないよ。家へ取り寄せて食べたが、どうもその店で食べるようにはいかないよ。だがね、猪や鹿は随分旨いが、牛が開けてから人様の話を聞くと、「牡丹[猪の肉]や紅葉[鹿の肉]はあんまり薬じゃあない、なんでも牛に限る。豚もたくさんはいけない」と言うことだから、もうもう今では、ももじいは御間御廃止にしてしまって、牛一点張りと決めたよ。おころさんは若い者のくせに、よく開けて牛を食べなれたね。本当にそれには感心するよ」
と、牛のような舌を出して、肉をぺろりとせしめる。
ころ 「それにはちっと訳があるのさ。今までお前にも話さなかったが、私は15の年に、父親が相場とかに負けて、母親と私を置き去りにして脱走(「だっそう」を詰めて言う癖がある)してしまったろうじゃあないか。その後で、いろいろ困窮して、家は分散して、母親の里が神奈川であったから、そこへ二人とも引き取られているうち、浜(横浜を略して言う)の親類の家から、『おころを異妾[外国人相手の妾]に出したらどうだ。先の異人さんは、イギリスの紺四郎(コンスル[領事]のこと)とかいう旦那で[名前と取り違えている]、髪の毛が縮れて赤いとはいえ、日本言葉もよく分かる。なかなか遠人なんぞと馬鹿にするけれど、どうしてどうして、万事に行き渡った心意気のいい人だから、今の世の世界で織元につかないのは[権力にこびへつらわないのは]、野暮の行き止まりで、それは開けないことだ』と勧められると、母親が、あの通りの欲張りときているから、すぐに話に乗って、『給金次第でやりましょう』と言ってやると、『月に50両で、他に小遣いが10両、支度は別段いらないが、身の回りを飾ってくる手当が25両で、親元が困る者なら3か月くらい給金の貸し越しもしてやろうし、先の気に入り次第で、珊瑚樹の五分玉や六分玉なんかは、日本のほうずき同様で、ねだり次第くれるし、あいの子でも懐妊して、おぎゃあとさえ言えば、たとえ旦那は本国に帰ろうが、一生困らせないようにしてやるとのことだから、すぐに目見えにかけろ』と言うので、人力車(人力車を、こう覚えているのである)で、その日に横浜へ行って目見えにかかった所が、私も親のためとは言うものの、日本に生まれて、千里万里先の得体も知れない遠人などの慰み者になるのはいやでいやで、浜の口入れ屋で待っているうちも、「波止場へ駆け出して身でも投げてしまうか。いやいや、そうすると年を取った母親が可哀そうだから、うわばみに呑まれた夢を見たつもりで我慢しようか」と、あれこれ思案の最中に、異人さんがお出でだと言うので、ぶるぶるしてさ、小さくなっていると、口入れの人と母親が気をもんで、『もっと前へ出て、顔を上げていろ』とお尻を押すやら、背中を突くやら。私はのぼせ上ったが、はたで気をもむから顔を上げて、その旦那を見るとね、本当にいい男さ。とんとこの間、菊五郎さん[尾上菊五郎]がした散切り鬘の洋服仕立ての通りの人で、こんなお多福だけれど、何だか気に入ったようで、私のそばへ来て、『あなた異人ペケありますか。私、あなた、たいさんよろしい』と、ちょいと私の手を握ったので、私もぽっとしてしまってさ。・・・おほほほほほほ。おほほほほほほ。・・・おやたいへん。つい浮かれて、盃をひっくりかえして。それ、おひきさん、前が汚れるからお立ちな、ねえ」
ひき 「おっと、散々のおのろけの受賃が、他人の盃をひっくり返して、よそ行きの前掛けをびしょびしょだよ」
ころ 「おほほほほほほ。真っ平、真っ平。つい話に身が入って、粗相、粗相。もうもう後はサランパアにして、さあ注ぎ直し、お酌をしましょう」
ひき 「まあ、止さなくてもいいから、後をお話よ。始まりを聞いて、落ちを聞かないと気になるわね。「のろけ御免」の札を出すから、その後の決まりをおつけな」
ころ 「私は、とんだことを言い出してさ。えええ、口走ったからには、身の懺悔だ、構わない。話してしまうから、みんなには内々に。とりわけ(親指をちょっと出して)これにはごく内々に」
ひき 「おころさん。私をそんな蓮っ葉[軽はずみな女]だとお思いか。この商売では人のあらすそを言うのは、ごく素人だわね。(人差し指で口をたたいて)ここの堅いのは、自慢ではないが、山[浅草の奥山]の姉さんたちが知っていて、内会のこと[内密に男に会うこと]を打ち明けて、頼まれたりまた頼んだりするのが、この婆の渡世だよ。そこは如才があるものかね」
ころ 「本当に、今、東京へ帰って来てみると、外聞の悪い話だから、口をつぐんでいるのだが、つい酔ったから、話しかけたのだがね。ええ、それからまあ、いい塩梅式に目見えが済んで、直ぐに取り決めになって、その日のうちに異人館へ引き取られて行ってみると、本当に肝をつぶしたよ。家と言ったら何から何まできれいで、本当に、いやだの、おうだのと言ったのは、もったいないようで、身で身をうらやむようだったが、私には旦那が三度の御膳も日本風にして食べさせてくれるうち、それ、この牛さ。あの旦那が二度の御膳の時には、必ず牛を食べるのを見慣れたら、情合いと言うものは不思議なものだと思ったよ。東京にいた時分には、牛屋の前を通るのもいやだったが、誰も進めもしないくせに、牛が食べたくなって、コックが煮ている所へ行って、小さく切ってもらって一口食べてみると、美味しくなって他のお魚などより、牛が好きになったのだから、私が牛を食べるのは素人ではない、玄人っぽいのですよ」
ひき 「おやおや、そうかえ。それでは牛の方は黒牛だね」[玄人(くろうと)にかけた洒落]。
ころ 「嫌ですよ」
ひき 「あはははは。時におころさん、明日の晩は、市六さんが鈍宅さんと一緒に、私の所へ来なさるつもりだから[私は休日だから]、もしお前の方に差し支えがあったら上手く繰り合わせて、五つ時の時分[午後8時ごろ]までに、出てきておくれよ。そして、小原さんにも、鈍宅さんが来ることを耳打ちをしておいておくれ。あの医者の奴は甚助[嫉妬深い]だからよ」
ころ 「おや、鈍宅さんが、散切り頭になって、甚助と名前を変えたのかえ。しゃんしゃんしているから、ほんにコツコツだよ[疲れ知らずだ]」
ひき 「そんなに悪くお言いでないよ。小原さんはずっと乗り込んでいるよ[私に夢中だよ]」
ころ 「まさか」
ひき 「いえ、そうではないのさ。先生は女にかけちゃあ、親切だよ」
ころ 「病人をかけちゃあ、不親切だろうね。おお、気味が悪い。おほほほほほ」
ひき 「いや、おころさんの口の悪いのには、呆れるよ。その口で市六さんやいけんの月宮さん[吉原の客、「吉原ばかり月夜かな」から]を殺すのだね[上手いこと言って丸め込むのだね]」
ころ 「おや、人聞きの悪い。よしてもおくれ。私に殺されるのは、血を吸い過ぎたヤブ蚊と、秋のノミばかりさ」
ひき 「上手く言いましたっけ。へへん、呆れもしねえ。さあもう、いい加減に御膳にしよう。家に誰か[客が]来ても、私がいないと、南馬道の抜け裏通りへそれられたり、北廓[吉原]へでもはしけてしまわれると、勘定づくだわね」
ころ 「ほんに、おひきさんは、欲がないよ。そんなに貯めてばかりいると、泥棒の用心が悪いから、たまには息休めに落ち着いてお飲みな。・・・・・・もし、姉さん、御酒と生肉を持ってお出で」
ひき 「あれさ、もうもう、たくさんだね。ちょうど御膳が来ているから、これで御積りとしようじゃないか」
ころ 「でも、もうそう言ったから、いいじゃあないか。あれさ、止めなくてもいいからさ。・・・姉さん、早くしておくれ」
18 新聞好きの生鍋
にわかに散切り頭になった西洋の身なりである。柳原[現、神田岩本町の神田川南岸]の朝市か、富沢町[現、日本橋]の大道で、途切れ途切れに買い集めた洋服ごしらえ。フランス仕立てのマントに、イギリスのチョッキ、かぶり物は歩兵の古物。靴の算段は完全ではなく、脱ぎ捨てたのは麻裏草履。時計の鎖だけでもぶら下げて、外見を繕おうとする人物であるが、その鎖の偽物は、銀メッキも手に入らない様子である。
人に時刻を聞かれると、「忘れた」と言い抜ける中年の半可通である。『世界国尽』[福澤諭吉著]、『世界都路』[仮名垣魯文著]などをちょっと初めの方ばかりを読んで、「西洋の事なら」と得意げに言いふらす困り者。生業が何か分からないが、よほどの怠け者である。弁舌は滔々としていて聞き取りにくく、俗人を驚かせるが、深く聞かれると一句も出ず、用にかこつけてその場を逃げ出すことは、作者の魯文によく似た人物である。
連れと両人は、牛鍋に冷や酒である。自分一人が開化の人物であるという顔をして、連れの者はほんの土台で、その実は辺りにいる客に自分の博学を吹聴するのである。紫呉絽の風呂敷包みより、新聞紙を3冊ばかり取り出して、読みもせずに傍らへ飾り物として置き、連れの男と相押さえの杯がある。
―――――――――――――
「おい、愚助さん、君の所の賢児はいくつになるね。倅はさ。・・・むむむ、もう9歳かね。それじゃあ従来の弊を追って遊ばせておいては、いけないよ。僕の所の豚児もさ、え、何。・・・うう、豚児では分かるまい。中国風で言うから解さないのも、むべなりむべなり。家のガキさ。これも今年8歳になるから、去年、くりくり坊主にしていた白雲頭、俗にしらくもあたまが、今年は散切りになったから、僕のかねての卓見で、「いろはにほへと」などはグッと廃して、混沌未分から英学さ。はて、西洋学も、なまじ漢学、史記、章句、論語、見の段の12万3千4百56石などを、ちょっとばかりやらせると、中国の因循が伝染して、大いに害になります。君の所の息子も、早く洋学を学ばせなさい。現今の形勢では、洋学でなければ夜は明けないよ。はてさ、何に習うとも覚えさせておけば、商人は商人、工人は工人だけの開化だね。まず、現今の御新政のありがたいことには、四民同一、自主自立の権を給わり、苗字帯刀、袴でも洋服でも、馬でも馬車でも、勝手次第。たとえ空乏困迫[蓄えが乏しい]の我輩であっても、往時の我輩ではない。ここがすなわち自主自立の権だ。しかし自立の権だの、自由の理だのと、一口に説いて聞かせると、無学文盲で野蛮な連中は、「それなら自分勝手な事をしても、善悪とも政府でお咎めがないものだ」と思う輩があるから困るよ。この節は都鄙、遠近となく、説教が解禁になって、諸社諸教の教導師が勉励するが、僕がこの職を命じられれば、静岡の中村敬宇[正直]先生が訳した『自由の理』[ JSミルの『自由論』]を訳解して聞かせて、世間の蒙昧を覚まさせたいものだ・・・」
「まず一杯」と杯のやりとり、そして牛を食うことが、長話のうちにあると知らなくてはならない。
「えええ、もし、すべて俗間の知覚を開き、人の知識を広めるのは、新聞紙の仕事だよ。今朝、米沢町の日新堂から届いた新聞[「日新真事誌」、西洋紙刷り日刊紙の祖]の58号だが、実に確証有益なことがあるよ。しかし伝聞の誤りがないとも言われない。横浜の「毎日新聞」に、「仮名垣魯文が街道で小便をして、罰金を取られて狂歌を詠んだ」などという大虚説が、次の号まで2日とも出ているが、当人は虚名家だから、歓喜雀躍、満足でいそうだが、随分おかしい間違いだね。
なに、これか。これは僕が退屈のあまりに書いておいた「珍聞紙」と号する「戯述」だが、いや、世の中には、新聞外の珍聞があるよ。ここにそれ、こう言うおかしな建言があるが、この建白書は、ごく真面目な篤実家で、この建言書がご採用になるという気で、町用掛りまで持ち出して、『あまり人を愚弄する文体だ、こんなものを政府へ出訴に及んだら、町用掛りまでの落ち度になる。とんだ男だ』と散々叱られたそうだが、随分珍説だね。この文面を、鍋と酒の代り目に、ちょっと読んで聞かせよう。
恐れながら書付けをもって建言を奉ります。おおよそ無用なものを有用に充てることは、経済が専ら当たるべき任務で、御国益の第一の義であると存じます。人民各戸は炎夏の時期になりますと、一般に蚤が生じない所はありません。この虫は、人身を刺傷し、短夜の睡眠の時間を破って、白昼の生計を妨げますので、実に無用有害な小虫と申せましょうが、彼も多数の生き物の少数です。採用によっては、有益の一端ともなるのではないかと存じます。つらつら愚考いたしました所、彼を火中に投げ入れますれば、たちまちに火気になって響きを発しますので、図らずもいい考えが浮かびました。彼のイギリスのジェイムズ・ワットなる者が、湯気に乗じて釜の蓋が沸躍いたしますことから、蒸気機関を発明しましたのと同じ議論で、小さな力を合して大きな力とするという道理であると存じます。
東京府下、および近郷のごく親しい人々に御布令をして頂いて、各戸に取り溜めさせ、数万匹の蚤をもって、毎日の12時の刻砲の火薬の代りとして頂き、夏季の3か月に使うことになりますれば、[これによって使用せずに済んだ]火薬を積み置いて頂きますと、百戦一勝の小さな端緒になるかもしれません。一粒万倍の成功、すなわち無用をもって有用に充てます。遠い慮りでございます。いやしい身を顧みず、愚案にまかせて、この建言を奉ります。億万に一つご採用になりますれば、この上の面目、ありがたく仕合わせに存じ奉ります。
恐懼謹言、頓首百万拝
浅草雷門前 富田利跳太郎
なんとおかしな奴があるものではないかね。これらがいわゆる喉元思案[浅薄な考え]だ。理屈のようだが有名無実で、何の役にも立ちはしない。とかく早呑み込みの生聞きがあるから、めったに西洋の話などはできないのさ。僕の今度の建白などは、実に国益の第一たるもので、必ずしも一個の利潤に関わらず一国の富をなし、我が大皇神国の貴い威力を地球一円に輝かせて、永遠に不朽の深策を奉るのだから、「蚤の建言」「蚊の脛の兵力」などとは同様に論じるべからずさ。
おや、また銚子の代り目だ。おいおい、姉さん、親方に言ってロースを大切りにして、焼き鍋を一枚あつらえてくれ。そして、このお客は煮たのがいいと言うから、タレ抜きのスープへ味醂と醤油を落として、よく煮てくれ。おいおい、愚先生、飯にはまだ「早野勘平」だぜ・・・」
と言う折に、12時[正午]の刻砲がドドドズドンと響いたので、
「ええ、びっくりした。ははあ、もう刻限かしらん。げええええええ」
〇第4、5編は、引き続いて出版します。次集は、『西洋膝栗毛』の6編でご披露した当世流行の散切り頭の洋学学生についての大穿ちで、その塾中での実地にわたる滑稽・諧謔であります。ご評判、ご評判。
[訳者注:『西洋膝栗毛』の中に、登場人物が『安愚楽鍋』を書いて読ませる場面がある。実際には第4、5編は書かれなかった]
安愚楽鍋第3編下了
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
