
こんな風に世界は終わる 爆音ではなくて、すすり泣きとともに/【感想】『映画と黙示録』岡田温司
核による人類滅亡、宇宙戦争、他者としての宇宙人(異星人)の表象、救われる者と救われない者、9・11という虚実の転倒と終末映画、そして、コンピューターやロボット、AIに支配される社会…。ホラー、パニック、アクション、戦争、SF、ミステリー、フィルム・ノワールなど、約250作を取り上げ、原典があらわすイメージ・思想と今日の私たちとの影響関係を解き明かす、西洋美術史・思想史家の面目躍如たる一冊。
「起こりうること」「間近に迫っていること」にとらわれて生きる私たち人間は、黙示録的な世界の鑑賞を欲しているのだろうか
アポカリプス、またはポストアポカリプスと呼ばれる映画ジャンルがある。前者は『インディペンデンス・デイ』『ディープ・インパクト』『アルマゲドン』など人類の終末までの描いたもので、後者は『マッド・マックス2』や『ザ・ロード』、一連のゾンビ映画などの人類社会の終末“以後”を描いたものだ。
終末を“預言”した『黙示録』はユダヤ教、キリスト教の文脈で成立した本であるので、そこには「信じるものは救われる」の言葉通り、神の力を前提として信仰にかかわるものであるが、現代においては宗教的な『黙示録』というよりも、環境破壊や科学への奢り、人間の傲慢さによるところが大きく、科学技術や人間活動そのものへの不信が根にあるのだろう。
今や人類と地球の破滅を予告するのは宗教家ではなくて科学者というのも頷ける。
本書はテーマ別にそれぞれ映画内の黙示録的なシーンを解説しているが、時系列として時代と映画を見ていくと戦後の冷戦的ペシミズム(敗北主義と批判されたシドニー・ルメットの『未知への飛行』など)とオプティミズム(核兵器がカタストロフを食い止め人類を救う『地球が燃えつきる日』など)が映画に交互に表れているのがよくわかる。
しかし冷戦期では核兵器といった「科学」による終末が描かれていたものの、2001年のアメリカ同時多発テロ以降のハリウッドでは、それらにキリスト教的な『黙示録』観が含まれ出す。
“第4章 9・11ビフォー/アフター ポスト黙示録とキリスト教原理主義”の項での『アイ・アム・レジェンド』の例はわかりやすい。
ウィルスによって人類の9割が死滅し、残された人類もミュータント化した世界で、ウィル・スミス演じる科学者のネビルは独り血清の開発をし続けるというストーリーだが、ラストでネビルの自己犠牲によって救われたアナという女性とその子供がコロニー到着する。そのコロニーでは米軍の兵士と民間人の二人が機関銃を構えて母子を迎える。コロニーの中央には白い教会と星条旗。本書はこのシーンについて“アメリカのキリスト教原理主義がヒロイズムと結託する瞬間”という。しかもこのコロニーの場所がイギリスの清教徒たちがはじめて入植したニューイングランドに位置するというオマケまでついている。
もちろん原作であるリチャード・マシスンの小説『地球最後の男』(過去同名で2度映画化さている)はこのような話ではないが、映画の別バージョンでは原作と同じラストが描かれている。
読みながら考え込むのは、『黙示録』というユダヤ教とキリスト教の文脈の中で成立した宗教書にもかかわらず、「この世の終わり」を描いた映画が終末思想のない仏教圏である日本人でも惹きつけられているということだ。自分自身、子どもの頃から終末についての映画や漫画、小説に強く惹かれてきた。人類の絶滅や文明の崩壊は米ソ対立という冷戦と第三次世界大戦=核戦争といった現実の問題があり、そうしたどうしようもない日常の不安に「ノストラダムスの大予言」といったオカルトブームが拍車をかけた。
そこでキリスト教的な宗教観をもたない日本人がなぜ終末に惹かれるのか、その一つの答えを本書に見つけた。
黙示録の思想にはつねに二面性が付きまとう。それは終末には恐怖や不安と同時に希望や救いを求めることであるが、これは宗教的なイメージ以上に人間の存在が本源的に深く根ざしているからであるという。
実は十代のころにジョージ・A・ロメロの『ゾンビ』に衝撃を受けた世代にとって、この映画の世界は恐怖の対象ではなく憧れの対象であった。
それは十代特有の抑圧と感じる大人社会(権力)を崩壊(リセット)させた世界への喜びと、ショッピングモールで売り物を自由気ままに使用する解放感(自立)だったわけである。
ハリウッド映画でも管理社会に反旗をひるがえす若者たちといった『メイズ・ランナー』や『ハンガーゲーム』といった作品などはアポカリプスと密接な関係であるディストピアものとして10代の若者に人気を博しているのも頷ける。
また哲学者ドゥルーズの『批評と臨床』においての「黙示録」への批判が興味深い。(黙示録は)“「自分(たち)だけが生き残りだと考えるもの」のための書物であり、それは「怪物的な集団の自我」に他ならない。キリスト教が黙示録によってでっち上げるのは、生き残った救済者による「まったくあたらしい権力のイメージ」であり、最終的な「決め手となる恐ろしい権力」である”と言っている。
この「まったくあたらしい権力のイメージ」について、僕は漫画『アイアムアヒーロー』を想起した。花澤健吾のこの漫画はゾンビをテーマにした終末を描いたものだが、終末が訪れ文明社会が「リセット」された世界において「新しい権力」を握ったのは引きこもりや、無職であった若者たちであった。日本の「黙示録」には、固定化されてしまった社会階層の破壊願望が多分にあるのだろうと、ドゥルーズの言葉から宗教観を差し引いても日本の黙示録観に自分なりの一定の答えを本書から見出せた。
それほどまでに「ゾンビ」を扱った作品は「黙示録」「終末観」に強く影響を与えるものであるが、残念ながら本書では意図的に排しているという。
現代において、あの終末イメージが映画だけでなく漫画や小説、ドラマなどもはやカルチャーとなっているジャンルであり、「ゾンビ」も本書が繰り返し語る収斂文化の一つではないかと思うのは僕だけではないだろう。
本書ではそのほかに、デジタル化された映画において“「映画ー眼(キノ・アイ)」から「映画ー筆(キノ・ブラッシュ)」へと変貌を遂げる”といったレフ・マノヴィッチの言葉に映画ファンとして頷き、「こんな風に世界は終わる/こんな風に世界は終わる/こんな風に世界は終わる/爆音ではなくて、すすり泣きとともに」というT・S・エリオットの詩から連想する、小さく、短いアポカリプスがネットに溢れ、この世界ではすでに黙示録は始まって日常化しているという言葉にまた頷いてしまうのだった。
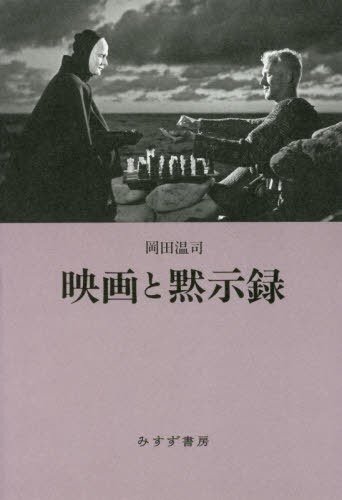
映画と黙示録
岡田温司/〔著〕
みすず書房
4,400円 ISBN:978-4-622-08873-8
最後までお読みいただきありがとうございました。 投げ銭でご支援いただけましたらとても幸せになれそうです。
