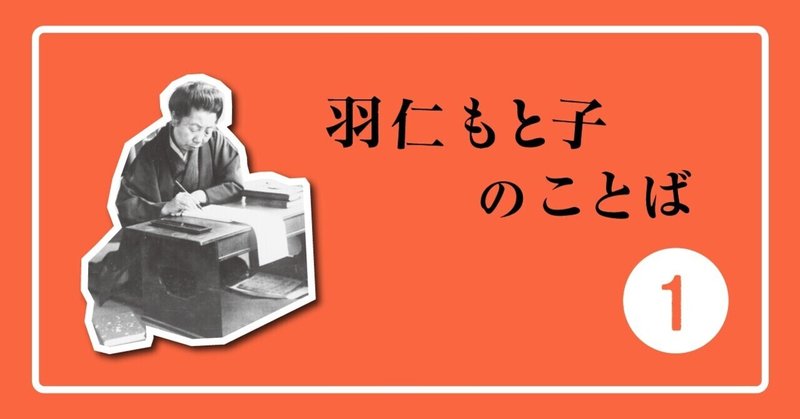
「いつでも予算超過」から生まれた家計簿
いつの時代も、新家庭の経済は、限られた収入の中でいかにやりくりするかが、課題ではないでしょうか。羽仁もと子(婦人之友社創業者、『羽仁もと子案 家計簿』創案者)も、新家庭の様子を次のように書き残しています。
*羽仁もと子の著作をまとめた『羽仁もと子著作集』(全21巻)が婦人之友社より発行されています。
「忙しい私たちの新家庭の経済は、いつでも予算超過をします。収入が段々多くなっても同じことです。どうしようかと始終心にかかっているうちに、ついに思いついたのは、今の家計簿の様式でした」
もう少し詳しく…… 当時のことを羽仁もと子の著作『家事家計篇』にこう書かれています。
「それは家庭之友を出して、間もないことのことでした。当時、新聞社に勤めていた主人の小遣は、月に十二円でした。何もむだづかいはする人でないのに、どうしてもそれが一と月もたないことから、こんなことを考えました。一日分をまず三十五銭ずつとして、一日にはがま口の中に三十五銭だけ入れておく、翌日はそれが十五銭あまっていても、また三十五銭入れておく、そういうことです。主人もそれは面白いといいました。月はじめに少しずつ倹約していると、六、七日目には銀貨が一円札になります。するとその一円札は使わないで、つぎつぎにいれる銀貨で間にあわせています。日曜など社に出ないで、どこか二人で散歩に行って、家計のほうの娯楽費からその費用をだした日にも、小遣は同じことです。それに日に三十五銭ずつとすれば、十二円のうちから大体一円五十銭あまっていることになり、それらを一緒にして、その時分の宴会費などはそれで支払うことができました。
それからふっとこの家計簿のことを思いついたのです。」
現在、婦人之友社より発行されている月刊『婦人之友』の前身である『家庭之友』が創刊されたのは、1903年(明治36年)。上記の“日々35銭”の試みは、『家庭之友』の記事となり、その翌年に『家庭之友 家計簿』が発行されています。
『家事家計篇』には、
「月収百円、その中から上述のように、貯金保険臨時費などで二割をのけて月八十円、東京住居とすれば、家賃が高いのですけれど、衣服家具の揃っている夫婦ぎりの新家庭でも、決してらくな暮らしではありません。」
という文章に続けて、食費32円、主人職業費10円……と、生活費の予算(80円の内訳)について書かれています。
夏目漱石が「東京朝日新聞社」入社した明治40年で、東京朝日新聞社の社長の月俸は150円と言いますから、引用の「決してらくな暮らしではありません」は、羽仁もと子の思いでもあったのかもしれませんね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
