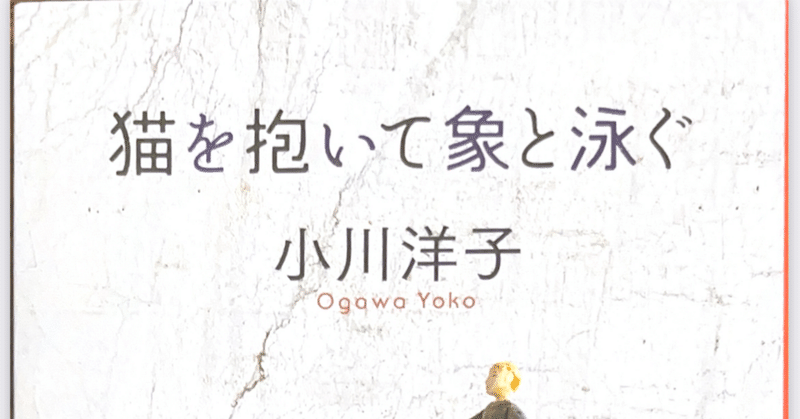
小川洋子『猫を抱いて象と泳ぐ』を読んで
『猫を抱いて象と泳ぐ』のあらすじは、「大きくなることは悲劇である」を箴言を胸に11歳の身体で成長を止めた少年、リトル・アリョーヒンはカラクリ人形を操りチェスを指す。盤面の海に無限の可能性を見出す彼は、いつしか「盤下の詩人」として奇跡のような棋譜を生み出す。と言うようなものだ。
本作の登場人物は、「仕方のないことへの諦め」みたいなものを各々持っている。例えば、リトル・アリョーヒンのチェスの師匠のマスターは、肥満によって自身の家であるバスの中から出ることが困難で、外に出ることはほとんど諦め、内側を充実してさせていた。デパートの屋上に住む象のインディラは、成長したことによって、登ってきたエレベーターに入ることができず、階段は彼には小さすぎたため、地上に降り立つことができなくなってしまった。しかし、降りることをしかたないとした彼は、子供達に愛嬌を振りまき、屋上で37年の人生の幕を閉じた。しかしながら、仕方がないことを諦めた彼らの人生は充実して幸せなものであった
この体験からリトル・アリョーヒンは大きくなることは悲劇と言う箴言を得た。リトル・アリョーヒンは仕方がない事を諦められなかったと私は感じた。少年が成長して青年になると言うのは当たり前のことで、或いは仕方が無い事だ。それをリトル・アリョーヒンは諦められなかった。カラクリ人形の中に入れる大きさで成長が終わる。
ここまで書いてきて分かった事がある。リトル・アリョーヒンは身に降りかかる仕方が無い事を全て諦める事ができなかった人物であることだ。チェスを打つこと、ポーンやミイラとの別れ、”リトル・アリョーヒン”でいることなど、物語で提示された全ての仕方がない別れのようなものを諦められなかった。このせいでリトル・アリョーヒンはあの最後を遂げる。それでも諦めず、右手にポーンの駒袋を抱いて、左手にビショップを持って、盤面の海を泳ぎ続けるのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
