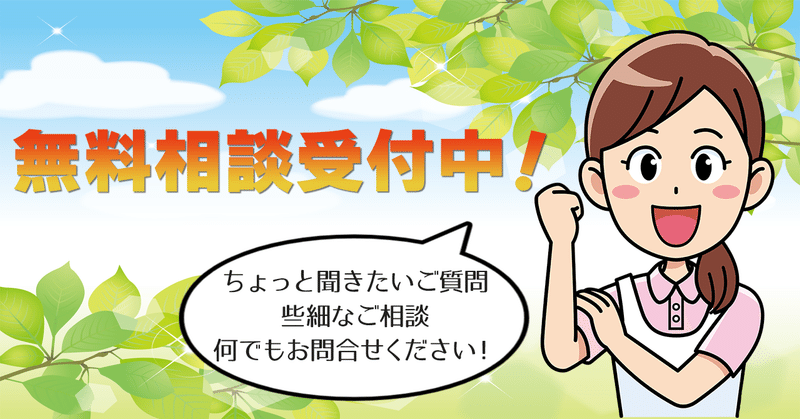快適な人生の実現に向けた施設入所のタイミングは?
少子高齢化や核家族化が進むにつれて、家族を取り巻く環境や価値観も大きく変わりつつあります。
一方で65歳以上の高齢者の人口は毎年増加傾向にあるため、高齢者同士の夫婦のみの世帯や独居世帯が増加傾向です。
住み慣れた自宅でいつまでも生活したいという思いがあっても、実際にはクリアしなければならない課題がたくさんあります。
QOL(クオリティーオブライフ ※1)の観点から「その人らしい生活」「心の満足度」という尺度で表すことがありますが、10人いれば10通りの人生観があるように、ひとりひとりの思いに寄り添った支援が求められます。
医療や福祉における判断基準だけではなく、本人や家族の思いを優先した適切な選択をしていくことが理想だと言えるでしょう。
では、どのようなタイミングで施設入所を検討すればよいのでしょうか。
家庭環境や状況に応じて、考えていきましょう。

高齢者の独居の場合
生活において支障がない場合には在宅生活の維持が可能ですが、これまで当たり前にできていたことが出来なくなった場合や、物忘れが多くなってきた場合には注意が必要です。
加齢に伴った脳機能の低下は誰にでも起こりうることですが、高齢者本人が物忘れをしている自覚がない場合には認知機能の低下が考えられます。
約束や収納場所などの小さな物忘れであれば支障はありませんが、体験そのものを忘れてしまった場合には取り返しのつかない事態を招くことが予測されます。
もし、体調の変化や生活機能の低下など気になることが増えてきた場合には、高齢者世帯のある自治体の地域包括センターや相談機関に相談してみられることをおすすめします。
介護保険サービスの提案など、在宅生活の継続に関する適切なアドバイスを得られるでしょう。
介護保険は社会全体で高齢者介護を支えることを目的として2000年に誕生した制度です。
要支援や要介護度によって、訪問介護(ホームヘルプサービス)・通所介護(デイサービス)・短期入所生活介護(ショートステイ)の利用が可能となるので独居の場合は心強いサポートになるでしょう。
また、なかなか会いに行けない場合には近くに住んでいる親戚やご近所さんと良好な関係を築いておくことで早めの対応が可能となります。
現在、自治体や企業が独自で導入している高齢者見守りサービスもあるので、必要に応じて活用してみるのもいいでしょう。

高齢者同士の夫婦世帯の場合
日常生活において問題がない場合には在宅生活を送ることが可能ですが、年齢的にいつ何が起きてもおかしくありません。
普段から、近所づきあいや交友関係などのコミュニティーを意識しておくことで暮らしやすい環境づくりが実現するでしょう。
どちらかに健康や認知面などで問題が生じた場合には、介護保険の活用によって在宅生活の継続が可能になります。
できない部分はプロに頼ることで、介護者(介護する側)・被介護者(介護される側)双方にとって快適な在宅生活の維持が可能になります。
もしも、介護保険サービスを活用しても生活の継続が困難になってきた場合には施設入所を考えるタイミングなのかもしれません。

65歳以下の家族と同居の場合
家族や高齢者の健康状態や認知面で問題がない場合には、生活に支障が生じることはないでしょう。
要介護認定を受けた場合でも、介護サービスの活用によって日常生活の維持が可能となります。
しかし、健康や介護面で家族の負担が大きくなった場合には家族が介護休暇や介護離職をしなければならない状況になることもあります。
そうなった場合にどのような選択があるのか、地域包括センターなどの相談窓口に聞いておくと安心です。

まとめ
在宅での介護生活は24時間365日休みがない状態なので、1人で悩みを抱え込んでしまいがちです。
金銭面を含む介護全般の悩みや不安はなかなか人には相談しづらいことですが、蓄積されると取り返しがつかない状況に陥ってしまうこともあります。
介護者・被介護者双方のQOLの観点から見た場合には、もしかしたら施設入所は希望に添うものではないかもしれません。
しかし、「心の満足度」として考えた場合、長い目で見ると最適な選択なのかもしれません。
普段から「どのような生活を送っていきたいのか」「最期をどのようにして迎えたいのか」についてしっかりと話し合っておくことで、快適な生活のヒントが見つかるのではないでしょうか。
※1 QOLとは
快適な人生の実現に向けた施設入所のタイミングは?
ベストのタイミングなど些細なことでも下記から相談してみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?