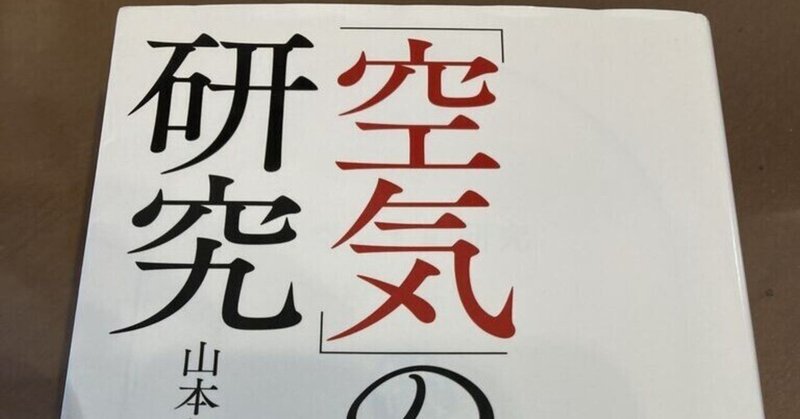
「空気の研究」 山本七平
「空気の研究」 山本七平 文藝春秋(1983/10)
「人は水と霊とによらずば、神の国に入ることあたわず」
このイエスの言葉を、
「人は「空気」と「水による心的転回」を知るに至らねば、人の国に入ることあたわず」
とすれば、それはまさに日本。
本書は、「空気」と「水」による絶えざる心的転回で、常に新しい心的秩序に入るという、日本的な人間的体制を探ることを主題としています。
「対象の相対性を排し、これを絶対化すると、人間は逆にその対象に支配されてしまう」
「空気」という、「超論理的存在」の発生から支配にいたるメカニズムを、徹底的に解明した名著です。
■目次■
1.「空気」の研究
2.「水=通常性」の研究
3.「日本的根本主義」について
■ポイント■
◆「空気」が「論理的結果」を凌駕する
・「空気」とは、絶対的拘束力を持つ「判断の基準」
「戦艦大和の特攻出撃」
「あの時の空気では、そうせざるを得なかった」(抗空気罪)
・「論理的判断基準」と「空気的判断基準」の二重基準
議論のおける言葉の交換そのものが、「空気」を醸成していき、最終的にその「空気」が決断の基準となっていく
・「空気」への抵抗は、多大なるエネルギーが必要
殉死の覚悟も必要
◆「人工空気醸成法」:「自動車「魔女裁判」」
・「自動車」という「物体」が被告人
・「NOx」が有害かどうかという議論ができない「空気」
・「交通事故」は、免許証濫発が原因と言えない「空気」
・「対象」への「臨在感的把握」に基づく判断基準
「物神論的宗教」化
・「NOx」と関係ない「死の臨在」(交通遺児)の登場
「超法規的な処断」
◆「物質の背後に何かが臨在していると感じ、知らず知らずのうちにその何かの影響を受ける状態」
「物質から何らかの心理的・宗教的影響を受ける」
・「啓蒙主義とは、一定の水準に民度を高める受験勉強型速成教育主義で、「かく考えるべし」の強制であっても、探求解明による超克ではない」
・「明治的啓蒙主義は、「あるもの」を「ないこと」にしてしまった」
その結果、逆にあらゆるところに転移してしまった
・「イタイイタイ病」と「カドミウム」の関係
「カドミウム棒」に「感情移入」(乗り移り)し、「臨在感的把握」を絶対化する
・「感情移入」の日常化、無意識化、生活化、
それをしないと「生きている」という実感がなくなる世界
・「神」という概念は、「恐れ」の対象:「偶像支配」
◆「西南戦争」の事例
・「農民徴募の兵士を使う官軍側は、戦争に「心理的参加」をさせる必要」
「官軍=正義、仁愛軍」「賊軍=不義、残虐集団」という図式に
→「空気」を醸成する計画的キャンペーン
・「対立概念で対象を把握すること」を排除すること
「善悪という対立概念」による対象把握は、「空気」に支配されない
「対象の相対性」を排して、「絶対化」すると、その対象に支配される
◆「空気」支配克服の要点
・「臨在感を歴史観的に把握」
・「対立概念による対象把握」
「経済成長」と「公害問題」を相対化する
◆「空気」:「プネウマ」(アニマ)=「風・空気・霊」
・「霊(プネウマ)の支配」
◆「一神教」の世界と「アニミズム」の世界
・「一神教」の世界では、すべては「相対化」される
「絶対化」されるのは「神」のみ
・「アニミズム」は「空気主義」
「絶対化」の対象は無数にあり、時間経過で変化する
◆「多数決」は「相対化」された命題の決定のみに使える方法
・「議場・飲み屋」二重方式の採用
◆「水=通常性」
・「最も具体的な目前の障害」を口にすることで「水を差す」
・「全体空気拘束主義者」は、「水を差す者」を罵言で沈黙させる
◆「消化酵素」:内部の実態を変質させ、名だけ残って消化吸収される
・「ぬいぐるみ」と「実態」
・「通常性」による「消化吸収」に基づく「変容」
「時間的な通常性」:日常性
「空間的な通常性」:常識
◆「情況倫理」
・「オール3」的文化:「絶対倫理」をねじ曲げる力
「特高のリンチ」と「共産党のリンチ」
・「伸縮自在な物差し」
「矛盾」こそが「支点」となる(「神格化」):異議は「不敬罪」
「一君万民」:「一人の絶対者」と「オール3民」
◆「空気」を創出しているものも、「水=通常性」
・「空気」と「水」の相互的呪縛から脱却できない
「日本の根本主義(ファンダメンタリズム)」
◆「それが絶えず対象から対象へと目移りがして、しかも移った一時期はこれに呪縛されたようになり、次に別の対象に移れば、前の対象はケロリと忘れる」
◆「相対化することで、空気に水を差すことはできるのだが、そのリスクは非常に高い。現代ではさらに高まっているかもしれない。空気こそがすべてという人にとって、水を差す人間は完全なる攻撃者である」
◆「空気が醸成され、さらにそれが加熱しはじめているとき、そこに水を差す人間は、ほとんどソクラテス的に迫害される。あるいはその可能性を持つ。反対意見の内容が問題なのではない。なにせ、「空気」は理路を持たないからだ」
◆「空気が忌み嫌うのは、反対意見があるということを提示するその行為自体である。
その存在は空気を相対化してしまい、自身の絶対性を傷つけてしまう。そのような存在は絶対に許容できない。だから、反対意見を述べるものを攻撃し、迫害し、疎外して、黙らせようとする」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
