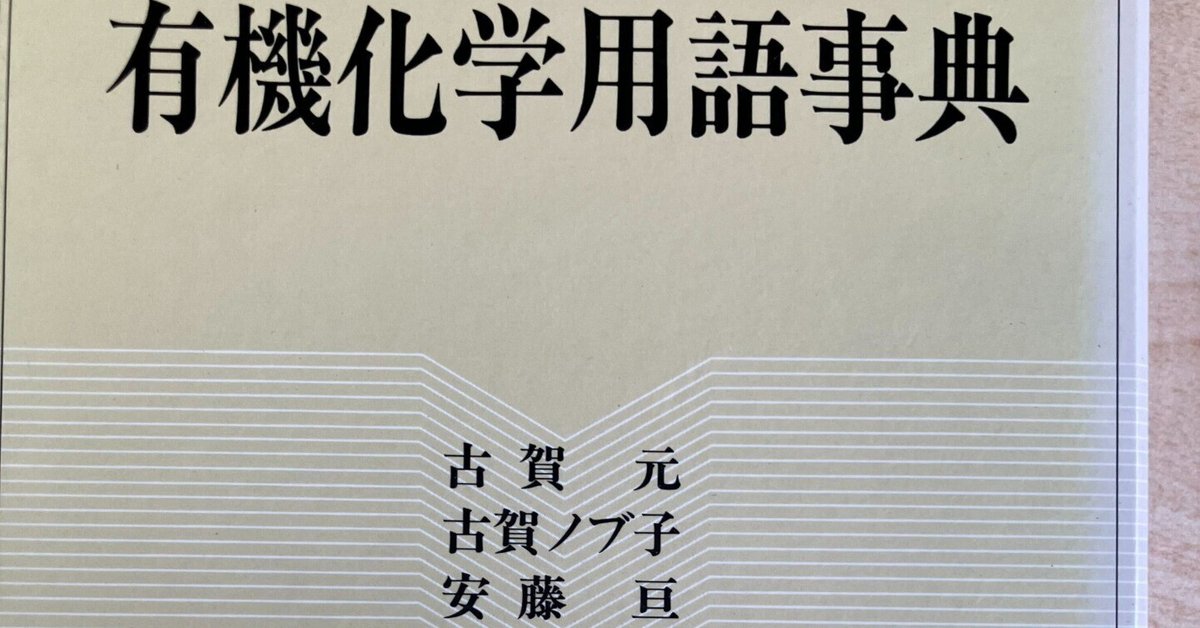
書評:有機化学用語事典
読んだ本
古賀 元・古賀 ノブ子・安藤 亘 著、有機化学用語事典、初版第1刷、朝倉書店、1990年

分野
有機化学全般
対象
有機化学に携わっている人
評価
難易度:無評価
文体:易 ★★☆☆☆ 難
内容:悪 ★★★★★ 良
総合評価:★★★★★
1冊は絶対持っておきたい名著
内容紹介
有機化学で使う用語約830を体系的に配列し,反応式・構造式も示しながら詳しく解説。その術語の語源や背景,さらには物質や事項にまつわる研究者の略歴や業績なども注記したユニークなハンドブック。この一冊で有機化学への知識がより深まる。学生・研究者の座右の書。〔内容〕分子と分子構造/化学結合の基礎理論/化合物の種別名称・命名法/分子のかたち/酸・塩基/イオンと反応中間化学種/熱力学・化学反応論/有機反応機構/人名反応・試薬と特有名称反応・試薬(引用: 有機化学用語事典 (普及版)|朝倉書店 (asakura.co.jp))(※自分が所持しているものは普及版ではない)
感想
化学事典のようなものはいくらでもその辺にころがっているが、多くの辞典は無駄に大きく、無駄に重く、無駄に単語数が多い。もちろん、その重厚感もたまらない (私は大艦巨砲主義なので、とにかくデカい本が好きである) のは事実だが、範囲が広すぎるが故に、読者の専門性が高まると基礎レベルのことしか書いておらず、あまり使えるものではなくなってくる。実際、自分も岩波書店の理化学辞典や、全10巻にも及ぶ共立出版の化学大辞典など、学部の頃は大変お世話になっていたが、修士の頃には全く使わなくなってしまった。その理由としては、やはり”化学”という広大な分野を対象としているので、高度な学術用語が掲載されていないという点。それから、自分にとっては無駄な単語が多いので、目的の単語を探すのに一苦労する。つまり、重くて大きいくせに、”濃度”が低いのであまり使う気にならないのだ。
それに比べて、当書は有機化学に特化した事典であり、それなりに有機化学に精通した人でも知らないようなマニアックな単語も掲載されている。何より”濃度”が高いので、目的もなく当書を眺めているだけでも面白い。また、一般的な事典と異なり、単語があいうえお順ではなく内容別に分類されているので、周辺知識を会得しやすい。一般的に事典を使うには、調べたい単語を知っている必要があるわけだが、内容別に分類されているが故に知らない単語でも調べやすい。
購入
購入したのは確か修士時代にamazonで、中古で数百円だったのだが、パラパラとめくった瞬間に当たりをひいたことを確信した。今でも1000~2000円程度で購入できる。ちなみに、私が所有しているものとは別に、普及版とやらが存在しているが、違いについてはよくわからない。
余談
浅学の身故、辞典と事典の違いを知らなかったのだが、今回の記事を書く際に少し調べてみた。あいかわらずネットで調べても信ぴょう性の怪しい個人運営?のサイトが検索トップにでてくる。ネットのことは詳しくないが、信ぴょう性と中身が薄いサイトを最上段にもってくるのはやめてほしいところである。話がそれたが、まともなサイトを調べていると、国立国会図書館が全国の図書館等と協同で構築しているレファレンス協同データベースに同様の質問があったので、以下にその内容を写させていただく。
質問:事典と辞典,字典の違いはなにか。
回答:「事典」は事物や事項を解説したもの、「辞典」は言葉や文字の意味・発音・表記等について解説したもの、「字典」は漢字の読みや意味について解説したもの。
(引用:事典と辞典,字典の違いはなにか。 | レファレンス協同データベース (ndl.go.jp))
レファレンス協同データベースという存在を初めて知ったのだが、中々いいサイトに出会えた。何より回答プロセスという欄で、その答えにたどり着いた過程を示しているので、参考文献をひとつも記載しないゴミサイトとはけた違いの信頼性である。回答を読んでみると、化学”じてん”の場合は事典のほうが適切のようだ。しかし文中に述べたように、岩波書店の理化学辞典や、共立出版の化学大辞典は”辞典”を用いているので、どちらでもいいのかもしれない。確かに化学用語という言葉の意味、という解釈なら辞典でもいいのだろうか。識者の回答を求む。
参考サイト
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
