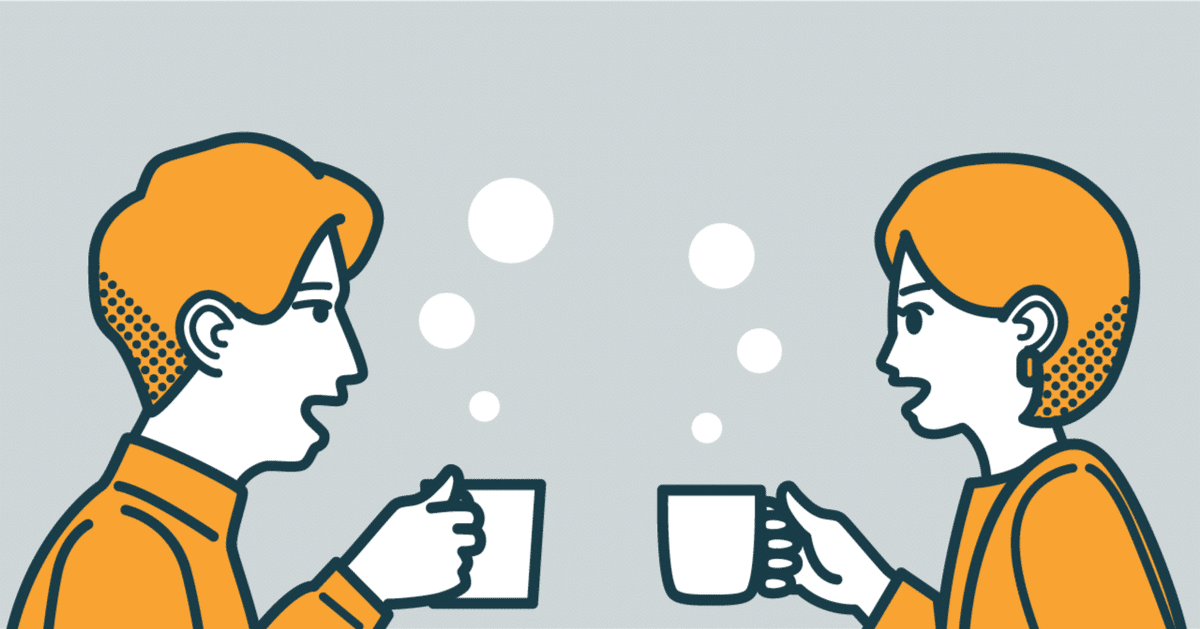
雑感への雑感。あるいはアンチワーク哲学の補修作業【アンチワーク哲学】
のり子さんが、本の感想を書いてくれた。
どうやらかなり共感してくれたらしく「ほとんど同じことを考えてる人がいた」という感想を書いてくれている。嬉しい。そして、共感してくれているがゆえにより鋭い疑問点や懸念点を提示してくれた。それも、多岐にわたるテーマについて触れてくれた。
どれも避けては通れない問題である。今回は一つ一つの論点にアンサーを返していくことによって、より思考を深め、アンチワーク哲学を進化させていきたい。
※ただし、まとまりきっているわけではないので、若干読みにくい文章になると思われる。
■インフレの話
順番にいこう。僕が「BIによってインフレは起きない(と思われる)」「インフレは需要が大きいときか、供給が少ないときに起きる」という議論を展開したのに対し、のり子さんは次のように書いてくれた。
インフレが「需要が大きくなりすぎたときか、供給が減ったときに起きる」というところ。
本題に関係ないので、あまり深くは掘りませんが、景気は資産家によって上下すると考えてます。そして投資的行為(株から仕入れまで——投機っていうんだっけ?)が行われている限りインフレになる。需要はそれに追いつくように追っかける。がどこかのラインで追いつかなくなる。そのときデフレに反転する。言うとすれば「需要が供給を追いかけてるときインフレになる」かなと考えてます。もちろんこれが正解という自信はさらさらないですが。
ここでのり子さんがなにを意図しているのかは明確ではないが、おそらく投資によって供給が拡大するのと同時に、需要が生み出されていく(だから需要が供給に追いつこうとする)ということなのだと思われる。
たしかにその説明も一理ある。僕の説明はあくまで教科書的なシンプルなものであり、需要と供給が独立して存在しているかのように単純化して説明している。実際はそうではない。供給過多の現代では、供給したいという企業の思惑に合わせて、需要がマーケティングによって人工的に発生させられている。
このプロセスにおいて供給サイドが価格をけん引していると言えるのか、それとも需要に応じて価格が決定されると言えるのか、正確なところはよくわからない。おそらく両方の側面がある。スタバのコーヒーが四百円もするのに、百円のコンビニコーヒーに淘汰されないことからも、価格は教科書的な単純な需給バランスでは説明がつかないことの方が多い。それはその通りである。
とはいえ、一定程度は教科書的なメカニズムで価格が決定されていることも事実だろう。ただ、それが現代においては変形していき、のり子仮説のメカニズムが生じているというだけであって。
要するに、教科書の説明と、のり子さんの説を組み合わせるとこういうことになるのだと思われる。
▼供給特大→企業が需要を拡大しようとするも追い付かずモノ余りでデフレ
▼供給大→企業が需要を大きくしようと投資して成功。投資の回収のためにややインフレ
▼供給並→需要を大きくしようともせずインフレもデフレも起きない
▼供給小→需要に供給が追い付かずインフレ
▼供給極小→ハイパーインフレ
さて、アンチワーク哲学が想定するのは、無意味に需要を煽り立てる必要がない社会である。そもそも強引にでも供給しなければ人々が食い扶持を稼げない状況が、ブルシットなマーケティング合戦によって需要を生み出す構造をつくりだしている。無理に供給せずとも食い扶持が保障されるなら、「供給したい」という企業の欲望によって生じる「需要が供給を追いかけてるときインフレになる」という構造は消えていくのではないかと考えている。
いずれにせよ、BIが問題解決になることは間違いない。過剰な供給は間違いなく減っていき、それによって過剰な需要は引き下げられる。とはいえ、ほどほどの需要と供給に落ち着くのではないだろうか?
とはいえ、この辺りは本題ではないのであり、あまり深入りはしたくない。次に進もう。
※余談。コロナ禍で、政府が金をばらまいたのにインフレにならなかったとか、時間がたってからちょっとだけインフレしたとかいう話は示唆的である。あのときあれだけ金をばらまいたうえでみんなが休んで家に引きこもっていたのに、ハイパーインフレは起きなかったのだ。BIを配ったところで、インフレ的な影響はないだろうに。
■お金のない世界の話
続いては、「お金のない世界」の話。これに関してはのり子さんは否定的な立場なようだ。
ホモ・ネーモさんはその先に、お金がなくなる社会を想定されていましたが、それはどうかなと。
「どうかな」という疑問は、「実現するか否か」というより「それを考える必要はあるか」というものです。お金が無くなる社会は、BIが実現してなお遠い未来の話っぽく、そうなるとほとんどSFなので想定の端っこにちょこんとあるだけならまだしも、大々的に掲げるほどのものかという気がします。
このSFをもっと踏み込んで考えてみると——
お金は本来コスパがいいから導入されたものです。違う文化圏同士でのやり取りの際に必要とされ生み出されたのが貨幣だとのり子は考えますが(柄谷行人が確かそういうことを言ってた気がする)、とすると、貨幣の無くなった世界に、また貨幣を再発明する奴がいるのではと想像してしまいます。
実際僕は「遠い未来の話」くらいに考えていたわけだが、それ以前に、のり子さんとはどうやら貨幣観の違いがある。
僕はお金はそもそも人々の利便性のために生み出されたのではなく、支配のための道具として生み出されたと考えている。
※以下の記事は寓話だが、ある程度、マジでこんな感じだったと思っている。
歴史的に最初期のお金は、支払いの約束=負債として生み出された(というか、いまでも日本銀行券は日本銀行の負債であり無利子無期限の借用証書なわけだが)。そもそも信用通貨として始まったものなので、同じ文化圏の中でしか通用しなかったはずだ。その後、戦争の物資補給の必要性からコイン(と租税のワンセット)が発明され信用貨幣ではない貴金属貨幣が生み出された。異文化交流はそこから生じた副産物であると考えられる。
もちろん、現代においては金はまた違った役割を果たしている。グローバルサプライチェーンからお金を引っこ抜いてiPhoneみたいなものをつくれるかどうかはわからない(メガサイトやバーニングマン、Linuxのような萌芽はたしかに存在するが)。だが、BIによって労働とお金が骨抜きになり、ある程度まで自発的な貢献で社会が組織化されていったあとに、人々がお金に代わる概念装置と組織メカニズムを生み出す可能性は十分にあると思っている。
お金はその管理に人類社会全体で手間がかかりすぎているし、貢献サイドと被貢献サイドを概念的に切り分けてしまい、欲求の二重の一致を妨げるネガティブな効果がある。
人間が本来持つ貢献欲は、お金によって見えなくなるだけではなく、抑圧されている。なので、いずれお金をなくすべきであると僕は思う。もしお金抜きで人類が協力できるなら、そうすべきでだという意見に異論はないだろう(とはいえ僕も二十一世紀のうちにお金がなくせるとは思っていない。二十二世紀中くらいにはできるんじゃないかなぁくらいの気持ちである)。
■ヴィーガニズムの話
続いてのり子さんはヴィーガニズムとアンチワーク哲学の親和性の高さを指摘してくれている。アンチワーク哲学とヴィーガニズムは親和性が高いことには同意見である(そもそも僕はなんちゃってヴィーガンなのである)。だが、日本人にとって食いつきのいい話とは言えないので、触れてこなかったというのが正直なところだ。
残酷な工場畜産は、結局のところ利潤追求動機によって生じている(好き好んでB5用紙一枚の面積に糞尿と共に鶏を閉じ込める人間などいないのである)。利潤追求動機が薄れていったとき、自ずと解決の方向へ向かうと思っている。
また、「食」を過剰に礼賛するのも、おそらく労働の仕業である。日本人が食べる量を半分に減らしたところで死人はほぼでないどころか、健康になる人の方が多いだろう。「食べることは生きること」というプロパガンダは、「食べる=被貢献=喜び=余暇」と「つくる=貢献=苦しみ=労働」という分断を生み出して、強化し続けている。人が食以外の喜びを思い出したとき、腹が出るまで焼き肉食べ放題に通い詰める事態は減っていくはずだ。その結果、動物も一定程度は解放されていく。いずれ、「道を歩いていたら通り魔に包丁で頸動脈を切られた」というレベルにまで、畜産の残虐さを減らしていくことは可能だろう。
このあたりの話も、ゆくゆくはアンチワーク哲学と絡めて書いていきたいところである。
■フェミニズムの話
また、のり子さんはフェミニズムもアンチワーク哲学と親和性が高いと書いてくれた。これも同意見である。
フェミニズムには二つの潮流がある。CEOの席に女性を座らせようとするタイプのフェミニズムと、CEOの席をぶっ壊そうとするフェミニズムだ。日本でフェミニズムと言えば、前者をイメージされるのがふつうであるが、僕は後者の考えに賛同しているし、アンチワーク哲学によってそれを実現したいと思っている(男性がボスにならなければいいという話ではなく、誰もボスにならないで欲しいという話である)。
ただし、ヴィーガン同様に、フェミニズムもノイズとなりがちな単語である。だからあえて僕はそこに立ち入らなかった。とはいえ、もう少し踏み込んでもいいかもしれない。
■モテ・非モテ問題の話
さて、続いての指摘はこれである。
見落としというか、見ないようにしているのか。
ひとつ解決されていない大きな、しかももしかすると一番根の深い問題が残っています。それは、モテる人モテない人の差です。
「アンチワーク哲学」的社会においてこの差はどう解消されるのでしょうか。
私には全く想像できない。うまく行くかもしれないし、事件が起こるかもしれない。
僕はいろんな観点から、モテるモテない問題は、たいした問題ではなくなっていくと考えている。
そもそも人はなぜモテる必要があるのか?
「セックスがしたいから」というだけではない。多くの場合、誰かと結婚して家族をつくって、子どもを産むことがステータスとなっているからである。
しかし、BIが実践された社会では、「家族」(正確に言えば「血縁」)の概念は徐々に崩壊していき、モテ・非モテの問題は問題でなくなっていくと考える。
どういうことか?
現代社会は、あるいは経済は「これをやるかわりにこれをよこせ」という交換原理だけですべてが成立しているかのように装っているが、実際のところ交換原理だけでは人間社会はどう考えても回らない。基盤的コミュニズムが不可欠である。とくに子どもの世話に見返りを求めることは不可能である(そんなことをしていたら子どもは死んでしまうのだ)。だからこそ「家族」や「血縁」というプロパガンダが必要だった。「血縁なのだから、見返りを考えずに子どもの世話をするのが自然ですよね? それは当然ですよね? とはいえ、それ以外の他人を相手にするときには、あなたは合理的計算を徹底するホモ・エコノミクスなのですが・・・」というわけだ。
(そして、もともと他人同士であった夫婦間は、エーリッヒ・フロム的な高尚な「愛」の実践や、あるいは「運命の出会い」によって成立させなければならないことにされた。)
こうした血縁のフィクションはほとんど嘘である。「育ての親より生みの親」であり「遠くの親戚より近くの他人」なのである。人は一緒に過ごす人に対して愛を抱くだけにすぎない。「血縁だから贈与、血縁でないから交換」という判断基準を持ち込むことは端的に間違っているのだ。
嘘は徐々に暴かれていく。強制による労働が消えれば、人は万人に対して貢献欲を抱く存在であることが明らかになっていく。そうなったときに、血縁というフィクションを正当化することはむずかしくなっていく。
また、現代社会が血縁を重視しなければならないのは、人々がそこから逃れられないという側面もある。結婚相手に腹が立っても離婚できないし、未成年は簡単に家出できない。BIによってそれが可能になれば、血縁関係を重視することのない、自由なコミュニティはどんどん生まれていくだろう。
するとどうなるか? モテる、モテないの概念は崩壊していくのである。
現代においてモテる男は安定収入のある公務員や大手企業のサラリーマンである。安定収入が求められるというのは、多くの人が安定していないからである。BIによって万人が安定すれば、金銭や社会的ステータスによるモテるモテないの問題は消滅していくだろう。
次に、現代においてモテる女は若い女である。若い女が求められるのは、子どもを産むためである。血縁という概念がなくなれば、自分の子どもを産む必要は必ずしもない。
血縁というフィクションが崩壊していけば、恋愛や結婚が排他的な独占権である必要がなくなる。男女関係はありふれて、気まぐれな関係性へと変わっていくはずだ。現代におけるモテ・非モテの問題は、少なくとも今よりマシになる。
そして家族はより能動的な共同体になっていく。「一緒にいたいから一緒にいる」というだけのコミュニティに変わっていくのだ。
■警察の話
最後に、権力の話である。アンチワーク哲学は徹底的な権力否定の思想なので、それを論理的に突き詰めたときに警察力の解体が生じる必要があるが、「それは可能なのか?」と、のり子さんは指摘する。
基本的には権力否定の思想ですが、権力は治安維持に最もよく働きます。治安維持を権力で行わなかった(行えなかった)時代に、日本の平安時代とアメリカの西部開拓時代がありますが、どちらも武士・ガンマンが自衛のために現れました。ニケの考える未来像で警察はどのようにあるのでしょうか。
権力の否定から、最終的に国家の警察力の否定という結論を読み解くあたりは・・・鋭いというか、正直そこまで踏み込まないで欲しいなぁと思いながら書いていたので、あたふたしているところである。
というのも、僕は自称隠れアナキストなので、最終的には国家と警察の解体を望んでいる。だが、「労働の撲滅」だけで十分に荒れそうなので、輪をかけて議論をかき乱す国家解体の論点は『14歳からのアンチワーク哲学』には盛り込まなかった。
とはいえ、こうなってしまった以上、避けては通れない。僕の考えを述べると、警察の解体は労働の廃絶の果てに自然発生すると考えている。
そもそもアンチワーク哲学では、BIによって生活を保障し、金のために労働を強制させられる状況を減らせば、犯罪は減っていくと考える。
窃盗や詐欺の多くは貧困が原因であり、殺人は馬の合わない人から逃れられない状況から生じる。ワイドショーで犯罪の報道をみたとき「この事件はBIがあったら起きていたかなぁ」と考えてみると明らかである。BIがあったなら起きなかったであろうと感じる事件にしか、ほとんどでくわさないのである。
そうなったときに警察、検察、刑務所、裁判所といった治安維持装置(官僚制に覆い尽くされた暴力装置)は、存在意義を失っていくだろう。
もしBIがなければ、警察は食い扶持と権力の維持のために、ありとあらゆる策を講じて(ブルシット・ジョブを生み出すなどして)自分たちに割かれる予算を確保しようとするはずだ。だが、BIがあるのだ。そんなことをせずに警察をやめて、好きなことをすればいいのである。
もちろん、全員が全員辞めるような事態にはなるまい。犯罪もゼロにはなるまい。だが、時間をかけて警察という存在が社会の後景に引っ込んでいくはずだ。
武士もガンマンも、貴族と農民、あるいは開拓者とインディアンという支配構造に対する反発を抑え込むための装置だったと思われる(いや、ごめん、詳しくは知らないんだけど)。そもそも揉め事があればすぐ警察を呼ぶという現代の状況は、ほんの百年前から見ても異常な事態に見えているはずだ。警察力が日本の津々浦々まで浸透していたのはほんの最近の出来事にすぎない。それまで長い間、治安が乱れたときには隣近所の男たちが「どうしたどうした?」と顔を出して解決していたわけだ。労働が廃絶されゆく社会なら、そうした地域コミュニティが回復するのも時間の問題だと思われる。
なにも一夜にして警察が撲滅される必要はない。それに「警察を廃止しろ」などという議論を巻き起こして、警察官たちが「はい、わかりました」と二つ返事をするわけがない。なので僕の結論は「成り行きに任せよう」である。この社会が、あるいは警察官たちが、「警察が必要である」と考えるのであれば、それはきっと必要なのかもしれない。無理に廃絶する必要はない。
つまり、国家の暴力が廃絶されたとき、日常的な治安維持には大きな問題は生じないと考えられる。より差し迫った問題は国防だろう。そっちの話に踏み込むと長くなるので割愛するが、それも成り行きで何とかなると思っている。
■最後に
こういう議論が巻き起こること自体が、問題が解決されるという見通しを確実なものに変えていくと思う。
どういうことか? 「こういう問題が生じる」という問題提起をしてくれる人はたくさんいる。「問題だ」と感じる人は、思う存分その問題を解決すればいいのである。生きるために労働する必要がなくないのだ。好きな問題を、好きに解決すればいい。非モテのためのコミュニティをつくってもいいし、工場畜産への抗議活動を始めてもいい。少なくとも、いまの社会よりはやりやすいだろうし、協力してくれる人も多いはずだ。
残念ながらいまの社会ではなんらかの問題解決にフルコミットしようとすれば、即座に食い扶持を失ってしまう可能性が高い。あるいは、問題解決に取り組んでいるように見える企業に就職したとして、ブルシット・ジョブに覆い尽くされている現状に絶望する未来が目に見えている。
僕はあらゆる問題についての解決策を提示するために共産党中央委員会を組織するつもりはない。労働という支配がなくなったなら、人々は自発的に問題を解決することが可能になるだろうし、その時点でほとんどの問題は解決されているであろうと見立てているにすぎない。
僕の思い描くロードマップは予想にすぎない。自由ならなにが起こるかわからないのが当たり前なのである。とはいえ、僕が思い描くロードマップでは警察も、国家も、お金も、とりあえずは存在したままである。なにも一夜にして、すべてが自発的な貢献だけで賄われる社会になるわけではない。BIという形でお金に頼って、社会を組織化する時代は一定期間続くだろうし、人類滅亡まで続くかもしれない。
お金が配られるということは、社会から最低限の貢献を向けてもらえるだけの権力を強制的に付与されるということだ。今の社会では、それすらも簡単には与えられない。労働するか、生活保護の水際作戦に勝ち残るか、その他の方法を試さなければならないのである。今の社会よりも弱者が保護されている状況にあるのは間違いない。
もしお金がなくなったとき、万人が貢献を享受できる社会であり続けるかどうかはわからない。だが、BIという移行期間の中で、人々は弱者救済のシステムを編み出していくことだろう。狩猟採集民ですら、食べ物を生産できない障碍者を優しくいたわり年寄りになるまで世話していたという話もあるのだ。現代のテクノロジーをもってして、できないと考える方がおかしいだろう。
僕の言うことに多くの人が違和感を抱くのは、多くの人が僕とは違うパラダイムでできたメガネをしているからであって、僕がやりたいことはメガネを付け替えることである(当然、メガネを外してありのままに見つめている・・・などと主張するつもりはない)。そして、哲学とはメガネを付け替える営みなのだ。だからアンチワーク哲学は哲学なのである。
※最近、頭がこんがらがって、文章が書けなくなっている。たぶんこの文章もわかりにくいと思う。ちょっと休憩しようと思うのだけれど、そのためにもこの文章を一旦仕上げなければならなかった。とりあえず仕上げた。読みにくかったらすんません。
1回でもサポートしてくれれば「ホモ・ネーモはワシが育てた」って言っていいよ!
