
ひねくれ者、食いしん坊、太っ腹 横須賀俊司と私の大学時代
大学時代の友人で、県立広島大学准教授だった横須賀俊司が、一昨年の10月に肺ガンで亡くなった。享年58。中学時代にプール事故で頸椎を損傷し、重度障害者となった。頸椎とは背骨の最上部にある、いわゆる首の骨である。発話、飲食、筆記はできるが、移動・入浴、排泄には介護者が必要だった。大学卒業後は、大学院で社会福祉を専攻し、鳥取大学や上述の大学に勤めた。故人を偲ぶ書籍に、私も寄稿したので加筆し、転載する。
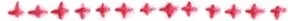
1983年に関西学院大学(兵庫県西宮市、以下「関学」)に入学した私は、ある先輩に誘われ、重度障害者の介護に通うようになった。「介護」という言葉は、現在では「介助」に変わりつつあるが、ここでは当時つかわれていた言葉をそのまま採用する。
介護先の障害者が、泣く子も黙る、脳性まひ者の運動団体「兵庫青い芝の会」の会員だった。彼らは親元や施設ではなく、アパートで生活を送っていた自立障害者の走りである。兵庫青い芝の歩みについて、私は出会いから四半世紀後に、『カニは横に歩く 自立障害者たちの半世紀』(講談社、2010年)を上梓する。
自立障害者の介護の主戦力は、私たち大学生だった。ヘルパー派遣などの福祉制度が始まる、はるか前の話である。
介護先の青い芝の会員から「関学に重度障害者がおるから、いっぺん会うたってくれへんか」と言われて横須賀俊司に会った…という話を彼の通夜で会った、私を介護にいざなった先輩に聞いた。
ともあれ私がキャンパスで横須賀と初めて会ったのは、3回生だったと記憶する。スポーツ刈りに、ジャージ・ズボンの超ダサダサの男が、手動式の車いすに座っていた。読売巨人軍の原辰徳選手(現監督)によく似ているなあと思った。その後、車いすテニスの第一人者・国枝慎吾が現れ、原辰徳にとってかわる(私の頭の中で)。
話してみると、私と同年齢・同学年で、さっぱりした性格だった。たちまち親しくなり、何でもあけすけに語り合うようになった。
中学時代のプール事故で受傷したことを尋ねたことがある。
「事故の時のことを思い出して、あれこれ思い悩むことあるの?」
「別に。そんなんでいちいち悩んでてもしょうがないやろ」
虚勢を張っている風でもなかった。
あっさりした性格ではあったが、ひねくれ者でもあった。人の悪口を言うのが大好き。「変な顔」「変な髪型」など思ったことをすぐに口にする。障害者の置かれた状況からの非社会性ではなく、もともと性格が悪いのだ、と私は解釈していた。
私は青い芝の会員の介護に入ってから障害者問題に俄然関心を持ち、横須賀と知り合ったころに、仲間とともに開店休業状態だった「障害者」解放研究部(「障」解研)を再建した。
いや、横須賀がいたから「障」解研を始めたのかもしれない。もちろん、彼も部員に名を連ねた。現在は日本の障害者運動を牽引する、DPI(Disabled People's International)日本会議事務局長を務める佐藤聡は、クラブの後輩である。佐藤は横須賀を呼び捨てにし続けた。両者とも鷹揚なのか鈍感なのか、よくわからない。
私たち「障」解研のメンバーは、視覚や聴覚に障害をもつ学生に会って「何か困ったことはないですか?」と御用聞きよろしく接近したが、あまり信用されていなかったようで、ほとんど彼ら彼女らの役には立てなかった。
私の編集で、「障」解研メンバー&シンパによる雑文集『ファイト!』を88年につくった。60㌻足らずの小冊子である。横須賀は「Y君のちょっとHなお話」を寄稿した。受傷後の性に関するエッセイで、彼が書き残したものの中で、一番おもしろい文章だと私は思っている。
「あれを超えるものをはよ書けよ」
彼と会うたびにハッパをかけたものである。
「お前は以前は健全者だったんやから、中途障害者学というジャンルを始めたらどうや。お前ならできるやろ」
障害学というジャンルはあったが、先天性と中途障害では、いろいろ違うはずである。その一端をあらわしたのが「Y君の…」だった。それを言い続けのだたが、その気配はなかった。
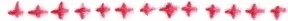
私が横須賀と知り合ったころは、通学に1時間ほどかかる団地に、タクシー運転手の父親とふたりで住んでいた。父親が介護していたようだ。私も通学の介護者として、何度か家を訪れたことがある。
団地の通路から呼びかけ、鍵のかかっていない窓を開けると、彼が棒にぶらさげた鍵をつきだす。それを受け取り、中に入る。部屋のベランダからは、西宮の海が見渡せた。素晴らしい光景だった。
だが、車いすかベッドにしか定位置がなかった彼には、その景色は見えない。抱え上げて見せるほどの優しさが、当時の私にはなかった。
その後、横須賀は大学が所有する学生寮に入寮し、いよいよ自立生活をスタートさせる。これも知り合って、すぐだったと記憶する。その意味では兵庫青い芝との縁が、在宅障害者であった彼の人生を一変させたと言える。
昼間は学内にいる学生が移動などを手伝い、夜に交代で介護者を入れて、入浴・着替え・ベッド移動・排便などを担った。もちろん私もそのひとりである。
「お前は介護要請したら、嫌な顔をする。あかんで、それは」
感情がすぐ顔に出る私の本性を彼は見抜いていた。
介護者がいなければ生活が成り立たないこともあって、彼の交友関係は一挙に広がった。30~50人は介護要員がいたのではないだろうか。そのほとんどが介護経験のない初心者だった。
「人間の体の仕組みって、ああなってるんやなあって思った」
初めての介護体験をそう表現した友人がいた。まるで献体された遺体を見る医学生ではないか。青い芝の会員の介護に誘っても来なかったが、横須賀にだけ心を許した(?)知り合いもいる。放っておけないと思ったのか、それとも彼に魅力があったのか。
「障害者は食うことだけが楽しみなんや!」
口癖のように、横須賀はそう言っていた。お前がそうなだけで、障害者みんながそうではないやろと思っていたが、障害年金という ” 定収入 ” があり、よく奢ってもらっていた私は、それを口には出せなかった。服装こそダサかったが(私も言えない)、飲食に関しては、財布のひもはゆるかった。また、気前もよかった。
父親の趣味が釣りで、幼いころから新鮮な魚を食べつけていたと話してくれたことがある。確かに食通ではあった。寮のキッチンで、よくパスタを介護者に作らせていた。沸騰した湯にパスタがからまないよう放射状に入れると「お、料理を知ってるな」と褒めた。調理にも割合うるさかった。
たまたま寮の近くに下宿していた私は、介護の日でもないのに横須賀の部屋を頻繁に訪れ、一緒に酒を飲んでは介護者とともに夜更けまで話しこんだりした。彼はビール党で、そのころはけっこう飲めた。
部屋にあるテレビでは、三菱電機がスポンサーのロック特集を組んでいた。「ポリス」や「マドンナ」が出演していて、加古川の田舎で育った私を刺激した。
「マドンナって、本名なんやで」
横須賀が少し自慢げに教えてくれたものである。
「おい、シンクロニシティって、どういう意味や?」
ポリスのアルバム名の和訳を突然聞かれたことがある。偶然に別の場所で同じことが起きる「共時性」を意味するユング提唱の心理学用語で、そんな難易度の高い英単語を私が知るわけがない。
「パラダイムって何や?」
やはり、突然聞いてくる。
「その業界で常識とされている思考の範囲やがな」
おおざっぱな説明に納得せず、何度も聞かれたおぼえがある。
寮には日替わりで介護者が来るので、私の交友関係も広がった。ときには学外の障害者が訪れてくることもあった。ミスタードーナツの奨学生としてアメリカに留学していた同志社大学の山下君は、いまどうしているのだろうか。
数年前に肺がんに罹患し、病院から自宅療養へと切り替えた当初は、毎日のように知人が彼を訪ねてきた。横須賀を軸にして人が集う。その場にいながら私は、30年以上前の寮にあった、にぎやかな横須賀部屋を思い出していた。
「障」解研の雑文集『ファイト!』で寄稿したように、彼は障害者と性の問題に早くから関心を持っていた。アメリカの障害者がどのようにセックスをしているか、実演入りのビデオを所持していた。米国・バークレーに視察か短期留学した際に入手したとか言っていた。まじめなビデオだったが、無修正だった。よく持ち込めたたなあと感心したものである。彼には役に立ったのだろうか。
ともに二十歳過ぎで、青春の真っ盛り。当時の横須賀は、恋愛に飢えていた。
「彼女ができたら、どんなつらいことでも耐えられる」
冗談交じりにそう嘯いていた。こと恋愛に関しては、障害者であることを過剰に意識していて「これを逃したら後がない」と言わんばかりに前のめりだった。障害者の自分と付き合ってくれる女性は少ないと思っていたようで、本人に確かめるとあっさり認めた。
どうしようもないほど惚れっぽく、相性が悪過ぎるやろというような女性を好きになっては、何度も門前払いされていた。例外的に付き合うことになった女性は、懐の深い人物ばかりである。この点においてのみ、彼と私は共通する。
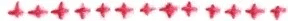
ともに4回生になり、そろそろ就職を考えなければならなくなった。80年代半ばは、バブル経済による好景気で、大学生は引く手あまただったが、障害者は例外である。とりわけ介護を必要とする重度障害者は。
学部時代、彼は法学部に所属していた。
「重度障害者は資格がないと生きていけないと思った」
彼の口からそう聞いたおぼえがある。司法試験でも目指すつもりだったのだろうか。アメフトの試合中の事故で受傷し、その後、税理士になった大学の先輩が頭にあったとも語っていた。いずれにしても、司法試験やその他の資格試験の準備はしていなかった。自分には向いていないと思ったのだろう。
当時は官公庁であっても重度障害者の採用はないに等しく、横須賀は母校である学校法人・関西学院の職員となることを目指した。母校愛があったわけではない。あくまでも消去法である。 ” 迷える子羊 ” の救いを、キリスト教精神をモットーとする学校法人・関西学院に賭けたのである。
ところが学校法人は、通勤・勤務中に介護を必要としないことが勤務条件だった。「障」解研を中心に「横須賀君の就職を実現する会」(実現する会)を結成し、当局と何度も交渉したが、条件は変わらなかった。
「そんな条件はおかしいやないか!受験するだけでもさせたってくれや!」
二十歳前後の生意気なメンバーが、父親ほどの年齢の法人幹部に声を荒げる。
「あんたも障害者なら、横須賀の気持ちもわかるやろ!」
足に障害をもった祖父くらいの年齢の理事にも食い下がった。
団体交渉は当局の姿勢を頑なにさせ、打開を図ることはできなかった。マスコミ各社に手紙を書き、1社だけ取材に来てくれたのが、地元紙の神戸新聞だった。だが、なぜか記事にはならなかった。後年私は、同社に入社することになるのだが、そのころは想像もしていない。
もう1年就労闘争を続けることになり、彼も私も留年した。だが、その翌年も条件は変わらず、受験さえできなかった。仮に受験できたとしても、その性格の悪さから面接では落とされるのではないかと、実現する会のメンバーはささやきあった。
大学の職員になる道を諦め、彼は社会学部の大学院で社会福祉を学ぶことにした。無事に合格し、実現する会は解散した。研究者への方向転換が、消去法なのかどうか、私は確認していない。それしか進むべき道がなかったのではないかと今になって思う。
大学院を修了後は、大阪・和泉市の社会福祉専門学校の専任講師、鳥取大学助教授、そして県立広島大学の准教授を務めた。
「横須賀の就職が、鳥取大学に決まりました」
たまたま飲み屋で会った関学社会学部のK教授に報告したことがあった。私は社会学部の出身である。
「そうか、よかったな」
K教授はそう言って喜んでくれた。実は鳥取大学への就職は、このK教授の尽力によるものであることを後に知った。かなり恥ずかしい話である。
鳥取大就任1年目だかに、仲間とともに彼を訪れたことがあった。山陰地方は魚は美味いが彼には合わなかったようで、関西に帰りたがっていた。
和泉、鳥取、広島、西宮と住所が変わるたびに、私は彼の自宅を訪れた。どんな生活を送っているのか、気になった。転居先のどこへ行っても教え子が訪ねてきていた。意外と面倒見がよく、慕われていたようだ。
大学の職員にはなれず教員になったが、そのほうがよかったのではないかと思わないでもない。
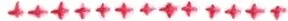
晩年に西宮の自宅での闘病中、何度か見舞いに行った。ずいぶん前から鬱病を患い、何を言っても反応は薄かったが、「むかし親友やったなあ」と言ったときだけ、顔の表情が少しだけゆるんだ。最後に見せた笑顔だった。
ひねくれ者で、食いしん坊で、太っ腹で、恋多き男は、まごうかたなき私の親友だった。<2023・5・29>
彼の業績や横顔を紹介した『「横須賀俊司」という生き方 自立を目指して闘った研究者からのメッセージ』は以下☟
https://www.amazon.co.jp/%E3%80%8C%E6%A8%AA%E9%A0%88%E8%B3%80%E4%BF%8A%E5%8F%B8%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E7%94%9F%E3%81%8D%E6%96%B9-%E8%87%AA%E7%AB%8B%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%97%E3%81%A6%E9%97%98%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%A0%94%E7%A9%B6%E8%80%85%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8-%E6%A8%AA%E9%A0%88%E8%B3%80%E4%BF%8A%E5%8F%B8%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E7%B7%A8%E9%9B%86%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A-%E6%AD%A6%E7%94%B0%E4%B8%88%EF%BC%88%E4%BB%A3%E8%A1%A8%EF%BC%89/dp/B0BZ6KFBMR
あなたのサポートによって愛犬ももじろうのおやつがグレードアップします。よろしくお願いします。
