
ハラハラヒリヒリ 東京&千葉、最高のメニュー
伊丹空港は快晴だったが、羽田は小雨が降っていた。晴天が大好物な私は、雨が降ると気分が落ち込む。幸先はよくない。
11月中旬に、浄土宗の東京教区で人権問題の研修があり、私が部落問題について話をした。会場は安倍元首相の葬儀がとりおこなわれた、あの増上寺である。
さすがに東の総本山だけあって、何もかもが立派だった。背後の東京タワーが、仏像の後背に見える。
研修の担当者から事前に「できれば食のお話なども交えて…」という要望があった。食の話? 珍しい注文である。研修後の懇親会がホルモン焼屋でおこなわれることを知るに至って、鈍感な私もようやく気がついた。担当者は拙著『ホルモン奉行』(解放出版社、2003年)を読んでおられるに違いない…。
同書は被差別部落を中心に、国内外でホルモンがどのように食べられているかをルポした奇書である(自分で言うか)。
私は考えた。部落の食文化について話をするだけでは、面白くない。実際に口にしてもらおう。被差別部落で作られ食べられている、馬肉の燻製・サイボシの最高級品を大阪で買い求め、会場入りした。

とはいえ、不安もあった。以前に講演や研修で、部落の食文化を楽しむというコーナーをもうけていたが、コロナ・ウィルスが蔓延してからは控えていた。社会全体が飲食にナーバスになっていたので、とても食べ物を提供する雰囲気ではない。現在は、以前に比べてゆるくなったとはいえ、安心はできない。
控室で主催者が用意した昼食の弁当をいただいた。蓋を開けると全体に茶色っぽく、精進料理のようである。東京だけあって、関西人には味が濃い。かろうじて鶏肉を見つけ、精進料理ではないことを確認する。これが本当の精進料理だと、馬肉を提供することにますます不安がつのるではないか。
そもそも研修会場で、飲食はオッケーなのだろうか。担当者に事前に問い合わせて「NO」であれば計画は遂行できないので、敢えて聞かなかった。
会場を覗くと、僧衣をまとった怖そうな僧侶ばかりである。空気がピンと張りつめている。ハラハラ、ドキドキ、妙な胸騒ぎがする。
さて、本番である。部落問題には差別が付きものであるが、そればかり言いつのるだけでは展望がない。さまざまな文化もあるんですよ、と前置きした上で、サイボシを取り出し、包丁で一口大に切った。体温測定、マスク着用、手の消毒…現代科学の粋を極めたコロナ対策は万全だ。
会場がザワザワし始める。
「しょうがと醤油をかけると美味しいんです」
しょうがを擦り、小分けしたサイボシにしぼり汁をかける。醤油も忘れずに。食材はもとより調理器具、調味料は持参してきている。会場はどよめき、沸きに沸いた。中には拍手喝采する僧侶も。めっちゃ、受けてるやんか…。
あとで聞くと、会場は結婚式の披露宴にも使われているとのことで、飲食は何の問題もなかった。なんだ、そうだったのか…。拍子抜けした。
このサイボシの試食は、部落問題理解の伏線になっていて、最後に回収されるのだが、それは見てのお楽しみである。
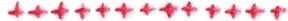
研修が終わり、打ち上げが増上寺から徒歩10分余りのホルモン焼き屋で開かれた。「ホルモン焼」の文字が染め抜かれた暖簾をくぐると、まさに夢舞台。くすんだ板壁、ずらりと貼られた短冊メニュー…。これぞ、ホルモン焼き屋!というたたずまいだった。
ハラミ、軟骨、ハツ、カシラ。豚の内臓の新鮮なこと。これを炭火でじっくり焼き、朱色の辛いタレにつけて食べる。
大阪では焼肉といえば牛肉。豚のそれを口にすることはめったにない。なのでこの日は、2年分くらいを腹におさめた。ごちそうさんです!
店主によると、芝浦の屠場から仕入れているとのこと。それは美味いはずですわ。
店は研修会の参加者の貸し切りで、私以外は全員が、剃髪 or 坊主頭だった。別の星に来たような感覚に襲われ、私にしては珍しく、スマホで写真を撮った。地球最後の日に見るつもりだ。
打ち上げは午後6時にスタートし、河岸を何度も変え、日付を超えて午前3時ごろに終了した。浄土宗の僧侶は、こんなに解放されているのかと思った。
研修の担当者には、最後まで付き合っていただいた。じっくり会話してわかったことなのだが、私とほぼ同年代の彼は、やはり『ホルモン奉行』を読んでおられた。そしてかつてはNHKで『きょうの料理』を担当していたスタッフだった! そりゃ料理に興味を持ってもおかしくない。最初に言うてよ~。

翌日は、千葉県銚子市内のカトリック教会にお邪魔する。こちらの神父が、浄土宗の研修にも参加され、私とは旧知の飲み友である。
風光明媚な当地を車で案内してもらい、太平洋が見渡せる温泉につかる。極楽ではないか。夜は神父いきつけの居酒屋で、刺身を堪能する。キンメダイ、生ガキ、ボタンエビ、ヒラメ…。どれも美味だった。アジのなめろうも。アジフライがメニューからすぐに消え、早く注文しておくべきだったと後悔する。
が、最高のごちそうは、実は神父の話だった。下ネタから宗教の話までできる人は、そうはいない。
「神父、そんなこと言うてたら、地獄に堕ちますよ!」
私がたしなめると、
「いえ、私たちは死んだら、例外なく天国に召されるのです」
神父が平然と答える。
フィリピンパブに通い詰めたという話も、あとになって考えると、カソリック教徒が多いフィリピン人との接触・交流が目的だったのかもしれない。すっかり偽悪者に騙されるところだった。
時間を忘れて深酒になる前に、長距離バスで東京にたどりつく。

翌日、国会図書館で、昔の新聞紙面をマイクロフィルムで検索する。国会図書館の検索機器が、とても扱いやすい。たとえば神戸市立中央図書館のそれは、コントロールが難しく、画面が早く行きすぎたり、逆に遅すぎたりして検索するのに往生する。さすがは国立である。首都である。しかも機械が、ピカピカの金色だ。
館内の食堂の入口に、この日のランチの実物が陳列してあった。前夜に食べそびれたアジフライの定食ではないか。値段は670円とお手頃。かなり惹かれたが、昼食は決めている。
上京した際に、必ず食べたくなるメニューがある。地下鉄・曙橋駅(新宿区)近くにある香港料理店。メニューの中に、四川料理の一品がある。豚バラの煮込みなのだが、これが辛くて辛くて…。ただ辛いだけではなく、うまみがあって、また行きたくなるのだ。何度行ったことか。
さっそくいつもの「水煮肉片」(1000円)を注文する。白い鍋に、真っ赤な具と汁が映える。真っ先に目に飛び込む豚バラは上質で、味わいがある。その下にはキャベツ、もやし、タケノコ、マッシュルームがどっさり控えている。
けっこうな量で、食べ進むうちに、もうすぐ冬本番というのに、体から汗が噴き出てくる。ふんだんに香辛料を使っているからか、鼻水も頻繁にお出ましになる。
店員に聞くとチェーン店ではないという。厨房の料理人を見る限り、中国人の料理人だと思う。ごちそうさまでした。また来ま~す。
ところが…。店を出て30分を過ぎたころ、口の中に違和感が。猛烈に化学調味料の味が舌の根を刺激しだした。私はこれが苦手である。私の場合、時間が経って、こいつが襲ってくる。
これまで何度もあの店で同じ料理を口にしてきたが、こんなことはなかった。私の化学調味料嫌いは、かなり前からである。ということは最近になって投入しだしたのだろうか?
真実はわからないが、もう行くことはないだろう。別にそれを入れなくても十分に味で勝負できると思うんだけどなぁ(ため息)。さようなら、曙橋。

東京3日目の昼に、編集者と会う約束をしていた。編集の現場を離れて久しいエラい人なのだが、私の中ではいまだに編集者なのでそう記す。別の用件で連絡を取り合ううち、近く上京することを伝え、昼食に付き合ってもらうことになった。
ここ数年は、同世代の友人をはじめ、身近に思う人が亡くなったり、病にかかったりしている。加えて私も還暦をひかえ、体力気力の衰えを自覚し、死を身近に感じるようになった。なので自分にとってかけがえのない人に、積極的に会うようにしている。緩慢なお別れである。
水道橋駅近くの東京ドームホテルのロビーで待ち合わせをする。合流後、近くの中国料理店へ。当初は編集者とふたりで会食するつもりが、もうひとり加わった。というのも…。
前の日の夜に、在京の新聞記者と、私が投宿する水道橋のホテル近くの居酒屋で飲んだ。記者歴10年を超えた中堅だが、私から見れば青年である。
店は彼が事前に調べてくれていたのだと思う。刺身が美味い店で、値段も手頃。炙りしめサバが半身(15㌢くらい)で700円だった。ふつうは4~5切れ入っているだけである。
青年記者は、以前、大阪の自宅で取材してくれたことがあった。わざわざ遠方から来られたので、取材終わりに自宅で簡易居酒屋を開いて小宴会を持った。コロナが私を居酒屋店主に仕立てたのである。
その後、私のインタビュー記事とは別に、自分が書いたそれを送ってくれたりした。そんな記者はいないので、上京する前に私が声をかけたのである。
炙りしめサバが美味い店で、どんな話の流れかは忘れたが、ノンフィクション作家の故・本田靖春(1933-2004)の話になった。
「明日、本田さんが一番信頼していた編集者と会うけど、来る?」
酔った勢いで軽い気持ちで誘うと、是非行きたいと言う。
そういうわけで、翌日は3人の会食になった。もちろん、事前に編集者には話をし、快諾は得ていた。

テーブルにつき、私は「牛脊麻辣麺・牛リブロースを使った山椒辛味麺・Spicy Noodle with Spencer Roll」(2300円)を頼んだ。値段はもとより、中国語、日本語、英語でメニューが書かれているだけで、高級店であることがわかるではないか。
中国語では「麻」は舌がしびれる、「辣」は舌がヒリヒリする、という意味がある。やばいよ、やばいよ…。
看板に偽りはなかった。まさに舌がしびれる辛さ。これやがな、これ! もちろん、ただ辛いだけではない。ほのかな甘味、酸味が合わさって、辛味を引き立てている。牛リブロースのやわらいこと、絹のごとし。曙橋は卒業し、水道橋への入学を検討することにした。
編集者がおもむろに鞄から『文藝別冊 本田靖春』(河出書房新社、2010年)を取り出し、青年記者に渡そうとした。
本田亡き後に刊行されたムック本で、足立倫行、野村進、斎藤貴男、筑紫哲也ら錚々たるライターが寄稿している。ちなみにこのムック本、河出にいた編集者時代の武田砂鉄の手による名著である。
そのムック本に、編集者がひとりだけ寄稿している。鞄から取り出した、その人である。
「あ、それ、持ってます」
青年記者はそう言いながら、鞄から同じ物を取り出した。なかなか面白い展開ではないか。青年は、本田の最後の著書『我、拗ね者として生涯を閉ず』(講談社、2005年)の文庫本も持ってきていた。
同書も、目前の編集者が「編集付記」を書いている。青年記者は、前の晩も編集者が書いた原稿を読み返したらしい。
青年は亡くなってから本田の本を読み始め、少なくない著作のほとんどを読破しているという。また『警察回り』(新潮社、1986年)を読んで、新聞記者になることを決心したとか(『我、拗ね者』と『警察回り』は、私の本田本ベストスリーに入る名著だ)。
亡き本田に会うことはできないが、彼が一番信頼を置いていた編集者にまみえることができたのは嬉しかったにちがいない(編集者と別れ、ふたりきりになったとき「めっちゃ緊張しました」と言っていた)。
「ムック本は、本田夫人のインタビューがよかったですね」
私が言うと、本田の競馬狂いの話になった。編集者が腕時計を指しながら口を開いた。
「これは奥さんに形見としていただいたものなんですが、『高価な時計でもないのに、これも本田が何度質屋に入れたかわかりません』とおっしゃってましたね」
文筆家としては一流だが、生活人としては「?」が付くところが可笑しかった。後者だけは、私と共通する。
腕時計を見ると、確かに高価なものではなかった。だが、亡くなって20年近くが経って、いまだに肌身離さず付けている編集者がいるのも凄いと思った。それだけの磁力を持つ書き手だった。
だからこそ死後も長らく読まれ、若者をジャーナリストへの道へと誘う着火剤であり続けたのだ。私の腕時計を、誰が付けたいと思うだろう(卑屈になるな)。
山椒辛味麺を口にしながら、あるいは食後のコーヒーを嗜みながら、本田作品のあれこれを語り合った。私の舌と脳はヒリヒリし、しばらくその興奮は冷めやらなかった。
銚子の居酒屋の最高メニューは、神父との対話だったが、この日のそれは本田靖春だったのかもしれない。<2020・11・30>
あなたのサポートによって愛犬ももじろうのおやつがグレードアップします。よろしくお願いします。
