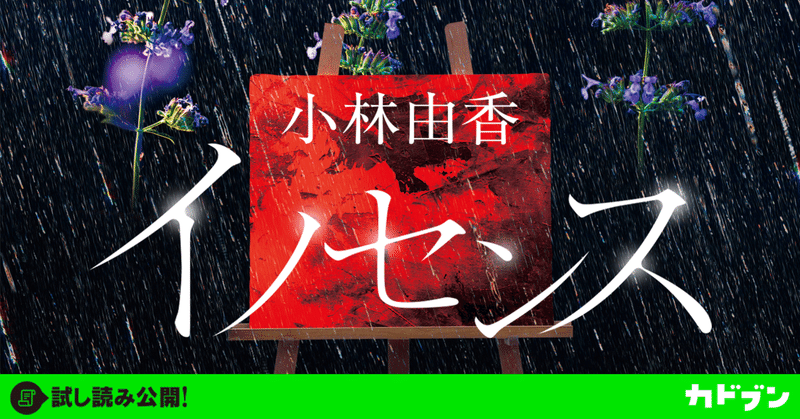
ネットで拡散する少年への誹謗中傷。高校名や顔写真まで晒されて――/小林由香『イノセンス』発売前特別試し読み#2
連載中から賛否両論の嵐。
小林由香『イノセンス』期間限定「ほぼ全文試し読み!」
カドブンノベル一挙掲載、WEB文芸マガジン「カドブン」で連載中から大きな反響を読んでいる話題作『イノセンス』。
10月1日の発売に先駆けて、このたびnote上でほぼ全文試し読みを行います。
あなたは、主人公の取った行動は許されると思いますか?
2020年最大の問題作をお見逃しなく!
2
大学の正門に着いた頃には、すでに小雨が降っていた。
星吾は乱れた呼吸を整えながら、敷地内の遊歩道を足早に進んでいく。駅から走ってきたせいで、折りたたみ傘を広げるのも面倒なほど、ぐったり疲れ切っていた。ホームで転倒したときにできた腕の傷が雨に濡れ、痛みがぶり返してくる。
微かに苛立ちを覚えながら中庭に目を向けると、背の高い時計台は二限目のドイツ語に二十分ほど遅刻してしまったことを示していた。
ドイツ語の教授は、試験よりも出席率を重視する。電車の遅延が原因だったとしても、「遅れるのを予見し、もっと早く来ればいい」と嫌みを言う人だった。だから遅延証明書を提出しても出席にしてくれるかどうか不安になってしまう。
電車が遅れたのは、乗客が線路に物を落とし、係員が拾い上げるのに思いのほか時間がかかったからだ。結局、色白の男が飛び込まなくても遅れる運命だったのだ。
運の悪さはどこまでも続いているようで気が滅入ってくる。
ドイツ語の講義が終わってから、星吾は学食で昼食を済ませた。
スマホで大学のサイトを確認してみると、三限目の講義が休講になっていたので、時間をつぶすために別棟にある美術室に向かった。入学したての頃は空き時間のたびにどこに行こうか迷ったが、二年になると行く場所はおのずと定まってくる。
講義がすでに始まっていたせいか、B棟のエントランスは閑散としていた。周囲に目を走らせてみても、学生の姿はどこにも見当たらない。人気のない構内は、妙に心が安らぐ。
エントランスの右側にはエレベーターが一基設置されていた。
美術室は四階。星吾は乗降用ボタンを押し、エレベーターが降りてくるのを待っていると、廊下の先に黒い人影が見えた。
漠然とした不安が波紋のように胸に広がっていく。
一瞬見えた人影は、駅のホームで会った女に似ていたのだ。
同一人物かどうか確認したいという衝動に駆られた。人影が見えた場所まで駆けていくと、階段をのぼる白い足が目に飛び込んでくる。
黒いワンピース姿の女は靴音を鳴らし、どんどん上階へ駆け上がっていった。
星吾はできるだけ足音を忍ばせ、あとを追いかけた。
汗でシャツが背中に張りつく嫌な感覚がする。息を切らしながら上がると、三階に続く階段に人の気配はなかったので、壁に隠れるようにして二階の廊下の様子を窺った。けれど、そこには誰の姿もなく、ひっそりと長い廊下が左右に延びているだけだった。
もし駅で会った女と同一人物なら、同じ大学の学生だったのかもしれない。
波立っていた心が鎮まると、今度は奇妙な感覚に囚われた。
たしかに女の姿を見たはずなのに、現実感に乏しく夢を見ていたような気分になり、幻覚や幻聴だったのではないかと思えてくる。
あの事件以来、記憶はいつも曖昧で、はっきり思い起こせないことが多くなった。
右腕の傷が疼くと、連動するように頭が痛くなる。こめかみを指で押さえ、緩慢な足取りで四階まで上がり廊下に出た。
美術室は廊下の突き当りにあった。
学生に人気のない寂れた美術サークルに所属しているのは三人。そのひとりが星吾だった。他の学生と関わるのは苦手だったので、サークルに入るつもりはなかったが、顧問の宇佐美弦太に強く頼まれ、入会することにしたのだ。
宇佐美はこの大学の准教授で、教育学部の美術専攻の学生たちに専門科目を教えている。作品制作をするアトリエや工房室は別棟にあるため、B棟の美術室は部員しか使用していなかった。
美術サークルの三年は就職活動、四年は卒論に忙しいらしく、サークルにはほとんど顔をださない。もともと先輩たちは就活時の自己PRのためにだけ籍を置いているので、実際に美術室を使用するのは星吾くらいだった。
幼稚園の頃、星吾は初めての集団生活に馴染めず泣いてばかりいたが、クレヨンや色鉛筆を持つと不思議と心が落ち着いた。特に嫌な出来事があった日は、絵を描きたくなる。夢中で描いていると、いつの間にか負の感情は消え去り、心が穏やかな気持ちで満たされていくのだ。まるで真っ白な画用紙が哀しみや不安を吸い取ってくれるようだった。
見慣れたベージュのドアを開けると、もわっとした熱気とラベンダーの香りが鼻孔をくすぐった。室内はうんざりするほど蒸し暑くてたまらない。
星吾は美術室に入ると、すぐに足を止めた。
なにか違和感を覚えたのだ。けれど、首を巡らせて教室を見回してみるも、違和感の源がどこにあるのかわからなかった。
机と椅子は後方に押しやられ、前方には広いスペースが作られている。スペースの中央には、いつもと変わらず、画板を載せたイーゼルが置いてあった。画板には、上部をダブルクリップで留めた画用紙がついている。
教卓の上には、デッサンのモチーフにしているドライフラワーのラベンダーが白い陶器の花瓶に飾られていた。教卓の近くには腰くらいまである棚があり、その上には両腕のない上半身裸の女性の石膏像が置いてある。
冷静に確認すると、すべてが見慣れた光景だった。
額の汗を手で拭いながら窓際まで歩いた。鍵を外し、大きな窓ガラスを両手で開ける。目の前にあるクスノキがさわさわと揺れ、心地いい風が室内に流れ込んでくる。涼やかな光景を眺めていると、ゆっくり汗が引いていくのを感じた。
教室にはエアコンが設置されていたが、ずいぶん前から故障中で使い物にならなかった。経費が足りないのか、そもそも修理する気がないのか、事務局に頼んでいるのになんの連絡もなかった。美術サークルは、大学に貢献できるような結果を残していないのが原因かもしれない。
星吾はイーゼルの前まで足を運び、椅子に腰を下ろそうとして動きを止めた。
ガタン、と音を立てて飛び退くようにイーゼルから遠のき、デッサン画を凝視した。
引いたはずの汗がまた噴きだし、呼吸が少し速まっていく。
画用紙に血痕のようなものが飛び散っていたのだ。
鉛筆で描かれているラベンダーのデッサン画。それを汚すように赤い染みが滲んでいる。
ゆっくり周囲に目を走らせた。
きっと、水彩絵具だろう。赤色の絵具をたっぷりの水で溶き、それを絵筆につけて飛ばした形跡があった。よく見ると床にも少しだけ赤い染みが点々とついている。
文庫本の真紅の文字が一瞬、網膜に浮かぶ。
頭では絵具だと認識しているのに、強い息苦しさを覚えた。
浅い呼吸を繰り返す。赤い光が揺らめき、不吉な予感に苛まれた。
2月9日月野木――。
なにか胸騒ぎがする。ただの嫌がらせではなく、あの警告文はもっと重要ななにかを伝えようとしているのかもしれない。すぐにスマホを取りだし、文末に記されていた暗号めいた言葉を検索する。指が強張り、うまくタップできなかった。
検索結果の上位に『月野木』という苗字の人物や会社名などがヒットした。
暗号ではなく、誰かの苗字?
指でスクロールすると、ページの下のほうに交通事故の記事が見つかった。国道で起きた事故のようだ。
去年の二月九日の夕方、直進していた軽乗用車と対向車線から右折しようとした大型バイクが衝突する事故があったようだ。運転していたバイクが転倒し、名古屋市のアルバイト従業員、月野木礼司という二十歳の男が上半身を強く打って死亡したという。軽乗用車を運転していた六十歳の女性は軽傷で済んだようだ。
心拍数が急速に上がっていくのを感じながらも、検索する指を止められなかった。
震える指で『月野木礼司』という名前を入力していく。
スマホの画面に『ヒーロー殺害事件』というタイトルがずらりと並んでいた。
思考が空回りして、現実を受け入れられない。
これまでも自分の名前を入力してエゴサーチしたことは何度もあったが、氷室を殺害した加害者について調べたのは初めてだった。あの事件から遠ざかりたくて、ずっと避けてきたのだ。
当時、加害者たちは未成年のため、新聞の記事では名前は伏せられていた。けれど、ネット上では晒されている。
加害者たちの名前を目にしたとき、はっと息を呑んだ。文字がぐらぐら揺れている。スマホを持つ手が震えていることに気づいた。
実刑が言い渡されたのは、当時十九歳の川口三弥、冴島翔哉のふたり。少年院送致になったのは、当時十七歳の月野木礼司――。
あるサイトには、犯人たちの小学生くらいのときの写真が掲載されている。純朴そうな少年の顔からは、殺人に手を染めるような凶暴さは微塵も感じられなかった。
必死に嫌な記憶を呼び起こし、氷室を襲った加害者たちと写真の少年を重ねてみるも、まったくの別人に見える。
アパートのベランダに文庫本を投げ入れたのは、氷室に近しい人間なのだろうか――。
あの事件の加害者に天罰が下ったことを伝えたかったのかもしれない。
星吾は赤く汚されたデッサン画に視線を移した。
美術室に忍び込み、嫌がらせをしたのは大学の関係者かもしれない。氷室の事件のことを耳にした学生の誰かの仕業だろうか――。
静かな教室に、不吉な予感が満ちていく。
頭を目まぐるしく回転させ、想像を膨らませてみても憶測の域をでなかった。
月野木は交通事故で亡くなったはずなのに、誰かに仕組まれたように思えて恐ろしくなる。
日本の警察は優秀だ。事故に見せかけて殺害するのは簡単ではない。そう自分に言い聞かせても、不安を完全に払拭することはできなかった。
汗ばんでいる手で、残りのふたりの加害者の名前を検索する。
主犯の川口三弥は懲役九年、冴島翔哉は懲役五年の実刑判決が言い渡されていた。
事件から四年八ヵ月が経過していることを考慮すると、彼らはまだ刑務所にいるはずだ。
すぐに『仮釈放』について調べてみた。
その結果に頬をぶたれたような衝撃を受けた。
有期刑の場合は、受刑態度が良好な場合、判決で言い渡された刑期の三分の二を経過すれば、仮釈放が認められることがあるようだ。
こんなにも短い刑期で社会に戻ってこられるという事実に怒りを覚えた。
川口三弥は、六年以上経たなければ仮釈放は無理だ。けれど、冴島翔哉はすでに出所している可能性がある。
次に『冴島翔哉』と入力してみたが、氷室の事件以外の記事は見当たらなかった。刑務所から出所しているかどうかさえわからない。
星吾は顔を上げると、教卓のラベンダーを凝視した。
胸の鼓動がまた俄に騒ぎだす。
先ほど覚えた違和感の原因に気づき、教卓まで足早に向かった。
花瓶に入っているラベンダーの形がおかしい。デッサンのときにずっと眺めていたから気づいたのだ。小さな花が茎の先に集まって咲いていたのに、一部だけ花がなくなっているところがある。花瓶の位置も少しだけずれている気がした。
ゆっくり視線を落とすと、青紫の花が教卓の下に少しだけ散らばっている。まるで誰かが花を握りつぶし、床にばらまいたようだ。
窓から風が吹き込み、カーテンがなにかを包み込むように揺れた。人が隠れているような気がして、腕にぞわっと鳥肌が立った。ただの嫌がらせではなく、得体の知れないなにかが動きだしている予感がする。
またネット上に名前を晒され、悪意のある書き込みをされているのだろうか――。
スマホでエゴサーチしてみたが、星吾の個人情報は書き込まれていないようだった。
氷室の事件後、心に傷を抱えてはいたものの、高校に進学してからは仲のいい友人もできて普通の学校生活を送れるようになった。
けれど、そんな平穏な日々は長くは続かなかった。
高校二年のとき、自宅にいたずら電話が頻繁にかかってくるようになったのだ。〈音海星吾死ね〉〈お前も同じように刺されろ〉〈卑怯者〉〈この世から消えろ〉すべてあの事件に関係する内容だった。
家族のみんなが困惑している最中、家のチャイムが鳴り、母が恐る恐る玄関のドアを開けると、そこには週刊誌の記者が立っていた。パニックになった母が、なぜうちの子を調べているのか、と尋ねると、記者は淡々とネットの情報を教えてくれた。
ネットの匿名掲示板に『氷室慶一郎を見殺しにした少年GKの名は、音海星吾』と書かれていたようだ。それだけではなく、星吾の通学している高校名や顔写真も晒されていた。
その日のうちに母は警察署に赴き、事情を説明した。
警察はネットでの誹謗中傷などの対応には消極的だと聞いていたが、個人情報が晒されていたため、すぐに捜査に動いてくれた。プロバイダーに情報を提出させ、掲示板の運営サイトにも連絡し、懸命に削除を行ってくれたが、しばらくすると今度は匿名のブログに個人情報を晒された。
母は高校の担任に相談に行き、「息子を守ってほしい」と頭を下げた。
クラスメイトたちの間でも噂になっていたのだ。しばらくは問題なく学校生活を送ることができたが、裏の世界では密かに悪意が充満していた。
ネットに掲載された写真のひとつは、クラスメイトの小笠原しか持っていないものだったのだ。星吾が問い詰めると、小笠原は「ごめん。無料のアプリをインストールしたときにウイルスに感染して画像を盗まれたんじゃないかな」と半笑いで謝ってきた。それが事実なのか、それとも悪意があって載せたのか判然としない。いつも快活な小笠原はクラスの人気者。証拠もないのに相手を責めれば、クラスメイトたちから非難される。それ以上の追及はできなかった。
なによりも辛かったのは、ネット上に家族の個人情報まで晒されたことだ。
その頃、精神的に追い込まれた星吾は不可思議な怪異現象を目にするようになり、祖父に付き添われて心療内科に通うようになっていた。
一瞬だが、鏡や電車の窓に死んだはずの氷室の幻影があらわれるようになったのだ。薄暗い雨の日に起きることが多かった。通学途中、亡者を目にするたび大声を上げてしまい、車内にいる乗客たちから不審の目で見られ、日常生活をうまく送れなくなっていた。
心療内科の医師は、不安になっている星吾に、『輪郭誘導現象』について教えてくれた。
人間は三つある黒い染みを見ただけで、誰かの顔だと認識してしまうことがあるそうだ。天井の木目が人の顔に見えることもあり、すべては脳の錯覚によるものだという。
それから何回か心療内科に通ったあと、『心的外傷後ストレス障害』と診断され、週に一度通院してカウンセリングを受けることになった。
祖父は心療内科の帰り道、落ち込んでいる星吾にカフェオレを買ってくれた。
家の近くの公園であたたかいカフェオレを飲みながら、祖父は穏やかな声で言った。
「今は不寛容な時代だと言われているけどな、人を許すのはとても大切なことなんだ」
祖父はまっすぐ前を見つめたまま言葉を続けた。「人間は誰しも失敗する生き物だよ。完璧に生きられる者なんていやしない。過去を探れば誰だって愚かな出来事のひとつやふたつ見つかるもんさ。心から反省しているのに、それをずっと責められたら誰も生きてはいけない。もちろん、自分自身の過ちも許してやらなければならないよ。歳を重ねるとな、ときどき誰も悪くなかったんじゃないか、そう思うことがあるんだ。ただ、みんな必死に生きようとしていただけなんじゃないか」
家族の前で涙を流したのは初めてだった。迷惑をかけている当事者が泣いてはいけない。けれど、押し殺した嗚咽がもれてきて止められなかった。
「お前が優しい子なのは、じいちゃんはよくわかっている。これだけは忘れないでくれ。星吾はじいちゃんの大切な宝物だからな」
あのとき背中を撫でてくれた祖父の優しい手や体温が忘れられなかった。幾度となく、この祖父という存在に助けられた。星吾は心の底から「ごめんなさい」と謝罪し、何度も頭を下げた。
救いだったのは、警察のおかげで悪質な投稿者が特定され、個人情報を削除してもらえたことだ。多くの人間に恨まれていると思い込んでいたが、個人情報を書き込んでいたのは数名だったそうだ。
それからは前向きに勉強に取り組み、できるだけ親に負担をかけないように、学費が安い国公立の大学を目指した。なるべくいい大学に合格し、失った家族の信頼を取り戻したいと思ったのだ。けれど、そう意気込んでも雨粒が窓を叩く夜は強い自責の念と不安に襲われ、心が潰れてしまいそうになる。
そんな日々を繰り返した先に、微かな光が生まれた。
県外の国立大学と私立大学に合格できたのだ。ネットにフルネームを晒されたが、音海星吾という名前でも受け入れてくれる場所がある。またやり直せるかもしれない。
しかし、その希望は簡単に打ち砕かれた。
地元を離れ、ひとり暮らしを開始してまもなく、星吾はファストフード店のバイトに採用された。しばらくは大学もバイトも順調だったのに、一ヵ月も経たないうちにバイト先の店舗や本部に匿名の電話がかかってくるようになったのだ。
――人を見殺しにした音海星吾の作るハンバーガーは食べたくない。
店長は、本部からの問い合わせに「仕事ぶりは真面目で問題ない」と報告してくれた。けれど、自ら店を辞めた。辞めてほしいと言われるのは、時間の問題だと予想できたからだ。
次のバイト先のネットカフェでも同じような状況になり、ガソリンスタンド、居酒屋のバイトもすぐに辞める羽目になった。
見えない敵からの攻撃はやむことはなく、大学の廊下でも「あれが音海星吾だよ」という声を耳にした。なんの噂をされているのか判然としなかったが、疑心暗鬼になるには充分だった。
またネット上に名前を晒されていると思い、星吾はパソコンで検索してみたが、個人情報は書かれていなかった。
廊下で耳にした声は幻聴だったのだろうか――。
キーボードに載せた手が震えているのに気づき、消えてしまいたい衝動に駆られた。
大学生活を楽しいと思ったことは一度もない。だからといって中退する勇気も、他にやりたい夢を見つける意欲もなかった。
一度は嫌がらせを罰として受け入れて生きていこうと覚悟を決めた。けれど、安易な覚悟は簡単に揺らいだ。
新しく始めたカフェのバイト先に、また悪質な電話がかかってきたのだ。
惨めで他人の目が怖くてしかたなかった。愚かな過去をどうにか心の隅に押しやり、前向きに生きようとしても誰かがそれを許してくれない。
だから被害者遺族に謝罪の手紙を書こうと決意した。
ネットに悪い情報を書き込んだのは、被害者遺族なのではないか、そんな疑念を消し去れなかったからだ。手紙を書けばやめてもらえるのではないかという浅ましい気持ちもあった。
そもそも遺族は誹謗中傷などしていないかもしれないのに――。
事件のとき事情聴取を受けた警察署に連絡し、手紙を届けてもらえないか相談したが、遺族側に受け取りを拒否された。
謝罪の言葉をひとりで何万回つぶやいても、もう贖罪を為して生まれ変わることはできないのだ。許してほしい、友だちがほしい、人に優しくされたい、そんな人並みの幸せを求めてはいけない。なにかを望めば、自分自身も深く傷つくからだ。
無限に広がる絶望の中で生きるなら、これからは心を閉ざし、他人に無関心でいられる強さを身につけ、冷酷な人間になればいい。
心をなくすのは、意外に簡単だった。涙が出なくなるほどの哀しい経験をし、痛みがなくなるほど苦しみを受け続ければいい。
けれど、あの男があらわれる現象だけはやむことはなかった。
ふいに人の気配がして、星吾は弾かれたように後方を振り返った。
美術室のドア付近にひとりの男が立っている。彼は笑いを堪えているような顔つきで、顎鬚をしきりに撫でながら口を開いた。
「まるで幽霊でも見たような顔つきだな。相変わらず謎めいた学生だ」
「先生……」
朝から不快な出来事が相次ぎ、ひどく頭が混乱していた。けれど、見慣れた美術サークルの顧問を目にすると、緊張が少し和らいでいくのを感じた。
宇佐美は今年四十歳になるというのに、かなり奇抜な風貌をしている。長い髪を後ろでひとつに結び、いつも派手な甚平を着ていた。今日はスカル柄だ。上背はあまりないが、プロレスラーのような屈強な体格をしている。大きな足にはいぐさの草履。誰が見ても、准教授だとは思えないような人物だった。
宇佐美はパタパタと草履を鳴らしながら近寄ってくると、ラベンダーの残骸を訝しげに眺めただけで、花については触れなかった。
「この大学でも無差別殺傷事件が起きたのか? 腕を怪我しているぞ」
数日前、他の大学の構内で学生が包丁を振り回す事件が起きた。
まだ十九歳の犯人は、次々に教授や学生たちを斬りつけ、講義室や廊下は血の海と化したようだ。警察の取り調べに対し、犯人は「モラトリアム人間に恨みがあった」と供述しているという。多数の負傷者がでたため、連日、事件はマスコミによって扇情的に報じられていた。
「もしくは、熊にやられた可能性もあるな。さっきネットニュースで見たが、その腕の傷は『熊と戦った』っていう爺さんの傷にそっくりだ」
宇佐美は軽口を叩いてから「手当てしてやるよ」と言い残し、美術室をあとにした。
鞄を手に取り、急いで廊下に出ると周囲に目を配った。
奇妙な出来事のせいで疑心暗鬼に陥ってしまう。辺りに誰もいないのを確認してから、廊下の先にいる甚平姿を追いかけた。ずいぶん距離が開いてしまったのに、先生は一度もこちらを振り返らなかった。
自由奔放で捉えどころのない宇佐美は、若かりし頃、名の通った彫刻家だったらしい。手を負傷してからは専門学校や大学の非常勤講師を務め、去年この大学の正規教員になり、一般教養科目や教育学部の美術専攻の学生たちに彫刻論や塑像、木工などを教えていた。
美術室のあるB棟の四階には、宇佐美の研究室もあった。
研究室は狭いせいか、いつ訪れても圧迫感を覚える。小窓しかないため、天井の照明が常に人工的な光を放っていた。
周囲にはふたり掛けのソファと丸テーブル、奥には木製の長机。その上には一台のノートパソコンと黒猫の絵が描かれたマグカップ。両サイドの壁には背の高い棚が並び、書籍が乱雑に置いてある。
棚に並んでいるのは、学術書よりも小説のほうが断然多かった。幼い頃、刑事になりたかったという宇佐美は、ミステリ小説を好んで読んでいるようだ。
棚の上段で目を留めた。ざわざわと胸が騒ぎだす。
単行本の『罪の果て』が並んでいたのだ。ページをめくると、潰れたジョロウグモと滲んだ真紅の文字があらわれる気がして目をそらした。
星吾は棚から離れ、疲れた身体をソファに沈ませた。
宇佐美は引き出しから救急箱を取りだすと、慣れた手つきで消毒してくれた。ごつい手なのに、繊細で丁寧な動きだった。作品の制作中に怪我をする学生がいるため、救急箱を常備しているようだ。
傷は乾燥していたが、触れられると痛みがぶり返してくる。
悪いと思いながらも、つい宇佐美の手首に目がいってしまう。左手首には、三センチほどのケロイド状の傷がある。昔、手首の腱を木工道具で深く傷つけてしまったそうだ。それが原因なのか、左指の三本は石像のように固まり、動かせないようだった。
心情をすべて理解しているわけではないが、宇佐美からは指が動かない憂いや、苦悩などの暗い翳は微塵も感じられなかった。
人生の不幸や悲劇を特別視しないタイプなのかもしれない。
半年ほど前、星吾は祖父を亡くした。そのことを伝えたときも、気遣う素振りもなく、淡々と「俺もお前もあとどれだけ生きられるかわからない。哀しみに浸れる時間は、そう長くはない」と微笑んだ。
冷たい物言いは沈んでいる学生の身を案じ、これ以上哀しみに暮れさせたくないという、宇佐美なりの優しさにも思えた。なぜなら彼のストレートな物言いや考え方は、いつも星吾の心を軽くしてくれたからだ。
美術サークルに入会したのも、顧問に魅力を感じたのが理由のひとつだった。
絵を描くのが好きだった星吾は、小学生になると様々な絵画コンクールで受賞を重ね、そのたびに全校生徒の前で賞状や盾をもらい表彰された。中学の文化祭のポスターにも三年連続で選ばれ、それなりに自信も持っていたが、氷室の事件以来、色を塗ることができなくなってしまった。
それなのに祖父だけは「色がなくても感情が伝わってくる、躍動感のあるすばらしい絵だ」と褒めてくれた。祖父は気に入らないことがあっても決して感情的にならず、常に気を遣いながら生きている人だった。これまでも声を荒らげる場面や不機嫌な態度を一度も目にしたことがない。振り返れば、祖父との思い出は、どれも穏やかな風景画のように心地いいものばかりだった。
一年前、そんな祖父から「絵画展に行かないか」と誘われた。絵画展は、星吾の大学の近くにある美術館で開催されていた。
今にして思えば、死を予感しての気遣いだったのかもしれない。
星吾はひとり暮らしを始めてから実家に寄りつかなくなり、家族とは連絡を取らない状態が続いていた。距離ができてしまったことを、ずっと心配していた祖父は、なにか理由をつけなければ県外にいる孫に会いに行けないと思ったのだろう。
ふたりで時間をかけて、ゆっくり絵画展を観て回った。ときどき祖父の視線を感じたが、敢えて気づかないふりをした。絵画よりも孫の顔が見たかったという想いがひしひしと伝わってきて戸惑ってしまったのだ。
絵画鑑賞を終えてから広々としたロビーに出ると、たくさんいる客の中でひときわ異彩を放っている人物が目についた。
長髪に甚平姿の男――。すぐに宇佐美だと気づいたが、まさか声をかけてくるとは思いもしなかった。
星吾は一年のとき一般教養料目で宇佐美の講義を受講した。人気があったのか、受講している学生は他にも大勢いた。それなのに近寄ってきた宇佐美は、祖父にぺこぺこ頭を下げながら自己紹介を始めたのだ。そのうえ、星吾の絵を一度も見たことがないのに、「音海君はとても才能のある学生で、彼の絵に一目置いているんです」と適当な嘘を並べた。
最初はなにか魂胆があるのではないかと警戒心が働いたが、祖父が目に涙を浮かべて喜ぶので、星吾も思わず親しいふりをしてしまった。
祖父はすっかり信じ込んだ様子で「この子には絵の才能があると思っています。どうか、どうか、星吾のことをよろしくお願いします」と深々と頭を下げた。
祖父の祈りのような言葉に、胸に微かな痛みを覚えた。騙しているという後ろめたさはあったが、久しぶりの祖父の笑顔が嬉しくて、罪悪感よりも安堵感のほうが勝った。
数日後、宇佐美に学食で声をかけられ、美術サークルに入会してほしいと頼まれたときは、やはり裏があったのかと不信感が募った。
宇佐美は「新入生がひとりも入らないから、部を存続させるためにも頼む」と誘ってきたのだが、それは本当の理由ではなかった。廃部になるのを避けたいというよりも、おしゃべり好きの准教授は、誰か聞き役になってくれる相手がほしかったのだ。
一度はバイトが忙しいという理由で入会を断ったが、祖父の死で気持ちは変わった。
祖父は縁側で日向ぼっこをしている最中、息を引き取った。とても安らかな死に顔だったという。絵画展は、ふたりで過ごした最後の思い出の場となったのだ。あのときの先生の嘘に心から感謝した。祖父を少しだけ安心させられたからだ。
宇佐美は消毒を終えると、平坦な口調で訊いた。
「この怪我はどうした?」
「駅のホームで……転んだんです」
星吾は蚊の鳴くような声で短く返答した。色白の男に投げた自分の残酷な言葉を思いだし、ホームでの出来事を詳細に語りたくなかったのだ。
宇佐美はなにかを見抜いているような眼差しで言った。
「駅のホームか。とにかく自傷行為じゃなくて安心したよ」
(#3に続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
