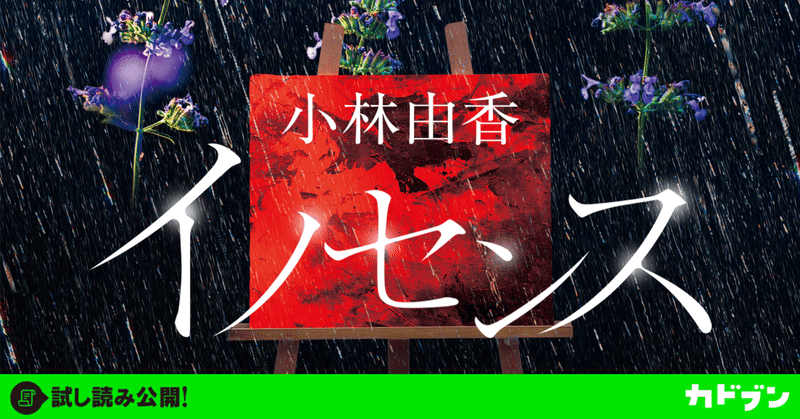
明日、十月一日、それが最期の日になってもかまわない/小林由香『イノセンス』発売前特別試し読み#11
犯人当てキャンペーンも開催中!
カドブンノベル一挙掲載、WEB文芸マガジン「カドブン」で連載中から大きな反響を読んでいる話題作『イノセンス』。
10月1日の発売に先駆けて、note上でほぼ全文試し読みを実施中。
主人公・星吾を追い詰める犯人の正体は?
・犯人当てキャンペーンの詳細は文末をご覧ください。
>>>
翌日、美術室でジャージに着替えると、星吾は床一面に新聞紙を広げた。その上にイーゼルを置き、下描きが完成したキャンバスを立てかける。
キャンバスの正面に椅子を移動させ、ゆっくり腰を下ろしてから絵と向き合った。
絵にも感情がある。彼らはみんな自分だけの色を持っていた。それなのに、しばらく眺めていても的確な色調が想像できない。どのようなものを求めているのかもわからなかった。
余計な感情を払拭し、この世にひとつしかない色彩を頭の中に創り上げていく。
絵筆を持つ手が震えてしまう。心身ともに色を強く拒んでいる。ひどく息苦しかった。
呼吸が止まってもかまわない――。
遺品整理のとき、祖父の部屋から見つかったプレゼント。色を塗れなくなった孫に、どんな想いで油絵具を買ってくれたのだろう。そのときの気持ちを想像するだけで胸が圧され、両目の奥が熱を孕んだ。
祖父は、ずっと信じてくれていたのだ。いつか色を取り戻し、また人とつながれる日が来ることを――。
星吾は覚悟を決め、パレットに油絵具をしぼり、油つぼに絵筆を入れ、カドミウムレッドを溶いていく。手の震えが激しさを増す。
最初に反応したのは嗅覚だ。血を連想させるような鉄の幻臭が室内に立ち込める。アイボリーブラックを加えると、氷室の血液を混ぜているような錯覚に陥った。辺りに鉄錆のような臭いが増していく。強い吐き気を催し、喉の奥に力を込めた。
突き刺さるような幻臭が、あの日のおぞましい記憶を呼び覚ます。
教室の隅に氷室の気配を感じた。怖くない。そのまま、そばにいてほしい。この絵が完成するまで、最後まで見届けてほしい。
絵筆を動かすたび、氷室の気配が濃くなってくる。
油絵具を塗り、乾かし、色を重ね、全体の明度や彩度を確認し、また乾かし、あらゆる感情を破壊し、再生させる。抱えている憎しみや哀しみが油絵具に溶けていき、感情を持つ絵となり昇華していく。
今まで幾度も絵に助けられてきた。
キャンバスは絵筆から流れる負の感情を、いつだって黙って受け止めてくれる。もっと輝かしい色をよこせとは言わない。思い描いた色彩でいいと認めてくれた。
美術室に通いつめて絵筆を握り続けていると、次第に遺書を書いているのではないかと自覚し始めた。氷室をそばに感じても怖くない理由がわかり、複雑な心境になる。
誰かに命を狙われ、死を身近に感じたとき、恐怖は原動力に変わった。
冴島を殺害した犯人は、まだ捕まっていない。いまだに特定できずにいるのは、被害者とあまり接点のない人物の犯行を臭わせている。もしくは、突発的な殺人ではなく、緻密に考え抜かれた計画的殺人の可能性も高い。
もしも冴島と同じ運命をたどるなら、どうしても残したい想いがあった。
言い知れぬ切迫感が手を動かしていく。
唐突に高音性の耳鳴りが始まった。同時にごぼごぼと蠢くような低い音も聞こえてくる。
耳の奥から「ただの自己満足だな」そう嘲るような声が響いてきた。
罪から逃れたくて絵を描いているんじゃない――。
星吾は教室の中に感じる気配に向けて、祈るようにつぶやいた。
だったらなんのために描いているんだ?
そう尋ねる低音の声に聞き覚えはなく、誰のものかわからなかった。
なにも答えられず、星吾はおもむろに手を止めた。
一瞬にして目の前の絵が、創りだした色彩が、とてもチープで拙いものに成り下がっていく。夢中で絵筆を走らせていた情熱が溶けていき、なにを描きたかったのかさえ、霞んで見失ってしまう。
心に絶望の波が押し寄せてくる。原油が流出した海のようなどす黒い波。一度呑まれてしまえば二度と海面に浮上できない。最後まで描けなくなる不穏な予感を覚えた。
星吾は弾かれたようにドアのほうに目を向けた。
ぱちんと電気がつけられたとき、初めて室内が薄暗いことに気づいた。
「夏休みなのに毎日大学に来るなんて、気味の悪い学生だな」
宇佐美はそう言いながら室内に入ってくると、教卓に置いてある紙を手に取った。「学生アートコンクール……応募する気になったのか?」
「入選は難しいかもしれませんが、どうしても描きたい絵があって、今なら最後まで描けるような気がするんです」
描きたい絵が見つかったことは報告したが、コンクールに応募するのは伝えていなかった。
「やっぱり、美術部員にはジャージがよく似合う」
宇佐美は笑いながら続けた。「美術部は文化部に属しているが、俺からしたら体育部だ。絵と格闘し、腕が痺れるまで絵筆を握り、完成する頃には身も心もくたくたになる」
宇佐美はキャンバスの近くまで移動すると、顎鬚を触りながら絵を眺めた。哀しげに目を細め、唇を引き結んでいる。まるで痛みを堪えているような表情だった。
物音ひとつしない室内に、重苦しい沈黙が満ちていく。
気まずい空気に耐えられなくなり、星吾が口を開きかけたとき、宇佐美は真顔で言った。
「まるでラブレターだな」
その感想は意外だった。けれど、そう言われればそんな気もしてくる。
「納得できる絵が描けなくて……急に不安になってしまって」
追いつめられていたせいか、素直な気持ちを口にしていた。
宇佐美は、窓際に置いてある椅子に腰を下ろしてから尋ねた。
「小学三年の頃、『全国絵画・工作コンクール』で賞をもらったのを覚えているか?」
たしか、美術の授業で『家族』をテーマに描けと言われ、金賞をもらったことがあった。星吾は父親の絵を描いた。賞状をもらって家に帰ると、父がとても喜んでくれたのを覚えている。
胸の内に、ある疑問がよぎった。
「どうして……先生が知っているんですか?」
宇佐美は遠くを見つめながら口を開いた。
「俺の指が動かないのは、嫁に手首を刺されたからだ」
星吾は衝撃的な告白に二の句が継げなくなり、思わず顔を見た。予想に反して、宇佐美は少年のような無邪気な笑みを浮かべている。
「俺たちは学生結婚だった。嫁はピアニストを目指して音大に通っていた。でもな、大学三年の頃、彼女は妊娠していることに気づいて退学した。自分の夢よりも子どもが大切だったんだ。それなのに俺たちの息子は五歳のとき事故で命を落とした」
宇佐美は動かない指に視線を落としてから、穏やかな声で話しだした。まるで昔話をするような語り口だった。
甚平をデザインしていた宇佐美の友人が、日本人オーナーが営むニューヨークのアートギャラリーで個展を開催した。甚平を着るのはマネキンではなく、身体は人間、顔は植物や動物という得体の知れない宇佐美の彫刻作品だった。彫刻作品は甚平よりも注目を集め、有名な雑誌にも取り上げられ、名高いブランドショップからも注文が入ったという。
「俺は作品を創るのに夢中になって、嫁も息子も蔑ろにしてしまった時期があったんだ。多くの時間を作品制作に費やし、ほとんど海外にいた。久しぶりに帰国したとき、息子とたくさん遊んでやろうと思って、ふたりで広い公園へ行ったんだ。だが、ちょっと目を離した隙きに、息子は高校生の乗っていた自転車に撥ねられて内臓破裂で死亡した」
宇佐美は哀しげに笑うと「車じゃなくて、自転車だぞ」と言ったきり、黙り込んでしまった。
「だから奥さんは……先生を刺したんですか?」
「あぁ、彼女も罪を犯した」
宇佐美はしゃがれた声で言葉を継いだ。「息子を亡くしてから毎日、嫁から穏やかな声で『家に帰ってこなければよかったのに』と言われ続けた。まるで天気の話でもするかのように、さらりと口にするから余計にきつかった。息子を亡くしてからしばらく経った頃、『あなたは本当に反省しているの?』って訊かれたんだ。俺は、もちろん反省していると答えた。嫁に『だったらプレゼントをあげるから手をだして』と言われ、俺は机の上に手を載せた。そのとき彼女は隠し持っていた彫刻刀で俺の手首を刺したんだ。まるでホラーだろ?」
星吾は言葉が見つからず身を硬くした。
宇佐美は追想するように、また遠くに目を向けた。
「いつもは冷静沈着なのに、刺したあとは子どもみたいに泣きじゃくっていた。まるで自分が刺されたかのようにな。医者には仕事中に怪我をしたと嘘をついた。せめてもの罪滅ぼしだ。それ以来、彼女は俺に暴言を吐かなくなった。いや、罵りたくなるたびに傷つけた手首に目を向け、泣きだしそうな顔をしている。だが、誰からも責められなくなると、今度は自責の念に苦しめられるようになった。それは想像以上にきつかったよ」
他人から暴言を吐かれるよりも、自分自身に責められたときのほうがきつい。もう逃げ場はどこにもないからだ。
宇佐美はキャンバスに目を向けながら言った。
「息子を亡くしてから、『小学生全国絵画・工作コンクール』の工作部門の審査員のひとりだった俺は、入選した子どもたちの展示作品を観に行ったことがあったんだ。そこで『音海星吾』の絵に出会った。変わった名前だったから記憶に残っていた。児童たちの作品にはありとあらゆる笑顔の家族が描かれていて、すべてが善意にあふれたものだった。だが、ひとりだけ違った。画用紙の左上に泣き顔の父親、右上には頬を真っ赤にして怒る父親、左下には無表情の父親、右下は目を閉じている父親、中央には笑顔の父親が描いてあった。お前の絵からは泣いていても、怒っていても、無表情でも、眠っていても『お父さんが大好きです』という気持ちが伝わってきた」
絵画展で祖父に初めて会ったとき、宇佐美は「音海君はとても才能のある学生で、彼の絵に一目置いているんです」と言っていた。あのときの発言は嘘ではなかったのだ。
宇佐美は、甚平のポケットから薄汚れた紙を取りだして広げた。
そこには、拙い文字で『あまりおうちにかえってこないけど、いそがしくてあそんでくれないけど、ぼくはパパがスキだからいっしょにあそんであげます』と書いてあった。
「あの日、音海星吾の絵を観た俺は、ガキの絵に泣かされた。帰宅してから、どうしても息子の絵を観たくなって落書き帳を開いてみたら、最後のページに拙い字で書いてあった。お前の絵を観なければ、息子のメッセージに一生気づけなかったかもしれない」
宇佐美は緩慢な動きで紙をしまうと、今度はポケットから写真を取りだした。色褪せた古い写真だった。甚平を着た少年が無邪気に笑っている。その隣で微笑んでいる父親の姿がせつなかった。
「何度も彫刻で息子を創ろうと思ったが、俺には無理だった。他の作品さえ、まともに創れなくなった。だから……お前が色を使えるようになって、心底嬉しかったよ」
感情が掻き乱され、星吾は顔を伏せた。
宇佐美はまたキャンバスの前に立つと、絵を凝視しながら言った。
「綿密な市場調査を重ね、商品がひとつでも多く売れる広告を作りたいと願い、必死にデザインを考えているデザイナーたちを俺はリスペクトしている。でもな、コンクールは好きなものを描いていいんだ。気を遣わなければならないクライアントも存在しない。だったら、お前が描きたいものをぶちかませばいい。周囲からどれだけ批判されてもかまわない。もしも罵られたら、そいつらに胸を張って言ってやれ。『お前のために描いてない。この絵はたったひとりのために描いているんだ』ってな。それが許されないなら、絵画が存在する意味なんてないだろ」
星吾は、宇佐美の目を見据えながら尋ねた。
「この絵は……僕の絵は伝わりますか」
「きっと伝わるさ。信じる余地を与えてくれないものなんて芸術じゃない」
宇佐美は不敵な笑みを浮べると、「せいぜいがんばれよ」と言い残し、教室をあとにした。
いつか尋ねたことがあった。
どうして先生は、そんなにも親身になってくれるんですか――。
小学生の頃の絵が、先生と自分をつないでくれていたのだ。
完成したのは、夏休みの最終日だった。学生アートコンクールのエントリーサイトから応募を済ませ、作品の搬入作業は二日後に宇佐美が手伝ってくれる予定になっていた。
パレットを持っていた左腕が重く痺れている。
星吾はキャンバスから離れた場所に椅子を置き、そこから描いた絵を眺めた。
少年の嗚咽が聞こえてくる。もう彼を許してあげたかった。あの日の自分自身を許せたなら、絶望しか見出せない未来は変えられるだろうか――。
窓の外を見ると、いつのまにか夜闇が空を覆っていた。
慌てて腕時計を確認する。十九時半を過ぎていた。
急いで絵筆をクリーナーポットで濯ぎ、ジャージから私服に着替え、教室の電気を消して廊下に飛びだした。
明日は、紗椰と新緑美術館に行く日だった。星吾は午前中に講義が入っていたため、美術館の最寄り駅に十四時に待ち合わせをしていた。
キャンパスを出て駅までの道を足早に進んでいく。足取りは軽く、妙に気分が高揚している。気づけば、全力で駆けだしていた。
完成した喜びが胸に迫ってくる。見慣れているはずの街路樹、街灯、信号機、それらのすべてが息づいているように感じられた。まるで舞台のセットの中を走っているような不思議な気分になる。
いつもとは反対方向の電車に飛び乗り、賑やかな繁華街まで向かう。
駅の広告で目にした『エバーグリーン』という店名。目的の駅で下車すると、スマホを取りだし、地図アプリで確認しながら店まで歩を進めた。
大通り沿いを五分ほど歩くと、ひときわ明るい店舗が見えてくる。そこはジュエリーショップだった。
店内に足を踏み入れた途端、星吾は現実に引き戻された。
想像以上にきらびやかな内装だったため、萎縮してしまう。油絵具で汚れている爪が急に恥ずかしくなり、少し戸惑ってしまった。
覚悟を決めてカウンターに向かうと、爪をライラック色に塗った店員が、手袋をしてから注文しておいた商品を見せてくれた。
小さなメッセージカードをもらい、星吾は近くにあるソファに座り、できるだけ丁寧な字でメッセージを書き込んでいく。
ふと顔を上げたとき、不思議な感覚が湧き起こった。
正面にある大型の鏡に映っているのは、いつもの自分ではないように思えたのだ。どこが違うのか判然としないが、自分とそっくりな顔をした別人を見ているような奇妙な気分に包まれた。
深夜勤務だったため、一旦アパートに戻ってからコンビニに向かった。
タイムカードを押し、制服に着替え、バックヤードを出ると、弁当コーナーに女性客がふたり、デザートコーナーに男性客がひとりいた。
星吾は店内の様子をひと通り確認してから、レジカウンターに視線を移した瞬間、はっと息を呑んだ。
光輝の右頬が殴られたように赤黒く腫れ上がっていたのだ。近くで見ると顎にも擦り傷があり、腕には引っ掻かれたような痕がいくつも走っていた。皮膚がめくれて血が滲んでいる。見ているだけでひりひりするような痛みを感じた。
転んでできた傷には見えなかった。そうかと言って、いつも温厚な光輝が誰かと喧嘩するとは思えない。
女性客がレジカウンターに商品を置くと、光輝は顔を伏せぎみにして、「いらっしゃいませ」と暗い声で挨拶する。普段の明るい雰囲気はなく、表情からは悲愴感が漂っていた。ときどき眼鏡を指で押し上げながら、レジ業務をこなしている。
星吾と交替するバイト仲間に近寄ると、小声で怪我のことを訊いてみた。けれど、彼も詳しい事情は知らないようだった。
ふたりきりになってから本人に尋ねてみようと思ったが、光輝はレジを終えると避けるかのようにバックヤードに姿を消した。しばらくしてからモップを手に戻ってくると、今度は黙々と床掃除を始める。
明らかに様子がおかしい――。
壁の時計が零時を過ぎる頃、店内はふたりきりになった。目立つ汚れはないのに、光輝は同じ床を繰り返しモップで拭いていた。心ここにあらずといった様子で心配になってくる。
気まずい空気に耐えられなくなり、星吾は近寄ると思いきって声をかけた。
「その傷、どうしたんだよ」
「星吾のほうが『どうしたの』だよ」
光輝はふてくされたような顔で続けた。「最近、やけに明るいし、前とは別人みたい」
ジュエリーショップの鏡を見たとき、同じことを感じたのを思いだした。理由は薄々気づいているが、照れくさくて言葉にできなかったので、星吾は改めて尋ねた。
「なにをしたらそんな傷になるの」
「どうして話をそこに戻すかな。別れ際に女にやられたんだ」
「女って……誰にやられたんだよ」
「簡単に言えば、愛してほしい人」
光輝は恥ずかしげもなく、子どもみたいな口調で言った。
相手は、司書の松原だろうか――。けれど、あの静謐な雰囲気の松原が暴力をふるうとは思えない。
「俺よりも……紗椰のことを気にかけてあげたほうがいいよ」
その脈絡のない言葉に疑念が湧き、思わず顔を見ると傷のせいもあるが、彼の顔には色濃い苦悩が滲み出ているように見えた。
「人生ってさ、ときどきどうしてこんなふうになったんだろう、って思うことがあるんだ」
光輝はそう言うとモップをコピー機に立てかけ、売り物の夕刊に手を伸ばした。
彼が広げた夕刊を目にしたとき、驚きのあまり声を上げそうになった。
――氷室リゾート食品偽装。
星吾もすぐに夕刊を手に取り、記事に目を走らせた。
氷室リゾートが運営するホテルで、いくつもの食品偽装が見つかったという。
光輝は唐突に険しい声音で言った。
「不運はどこまでも続くのかな。紗椰の家、これから大変になるだろうな」
一瞬耳を疑った。直後、星吾は確信に近い予感に駆られ、身を固くした。
「どうして……黒川さんの家が大変になるの?」
内心の怯えを気取られないように訊くと、光輝は少し顔をしかめながら口を開いた。
「俺らが中学三年の頃にひどい事件が起きたんだ」
「事件?」
「大学生が金を巻き上げられている中学生を助けようとして、犯人に刺された挙句、助けた相手に放置されて死亡した事件」
心臓は早鐘を打ち、全身が小刻みに震え始めた。
光輝はしばらく黙考したあと、気の毒そうに表情を曇らせてから言った。
「高校の頃、紗椰と同じ中学だった人に聞いたんだ。あのとき殺された大学生は、紗椰の兄貴だったらしい」
なにかを警告するかのように、耳の奥から自分の鼓動音が強く鳴り響いてくる。
氷室は十四歳の頃、川で溺れそうになった少年を助け、山梨県警察本部から感謝状をもらっていたはずだ。その話は中学や予備校でも話題になっていた。
氷室は山梨の出身だと思ったから、気をつけて他県の大学を受験したのだ。駅のホームで会ったとき、紗椰は実家から大学に通っていると言っていた。
「黒川さんはここが地元だから……山梨の出身ではないよね? たしか、あの事件の被害者の大学生は、川で溺れている子どもを助けて山梨県警から感謝状をもらったって……」
星吾が訥々と疑問を言葉にすると、光輝は思案顔で口を開いた。
「そういえば……テレビかなにかで見たことがある。あれは夏休みに家族旅行に行ったとき、子どもを助けたって話でしょ。紗椰の兄貴って、どこでもヒーローになれるタイプだよね」
そんな報道があったのだろうか――。
当時、事件の内容はマスコミによって扇情的に報じられた。痛みを伴いながらも目をそらさず、もっと週刊誌の記事や報道番組を見るべきだったのだ。
紗椰の母親が自殺したのは、あの事件が関係しているのだろうか。
「さっき、不幸はどこまでも続くって……」
星吾がそこまで言葉にすると、光輝は心中を察したらしく、神妙な面持ちで言った。
「紗椰の母親は、医学部に通う息子が相当自慢だったらしい。事件のあと、息子を厳格に育ててきた父親を責めて、毎日喧嘩が絶えなかったみたい。それで浮気されて……もしかしたら父親もなにかから逃げたかったのかもね」
ネットに掲載されていた食中毒事件の記事が脳裏に立ちあらわれる。
星吾は夕刊に目を落としたまま尋ねた。
「氷室リゾートって、黒川さんのお父さんの会社なの?」
「そうだよ。前に食中毒事件も起きているみたいだし、ますます経営が厳しくなるだろうな。どうして嫌なことって続くんだろう」
星吾はすがるような思いで必死に言葉を吐きだした。
「だけど……彼女の苗字は黒川だよね」
「好きな相手にはあまり知られたくない話なのかもしれないけど……」
光輝は言いづらそうに言葉を継いだ。「母親が自殺したあと、父親が許せなかった紗椰は祖父母の養子になったんだ。たぶん、父親と縁を切りたかったんだと思う」
数年前、星吾のフルネームがネット上に晒された。氷室の関係者ならば、一度は目にしていてもおかしくないはずだ。彼女はすべて知っていて、自分に近づいてきたのだろうか。そう考えるのが自然だ。
十月一日は誕生日だと言っていた。
どんな思惑があるのかわからないが、もしかしたら兄の命日に報復しようと考えているのかもしれない。
星吾は、紗椰の誕生日に過去の罪を打ち明けようとしていた。
彼女には無関係の出来事として――。けれど、それは大きな間違いだった。紗椰は無関係な人間ではなく、あの事件と強く結びついていたのだ。
「プライベートな話を俺が伝えるのはよくないと思ったけど……これから紗椰も大変になると思うから支えてあげてほしくて」
「吉田……僕は……」
舌がもつれてうまく話せなかった。ひとりでは抱えきれない真実を聞いてもらいたい。たとえ、最低だと罵られたとしても――。
「最低だよな、犯人も逃げた奴も」
光輝の怒りに満ちた鋭い言葉に喉を切り裂かれ、声がだせなかった。哀しみが、堪えきれないほどの痛みに変わる。きつく口を結び、震えている手を隠すように固く握りしめた。
耳の奥で繰り返し再生される「最低だよな」という言葉が、芽生えた勇気を奪っていく。浅はかな覚悟は簡単に消し飛んだ。
星吾は足に力を入れ、どうにか声を振り絞った。
「在庫チェックに行ってくる」
「俺も手伝おうか?」
星吾は「ひとりで大丈夫」と言い残し、バックヤードを目指した。
うまく歩けているのか、まっすぐ進めているのかさえわからない。指先が冷たくなり、膝が笑っている。歩く振動に合わせて周囲の景色がぐらぐら揺れていた。
恐怖に苛まれているのに頭がぼうっとする。どうにかバックヤードに駆け込み、素早くドアを閉めると目眩がして床に崩れ落ちた。指の感覚がなくなり、手から夕刊が離れていく。
食品偽装問題は、氷室の事件とはなんの関係もないはずだ。それなのに、すべての不幸が、あの事件と関連しているように思えてしまう。
まるで蟻地獄に呑まれていくようだった。抜け道も助かる方法も見つからず、深い絶望感に打ちのめされた。
真相を聞いたはずなのに、さっきから頭は混乱をきたしていた。なぜか、実際の紗椰ではなく、絵に描いた彼女の姿ばかりが網膜に浮かぶ。
――私はこんなふうに笑ってるの?
自然公園に行ったとき、彼女はそう訊いた。あんなにもたくさん描いたのに、本心をなにひとつ見抜けなかった。
「具合が悪いのか?」
遠くから声が聞こえる。ゆっくり顔を上げると、目の前に光輝が立っていた。
「椅子を並べるから、少し横になる?」
星吾は黙ったままかぶりを振ると、光輝はぎこちない動きで背に触れた。
「深夜はあまり客が来ないから、バイトは俺ひとりでも大丈夫だからね」
友人の姿がぼやけていく。とめどなく涙がこぼれ落ちた。星吾は懺悔するように床に頭をつけ、嗚咽をもらした。取り返しのつかない罪を、大切な友を、そして好きな人を想ってむせび泣いた。胸が波打つたび、強い吐き気に襲われる。
光輝は「どうしたんだよ」と不安げな声を上げながら、背中を優しくさすってくれた。
「あのとき……逃げだした中学生は……」
星吾は必死に声を振り絞った。「被害者の大学生を置き去りにして……逃げだしたのは……僕なんだ」
背中の手が止まり、すっと離れていく。
光輝の顔を見ることができなかった。彼の軽蔑した表情が目に浮かぶ。
「ずっと……助けてくれた大学生を恨んでた」
星吾は堪えきれず、正直に気持ちを打ち明けた。「どうして警察も呼ばずに助けに来たのか……本当は誰も犠牲にしたくなかった。逃げだした自分自身も許せなかった」
「星吾……」
光輝の声には動揺が滲み出ていた。
「こんな人生を送らなきゃならないなら……僕が死ねばよかった……あのとき逃げずに……許してください。許してください……」
静かな室内に、星吾の押し殺した嗚咽が響いた。「吉田……ごめん……」
今まで過去の罪を隠して交友関係を築いてきたのだ。
そのとき、ふたたび背にあたたかい体温を感じた。
光輝の手は、公園のベンチで背中を撫でてくれた祖父のぬくもりによく似ていた。まるで、凍えている身体を必死にあたためるように、傷口をそっと塞ぐように――。
星吾の中で揺るぎない決意が固まった。
明日、十月一日、それが最期の日になってもかまわない。残酷な未来が待ち受けていたとしても、もう逃げだすという選択肢は残っていなかった。
(星吾を待ち受ける意外な真実とは――。
この続きは、10月1日発売の単行本『イノセンス』でお楽しみください)
【『イノセンス』犯人当てキャンペーン、開催!】
★キャンペーンの参加方法★
1.noteにて『角川文芸ch「カドブンnote」』をフォローしてください。
2.ハッシュタグ「#イノセンス犯人当て」をつけて、あなたの思う犯人の名前と、お読みになった感想をご自身のnoteアカウントで発表してください。
3.抽選で5名様に、『イノセンス』小林由香さんのサイン本をプレゼントいたします(当選者にはnoteの「クリエイターへのお問い合わせ」欄を通じて、ご連絡差し上げます)。
★キャンペーン期間★
2020年9月25日(金)12:00~2020年10月1日(木)23:59
・賞品の発送先は日本国内に限らせていただきます。
・投稿内容は、『イノセンス』の広告宣伝、販売促進、関連記事や番組などで使用させていただくことがあります。
・感想をご紹介する際には、誤字脱字や語尾の修正、スペースにあわせて一部のみをピックアップさせていただくなど、本来の意味を損なわない範囲で変更を加えさせていただく場合があります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
