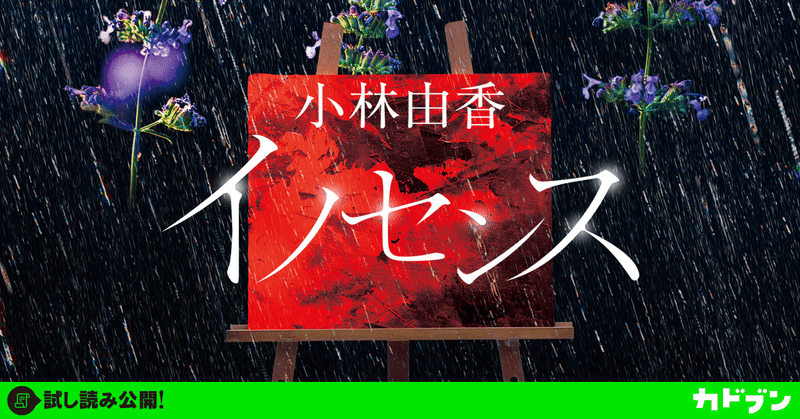
あの人、死んだみたいよ。あなたの望み通り夜に電車に飛び込んで自殺したみたい/小林由香『イノセンス』発売前特別試し読み#4
連載中から賛否両論の嵐。
小林由香『イノセンス』期間限定「ほぼ全文試し読み!」
カドブンノベル一挙掲載、WEB文芸マガジン「カドブン」で連載中から大きな反響を読んでいる話題作『イノセンス』。
10月1日の発売に先駆けて、このたびnote上でほぼ全文試し読みを行います。
主人公・星吾を追い詰める犯人の正体は?
犯人当てキャンペーン、近日実施予定!
>>>
4
大学の構内にある学食は、半年前に有名な建築デザイナーによって改装されたばかりだった。以前は長机と椅子が並ぶ簡素なつくりで、学生たちからの評判はあまりよくなかった。少子化が深刻化しているのを考慮し、大学の維持発展のためにも改装に踏み切ったようだ。
今は高級ホテルのラウンジのように、洗練された照明の下に絵画が飾られている。他の学生には評判がいいが、ひとりで食事をする星吾には、以前の庶民的な雰囲気のほうが利用しやすかった。
学食の一面はガラス張りで、そこから広い中庭が見渡せる。初夏の陽光が青々と茂った芝生に降り注いでいた。
束の間、穏やかな気分に満たされたが、それもすぐに耳障りな笑い声に掻き消された。反射的に目を向けると、隣のテーブルの学生たちがテレビドラマの話題で盛り上がっている。
なにげなく周囲に目を配ると、ひとりで食事をしている者はいなかった。大学生になっても、友だちがいないのは恥ずかしいという空気は残っている。友人のいない学生は、食事の時間が苦痛で空いている教室やトイレで食べる者もいるらしいが、星吾はそこまでする気にはなれなかった。
日替わり定食についているポテトサラダに箸を伸ばしたとき、室内が微かに暗くなった。心なしか、みんなの話し声も小さくなる。
窓に視線を移すと、灰色の雲が太陽を覆い隠していた。
雨雲はいつも心を暗く沈ませ、不吉な予感を連れてくる。まるで条件反射だ。深い海の底へ沈んでいくような息苦しさを覚えた。一瞬、視界が赤く染まる。目を閉じると、凪いだ海原が脳裏に浮かんだ。生物の気配はなく、潮の香りもしない。常に死の匂いが漂っている静かな赤い海。その光景は、胸が苦しくなるほど見慣れたものだった。
星吾は早く食事を済ませようと懸命に箸を動かした。少し胃のむかつきを感じる。
バイト中に見た悪夢のせいで、あれから心身の疲れがとれない。もう二日前の出来事なのに、まだ鮮明に記憶に残っていた。思い返すたび、夢ではなく、本当に境界線の向こうから亡者があらわれたのではないかと錯覚してしまいそうになる。
痛み始めたこめかみを指で押さえた。
すべて忘却したいのに足首をつかまれたときの嫌な感触をいつまでも消し去れなかった。気を抜くと生ぬるい体温がよみがえり、恐怖が足もとから這いのぼってくる。
どうして氷室の夢だけは、こんなにも鮮明なのだろう。
「この前はありがとう」
明るい声が降ってきて、星吾は弾かれたように顔を上げた。
テーブルの向かいに笑顔の光輝が立っている。手にあるトレイにはオムライスとサラダ、紙パックのアイスカフェオレがふたつ置いてある。まるで約束でもしていたかのように、彼は正面の席に座った。
星吾は思わず周囲を確認してしまう。嫌われ者の自分と同じテーブルに座れば、彼も白い目で見られるのではないかと少し不安になったのだ。
光輝は柔らかい笑みを浮かべ、紙パックのカフェオレを差しだしながら言った。
「これは、お礼」
星吾は軽く頭を下げてから受け取ると、呆然とカフェオレを眺めた。
ふいに、ある疑問がよぎった。
何気ない会話の中で、ブラックコーヒーが苦手だと言ったのを覚えていてくれたのだろうか――。
光輝に信頼を寄せ始めているのは、こんな優しさがあるからだ。もうひとつ自分の本心に気づいた。ひとりで食事をするのは慣れていると思い込んでいたが、それは強がりだったのかもしれない。光輝と一緒にいると張りつめた緊張感が和らぎ、昼食の時間が急に苦痛ではなくなってくる。
そう思った直後、胸に奇妙な恐怖心が生まれた。
友人の多い光輝が、星吾の悪い噂を耳にするのは時間の問題だ。胸の中に「嫌われたくない」という切実な感情が芽生えた。
「ちょっと顔色が悪いみたいだけど大丈夫?」
光輝は心配と不安が入り混じったような表情で訊いた。
「ただの寝不足だから大丈夫。そういえば、あれから彼女には会えた?」
星吾が咄嗟に話をそらすと、彼の表情が少し翳ったように見えた。
申し訳ない気持ちになってくる。不躾な質問をしてしまった気がして、すぐに後悔に襲われた。
「あの夜、終電には間に合ったけど……結果は微妙だった」
光輝はそれ以上話したくないのか、今度は彼が話題を変えた。
「最近ついてないんだ。二限目は『心理学基礎』の試験だったんだけど、ちゃんと講義内容を覚えていったのに問題が一問だけで焦ったよ」
星吾も一年のときに選択科目で同じ講義を受講した。今は試験期間ではないが、心理学基礎の教授は前期後期の試験を行わず、月一で小テストを実施する人だった。
「どんな問題?」
星吾が訊くと、光輝は眉をひそめながら答えた。
「学習性無力感に陥った子どもに、もう一度、学習意欲を持たせる方法を答えなさい」
「なんて解答したの?」
「それは……『そんなの無理』って書いた」
どこまで正直者なのだろうと苦笑しながら、星吾はもらったカフェオレを飲んだ。
「でも、単位を落としたくないから、そいつが信頼できる親友に助けてもらえばいい、って追記しておいた。だってさ、自分ではもうどうにもならないと思い込んでいるなら、誰か他の人間が導いてやるしかないよね」
光輝はオムライスを口いっぱいに詰め込んでから続けた。「たとえ、相手を救える方法を知っていたとしても、根気よく関わってくれるのは親友以外いないだろ」
星吾はいつも気遣ってくれた祖父を思い浮かべ、思わず尋ねた。
「家族は?」
光輝はオムライスを切り裂くようにスプーンを突き刺してから言った。
「あの問題の前提が、親に否定され続けた子どもだったから、それは書けなかった」
そう話す声はどこか沈んでいるようだった。
光輝の暗い表情が気になったが、甲高い笑い声に気を取られ、騒いでいる学生たちに目を向けた。窓際のテーブル席だ。
男子学生がふざけて教授のモノマネをしている。それを見ている女子学生たちが手を叩いて笑っていた。
よくある光景なのに目が離せなくなり、緊張で身体が強張ってくる。
笑っているグループの中に、駅のホームで会った女の姿があったのだ。本当に同一人物なのだろうかと思うほど、朗らかな表情を作っている。
女と目が合いそうになり、慌てて顔を伏せた。
「星吾、どうした?」
その声に我に返り、すぐに尋ねた。
「あの窓際のテーブルの白いカットソーを着た女の人、知ってる?」
光輝は振り返ってテーブルを確認してから、なにを勘違いしたのか意味深な笑みを浮かべた。
「あの子は難しいよ。名前は黒川紗椰。経済学部の武本伸二と付き合っているみたいだよ」
いくら顔が広いとはいえ、どうして光輝がそこまで知っているのか疑問が湧いた。
彼女はまた楽しそうに声を上げて笑っている。外見はまったく同じなのに、駅のホームで会ったときと、あまりにも印象が違う。あのときは特殊な状況だったが、全体的に陰気な雰囲気を宿していた。
星吾は動揺を悟られないように尋ねた。
「彼女も経済学部?」
「紗椰は……たしか教育学部」
B棟は教育学部の講義棟だ。やはり、B棟で見かけた人物は彼女だったのだ。講義の時間に遅れて急いでいたのかもしれない。
光輝は探るような目で訊いてくる。
「紗椰みたいな子がタイプなんだ」
「違うよ」
「気になってるんじゃないの?」
「そうじゃなくて……」
言葉が続かない。どう説明すればいいのかわからず、しばらく逡巡したが、適切な言葉が見つからなかった。
「紗椰とは同じ高校で、高二からクラスも一緒だったんだ。この大学の近くにある高校だよ。顔は可愛いけど、なんか難しくてね」
光輝の口調は、どこか誇らしげだった。
「難しいって?」
「仲のいいクラスメイトたちと夏休みにキャンプに行く約束も、門限があるから行けないって断られたし。高校の頃はかなりノリが悪かったのに、大学に入った途端、武本と付き合いだしたみたいで、かなりびっくりしたよ」
「武本って人も同じ高校だったの?」
「あいつも同じ。紗椰と武本は幼馴染なんだよね」
光輝は身を乗りだすと声量を少し落とした。「武本の親父はすげぇ金持ちなんだ。まだ学生の身分なのに、パパに買ってもらった外車で優雅に通学。女子には人気があるみたいだけど、俺はそんな男、絶対信用しないね」
「彼女は偽善的な性格なの?」
光輝は「偽善的?」と少し首を傾げたので、別の言い方で尋ねた。
「正義感が強いタイプ?」
「よくわからないけど、気が強いっていうか、しっかりしてる感じかな……」
白百合の花束を抱え、目に涙を浮かべていた彼女の姿――。
あの日から、どうしても違和感を拭えないままでいた。
光輝は困惑顔で訊いた。
「どうしたんだよ。紗椰となにかあったの?」
「なにもないけど……どんな性格なのか気になったんだ」
「高校のときは、ちょっと異質だった。同調圧力に屈しないっていうのかな、いつもひとりで行動していて、できるだけ人と深く関わらないようにしているっていうか……だから紗椰を嫌っているクラスメイトもいたけどね」
先ほど目にした明るい姿を思い返すと、ますます混乱が深くなる。
その気持ちを察したのか、光輝は微笑を湛えながら口を開いた。
「高校を卒業してから変わったのかも。でも、星吾が他人に興味を示すなんて珍しいよね」
「別に……興味とかじゃなくて」
しばらく気まずい沈黙が流れたあと、光輝は眼鏡の奥の目を細めて微笑んだ。
「まぁ、悩みがあったらいつでも相談してよね。頼りになる心の友に」
学生たちの笑い声がまた響いてくる。
改めて紗椰に目を向けると、彼女の笑顔はひどく強張っているように映った。
大学の中庭を左右に切り裂くように、レンガ敷きの遊歩道が延びている。まっすぐ続く遊歩道の先には、赤茶色の古い洋館のような建物があった。
そこは旧図書館。数年前、新図書館の建設計画が持ち上がり、去年の夏に竣工したばかりだ。
書籍のほとんどが新図書館へ移動し、旧図書館には大型本や絶版になった本などが残された。
旧図書館はとても古く、併設されているトイレには幽霊が出るという噂が囁かれている。閉館作業のとき、司書が個室トイレを確認すると、ドアが閉まっていることがあったらしい。誰かが使用しているのかと思い、声をかけてみるも返事はなく、しばらく待つと、ゆるりとドアが開くそうだ。恐る恐る中を確認してみても、誰もいないという。
学生の間で噂になっている怪談話のひとつだった。
旧図書館は講義棟から少し距離があるため、利用する学生が少なく、いつ訪れても閑散としていた。
静寂に包まれた空間、木造建築物の落ち着いた雰囲気、明るすぎない照明、そのすべてが心を落ち着かせてくれる。
アーチ状の扉を抜けて館内に入ると、すぐ右側に受付カウンターが設置されていて、そこに司書の松原が座っていた。
彼女はこちらを一瞥したあと、また手もとの本に視線を落とした。
松原は二十代半ばくらい。いつも無愛想で必要なこと以外は話さない人物だった。肩で切り揃えた黒髪、薄化粧、控えめな目鼻立ち、最初は地味な印象を受けたが、よく見ると瞳は深く澄んでいて整った綺麗な顔をしていた。
愛想がないので、学生たちからの評判はかなり悪かった。彼女は人気がないため、旧図書館に残されたのではないか、そう噂する者もいる。けれど星吾にとっては、この寡黙な司書の存在も居心地のいい理由のひとつだった。
ふと、嫌な予感がして視線を移すと、窓に雨粒が張りついていた。透明な虫がずらりと並んでいるように見えて鳥肌が立つ。
数分後には激しい雨が降りだしてきた。叩きつけるような雨音は、いつも威圧的なものに感じられて恐ろしくなってくる。
空全体に閃光が走り、遠くで雷鳴が響いた。
いちばん奥にある四人がけの机は、星吾のお気に入りの席だった。利用者が少ないので大抵はそこに座れる。
椅子を引いて鞄を置くと、絵画全集が並んでいる書架に向かった。
利用者が少ないせいか、少しだけ埃っぽい臭いが漂ってくる。そっと手を伸ばし、フランスの画家の画集を取りだした。確認したいことがあったのだ。どんどんページをめくっていく。
大きな画集だったので、片手で支えるのが辛くなり、近くにある脚立の上に腰を下ろした。
画集にはバレリーナの絵がたくさん載っている。ほとんどが、ステージ上で脚光を浴びている踊り子の姿ではなかった。厳しい練習に疲れ果て、ぐったり地面に座り込んでいる少女たちが描かれている。酷使しているせいか、足の指先に血が滲んでいた。ステージ上で輝いている姿よりも、裏にある翳の部分を愛した画家だったのかもしれない。
雷が近づいてきているのか、先ほどよりも大きな雷鳴が鼓膜を震わせる。
星吾はページをめくっていた手を止め、少女の絵をしばらく眺めた。ぼんやり見つめていると、徐々に紗椰の姿と重なっていく。このモデルは、彼女なのではないかと思うほど酷似していたのだ。
描かれている少女は後ろ姿だったが、長い黒髪や線の細い華奢な肩、醸しだす雰囲気がそっくりだった。
駅のホームで初めて会ったとき、どこか見覚えがあるような気がしたのは、この絵の記憶が残っていたからかもしれない。
そのとき、強烈な稲妻が室内に射し込み、周囲を明るく染めた。直後、地面を震わせるほどの大きな雷鳴が轟く。
すべての照明が消え、館内が一気に暗くなった。
近くの電柱に落雷したのかもしれない。
薄暗い室内にふたたび閃光が走り、数秒後には激しい雷の音が炸裂した。
星吾は身を強張らせた。
頭上からなにかが落ちてきたと気づいたときには、辺りに大きな衝撃音が響いていた。
一瞬にして顔から血の気が引き、思考が凍りつく。
ぎこちない動きで足もとに視線を落とすと、巨大な画集が転がっていた。三十センチ四方ほどの分厚くて重量のある画集だ。
星吾は咄嗟に立ち上がると、緩慢な動きで首をそらし、背の高い書架を見上げた。
すべての書籍がきちんと並んでいる。もう一度、確認するように床の画集に目を向けると、鼓動が俄に速まるのを感じた。
この画集は、どこに置いてあったのだろう。書架にしっかり収まっていなかったのか――。頭を直撃していたら強い衝撃を受け、脳震盪を起こしていた可能性もある。
雨音はさらに強まり、雷もまだ近くを彷徨っている様子だった。
ゆっくり顔を上げたとき、胸騒ぎを覚えた。
館内に人影が見えたのだ。
確信に近い予感を覚え、衝動的に駆けだすと、ちょうど書庫から出たところで足を止めた。
背筋がすっと寒くなる。
そこには、ひとりの女が立っていた。
視線がぶつかった瞬間、周囲の闇が深くなった気がした。
彼女の目に警戒の色が宿る。互いの顔を見つめたまま、なにも言葉にできず、その場に凍りついたように立ち尽くしていた。
仄暗い空間に重苦しい沈黙が立ち込める。
目の前にいる紗椰は、不自然なほど身動きひとつしない。白いカットソーに細身のジーンズ姿。まるで閉店後のマネキンのようだ。
轟く雷鳴が恐怖心をいっそう募らせる。先ほどから心臓が早鐘を打っていた。
紗椰は唇の端を吊り上げてから言葉を吐きだした。
「おめでとう。願いが叶ってよかったね」
星吾は意味がつかめず眉根を寄せると、彼女は薄い笑みをこぼした。
「あの人、死んだみたいよ」
「あの人って……」
「駅で死のうとしていた男性。あなたの望みどおり、夜に電車に飛び込んで自殺したみたい」
現実感に乏しいため、悪夢を見ているような心境だった。
死んだと聞かされた途端、男の存在が色濃くなってくる。
痩せこけた頬、血の気のない顔、よれた灰色のスーツ、気味の悪い微笑。じりじりとホームの際にすり寄っていく男の姿が脳裏に浮かび上がり、背に冷たい汗が流れた。
――そんなに死にたいなら、夜にやってよ。朝やられると迷惑なんだ。
聞き慣れた自分の声が耳の奥で何度もこだましている。
その声を振り払うように、星吾は強い口調で言った。
「だからなに?」
「そんな生き方しかできなくて後悔しないの」
「生き方? 僕のなにを知ってるっていうんだよ」
学食で目にした朗らかな表情とは違い、紗椰の顔にはなんの感情も見受けられない。
彼女は淡々とした口調で驚く言葉を口にした。
「白杖を持っていた女性が定期を落としたのに、なぜ拾ってあげなかったの? 横断歩道で子どもが転んだとき、どうして助けてあげなかったの?」
星吾は不安と憤りで息がつまり、言葉がうまく発せられなかった。ひどく頭が混乱してくる。
すべて身に覚えがある出来事だったのだ。
数日前、目の悪い女性が定期券を落とした際、気づかないふりをして横を通り過ぎた。横断歩道で転倒し、泣いていた小学生を無視したこともあった。
「あの人たちと僕はなんの関係もない。だから助ける必要も義務もない」
知らないうちに、行動を観察されていたと思うと不快な気分になる。
紗椰は戸惑いを言葉に滲ませながら言った。
「義務はなくても、普通は心配になるはずよ」
「自分の価値観を押し付けないでほしい。知らない人には関わらない主義なんだ」
「立派な主義ね」
「なにが言いたいんだよ」
彼女は唇に笑みを刻んでいる。まるで軽蔑しているような表情だった。
その場違いな表情を目にした瞬間、ある疑念が湧き上がってきた。
なぜ他人の死をわざわざ知らせに来るのだろう。純粋な正義感? それとも、なにか嫌がらせをしたいのか――。
頭を働かせて浮かんだ考えを整理してみるも、彼女の意図がまったくつかめない。
突然、室内がぱっと明るくなる。
どうやら停電は解消されたようだが、窓の外はどんよりと薄暗く、まだ小雨が降り続いていた。遠雷の音も微かに聞こえてくる。
「あのとき『夜に死ね』って言ったのを後悔してる?」
紗椰の追いつめるような口調に嫌悪感を覚えたが、星吾はなにか言い返そうにも言葉にならなかった。
「ねぇ、どんな気分?」
その幼子のような無邪気な問いかけに、戸惑いと同時に強い苛立ちが込み上げてくる。
星吾は一呼吸置いてから弁明した。
「死を選択したのは彼自身だ」
「でも、あなたの言葉に傷ついた可能性はある」
「僕に恨みでもあるの」
「恨みなんてない。ただ知りたいだけ」
「こっちは、あんたと関わり合いたくない」
「安心した。あなたにも人並みの感情があるのね」
棘のある言葉を投げつけられ、自分でも驚くほど頭に血がのぼっていることに気づいた。それを隠すように、星吾はできるだけ冷静を装いながら答えた。
「残念ながら感情はあるみたいだ」
紗椰は憐れむような目を向けたあと、今度は内に秘めた想いを探るように問いかけてくる。
「哀しい? 苦しい? それとも辛い?」
瞳を輝かせている彼女の姿を見たとき、不安が心に宿った。憤りだけでなく、薄気味悪さを感じて視線をそらした。
学食にいたときは、いたって普通の学生に見えたが、マトモな人間ではないのかもしれない。本能的に深入りしないほうがいいと判断し、星吾は鞄が置いてある場所まで歩を進めた。
「後悔しているかどうかだけ教えて」
紗椰はそう言うと、後ろから強く腕をつかんできた。
皮膚に指が食い込む感触が走り、反射的に振り返ると、彼女は物怖じすることなく堂々と挑戦的な眼差しを投げてくる。答えなければ、永遠に追いかけてきそうな執念のようなものを感じてぞっとした。
星吾は視線を正面から受け止め、重い口を動かした。
「自分の失言を悔やんでる。これで満足? 人を追いつめて、なにが楽しいんだよ」
「追いつめたいわけじゃない」
「矛盾だらけだ」
「ただ……あなたの気持ちを知りたかった」
紗椰は今にも泣きだしそうだった。まるで心配していると言わんばかりの表情だ。
他人の心を平気で傷つけてくるくせに、言葉とはちぐはぐな表情を覗かせるのが腹立たしい。支離滅裂でまともに会話が成立しない不気味さを感じた。
なにが目的か訊けば、「気持ちを知りたい」と答える。もう限界だった。
「人間は完璧な生き物じゃない。誰だって観察していれば、ひとつやふたつ悪い部分は見つかる。あんたがしているのは嫌がらせだ」
星吾はそう吐き捨てると、鞄を乱暴につかんで足早に歩きだした。
一刻も早くこの場から逃げだしたい。いつもとは違い、閑散としている館内が恐ろしく感じられる。
扉に向かって歩いているとき、カウンターにいる松原と目が合った。
一瞬、安堵を覚えたが、松原はどこか蔑むような表情ですぐに視線をそらした。司書にまで軽蔑されているような気がして、闇雲に不安は増大していく。
逃げるように館外に出た。外の空気に触れると、徐々に心が鎮まっていくのを感じた。
ときどき空全体が光るが、もう雨はやんでいる。微かに聞こえる遠雷の音を耳にしながら、星吾は迷うことなくB棟に向かった。
エントランスを抜け、エレベーターに乗り込み、四階で降りて廊下に出た。
美術室に続く長い廊下を足早に歩きながら、紗椰に関する断片的な情報を整理しようと試みるも、やはり不審な言動の根源がどこにあるか判然としなかった。
なぜあんなにも他人の感情を知りたいと思うのか――まったく真意がつかめない。
心を落ち着かせ、考えられる可能性を絞っていく。
色白の男と彼女には、強いつながりはないような気がした。もしも、ふたりが親密な関係ならば、男が自殺しようとしたあの朝、彼のあとをすぐに追いかけたはずだ。
胸がどきりとして、足を止めた。
もしかしたら氷室の関係者なのかもしれない。そう考えれば、執拗に追いつめてくるのも納得がいく。ネットに悪意に満ちた言葉を書き込み、バイト先に嫌がらせの電話をかけてきたのも彼女だとしたら。文庫本に書かれた脅迫文、デッサン画の落書き――。
ベランダに投げ込まれた『罪の果て』が脳裏にありありと浮かんでくる。
小説の中で被害者の父親に最初に復讐された男は、落下してきた鉄パイプの下敷きになり死亡した。考えすぎかもしれないが、物語と現実が関連しているように思えてしまう。
画集が落ちてきたのは偶然ではなく彼女の犯行なのか。次は命を脅かす復讐を企てているのだろうか――。けれど、妙な違和感が残った。
匿名で嫌がらせをしている人間が、実際に姿をあらわして関わってくるだろうか。
そこまで考えを巡らしたあと、ひどい徒労感に襲われた。
答えのない自問を繰り返しても意味はない。真実を知りたいなら彼女と相対するしかないのだ。
美術室のドアを目前にして、しばらく逡巡してから方向転換し、星吾は廊下を駆けだした。
目的の場所までたどり着いたとき、息切れを起こしていた。
宇佐美の研究室のドアを祈るようにノックする。いつもよりもドアを叩く手に力がこもってしまう。気づけば拳で叩いていた。けれど、どれだけ待っても間の抜けた「ほぉーい」という返事は聞こえてこなかった。
ドアの前に佇んだまま、無意味な時間ばかりが過ぎていく。
なぜか見捨てられた気分になる。迷子になった幼子のように急に心細くなり、どこに行けばいいのかわからなくなってしまう。
唐突に、刑事の言葉が耳によみがえってくる。
――あのときどうすべきだったのか、ゆっくり考え続けてほしい。
(#5へ続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
