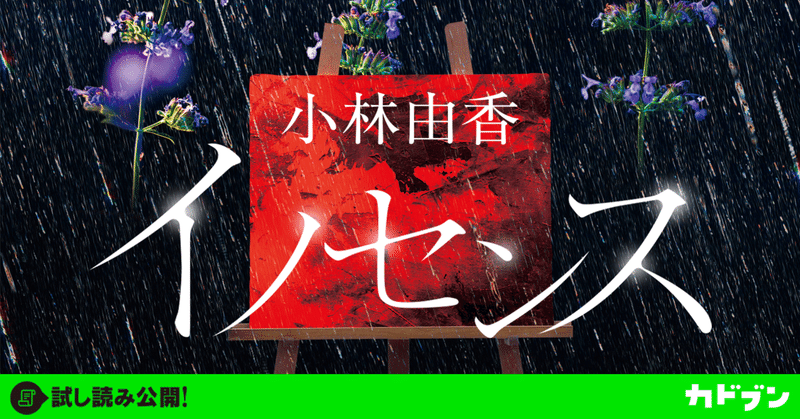
被害者の遺族に教えてもらいたい。僕に人を好きになる権利はありますか――/小林由香『イノセンス』発売前特別試し読み#10
連載中から賛否両論の嵐。
小林由香『イノセンス』期間限定「ほぼ全文試し読み!」
カドブンノベル一挙掲載、WEB文芸マガジン「カドブン」で連載中から大きな反響を読んでいる話題作『イノセンス』。
10月1日の発売に先駆けて、このたびnote上でほぼ全文試し読みを行います。
主人公・星吾を追い詰める犯人の正体は?
犯人当てキャンペーン、近日実施予定!
>>>
通話をオンにした瞬間、怒声が耳に飛び込んでくる。
スマホを持つ手が震え、一気に血の気が引いていくのを感じた。
電話の向こうで格闘しているような音と怒鳴り声が聞こえてくる。
焦燥感に駆られているのに、星吾は身動きすらできなくなっていた。
「どうした? なにかあったのか?」光輝は顔をしかめた。
その声に我に返り、星吾は勢いよく立ち上がった。
「美術室で……」
そこまで言うと鞄をつかみ、椅子が倒れるのも構わず、外に向かって走りだした。
犯人?
美術室でなにが起きているのだろう――。
気が急いて何度も転びそうになる。人にぶつかりながら学食を出て、B棟に続く道を全力で駆けていく。
宇佐美が言う「犯人」とは、花瓶を落とした人物のことだろうか。もしも複数犯だったら、そいつがナイフを持っていたら――。
次から次へと悪い妄想が膨らんでいく。
脳裏に過去の悪夢がよみがえる。
腹から血を流して倒れている氷室の姿がフラッシュバックし、恐怖から足が止まってしまいそうになる。鞄の外ポケットに手を入れると、お守りをつかんだ。すぐに取りだせるようにズボンのポケットに移動させた。
なぜこんな危険な状態になったのだろう。まさか、先生は犯人を捜していたのか。いや、偶然、美術室で犯人と鉢合わせしてしまった可能性も考えられる。
とにかく無事でいてほしい――。
星吾は走りながら美術室の窓を見上げた。花瓶のときとは違い、窓もカーテンも閉まっている。
B棟に駆け込み、エレベーターに乗り込んだ。
強張った指でボタンを連打する。鼓動は速まり、ひどい耳鳴りがしてくる。エレベーターが上昇するにつれ、息苦しさが増していく。必死の思いで呼吸を繰り返した。
寒気を感じているのに、額からは汗が噴き出てくる。
心を落ち着かせるために目を強く閉じた。暗闇の中、血まみれの氷室が左目を細めて笑っている。その姿は古い映像のように歪み、ゆっくり遠ざかっていく。
エレベーターを出て、長い廊下を全力で走り、美術室に駆け込んだ。
すっと体温が下がった気がした。
真っ白な頭部が、足もとに転がっている。棚の上にあるはずの石膏像――。
室内を見ると、そこには予想外の人物がいた。
武本伸二――。
筋肉質な宇佐美と線の細い武本とでは、力の差は歴然としている。けれど、指が動かないせいか、全力で暴れる武本を床に組み伏せるのに苦労していた。
武本の手に凶器がないのを確認し、星吾は安堵のあまりその場にくずおれそうになった。
教卓の下には、頭のない割れた石膏像が散らばっている。争っている最中に棚から落下したのかもしれない。
「お前が花瓶を落としたんだろ」
宇佐美は興奮気味に尋ねると、武本はわめいた。
「違うって言ってるじゃないですか! 僕はただ絵を……」
「絵をなんだ?」
宇佐美がそう訊くと、武本はまた激しく抵抗しようと試みるが、力尽きたのかおとなしくなっていく。
室内にはズタズタに切り裂かれた紗椰の肖像画が何枚も散らばっている。すべて鉛筆で描かれた絵だったが、実際に彼女が傷つけられたような気がして胸が痛んだ。近くには金属製のパレットナイフが転がっている。きっと、それで絵を突き刺して破いたのだろう。
一緒に動物園と自然公園に行ってから、紗椰は絵のモデルになってくれた。
星吾はひとりのときも、彼女の絵を描き続けた。ふたりに特別な進展はなかったが、描けば描くほど自分の想いに嘘がつけなくなるのを感じていた。けれど、過去の罪に阻まれて素直になれない。だからこそ絵を描くことで想いを表現したくなる。絵を観た武本は、なにかを感じ取ったのかもしれない。
「武本?」
声がして振り返ると、ドア付近に光輝が立っていた。
光輝はなにが起きているのかまったく理解できないという顔つきで室内に目を走らせている。
宇佐美は、背後から武本の両腕をつかみ上げ、無理やり彼の上半身を起こした。武本は抵抗する気力を失っているようだが、鋭い眼光を星吾へと向けてくる。
「こいつの鞄から学生証をだせ」
宇佐美はそう指示しながら、近くに落ちている深緑色の鞄に視線を送った。
星吾が鞄に手を伸ばそうとすると、光輝が口を開いた。
「経済学部二年、武本伸二」
武本は苛立った表情で光輝を睨んだ。
「どうして音海に危害を加えようとした?」
宇佐美は冷静さを取り戻したのか、今度は穏やかな声音で続けた。「花瓶の次は石膏像か? ガキじゃあるまいし、四階からものを落としたらどうなるか考えてみろ」
初めて聞く話だったせいか、光輝の顔には驚きの表情がよぎった。
花瓶が落下してきたとき、星吾はB棟の廊下で武本とすれ違ったことを思いだした。あのときの鋭い目つきを思い返せば、自然に悪い想像は働く。そのうえ、武本は長身だ。信号待ちをしていた母親の「背の高い男性」という目撃情報とも合致する。
武本は呆れた口調で言った。
「さっきから、なんの話をしているんですか? 花瓶なんて落としてない。この安っぽい絵を処分しようとしただけです」
光輝は、武本を見下ろしながら意外な言葉を口にした。
「好きな人を取られて嫌がらせするなんてダサいだろ。そんな程度の低い人間だから相手にされないんだよ。紗椰が選んだのは、お前じゃなくて星吾なんだ」
「驚いたよ。こいつと仲がいいんだな」
武本は非難めいた声で返した。
その言葉に苛立ったのか、光輝と武本の応酬が始まった。
「武本、お前は裕福な家庭で育ち、成績もいつもトップで、ほしいものはなんでも手に入る環境だった。そういう奴が人を好きになると厄介なんだ」
「幼稚園の頃からずっと紗椰を見守ってきた。大切に想ってきたんだ。紗椰の母親の葬儀の日だって、僕がそばにいて支えてきた」
「成績はいいくせに理解力がなさすぎて笑えるよ。紗椰が好きなら、告ってふられて諦めろよ。これ以上、星吾に関わるな」
「こんな最低な人間を好きになる紗椰も、嫌われ者の相手をして偽善者ぶっているお前もどうかしているよ」
その武本の言葉に、光輝の目尻が微かに痙攣した。
星吾は妙な胸騒ぎを覚えた。
もしかしたら、武本はなにか知っているのかもしれない。駅のホームで色白の男に投げた暴言、これまでの優しさに欠けた言動の数々……。もしそうならば、幼馴染を心配する気持ちは理解できる。武本が言うように、自分は誰かにかばってもらえるような人間ではないのだ。
星吾は覚悟を決めて、核心に迫る質問を投げた。
「信号待ちをしているとき、僕を車道に向けて突き飛ばしたのはあなたですか」
宇佐美と光輝は、驚いたらしく大きく目を見開いた。
武本は笑いながら答えた。
「本当に嫌われ者だな。そのとき死ねばよかったのに。僕はカスみたいな人間を殺して、自分の人生を台無しにするほど愚かじゃない。絵を切り裂いただけだ」
こちらをまっすぐ見据える目に、嘘は見当たらない。しばらく観察しても、武本は虚偽を口にしているようには見えなかった。
星吾は喉から絞りだすように声をだした。
「絵だけなら……もういいです」
宇佐美は一瞬物憂げな表情を浮かべた。
武本は拘束されている腕を振りほどくと、涼しい顔でドアに向かって歩きだした。
「おい待て、話はまだ終わってないぞ」宇佐美が怒鳴った。
振り返った武本は、不気味な笑みを浮かべながら言った。
「彼の言葉が聞こえなかったんですか。『もういい』そうですよ」
「芸術を軽視するなよ。絵を切り裂いたら器物損壊罪だ」
宇佐美が苦言を呈すると、武本は動揺する素振りも見せず言い返した。
「先生に無理やり取り押さえられたせいで服が少し破れました。これも器物損壊罪ですね。腕に痣ができているので傷害罪で告訴できるかもしれません。あぁそうだ。やってもいないことを疑われたので名誉毀損罪ですね。まずは父と相談して学長に報告するかどうか検討します」
武本は淀みなく言うと、勝ち誇った顔つきで微笑んだ。
宇佐美は真っ青な顔だったが、口もとに笑みを湛えている。
「大学生にもなって、パパに相談とは立派だな。俺を訴えたければ、やればいい。でも、もう二度と音海に危害を加えるな」
「ダメな子ほど可愛い、ってやつですか」
「本当にもういいです」
星吾は大事になるのを避けたくて声を上げた。
光輝は心情を察したのか、釘を刺した。
「お前が絵を切り裂いたのは事実だ。今日のことはお互い水に流そう」
「どっかの美術教員とは違って、吉田は頭が悪いくせに理解力があって助かるよ」
武本は嫌みを吐き捨てて教室を出ていった。
光輝は、星吾のそばに近寄ってくると真剣な面持ちで言った。
「もうすぐ講義の時間だから行くけど、高校の友だちに訊けば武本の住所がわかるから、なにかあったら俺に相談してよ」
星吾は「ありがとう」とつぶやくのが精一杯だった。
光輝は、宇佐美に軽く頭を下げてから教室をあとにした。
ドアがバタンと音を立てて閉まる。
騒々しかった室内がしんと静まり返った。
気まずい空気が漂っているのを感じて、星吾は少し顔を伏せた。
宇佐美から深い溜息がもれる。
「最近はずいぶん教員の立場が弱くなって、困ったもんだ」
「もしかして先生は……僕のために犯人を捜してくれていたんですか」
宇佐美は窓の外に目を向けた。
「大学側に相談してみたが、積極的に動く気はないようだった。だから時間があるときはちょくちょく美術室を見張っていたんだ。それより、どうして誰かに背中を押されたことを言わなかった?」
「虚勢を張っていたけれど……怖くなって警察に被害届をだしました。もっと早く動くべきだったと反省してます」
宇佐美は虚を衝かれたような顔をみせたが、すぐに難しい顔で腕を組んだ。
「お前がその気になってくれてよかった。車道に向けて突き飛ばした犯人は、まだ判明していないのか?」
「近くにいた人の目撃証言によれば、キャップを被った背の高い男で、口もとに髭があったそうです。でも、その人が犯人かどうかはわからなかったみたいで……。まだ犯人は特定されていません」
「カマをかけて武本を犯人呼ばわりしてみたが、あいつの態度からは真意は推し量れなかった」
「僕も……演じているようには見えませんでした。いくら黒川さんに好意があるからといって、彼は殺人に手を染めるような真似はしないと思います」
「俺がこの部屋に入ったとき、窓が閉まっていたところをみると、本当に絵を傷つけていただけかもしれない」
そこからふたりの格闘が始まったのだろう。
宇佐美はきつい口調で質した。
「もし武本が犯人じゃないなら、お前の命を狙っているのは誰だ。氷室の事件の関係者だと思うか?」
「子どもの頃、人を殺してしまった加害者の少年と殺された被害者の遺族が交流を深めるうち、互いに理解し合う日が来るという映画を観たんです。でも、現実には難しいと思いました。どんなに心をかよわせても、被害者遺族の怒りが消えることは永遠にないから……」
「お前は加害者じゃない」
宇佐美の声は怒りを孕んでいた。
――テメェが逃げだしたせいだからな。逃げたお前も同罪だ。
――救えたはずの命。
――あのときどうすべきだったのか、ゆっくり考え続けてほしい。
犯人、週刊誌、刑事の言葉がよみがえる。
見方によっては加害者だ。けれど、星吾は反論せず、重苦しい雰囲気を霧散したくて無理やり笑顔を作った。
「警察には連絡したので、先生はもう無茶なことはしないでください」
「心配しているのは俺だけじゃない」
星吾は意味が取れず、顎鬚を撫でている宇佐美を見つめた。
「さっきの学生も、お前のことを気にかけてくれているようだった」
「吉田とはコンビニのバイトで知り合ったんです。いい奴だとは思っていたけど、あそこまで親身になってくれるなんて予想外でした」
光輝が自分のことのように怒り、武本と対峙してくれた姿を思い返すと、嬉しさと同時に申し訳ない気持ちになる。過去の罪を隠して関係を継続するのは、とても卑怯な行為だからだ。
宇佐美は胸中を読み取ったかのように、軽い口調で言った。
「あまり気に病むな。すべての人間に過去を洗いざらい打ち明ける必要はない」
「僕の場合は、卑怯だけど……いずれバレる可能性があるから不安なんだと思います」
きっと、人間にとって『別れ』は貴重なものだ。別れてリセットして、また新しい人生を生きる。けれどネットが普及した現代、過去の過ちと決別するのはそう簡単ではない。
「嫁に相談したんだが、しばらく俺の家から大学に通わないか」
嫁? 宇佐美が結婚していたのに驚いたが、それ以上に、そこまで心配してくれているとは考えてもみなかった。
鼻の奥がつんとした。視界が潤み、星吾は目を伏せた。
武本の父親は、大手企業の重役。本当に学長に報告するのだろうか。そうなれば宇佐美に多大な負担を強いることになる。
家族に散々迷惑をかけ、今度は先生に甘えるのか――。
これ以上迷惑をかけたくなくて、冴島が殺害された事件については話せなかった。今の段階では、なんの関連性もなく、むやみに不安を煽っても意味はない。
星吾はできるだけ明るい声で言った。
「最近は危ない目にも遭っていないから大丈夫だと思います。でも……ありがとうございます」
宇佐美は小さく息を吐き、「紅茶でも飲まないか」と微笑んだ。
8
武本の一件は、心に深い傷を残した。
それなのに、美術室には紗椰の絵ばかりが増えていく。どうしても描くのをやめられない。
雨の夜の歩道、動物園、自然公園、彼女の笑顔をすべて記憶に焼きつけたくなる。記憶はいつだって曖昧なものだから、描いて残したいという衝動に駆られた。芽生えた感情が歪んで変化してしまう前に――。
最近、紗椰は美術室に姿を見せなくなった。
避けられているような気がして、漠とした不安が胸に宿っていた。
武本になにか忠告されたのだろうか。思い当たる原因はそれだけではなかった。星吾は緊張を悟られたくなくて、紗椰に対して冷たい態度を取ってしまうことも多く、嫌われてしまった可能性も捨てきれない。彼女が好意を示してくれても、素直に受け止められない自分がいたのだ。
美術室に続く長い廊下を歩いていると、強い虚しさに襲われた。
教卓に置いてあった花瓶やドライフラワーのラベンダーはもうない。幾度もデッサンした石膏像も割れてしまった。自分がそばにいると、相手を粉々に壊してしまうようで、どうしようもない哀しみが込み上げてくる。
見慣れたベージュのドアがやけに重く感じられた。
ゆっくり開けると、西日が窓から射し込み、室内を穏やかな光が照らしていた。
その光景を目にした瞬間、胸が熱くなると同時に奇妙な懐かしさを覚えた。魅入られたように、その場をしばらく動けなくなる。
星吾は逸る気持ちをどうにか抑え、静かにドアを閉めた。
画板に真新しい画用紙をダブルクリップで留める。そっとイーゼルに立てかけた。音を立てないように椅子を移動させ、そこにいる紗椰に目を向ける。
描きたい角度を決めてから椅子に腰を下ろし、強張っている手で鉛筆をつかんだ。
紗椰は窓際の席に座り、自分の腕を枕にして目を閉じている。
透き通るような白い肌が、西日に染められていた。
ふいに触れてみたいという感情が湧き上がってくる。髪、肩、腕、手、どこでもいい。その気持ちを抑えるように、ひたすら鉛筆を動かしていく。人の気持ちは移ろうものだが、絵の中に閉じ込めた感情は永遠に変わらない。だからこそ、こんなにも魅了されるのだ。
静寂に包まれた室内に、鉛筆が紙を擦る音だけが響いていた。
「光輝君から……シンちゃんのことを教えてもらった」
紗椰は上半身を起こすと小声で言った。
現実に引き戻され、手の動きを止めた。シンちゃんが、武本だと認識するまでに数秒かかった。
「子どもの頃から正義感が強くて優しかったから……シンちゃんがあんなひどいことをするなんて思わなかった」
なぜか星吾は「ひどいこと」という言葉が自分に向けられているような錯覚に陥った。本当にひどい行為をしたのは、ひどい生き方をしてきたのは誰なのだろう。
「彼の言動のすべてが間違っているわけじゃない」
思わず本音が口からこぼれた。
紗椰は意味がわからないという顔つきでこちらを眺めている。
星吾は、彼女の目をまっすぐ見返しながら言葉を吐きだした。
「僕は今まで思いやりのない生き方をしてきた。人の痛みにも気づかないふりをしていたんだ」
武本は的確に心の闇を見抜き、正直に発言しただけなのだ。
紗椰に近づきたいのに、拒むような行動しか取れない。なにがしたいのか自分でもわからなくなる。胸の中に怒りや哀しみが渦巻いていた。
紗椰の戸惑ったような表情が母親の顔と重なり、余計に心が塞いでしまう。
息子が卑怯者だと知ったとき、母はどう思っただろう。その真実を知り得ても、親だから息子を受け入れなければならなかった。この世に誕生させたのは、紛れもなく両親だからだ。けれど、母と紗椰は違う。そんな義務は彼女にはない。
「ラベンダーの花言葉を知ってる?」紗椰は唐突に訊いた。
「……知らない」
「期待と疑惑」
彼女は弱々しい笑みを浮かべて言葉を継いだ。「違うかもしれないのにね。花言葉なんて誰かが勝手につけただけで、花自身は『それは違うよ』と必死に訴えているかもしれない」
星吾が黙したままでいると、紗椰は不思議な言葉を口にした。
「薬になれたらいいのにね」
「薬?」
「音海君はいつもひとりで葛藤してる。すごく苦しそうで……無理なのはわかっているけど、痛みを和らげてあげたい、救ってあげたいって思うときがある。きっと、光輝君も同じだと思う」
星吾も電車の中で見た紗椰の泣き顔が忘れられなかった。あのとき、彼女を孤独から救いたいと思った。そんな力なんてないのに――。
「自分さえ救えない人間が……誰かを救うことはできないよ」
星吾がそう言うと、彼女は誤解したのか気まずそうに目を伏せた。
「そうだよね。思い上がったことを言ってしまって……」
紗椰は泣きだしそうな表情で立ち上がった。
「僕には……人を好きになる権利がないんだ」
強い焦燥感に駆られ、咄嗟に本音が口からこぼれた。
好きな人を目の前に、頼りない言葉しか言えないのが情けなくて、苦しくて、本当の気持ちさえ見失ってしまいそうになる。
紗椰は緊張を孕んだ声で訊いた。
「権利? どうしてそんなことを思うの」
氷室がどこかで、人を見殺しにしたお前が誰かを大切にできるのか、と嘲笑っているような気がする。お前は必ず同じ過ちを繰り返す。また逃げだすだけだ――。
「嬉しいとか幸せとか、そういう感情が心の中に芽生えると、なにか悪いことをしている気分になって……息苦しくて、申し訳ない気持ちになって……だから、僕には権利がないから……」
星吾は続く言葉を呑み込んだ。伏せている顔を上げる勇気が持てない。黙したまま、床の木目を見つめていた。
心が満たされるほど、失うことの恐怖に駆られ、愛おしい人を怖いと感じてしまう。
室内に重苦しい沈黙が降り積もっていく。押し潰されないように、どうにか呼吸を繰り返し、拳を固く握りしめた。
「その権利はどうしたら……誰に頼めば手に入る? 世界中の人の承認? それとも神様? そんなのなくてもいいから……」
紗椰の声はひどく震えていた。「権利はなくてもいい……私は音海君と一緒にいたい」
顔を上げると、彼女の瞳に涙が浮かんでいる。星吾の視界も滲んだ。
白く細い指が小刻みに震えているのに気づいたとき、星吾は衝動的に立ち上がり、彼女を抱きしめていた。
自尊心、憎悪、後悔、不安、恐怖、そんな感情がゆっくり溶けていく。ただ彼女のそばにいたかった。目の前の現実が過去に潰され、消えてなくならないように腕に力を込めた。
誰かに想ってもらうことは、こんなにも安らぐものなのだろうか。人と心をかよわせられる瞬間があることを今なら信じられる。胸中にあたたかい光が差すと、心をきつく縛っていた鎖がゆっくり解けていくのを感じた。圧迫されていた心に血が巡り、ゆっくり色を取り戻す。
抱くはずのない気持ちがあふれてくる。ずっと曖昧で不確かなものを愛するのが怖かった。それなのに、どうしようもないほど人を信じたくなる。
あのときの刑事に、被害者の遺族に教えてもらいたい。
僕に人を好きになる権利はありますか――。
本心を言葉にした途端、不幸を引き寄せてしまいそうで芽生えた希望が滲んでしまう。
答えなんてもうでているのに、自分の素直な気持ちに寄り添えない。一緒にいれば、彼女に危険が及ぶのではないかと危惧の念を抱いてしまうからだ。
紗椰は戸惑っている心情を察したのか、少し距離を置いてから気遣うように言った。
「答えは急がない。でも……」
声には隠しきれない緊張が滲み出ていた。「夏休み明けの十月一日……私の誕生日なの。一緒に『新緑美術館』に行きたい」
大学から電車で三十分くらいの場所に、自然豊かな森がある。その奥に『新緑美術館』はあった。三角屋根、真っ白な外壁、アーチ状の大きな扉。緑の中に浮かびあがるように佇んでいる美術館。星吾も前から行ってみたかった場所だった。
けれど、十月一日という日付が不安に拍車をかける。
それは、氷室の事件が起きた日だったのだ。
忘却は許さないという神からの啓示なのだろうか――。
どんな運命が待っていたとしても、今できることはひとつしかない。月明かりに照らされた一本道を進んでいく。
彼女の誕生日に過去の罪をすべて告白しよう。
気象庁は梅雨明けの発表をし、本格的な夏を迎えた。
大学の前期試験が終了し、夏休みに入ると多くの学生が帰省した。けれど、星吾はバイトに励みながら、空いている時間は美術室に通いつめた。
車道に向かって突き飛ばされて以来、最近は身の危険を感じるような出来事には遭遇していなかった。これまでは特別な目的もなく生きてきたが、死の危機に直面して初めて、もう一度向き合いたいものがあることに改めて気づかされた。
大きなリュックから新聞紙やジャージを取りだす。近くにある机には、金槌、木炭、油絵具、パレット、油つぼ、ペインティングナイフなどが並んでいた。
油絵具以外は、中学のときに美術部に入部してから買い揃えたものだ。
教室の隅には、フレーム状に組んだ大きな木枠が壁に立てかけてある。それを持ってくると、床の上に広がっている白い布の上に置いた。木枠と布を固定するため、四辺に釘を打ち込む。緩みなく張り終えると、それをイーゼルに立てかけた。
正面に椅子を置き、まっさらなキャンバスと向き合う。
室内は深い静寂に閉ざされていた。
まだ名も知らない相手と見つめ合っているような独特の緊張感が生まれる。なにをモチーフに描くのか、どのような色彩をぶつけてくるのか、相手も身構えているようだった。
心地よい緊張感と同時に、あらゆる世界を創りだせるという高揚感を覚えた。
心の中にある気持ちを整理するためでも、混乱した感情を鎮めるためでもなく、こんなにも真剣に絵と向き合うのは久しぶりだった。
純粋に絵が好きだった頃の気持ちがよみがえってくる。けれど、木炭を持つ手がいっこうに動きだしてくれない。銃を構えているかのように手は強張り、彫像のごとく固まっている。
これほど表現したいという欲求に駆られているのに、キャンバスに触れるのが怖くてしかたなかった。手にあるのは木炭ではなく、なにもかもを撃ち抜いてしまう凶器に思えてくる。
描けばなにかを傷つけてしまうような錯覚に襲われた。
純粋に絵を描けないのは、過度に期待する気持ちが隠れているからだ。
絵を利用して、抱えている苦しみや哀しみを理解してほしいという承認欲求が芽生えている。だから戸惑いが生じるのだ。
強い慙愧の念を覚えた。焦燥が胸を焼く。
思うように描けなかったときの絶望を想像するだけで、描きたい景色が傾いて崩れていく。たとえ描けたとしても、相手に伝わらなければ意味はない。
けれど、言葉にできないなら絵で表現するしかないのだ。
モチーフは、すべて頭の中にある。目を閉じて幾度も見続けてきた光景を瞼の裏に焼きつけていく。息苦しくて深呼吸を繰り返した。
ゆっくり瞼を開けると、キャンバスに木炭を走らせる。指先に熱がこもった。
痛々しいほど継ぎ接ぎだらけでもかまわない。痛みと哀しみを縫い合わせるように描写していく。途中から、まるで自己主張するかのように絵がキャンバスに浮かび上がってくる。それをなぞるように木炭を動かし、一ミリもずれないように息吹く絵と呼吸を合わせ、呼応するように描き上げていく。
下描きした絵に指を使って明暗を作り、キャンバスから離れて全体を眺め、不要な部分を消し、また近づき、納得がいくまで描き直して修正し続ける。
先刻から絶望と希望が交互に胸にあらわれては姿を消していく。
描ききれなかったときの絶望、完成したときの希望――。
昼時はとっくに過ぎていたが、いっこうに腹は減らない。すべての欲は描きたいという欲求に勝てずに消失してしまう。
空が夜闇に染まる頃、やっと下描きが完成した。
指が微かに痺れ、利き腕がぐったり疲れ切っていた。壁の時計に視線を向けると、あと三十分で閉門時間だった。
木炭が溶けだしてこないようにフィキサチーフで下描きを定着させてから、急いでコンビニのバイトへ向かった。
紗椰は夏休みの間は実家を離れ、岐阜の祖父母の家に行くと言っていた。会えないのは少し寂しかったが、バイト先には光輝がいる。彼もバイトを優先していたので、普段よりも勤務時間が重なる日が多かった。
美術室の一件以来、光輝は、また危ない目に遭うのではないかと気にかけてくれている。けれど、武本からの嫌がらせは一度きりで終わった。それ以外にも脅威に晒される出来事は起きていない。まだ油断はできないが、星吾はあまり心配をかけたくなくて、バイト中はできるだけ明るく振る舞う努力をした。
絵が完成するまで、このまま穏やかな生活を送れることを願い続ける日々だった。
(#11に続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
