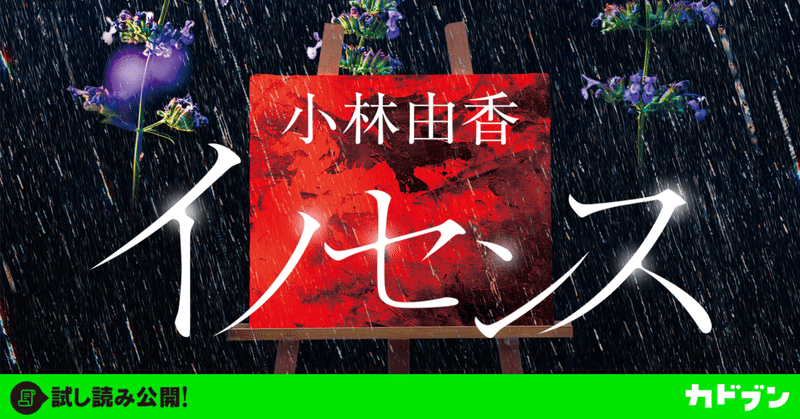
この国の自殺者数は年間二万人を超える。自殺なんて特別なことではない/小林由香『イノセンス』発売前特別試し読み#3
連載中から賛否両論の嵐。
小林由香『イノセンス』期間限定「ほぼ全文試し読み!」
カドブンノベル一挙掲載、WEB文芸マガジン「カドブン」で連載中から大きな反響を読んでいる話題作『イノセンス』。
10月1日の発売に先駆けて、このたびnote上でほぼ全文試し読みを行います。
あなたは、主人公の取った行動は許されると思いますか?
2020年最大の問題作をお見逃しなく!
一瞬耳を疑った。
そんなふうに思われていたとは知らず、不安と情けなさが募ってくる。
星吾は思いきって、芽生えた疑問を投げた。
「さっき無差別殺傷事件について話していましたが……それは、いつか僕もやりかねないと思ったからですか」
「お前には人を殺すことはできない。理不尽な悲劇に見舞われても、ひとりで静かに歯を食いしばって耐えるタイプだ」
そんなに強くない。咄嗟に、文庫本に書かれていた脅迫文やデッサン画を汚されたことを相談しようかと思ったが、喉もとまで出かかった甘えを懸命に呑み込んだ。その前にどうしても確認したいことがあったのだ。
「先生は本気で……」
あまり思いつめた声にならないように気をつけて言葉を継いだ。「本気で殺したいほど恨んでいる人はいますか」
宇佐美は引き出しに救急箱をしまいながら、必死に笑いを堪えているようだった。
「お前の質問はいつも衝撃的で心が弾むよ。そんなに恵まれた人生じゃない。俺にだって殺したいほど恨んでいる奴はいるさ」
笑っている表情とは違い、そう答える声には怒りに満ちた迫力があり、胸が騒いだ。
思わず棚に並んでいる『罪の果て』に目がいってしまう。
室内の空気が重くなるのを感じたが、星吾は問わずにはいられなかった。
「恨んでいる相手に脅迫文とか送って、嫌がらせをしたいと思いますか」
「嫌がらせなんて軽いものでは気がすまない。本気で息の根を止めてやりたいよ」
「それなら……どうして実行しないんですか」
「大切な人がいるからだ」
宇佐美は気まずそうに窓の外に視線を移してから続けた。「その人は意志が強いが、ずいぶん脆い。だから品行方正に生きて、ずっとそばにいて支えてやらないとならない。まぁ、俺の任務ってとこだな」
なんとなく相手は女性のような気がして、星吾は気恥ずかしくなり軽い口調で返した。
「案外ロマンチストなんですね」
「今頃気づいたのか? 長い付き合いだろ」
「まだ一年くらいじゃないですか」
「人間なんて、あっという間に死んじまう生き物だ。一年の付き合いは驚くほど長いよ」
宇佐美はファイルを開くと、おもむろに紙を取りだした。「一応、俺は美術サークルの顧問だからな」
渡された紙には『学生アートコンクール』と書いてある。指先が冷たくなっていく。
宇佐美はしばらく黙考するように間を取ってから、柔らかい口調で言った。
「コンクールに応募してみないか?」
星吾は首を振りながら答えた。
「コンクールにだせるような絵は描けないから……」
「どうして?」
「デッサンはできるけど、カドミウムレッドとか……まだ使えない色があって……」
赤系統の油絵具を混ぜていると手が震え、息苦しくなってしまうのだ。一度経験してから、もう怖くて油絵具に触れることさえ難しくなった。
宇佐美はマグカップを用意すると、紅茶のティーバッグを入れ、ポットのお湯を注ぎながら尋ねた。
「それが原因で美大ではなく、心理学を学べる大学を選んだのか?」
「違います。知りたいから……」
「お前が恨んでいる人間のことか」
星吾はなにも答えず、渡された紅茶を受け取った。
以前、宇佐美は学内で噂話を耳にしたようで、氷室の事件について尋ねてきた。責めるような口調ではなかったのに、愚かな過去を知られた恥と哀しみが込み上げてきて、星吾は鼻の奥が熱くなり、震える唇を噛みしめたのを覚えている。
事件の詳細を話したくなければ言わなくてもいい、と声をかけてくれたが、我慢の限界だった。バイトを始めれば、すぐに嫌がらせが始まり、次々辞める羽目になった。先生たちの耳に入るほど、大学でも噂になっているのだ。もう孤独に耐えられなかった。祖父を亡くし、寄る辺なかった星吾にとって、唯一本音を吐露できる相手は宇佐美しかいない。
すべて聞き終えた宇佐美は「お前だけじゃない。この世に罪のない人間なんていない。自分だけは罪はないと言い切れる奴は、気づかないふりがうまいだけだ」と小声で言った。
星吾の胸はわななき視界が滲んだ。今までは、卑怯者、最低なクズだと罵られてきた。それなのに、罪のない人間なんていない、と言ってくれたのだ。一緒に過ごす時間が増えるほど、宇佐美は愛情深い人だと気づかされる。実際、真実を知ってからも、いつもとなんら変わらない態度で接してくれた。
星吾が紅茶をぼんやり見つめていると、宇佐美は穏やかな声で忠告した。
「どれだけ学んでも、どんなに努力しても死んだ人間の真の気持ちは永遠にわからない」
「それでも……考えてしまうんです」
「考えるのをやめろとは言わない。だが、現実を喰われるな」
正面から見る人懐っこい表情とは違い、宇佐美の横顔はどこか厳しい顔つきに映った。
「常軌を逸するほどなにかに執着すれば、バランスが悪くなる。バランスを崩せば、いずれ立てなくなり、現実を喰われる日がくるぞ。心を深く蝕まれてしまう前に、もう見えない敵と闘うな」
星吾は重い空気を変えたくて、できるだけ明るい声で返した。
「先生が言うと妙に説得力がありますね」
宇佐美は自分の動かない指に視線を落とし、自嘲気味に笑った。
3
激しい疲労感が心身を覆っていた。
つり革をしっかり握りしめていなければ、バランスを崩してしまいそうになる。
星吾は電車に揺られながら、目の前に座っている二十代と思われる女性をなんの気なしに眺めた。彼女は細長い指を素早く動かし、熱心にスマホをいじっている。指揮者のタクトのように、柑橘色に塗られた爪が俊敏に動く。親指のネイルが少し剥がれていた。
指の動かない生活は、想像するよりもずっと不便なはずだ。
先生が殺したいほど恨んでいる相手とは誰だろう。
宇佐美にそんな人物がいるとは思わなかった。きっと、彼はなにかの被害者なのだ。
文庫本に記されていた脅迫文のことを相談できなかったのは、自分が加害者に近い人間だからだ。
氷室の事件以来、なにかが欠けている人間や完全ではない者と一緒にいると心が落ち着くようになった。けれど、そんな感情を他人には話せない。自分は歪んだ人間だと証明しているようなものだからだ。
電車に乗ってから、ずっと目を伏せている。車窓が視界に入るのが怖くてしかたなかった。どれだけ警戒しても、顔を上げると夜景が目の端に映ってしまう。瞼を固く閉じた。
逃げ場のない車内で亡者なんか見たくない――。
大学周辺は家賃相場が高いため、星吾は大学の最寄り駅から八駅ほど離れた場所にアパートを借りている。公共の乗り物は苦手だったが、これからも通学で電車を利用しなければならない。いつまでも逃げ続けるわけにはいかないのだ。
腹を決めて、顔を上げると車窓を睨んだ。
そこには亡者の姿はなく、明かりが灯った町並みに重なるように、憔悴した自分の顔がぼんやり映っているだけだった。
胸を撫でおろすと、星吾は肩で息をしているのに気づいた。弱冷房車ではないのに、つり革を持つ手や首筋がじっとり汗ばんでいる。
柔軟剤だろうか、どこからか甘い匂いが漂ってきた。唐突に白百合の花束が脳裏に浮かび、ホームで会った女の姿が頭の中にあらわれる。
今朝、同じ駅にいたということは近くに住んでいるのだろうか。なんの根拠もないのに、あの女と脅迫文が関連しているような気がして、余計に素性が知りたくなる。
ふいに寒気がして周囲に目を配った。
先ほどから誰かに観察されているような気がしたのだ。そう思い込むと、どんどん心のバランスが悪くなり、気分が沈んでいく。
突然、目の前の女性が勢いよく立ち上がった。少し身を引くと、彼女は閉まり始めたドアをすり抜けてホームに駆け降りていく。まるで猫のような身のこなしだった。
星吾は空いた席に腰を下ろし、乗客をゆっくり見回した。やはり誰かの視線を感じるが、特に不審な人物は見当たらなかった。
斜め前に座っている男は乱れた髪も気にせず、口を開けて眠っている。安心しきって寝ている姿が羨ましくてたまらなかった。
背もたれに身体を預けたとき、耳の奥で怒りに満ちた女の声がよみがえってきた。
――今日の夜、あの人が自殺したらどうする?
余計なことを言ったのはわかっている。けれど、色白の男に「どうして俺の邪魔をした」と訊かれた瞬間、苛立ちが抑えられなくなった。
電車に飛び込もうとした男を見殺しにした事実が世間に知れ渡れば、また罵倒される。そう思った刹那、星吾は怒鳴りつけてやりたい衝動に駆られ、辛辣な言葉を吐き捨てていた。
頭では荒唐無稽な考えだとわかっているのに、この世の不幸はすべて自分とつながっているような気がしてしまう。
この国の自殺者数は年間二万人を超える。自殺なんて特別なことではないが、その現場を目撃するのは珍しい。あんな状況に居合わせてしまった不運を呪いたくなる。
見慣れた駅名標が目に飛び込んできて、慌ててホームに駆け降りた。
気づけば、電車は最寄り駅に到着していた。
ホームの時計に目を向けると、もう二十一時を少し過ぎている。人混みを避け、しばらくホームに立ち尽くしていた。なぜか足が改札に向かってくれない。焦りに似た複雑な感情がじわじわと押し寄せてくる。
小さく溜息をつくと、星吾はホームの端から端まで歩き、色白の男がいないか確認してみた。なにをやっているのだろうという呆れと、どこにも彼の姿がないことに安堵する気持ちが綯い交ぜになっていた。
誰もいないベンチに腰を下ろし、鞄からスマホを取りだして電車の運行情報を確認してみる。検索する指先の感覚が鈍く、動きがぎこちなくなってしまう。
事故による遅延情報はないようだ。けれど、いまだに女の予言めいた言葉が頭の中を這いまわり、どうしても掻き消せないでいた。
ゆっくり立ち上がると、重い足取りでホームを歩き始めた。身体がだるい。
時間をかけて長い階段を上がり、改札前のコンコースに出た。改札の窓口には、年配の男性駅員がひとりいる。彼は目の前を通過する乗客たちに「ありがとうございました」と声をかけていた。特に変わった様子は見受けられない。
きっと、特別な事件は起きていないはずだ。
先刻から逐一確認し、安心している自分に嫌気が差す。なにを怯えているのだろう。
相手が悪いと思わなければ、うまく生きていけない。けれど、それをすれば生きていくのが嫌になる。いつだって心には相反する感情が巣くっていた。
完全に冷酷非道な人間になれたら、どれだけ楽だろう。
自分の中にある良心が邪魔で、どう折り合いをつければいいのかわからなくなる。
駅を出てから、すぐに空を振り仰いだ。
陰鬱な気分に拍車をかけるように、空は厚い雨雲に覆われている。今年は梅雨の時季に入っても本降りの雨にはならず、小雨の日ばかりだった。
テレビでやっていた天気予報によれば、台風三号が接近しているらしい。気象予報士は、梅雨入り後の台風は大雨を降らせると解説していた。
駅前の横断歩道を渡り、大通り沿いの道をまっすぐ進んでいく。しばらく行くと強い光を放つコンビニの看板が目に飛び込んできた。
星吾は思わず息を呑んだ。どっと汗が噴きだし、鼓動が速まっていく。
バイトが入っているのをすっかり忘れていたのだ。すぐに腕時計を確認すると、もう二十分の遅刻だった。
辞めさせられたら大変なことになる。
これまで誹謗中傷のメールや苦情の電話のせいで、幾度もバイトを辞めざるを得なくなった。また同じ目に遭うのではないかと怯えていたが、今のところ問題なく過ごせている。コンビニのバイトを始めてから五ヵ月が過ぎようとしていた。今度はできるだけ長く続けたい。
星吾は全速力で駆けだし、コンビニの車が四台ほど駐車できるスペースを抜け、建物の裏手にあるドアの前に立った。支給されたICカードをスキャナーに掲げてから、鉄製の重いドアを開け、事務所兼倉庫になっているバックヤードに駆け込んだ。
バックヤードに入ると、タイムカードに時刻を記録しようとして手を止めた。
どういうことだろう。
三十分前に出勤していることになっていた。
タイムカードの名前を確認すると、『音海星吾』と書いてある。他人のものではない。
星吾と交替するはずの男子高生のバイトは、すでに退勤していた。
彼がタイムカードを押してくれたのだろうか――。
状況を呑み込めないまま、ロッカーを開けて制服に着替えた。着替えている最中も不思議でしかたなかった。
急いで店内に入ると、デザートの棚の前にブランドバッグを持った若い女性がひとり、壁面の弁当コーナーに三十代くらいの男性がふたりいた。
ふたつあるレジカウンターの片方には、バイト仲間の吉田光輝がいる。
「重役出勤、お疲れさまです」
星吾が隣のレジカウンターに入ると、光輝はとびきりの笑顔でそう言った。
地毛だというライトブラウンの柔らかそうな髪。瞳の色素は薄く、肌理の細かい頬にそばかすが散っていた。大きなフレームのデミ柄の眼鏡をかけている。いつも柔和な笑顔を絶やさないせいか、人に優しげな印象を与えた。
光輝は、星吾と同い歳で大学の学部も専攻も一緒だった。けれど、彼は一年浪人しているので学年はひとつ下だ。
光輝はどこか誇らしげな顔で口を開いた。
「いつも十五分前には来ているから、『今日は遅刻かもしれない』と思ったんだ」
その言葉を聞いて先ほどまであった疑問は解消したが、妙な違和感が残った。
「どうして……タイムカードを押してくれたの?」
星吾は訊かずにいられなかった。
労働時間の虚偽申告は、不正に加担した者も処罰の対象になるはずだ。人の善意に見えるものの裏には、いつも悪意が潜んでいる気がしてしまう。仮に悪意がなくても誰かの善意に基づく行動は、悪い未来につながっているようで恐ろしくなるのだ。
まるであの日のように――。
光輝は不満そうな口調で言った。
「だって研修のとき、三回遅刻したらクビって言われたじゃん。店長はルーズなくせに、遅刻にはやたら厳しいからね」
「別に……クビになってもかまわないよ」
他人からの好意をうまく受け止められず、星吾は心にもないことを口走った。
「寂しいこと言わないで。辞められたら俺が困る」
「どうして」
「星吾のことが大好きだから」
しばらく彼と見つめ合ったが、なんの感情もわかない。
光輝は誰に対しても素直に好意を示す。世界中の生き物を愛している博愛主義者なのだ。以前、店の外で飼い主を待っていた犬に「世界でいちばんか可愛い犬だな」と言っているのを耳にしたことがある。他人が近づくと警戒して吠えるのに、光輝だけには妙に懐いていた。
これ以上不毛な会話を続けたくなくて、星吾はタバコの品出しを始めた。
この店は繁盛しているコンビニとは違い、売上はあまりよくない。けれど、店長に焦る気配はまったくなかった。本部組織のあるフランチャイズチェーンではなく、単独店なのをいいことに、彼は自由気ままに店を経営しているのだ。
最近は二十四時間営業の見直しが叫ばれているが、深夜営業をやめる気はないようだった。「夜に開いてないコンビニなんて、コンビニじゃない」というのが店長の持論だ。稼ぎたい星吾にとっては都合がよかった。
バイト仲間の噂によれば、店長は地主の息子で、父親から譲り受けたマンションの一階をコンビニにし、賃貸マンションのオーナー兼コンビニ経営をしているようだ。
店長が保有しているマンションは、1DKが二十四部屋あるという。光輝の実家は隣町にあるのに、なぜか彼はこのマンションの最上階でひとり暮らしをしている。以前、パートの女性が「実家が近いのに贅沢ねぇ」とやっかんでいたのを耳にしたことがあった。
「俺ね、子どもの頃から不思議な力があるんだ。信じてくれる?」
先ほどから忙しいふりをしているのに、光輝はかまわず話しかけてくる。
三ヵ月も一緒に働いているうちに、こういう唐突な会話には慣れた。彼は誰に対しても脈絡のない話をしてくるのだ。
「信じるよ」星吾は即答した。
肯定しなければ、「どうして信じないのか」と永遠に終わらない質問を繰り返されるので、素直に認めるほうが楽なのだ。
「信じてくれてありがとう。ときどき人が色に見えるんだ。純粋で明るい子は黄色。他人と距離を置きたいと思っている人は黒。人の世話が好きなタイプは紫とかね。色が濃い場合は、その特性がより強くなる。ちなみに星吾は、かなり濃い青だね」
光輝はぼんやりした声で続けた。「青は……後悔と哀しみの色」
思わず動揺を隠せず、タバコを並べていた手を止めた。
普通の人間なら軽口を叩いて終われるはずの会話なのに、怖気のようなざわめきが胸に広がっていく。
光輝に不思議な能力があるはずがない。今だって嘘だと言わんばかりに唇に笑みを刻んでいる。それなのに、後ろ暗い過去があるせいか、大学で変な噂を耳にしたのではないかと訝しく思ってしまう。それともコンビニに嫌がらせの電話やメールが届いたのだろうか――。
星吾は目の端で彼の様子を窺った。
光輝は「いらっしゃいませ!」と何事もなかったかのように明るい声を張り上げ、デザートを見ていた女性客のレジ対応を始めた。慣れた手つきで商品のバーコードにハンドスキャナーを当てていく。その姿に不穏なものは感じられない。なにか悪意を潜めているようにも見えなかった。
バイトのシフトは、昼はパートの主婦、夕方からは高校生、時給のいい夜は大学生が入ることが多かった。星吾は翌日の午前中に講義がないときは、深夜勤務を希望した。
光輝がバイトとして雇われたのは、三ヵ月前。最初は覚えることが多く、少し戸惑っている様子だったが、今は店長や常連客に気に入られている。誰に対しても屈託のない笑顔をふりまくので、年配の客からも「孫みたいに可愛い」と言われていた。
入店音が鳴り響く。赤茶色の髪をした若者が入ってくると、光輝は「いらっしゃいませ!」と大声を張り上げた。
万引き防止のため、入ってきた客の顔を見ながら大きな声で挨拶をしてください、そう研修のときに教わったが、自分がやられたくないせいか、星吾はそれが苦手だった。
今日は珍しく客の入りが多い。レジ業務をこなしながら、弁当を温めて袋に入れる作業をひたすら繰り返す。忙しい日は余計なことを考えないで済むから好都合だった。
客が少なくなる時間帯になると、店長から頼まれていた話題の商品のPOPを用意し、検品と品出し作業を終わらせた。
台風が近づいているせいか、二十二時を過ぎた頃には、客足がぱったり途絶えた。静かな店内に、購買意欲を削ぐようなヒーリング・ミュージックが流れている。
作業を終えて戻ると、隣のレジカウンターにいる光輝は一冊の本を睨みつけていた。本の表紙には『女心が手に取るように分かる!』と書いてある。
星吾が嫌な予感を覚えながら椅子に座ると、光輝は待ちかまえていたかのように早口でまくし立てた。
「ひどいと思わないか? 女心を知りたいから何度も熟読したのに、昨日、俺は好きな人を鬼のように怒らせたんだ。この本は犬が水着を着て海に行くくらい無意味な内容だったんだよ」
著者の名前が『もてるもてお』というところがすでに怪しいのに、なぜ買ったのだろう。
星吾は本についての会話を続けるのが面倒になり、話題を変えた。
「喧嘩の原因は?」
「すげぇ冷たい声で『あなたとは目指す方向や夢が違う』って言われたんだ。根本は同じなのに、どうして方向がずれるんだろう」
方向がずれるのは根本が違うからだと思い至ったが、敢えて口にはしなかった。
光輝は大きな溜息をついてから言った。
「目指す方向や夢か……星吾の将来の夢はなに?」
軽い気持ちで尋ねられたのはわかっているが、胸は微かに波立った。
光輝の真剣な眼差しに耐えられず、星吾は慎重に言葉を探したが、口からこぼれたのは素直な気持ちだった。
「夢は……普通に生活して、普通に会社員になって、生きて……普通に死にたい」
一瞬、光輝が物憂げな表情をしたので、星吾は慌てて明るい声で訊き返した。
「そっちの将来の夢は?」
「なんで俺の名前、いつも『そっち』なんだろう」
そう言うと彼は、肩を落としてわざと落ち込んでいるような態度を示した。
人を名前で呼ばなくなって久しい。呼ぶ必要もなかった。友だちなんてひとりもいなくなったのだから――。
黙ったまま俯いている星吾の顔を、光輝は下から覗き込んでくる。
「俺は『そっち』っていう名前でもいいけどね。星吾はプライベートな話はまったくしてくれないからバイト仲間としてはちょっと寂しいな、って思うときもあるんだよね」
「僕にはなにもないから」
「なにもないって?」
「大学行って、バイトして、アパートに帰って飯食って眠るだけ。特別な話なんてひとつもない」
星吾はレジの横に置いてある籠の中から飴を取り、小さな袋を破って口の中に入れた。キャンペーンでやっているハズレくじの景品だった。リンゴの風味がほのかに口に広がる。
光輝は気の毒そうに顔を曇らせながら言った。
「なんかそれって、生きているのに死んでいるみたいだよね」
悪意がないのはわかっているのに、心は哀しみに震えた。
実際、死んだように生きてきた。なるべく人と関わりを持たず、自分の気持ちや他人の感情を見て見ぬふりをし、誰にも深く介入しないようにしてきた。人と深く関われば、いずれ心を傷つけられ、当たり前のように関係は破綻していく。そんな経験をするくらいなら孤独感に苛まれたとしても、最初からひとりでいるほうがマシだった。
「でも俺は……星吾が羨ましいな」
光輝は意外な言葉を口にしながら、ストレッチをするように上半身を反らした。
「どうして……なにが羨ましいの?」
「同年代の友だちとは違って、気張ってないところが好きなんだ」
光輝の穏やかな笑顔を見たとき、胸に妙な懐かしさとせつなさが込み上げてきた。
心が安らぐようなあたたかい笑顔――。
まるで幼馴染に再会したような、どこかノスタルジックな気持ちが胸に押し寄せてくる。子どもの頃、無邪気な笑顔で「兄ちゃん」と駆け寄ってきた弟の俊樹に似ているのかもしれない。
光輝は淡々とした口調で言った。
「自分にはなにもない、そうはっきり言えるのは、すごく強い人間だからだよ。たまに、俺は臆病だから誰かとつるんでいる気がするんだ。でも星吾はいつもひとりで、不確かな将来の夢とか語って自分をデカく見せたりしないし、そういうところが俺は気に入っている」
突然、不快な音が耳に飛び込んでくる。
心拍数が急速に上がるのを感じながら、星吾はガラス窓に視線を向けた。大粒の激しい雨が窓を叩いている。
「台風が近づいているみたいだね」
そうつぶやいた光輝は、どこか虚ろな表情だった。
台風と雨が揃えば、嫌でもあの事件を思いだす。気分はどこまでも沈み、体調まで悪くなってくるようだった。
星吾は雨から気をそらしたくて、大して気にも留めていないことを口にした。
「喧嘩した彼女とは、もう仲直りしたの?」
「まだ彼女ではないんだ。強力なライバルがいて、どう考えても俺に勝ち目はない。それなのに、どうしても諦めきれない。つまり片思いだね。会って仲直りしたかったけど、今日はバイトだから終電に間に合わなくて会いに行けないし」
星吾の勤務時間は早朝までだったが、光輝のバイト終わりは二十三時だ。バイトの終了時間が、ちょうど終電の時刻というのはタイミングが悪い。
「さっきのお返しに、タイムカードの虚偽申告に加担するよ」
星吾がそう言うと、光輝は急に瞳を輝かせた。
「マジで? 不正とか死ぬほど嫌いなタイプかと思ってた」
正確に言うなら、借りが苦手なだけだ。
光輝は近寄ってくると、選挙運動中の候補者のように「吉田光輝、仲直りできるように全力でがんばります!」と、星吾の両手を強く握りしめてくる。
人の善意を疑わず素直に受け取り、心の底から嬉しそうに微笑んでいる姿が眩しかった。
「今夜、どうしても彼女と会って話したいことがあったんだ。やっぱり、星吾は優しいよ」
その言葉に少しだけ気が引けた。優しさから出たものではないからだ。
――生きていてもなんの役にも立たない卑怯者なのに。
ネットに書き込まれた言葉がいまだに瞼の裏に焼きついている。
いつか過去の愚行を知られる日が来るかと思うと、不安ではなく恐怖が胸に兆した。
かつてのバイト仲間たちは、過去の出来事を聞き知ると、親しみのこもった態度を一変させた。露骨に嫌悪感をあらわす者、憐れみながら離れていく者、必死になって築き上げた関係は、いつだって泡沫のごとく消えてしまう。
答えはわかりきっているのに、なぜか同じ質問ばかりが頭の中を駆け巡っていた。
薄汚い過去を聞き知ったとき、光輝もかつてのバイト仲間と同じように離れていくだろうか――。
ひとりで過ごす時間が多くなった星吾は、いつしか冷静に周りを観察するようになった。そのせいか、人が覆い隠そうとしている本質が嫌というほど透けて見えてしまうときがある。人間関係なんて欲望のぶつけ合いだ。親しくなればなるほど、それは増していく。
それなのに、光輝には利己的な面がほとんど見当たらない。どれだけ批判的な目で観察しても、悪い部分を見つけるのが難しかった。
制服を脱いでバックヤードから鞄を持ってくると、光輝は「ごめん」と手刀を切った。
「いいよ。台風で客もほとんど来ないと思うから」
「本当にありがとう」
光輝は礼を言ってから歩を進めると、自動ドアが開く手前で足を止めた。振り返った彼の顔は、いつもと変わらず笑顔だった。
「星吾ってさ、雨が嫌いなの? 雨の日はいつも怯えたような顔しているから気になったんだ」
その鋭い指摘に言葉を失った。
鋭敏な洞察力に驚かされたが、振り返れば、彼はこれまでも人の心の奥底を見抜いていることがあった。以前、具合の悪くなった客にいち早く気づき、声をかけていた。一見したところ、なんの問題もなさそうに思えたが、客は数時間前からひどい頭痛に苦しめられていたようだ。
まさか、本当に人が色に見えるのだろうか――。
光輝は神妙な面持ちで口を開いた。
「なにもないわけじゃない。きっと星吾にもいろいろあるんだよ。だからなにかあったら遠慮しないで相談してよね」
そう言い残すと、いつもの無邪気な笑顔を見せてから、傘も差さずに店の外に駆けだした。土砂降りの雨の中を走っていく。まるで少年のような後ろ姿だった。なぜか、いつまでもその姿を目にしていたいという奇妙な感覚に包まれた。
昔は雨が降り続く夜は一睡もできなかった。
そんな日は決まってベッドの中に潜り込み、頭の血管が浮き出るほど奥歯を噛みしめて泣き続けた。涙が流れていた頃は、まだマトモな人間だったのかもしれない。あの頃に比べれば、今は哀しみの感情が極端に乏しくなっている。
静寂に包まれた店内に入店音が響き、客がひとり入ってきた。
深夜番のときは、ときどき酔っ払いに絡まれて鬱陶しい思いもする。けれど、雨の夜は眠れないベッドで朝を待つより、バイト先にいたほうが精神的にも経済的にもプラスになった。
店内を物色していた客は、素早く缶ビールと弁当を買って出ていった。
時計の針が零時を過ぎると、台風のせいか客が来店する様子はなく、静かな時間が過ぎていく。みんな普段よりも仕事を早く切り上げたのかもしれない。そんなことをぼんやり考えていると、店の外になにか気配を感じた。すぐに視線を向けたが、目につくものは激しい雨だけで誰もいなかった。
気のせいだと思い直し、店内に視線を戻すとまた人の気配がする。
もう一度、外に目を転じた瞬間、背に怖気が走った。
真っ赤な血に染まった手。ひとりの男が、血まみれの両手を自動ドアにペタリと貼りつけ、店内を覗いている。
氷室は左目を細め、血走った右目をきょろきょろと動かしてなにかを探していた。開いた口から血の糸が滴る。彼はドアに多量の血を吐きだした。
「助けてほしいなんて頼んでない……勝手なことをしたのはあんたじゃないか」
星吾は思わず声を張り上げた。
足首に生暖かい感触が走る。視線を落とすと、真っ赤な手が足首をつかんでいた。右手、左手と這いのぼってくる。濃厚な腐敗臭が立ち込め、嘔気を覚えた。慌てて手で口を覆った。
星吾は叫び声と共に上半身を起こした。
全身に鳥肌が立っていた。
レジカウンターで荒い呼吸を繰り返す。額から流れ落ちてくる汗をそのままに、しばらく凍りついたように固まっていた。
現実に起きたことなのか、夢なのか判然としない。それほどリアルだった。
ゆっくり首を巡らして店内を確認したあと、思いきって自動ドアに目を向けた。
どこにも氷室の姿はない。それでもまだ肩の力が抜けず、足もとを確認する。血まみれの手も血痕もなかった。それなのに生々しい感触だけが残っていた。
大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫――。
きっと、うたた寝をしてしまったのだろう。これは間違いなく夢だ、そう自身に言い聞かせて気持ちを落ち着かせようとするも、鼓動は少しも鎮まってくれない。
あの日、犯人から投げられた言葉が、なぜか氷室の声音で耳に迫ってくる。
――逃げたお前も同罪だ。
頭の中に『救えたはずの命』という言葉が繰り返し流れてきて息苦しくなる。
気づけば、双眸から雫がこぼれ落ちていた。
もう涙なんて出ないと思っていたのに、雨粒のように頬を伝っていく。
星吾は放心状態のまま、しばらく動けずにいた。震える手で顔を拭いながら幾度もガラス窓や自動ドアに目を向けた。恐怖に支配されているせいで、完全に落ち着きを取り戻すことはできなかった。
(#4に続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
