
作品と再会するということ
作品と再会するということ。
かつて読んだ小説をもう一度読むということ。
まだ読んだことない作品との新鮮な出会いへ期待を寄せる機会に比べると、同じ作品を繰り返し読み重ねる贅沢さを実際に味わう機会は多くないかもしれません。
中高で生徒と学ぶことが幸福にも仕事となった私は、およそ3年か6年に一度、定番教材に再会することになります。例えば、『走れメロス』『羅生門』『こころ』。その都度、作品たちは新しい顔を見せてくれます。正確には、生徒たちが思いもよらない細部への疑問や違和感を投げかけることで、こちらの凝り固まったものの見方がほぐされていきます。「メロスは何匹の羊を飼っていたか」という問いは本文のどこを探しても「正解」は見つかりませんが、全く考えようとも思っていなかったことを考えさせられることで、作品世界を覗く新たな窓が与えられます。
作品の解釈の「正解」を作者の意図に求めることへの批判を「作者の死」と呼びます。それと呼応する様に「読者の誕生」という言葉が浮き上がってきます。作品と読者の間で立ち上がる意味にこそ価値があるという考えに私も共感します。ただし、それは読者が身勝手に妄想することを肯定しているわけではありません。作品から遠く離れて、際限なく開かれた解釈は、その開かれとは逆説的に己の世界に閉じこもり、他者と共有できる意味づけを失ってしまいます。あくまで作品の言葉から離れずに、一方で作者の意図や権威的な読みに囚われることなく解釈を創造すること。作品にも読者にも開かれている、半開きの対話とでも言うべき姿勢を大切にしたいのです。
読書は基本的にはごく個人的な行為です。しかし、同じ作品を複数人でそれも異なった背景を持った読者で読み合う贅沢な機会を得たとすれば(教室はまさにそのような場です)、読者の間でも半開きの対話が生じることになります。私の立場からすれば、再会する作品は同じだけれど、その都度、読み合うメンバーは異なっていて、当然そこで立ち上がってくる解釈も異なるという体験をしています。
かつて大学院で文学を専修していた際に、ひとりの教授は「君たちはこれからカフカに出会える。それが羨ましい。」と熱のこもった声で若い読者である私たちを文学の世界に招き入れました。いま、自身が教員となり、これから生徒たちが『羅生門』とどのようにドラマティックに出会えるのか、その演出をいかにデザインできるか頭を使っています。なるほど確かに、世の名作にこれから新鮮な驚きと共に出会える経験は羨ましいです。「大人」にとってもうそれは体の中の頼りない痕跡をたぐりよせ、ぼんやりと掴むことでしか思い出せない感覚であるからです。
ですが、作品と一定の時間を経て再会することで改めて新しい読みを発見する醍醐味があることに、ここでは光を当ててみたいのです。
それは生徒たちにはまだ、経験し得ぬ、時の流れが言葉に重みを与える瞬間です。とはいえ、実のところ最近の教科書には小学校で習った物語文を中学の教科書でも掲載しているものもあります。しかし、その学習目的を見る限りでは再読の価値に触れているわけではありません。ぜひ、発達段階の違いや、所属するコミュニティの違いが読みにどう影響を与えるのかを体感する教材があっても良いのではないかと本気で思っています。

つい先月、引越しをしました。
それはつまり、本棚で眠っている全ての本を手に取る作業と言い換えても良いでしょう。
擦れた背表紙や付箋の書き込みを目にするだけでも、その作品と再会した気分を味わいます。あるいは本を通してそれを読んだ過去の自分と再会します。大学近くにある、階下に本屋を抱える喫茶店で、先輩の真似ごとをしてハイライトのメンソールに火をつけながら、コーヒー一杯で何時間も居座って読書に耽っていました。同じように毎日そこへ通って司法試験の勉強をしていた髭面のお兄さんは今頃何をしているだろう。一度も話したことはなかったけれど、勝手に仲間意識を持って自分も頑張ねばと勇気づけていました。その店の閉店を知らされた時、私を含め経済的な支えにならないような客を優しく受け止めすぎたのではないか、と勝手に痛みを感じたりもしました。
とにかく、そんな再会に思いを馳せているとどれだけ時間が経っても引越しの準備は進みません。
その中でも思い入れのある背表紙に指が触れました。星野智幸『俺俺』、修士論文で中心的な題材として選んだ作品でした。
先の教授の言葉が蘇ります。十年経った今ならば、再読の喜びを発見できるかもしれないと思いました。しかし、親しかった友人ほど久しぶりの再会に緊張するように、たやすくページをめくり始めることはできず、とにかく段ボールへ放り込んでしまいました。
それでも、十年ぶりに読んでみようと思ったのは、引越し先の下北沢で荷解きの疲れから逃れるように本屋B&Bを訪れた時でした。かつてB&Bは別の場所にあったのですが、修士論文を書き終えた当時、運良く星野さんと接点を持つことができ、このB&Bで催された新刊トークイベントに参加しました。イベント後にお声かけして研究者としての道を卒業し教員になることを伝えると、星野さんは「これで自由に読めるね」と笑いました。その言葉に対してどのように反応したかは残念ながら記憶に残っていません。しかし、星野さんの言葉そのものは自分のなかで蓄積されていて、B&Bにはその後も何度も足を運んでいたのですが、なぜかこのタイミングで、ふと思い出しました。あれから十年が経って、文学研究という良くも悪くも狭い窓から離れて別の窓から「自由に読める」のか試したくなりました。
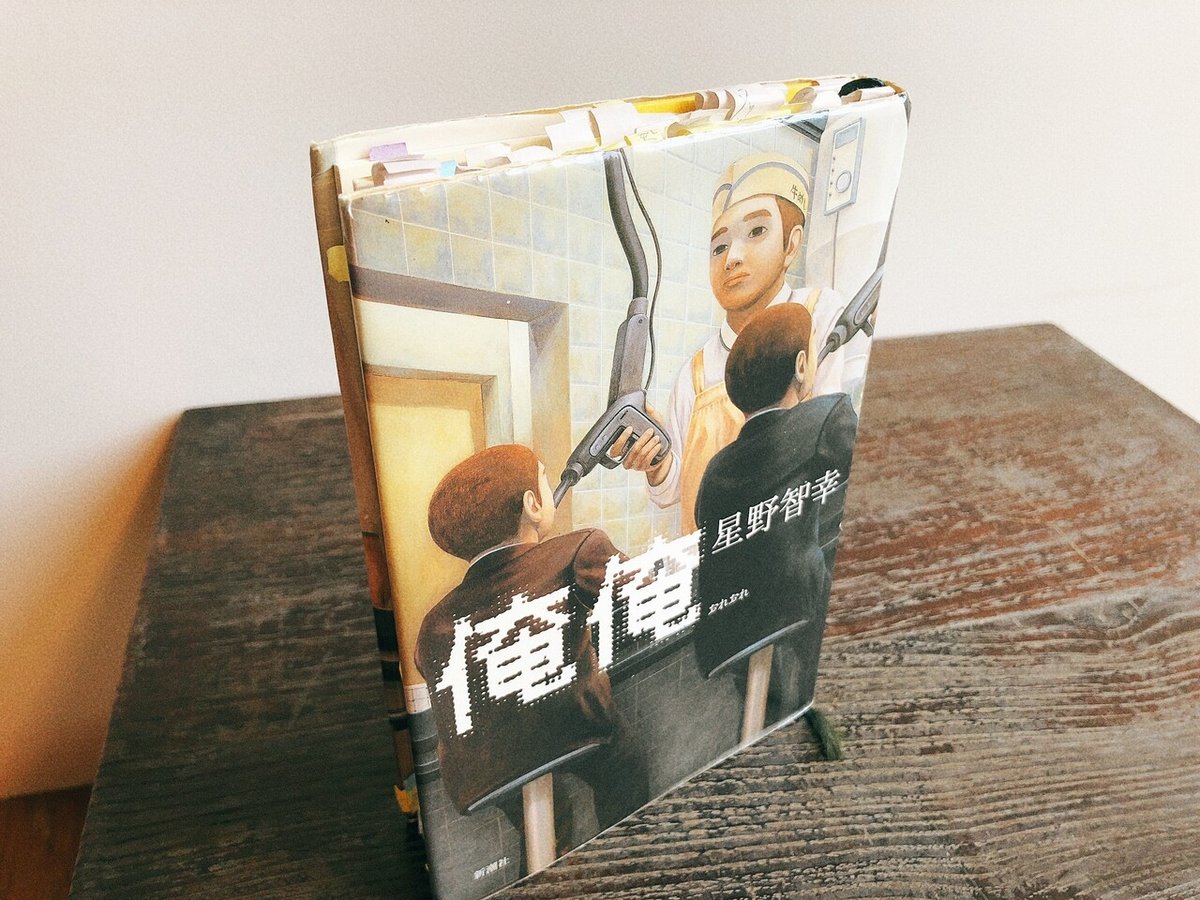
読み始めると、記憶が刺激されて少し先の展開が断片的に、しかし鮮明に思い出されました。どこにしまわれていたのだろうかと不思議な記憶の箱。逆にこんなにも輪郭のはっきりした記憶が不可抗力に引き出されることに驚きました。自分の中には再び開ける機会がないために無意識下で消えていく記憶の箱がいくつもあるのだろうな、と作品を離れて感慨に耽りました。
全てのページにメモや付箋が残っていて、十年前の自分の解釈の痕跡も同時にたどっていくことになります。「語る私と語られる私の距離」「バンヴェニストの人称性」「記号の一致」、引かれている線に納得するものもあれば、意図を思い出せない付箋の色分け(そもそも意図はなかったのかもしれない)。前半では、そういった当時の解釈を再現しながら読み進めるのが心地よかったです。思考の過程をなぞることで、当時の自分がどんな窓を磨き上げてそこから作品を覗いていたか生々しい感触が戻りました。しかし、だんだんとそれは焦りに変わり始めました。
かつての仲間と久しぶりに出会い、思い出話に花が咲き、若き日の瑞々しさをやや誇張ぎみに取り戻すものの、その帰り道、言い難い虚無感に襲われる、あの感覚と同じでした。「あれから自分はなにをしていたのだろうか」という問いが胸を突き刺してくるのです。過去の自分に出会えたものの、その読みから自由になれない今の自分の不甲斐なさに焦りました。
それでも、と後半を読み進めながら考えます。社会的な存在としては未熟だった過去の自分を実態以上に小さく捉えてしまっていたことに気づきました。これは大きな発見でした。十年の間に新しい窓から世界を覗き、今まで見たことのなかった風景をいくつも目にしてきた自覚があった故に、過去の自分の作品解釈から逃れられないことが皮肉で、ただそのつまずきを愛おしく感じました。あるいち側面において過去の自分が未熟だったのは間違いありません。ですが、そこに目を向けるばかりに別の側面、むしろ今の自分が失いかけている側面を見落としていました。過去の自分を「他者」として捉え直し、わかったつもりという沼から足を引っこ抜いて対話できたのは、作品を媒介としていたからでした。内省の機会としての読書。その作品をいま自分がどう受け取っているかをさらに見つめる読み。作品からやや距離が離れるが故に、今まで自分に許してこなかった読み方でした。
あるいは、と作品の終章にさしかかり思い至ります。過去の自分を否定しなければ今の自分を肯定できないとどこかで考えていたのかもしれないと。
自分は過去の自分より成長しているというフィクションにすがることで、はりぼての自信を得なければ自分の輪郭が崩れてしまうような不安を抱えていたように思えます。時間が経てば成長しているという神話をうっかり生きていたのです。随分と遠回りをしてそのことに気づきました。過去の成果に拘泥するわけではなく、過去を矮小化して捉えるわけでもなく、今の自分を意味づけられるようになりたい。
それを作品=フィクションを通して実感しました。
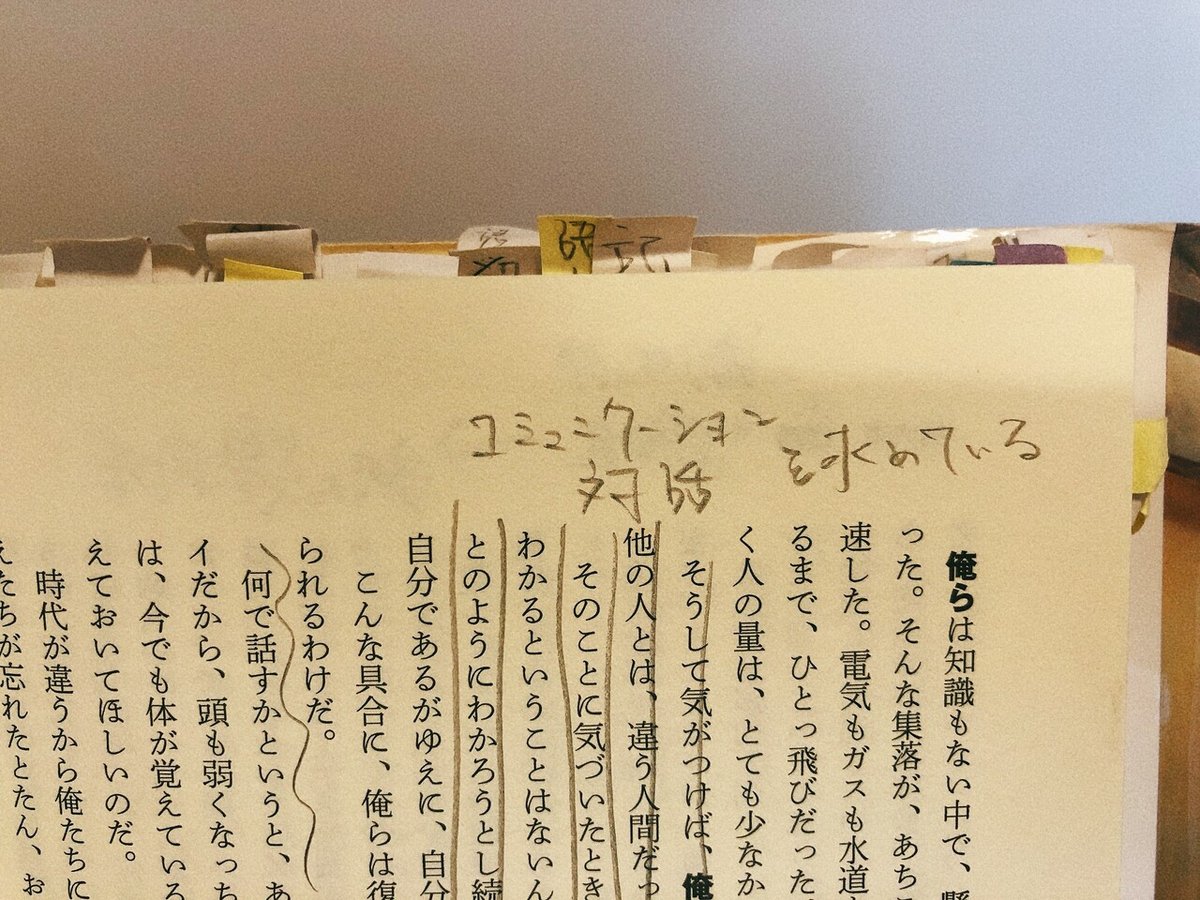
自由に読むということは、いいかげんに、考えなしに、適当に、読んでも責められない、気楽であるということではありませんでした。
星野さんはどのようなことを期待して「これで自由に読めるね」とおっしゃったのでしょう。
自由に読むためには技術がいる。
思い込みでは自由にはなれない。
『俺俺』の主人公は自己嫌悪と他者の排除に溺れた結果、極限の孤独状態に陥ります。そして最後に小さな集落に迎えいられる場面で物語は閉じます。
「俺と他の人とは、違う人間だった。そのことに気づいたとき、俺はそこはかとなく寂しかった。もう、誰かを自分のことのようにわかると言う事はないんだなぁ、と感傷的になった。いや、と俺は考え直す。相手を自分のことのようにわかろうとし続けていれば、たまにはわかるのだ。その程度で良いのだ。全て同じ自分であるがゆえに、自分が消えてしまうことの方が、ずっと恐ろしかったはずじゃないか。」
わかりあえないことを前提とした対話の歯車がかみあい回り始める瞬間です。むしろ、私たちの「自己」は他者との関係性のなかで構成されていくのです。
もし過去の自分と対話することにある限界を感じたのなら、流れ行く生活のその都度、寄り添う新しい読み手と対話して、角度を変えた風景をのぞかせてもらうことができる。そういう共同体を持ち続けることが、何より作品との再会をより豊かなものにしてくれるのかもしれません。だから今日、初めて妻にこの本を勧めてみました。
私はどれほど「自由に読む」ことができるようになったのか。
それを確かめたくて、今日もまた本棚の前に立っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
