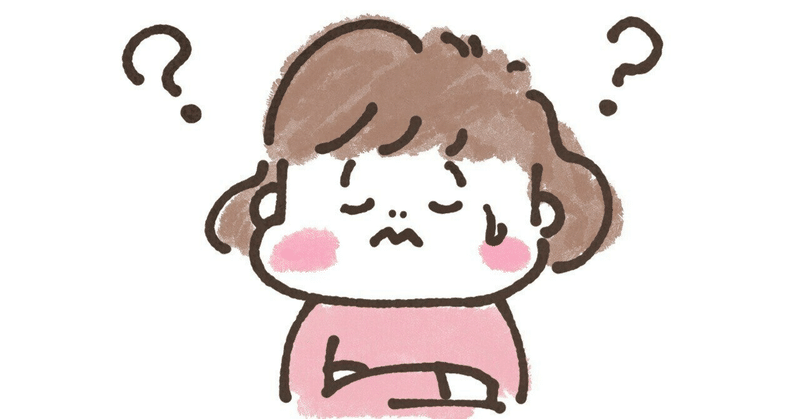
小学生に宿題は必要か
結論から言うと…「必要ありません」
しかし、「毎日、学ぶ習慣」や「疑問に思ったことを追究する力」は必要です。また、学校の授業で「学んだこと」を定着させ、自分の力(学力)とするためには、学校以外での「反復練習」や「繰り返しの学習」は必要です。
けれども、それは「先生が言うから」ではなく「どうして必要なのか納得して」行うから意味があるのです。
では、先生は「宿題」について、「人から言われるからやるもの」ではなく「自分のために納得してやるもの」ということを教えているのか、ということが問題です。
小学校の担任の先生は、「昭和の時代」から毎日のように「宿題」を出します。その「昭和の時代」に「子供」だった人が先生になって、また、なんの疑いもなく「宿題」を出します。そして、その時の「子供」が先生になって…「宿題」について、時代が変わっても、家庭の環境が変わっても、社会が変わっても、相変わらず、「同じこと」が繰り返されています。
そもそも、先生は子供のころ「学校教育」の中で、トップにいたわけではないにしても、少なくても「勉強がわからない」「学校教育の落ちこぼれ」「学校が嫌い」ではないのです。だから、「宿題」も「言われるまま」にやっていたとしても、「忘れずに」取り組んだだろうし、大きな「疑問」も持たずに学校教育を終え、「先生」になったのです。
学校現場では、「前年踏襲」が好まれます。運動会の「日程」も、「運営方法」も、持久走大会も、音楽会も、前年度とほとんど変わりなく、日にちと曜日を変えて、職員会議に提案され、大した「議論」も「検討」もなされないまま、実施されます。それでも、たいして「ご意見」をいただかない、「滞りなく実施される」のは、子供たちは「何が正しいのか」わからないし保護者は、自分が子供の時の「運営」「企画」と変わらないから、違和感を持たないのです。けれども、このように「前年踏襲」を繰り返すと、今、踏襲している「前年」は、「令和」からはるか昔の「昭和」なのです。
コロナが流行して、この「前年踏襲」ができなくなり、真剣に行事の「在り方」や「運営」について考える機会が到来しました。それでも、教員は「変化」を嫌います。
「宿題」についても、「昭和」の時代の「子供たちを取りまく環境」(塾・習い事・親の経済力など)は「令和」の時代には大きく変化しています。また、子供たちに「求められる学力」も変化しています。だから、「教員」も「保護者」も「やらされる宿題」「とりあえずやっておけばいい宿題」の考え方を改めるべきです。
最初に書いたように、「教員」が「なぜ学ばなければならないのか」「今、学ばなければ自分の人生にどれだけのデメリットが生じるのか」を、たとえ1年生であっても、発達の段階に応じて「理解できるように話す」「理解させる」「納得させる」ことができる「指導力」が必要です。
誤解を恐れずに言うと、「計算ドリル」「漢字の練習」「授業で終わらなかった練習問題」などを「宿題」にして、次の日「提出させ」「確認して」「やってこなかったことを責める」「期日に提出することは社会に出てから必要な能力だ」などと言っているとしたら、そんなことは「教員免許」を持たない「ちょっと賢い大学生」でもできることです。
教育の「プロ」だったら、子供たちに「なぜ学ぶのか」「学び事の意味」を教えることができる「指導力」が必要です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
