関裕美ソロ曲「楽園」の解釈、黛冬優子のネットミーム、公式と二次創作
ツイッターで「楽園」を解釈した話
この前、関裕美のソロ曲「楽園」についてのことをツイッターに流しました。それは2つあり、一つは↓

もう一つは↓
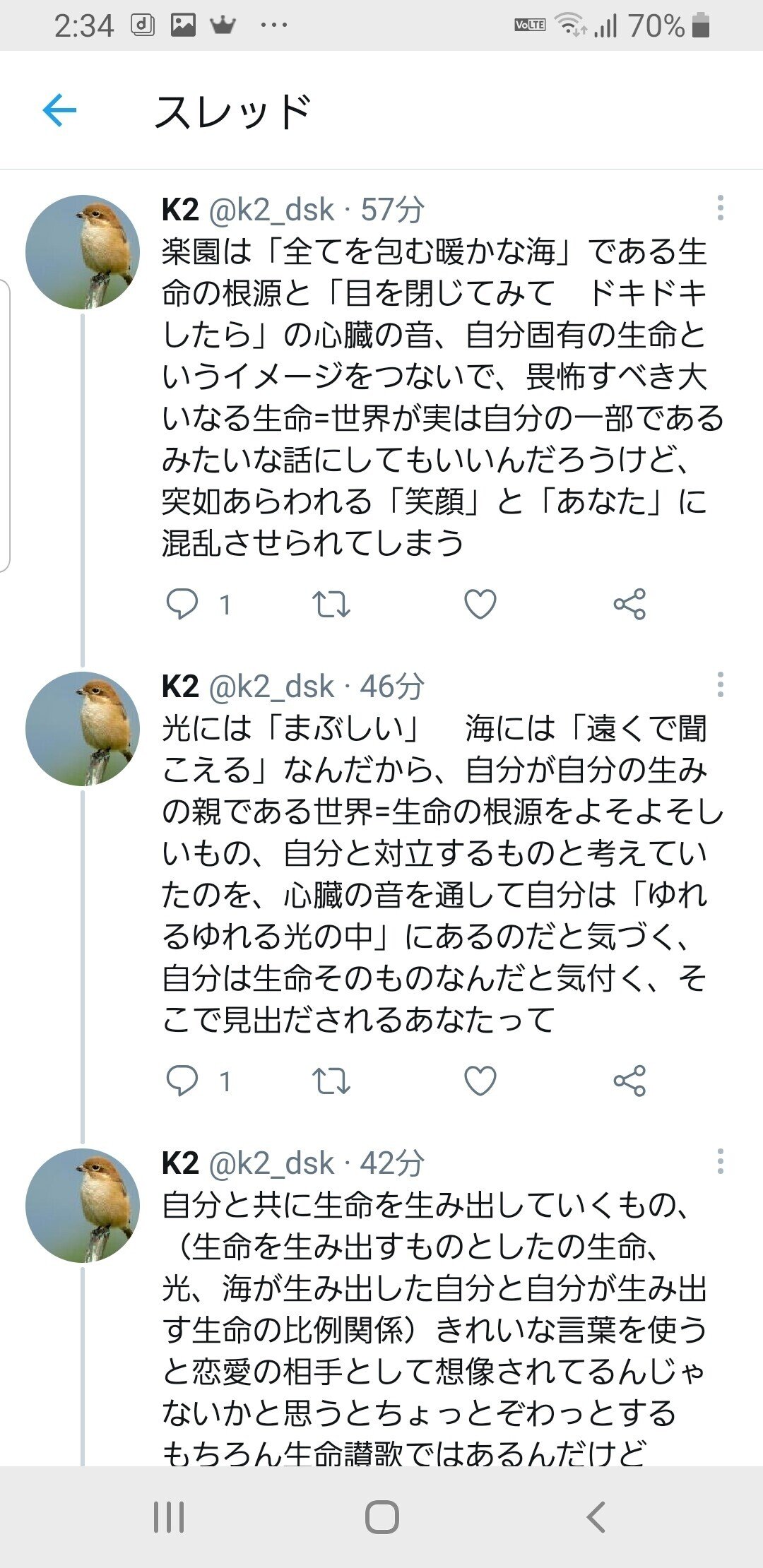

拡散のされかたに差がついているのを見て取れます(以下二つを上、下と呼びわけます)。上の方が広がったのはなぜなのか気になります。
この差の原因を考えたのですが、主観的には、下の方が与えられた意味を正確に読み取ろうという気分で行っていました。
下解釈では、曲冒頭から得られた生命のイメージを手がかりとした一貫した読みを提示しようと試みています(下手とかは置いておいて)。この読みからすると、「私らしく笑えるかな」とは、世界=生命の中で自分が固有の生命として楽しんでいけるかまだ不安な気持ちを表現していることになります。あるいは、「特別なこと何も出来ないよ」とつないで、世界の中での自身の固有性=特別性を引き受けることはまだ不安だけれど、「たくさんの笑顔 見せてあげるね あなたに向けて」と、少なくともあなたと共にあることについては不安がないという語りかけと読んでもよいかもしれません。
実際「特別なこと」とは何かや「あなた」とは誰のことかについて、歌詞だけから意味を確定することは困難です。上の方の解釈では、「特別なこと」を、自分が自分の中に見いだせる自分の特別さ、「あなた」をステージの向こうのファンの人達というように意味を付与しています。もひ「特別なこと」が「私らしく笑えるかな」を受けているとして、「笑えるかな」と「たくさんの笑顔」が同じ笑うという行為であるのに前者が「特別なこと」ではないなら、「私らしく」が「特別」の根拠であり、そうあることは出来ないけれど、「あなたに」「たくさん」笑顔を向けることは可能だ、という宣言となります。笑顔が喜びを生むものかどうかは完全に付け加えられた意味で、もしそれが正しかったとしても、ファンに喜びを与えることが自分固有の価値であるという「特別」に近いものと読むのは、ほとんど矛盾にも見えます。読みを進めるなら、この解釈自体を解釈して、人間が自分に固有のものを見出だしていくプロセスを読みとっているものだ、最初は固有と思っていなかったものが固有なものだと気づかれていくのだ、とさらに意味付与することになります。最早、歌詞に託して自分の言いたいことを言っている文になりかけています。
もちろん下のように海や光を生命のイメージと読むのが正当という訳ではなく、それを上のようにアイドルのステージやアイドルの誕生の隠喩なんだと読んではいけないという理由はないわけです。でも、比較の問題として、上の伸びたものの方が読解というより主観的解釈に近く、二次創作になりかけているとは言えると思います。そして、そちらが広く拡散されたのです。言い換えると、面白いようです。一応テキストに沿おうとしてはいるけれど、自分の主観や願望がかなり投影されたものになっていて、でもその方が創造的で面白い営みと見られています。
面白い解釈とは何かの話
ここから、面白い解釈とは何かという話ができると思います。下の読みでやっているのは、なるべく与えられたテキストだけからイメージを汲み取って解釈を与えていこうとしていますが、上の読みでは、関裕美がアイドルであること、アイドルの価値とは人に笑顔を与えられることなのだといった文脈が付与されています。解釈の面白さとは、この外から持ってこられる文脈の固有性やそれを与えることのふさわしさ、そしてそれが元のテキストと整合性が取れているかどうかといったことになるのでしょう。特に、アイドルとはどんな存在であるべきかといった価値観の問題については個人の主観が色濃く表れてきますので、自分が生きてきた歴史のようなものが解釈の面白さの源泉の一つとなってくる、言い換えると二次創作は自己表現にもなっていると言うことができます。
黛冬優子の話
ところで、黛冬優子さんについてのノート記事が今日出てました。
このノートの主張は大きく二つで①公式の一部といえるBRUTUSでの冬優子の紹介文に「腹黒」や「オタサ―の姫」という言葉が使われ、それが冬優子にそぐわず不適切である②公式は二次創作イメージを逆輸入すべきでない の二点に集約できます。「あんたはここでふゆと死ぬのよ」というネットミームについては、おそらく②の補強のために持ち出された論点で、本筋ではないのですが、筆者の思いがとても入っています。記事タイトルが「僕は冬優子に生きてほしい」となっていることなどから見られるように、公式の冬優子像が損なわれてしまうことと、「あんたは~」のネットミームの中で冬優子が死んでしまうことが重なっているのでしょう。私としては①には賛同できますが②は賛同できないと思いました。以下理由を書いていきます。
①について、まずBRUTUSが公式テキストの一部であることには同意したものとして話を進めます。その上で「腹黒」「オタサ―の姫」が何故不適切かという話をすると、この表現が公式テキストと矛盾するものだからです。記事内にあるように、シャニマスのゲームテキストからは冬優子が腹黒であることもオタサ―の姫であることも読み取れず、むしろその逆に両方ともそうでないと言えるからです。テキストの規範とは、文章が文章として意味をとれるか、イメージを作れるかにあって、ある生き物が猫でありかつ猫でないことがあり得ないのと同様冬優子が腹黒でありかつ腹黒でないことはあり得ないことだからです。注意して欲しいのは、冬優子が実際に腹黒ではないから不適切と考えた訳ではなく、公式テキスト全体のなかで両立不能な性質を両立するものであるようになってしまうという形式上の問題から不適切と判断していることです。現実世界と類似した法則の成り立った世界をイメージさせようとするテキストが、現実にあり得ないような矛盾を許容する世界のイメージを作ってしまってはいけないからです。
これを踏まえた上で②についてですが、公式イメージと両立不能なものは受け入れるべきでないとは言えますが、両立可能なものは未確定の状態にとどまっていると見るしかなく、禁止を完全に要求することは不可能と思います。
筆者はネットミーム「あんたは~」が許せないという思いがずっと積み重なっていたせいで、このイメージが公式に輸入される可能性を危惧しここまで強い主張をしたのだと思います。しかしこのネットミームがなぜ流行ったかというと、状況によっては言いそうだからだというキャラクターイメージが共有されたからでしょう。おおよそ、強い敵を前にして仲間を守るために言われる台詞として共有されていて、仲間思いの冬優子のイメージとも合致していたのです。このネットミームについては、キャラクターイメージの中に取り入れても深刻な矛盾は起こらないと考えられているのです。なのて、ここでこのネットミームを持ちだすのは全体の説得力を落としてしまうと考えられます。
キャラクターイメージの話
そもそもキャラクターイメージとは、読者が独自に公式テキストと向き合いながら作り上げていくもので、完全な「正解」を求めるのにはおそらく無理があります。そんなイメージ群の中でおかしいものとしては、矛盾しているなど世界の法則に違反しイメージを作ることができないはずなのにイメージだと主張しているようなものくらいでしょう。上で関裕美のソロ曲「楽園」を解釈しながら、意味の濃淡や取捨選択は本当に主観が入ってきてどうしても自分独自のものがあらわれてきてしまうと思いました。キャラクター解釈でいうなら、そのキャラクターの構成要素a.b.c.……について、まずどれを選択するか、そして選び取った要素はどれが一番強いか、あるシチュエーションの中で両立しがたくなったときどれが選ばれるかなど、個人でイメージは全然違って来るだろうと思われます。それをどう作るかについては個人に委ねられるところで、公式に規制を求めることはできないというしかないところでしょう。この生まれてくる差異こそがシャニマスを楽しむ文化を形作っているのでしょうから。
終わりに
公式テキストの規範はイメージを作り出すことができるかであって、このテキストから読み手は自由にイメージを作り、個性的な解釈が面白さの源泉になってくるので、テキストだけからイメージを作ろうとするのではなく外から文脈や意味を持ち込もうという個人の感想のお話でした。では。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
