
事業の解像度を上げる「保護猫1匹の年収を30万円にする」
neco-noteの2年目は、所属猫1匹の年収を30万円にする。
これが、僕が目指す"保護猫活動の自続性"の第一歩になると仮定しました。
保護猫1匹にかかるお金は、個体によってまちまち。「これだけあれば確実に大丈夫」という金額を算出できないのが現状です。¥5,000/月(¥60,000/年)で済むコもいれば、¥390,000/月の治療が必要なコもいる。
救う命を選ぶことは難しいけれど、費用と頭数などのバランスを鑑みると、¥300,000/年を稼ぐ猫が3~5匹いれば救える命の数が増える(と答える団体が多い)、と提携保護団体へのヒヤリングでわかってきました。
2年目の目標はそこへ置き、中長期的な目標は人間の所得を基準に定めてみました。
150万円(確定申告が必要)
130万円(扶養が外れる)
100万円(およそ5匹の世話代が賄える)
50万円(およそ2匹の世話代が賄える)
30万円(およそ1匹の世話代が賄える)←2年目の目標
この金額に、記載した以上の妥当性はないけれど、保護猫活動という予測できない現場を支えるには、粗くてもいいので指標が必要だと私は考えています。
neco-noteは、支援者であるバディが増えれば増えるほどお給料は増える仕組みなので、30万円を稼ぐのに必要なバディ数は320人。1匹の猫への支援と考えると、なかなか途方もない数です…。
ローンチ1年を迎えようとしている現在、多くの方が会員登録をしています。それを踏まえると取るべき戦略は大きく2つで、アップセルとクロスセルです。
【アップセル】
アップセルとは、顧客が現在利用している商品やサービスよりも高い商材を提案することで、客単価を向上する施策です。企業がアップセルを実現できれば、新規顧客や新たな販路を開拓しなくても収益を増加させられます。
【クロスセル】
クロスセルとは、顧客が購入しようとする商品やサービスとは違う商材を提案し、客単価の向上につなげる施策です。アップセルは現在利用している商品やサービスとは違うものに乗り換えてもらう施策であることに対し、クロスセルは追加商材を購入してもらう施策だといえます。
neco-noteの場合に置き換えると、
アップセル:無料会員の有料化(バディ化)、バディの推し猫増加
クロスセル:アセットを活用した他業界市場への進出
となります。
アップセル戦略_直感的な推し活体験を届ける
この戦略を実現する3つの戦術として、
u-1.購入フローの簡略化(ワンプラン化、購入手続きの見直し)
u-2.推し猫との出会いを演出(猫個体ページのUI改善)
u-3.既存ユーザーへ沼体験の提供(貢献の可視化、再訪の動機づけ)
まずは1周年を迎えるにあたり、u-1~2に注力。自然流入のユーザーに対しても効いてくる部分から改善を図ります。u-3はコストをかけずに打てる施策も存在するので、登録団体と連携を密にしながら、併行して対応していきます。
クロスセル戦略_保護猫プロダクション化
これを叶える2つの戦術が
c-1.『neco-note one』所属猫をモデルにアートを制作販売(厚利少売)
c-2.『neco-note shop』所属猫をモデルにグッズを制作販売(薄利多売)
両プロジェクトとも、売上の一部がモデルとなった猫のお給料となる仕組みです。
『neco-note one』はすでに、アーティスト『FRAGILE』とコラボを実現。現時点で100万円近い売上を出しています。

『neco-note shop』は、1周年を迎える2月22日にグランドオープン予定。グッズに使用するイラストを担当するのは、イラストレーター『yaka』。
過去に猫のイラストを書いてもらった時の作品がこれです。独特なタッチで、ふわふわの毛質とアンニュイな表情を絶妙に表現しています。今回はちょっとタッチを変える予定ですが、このイラストがトートバックやスマホケースになったら、ほしくないですか?

と、neco-noteの未来について語ってきました。「neco-noteを通してどんな未来を描きたいのか?」せっかくの年初めなので、頭の中を棚卸しです。
他の視点でもneco-noteの未来について考えてることがあるので、今度改めて文字に起こしたいと思います。お楽しみに。
・猫好き(およびバディ)にとってどんな存在になれるのか?
・猫好きがneco-noteに訪れた時、どんなストーリーで沼るのか?
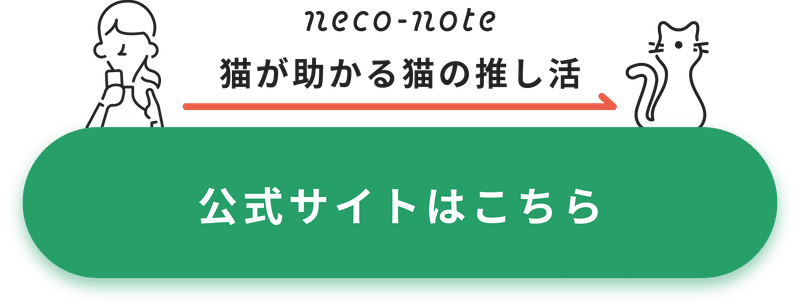
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
