
認知症書籍の歴史を辿る。 [1819〜1999年]
認知症にまつわる情報があふれている今——。書籍の出版も花盛りである。最近では、書店の一角に「認知症コーナー」が設けられていることも珍しくなくなった。
過去から現在を辿ってみると、実に多種多数の認知症書籍が出版されてきたのがわかる。医学書に始まり、介護書、看護技術書、介護体験記、予防術、テキスト、事業所実践記、翻訳書、小説、漫画……etc。そして近年では、認知症本人の手記などが散見される。
有吉佐和子氏の小説『恍惚(こうこつ)の人』(新潮社)が発表されたのが1972年。今からもう45年以上前になる。深沢七郎氏の『楢山節考(ならやまぶしこう)』(中央公論社)は、さらに15年遡ること、1957年の発刊だ。

いうまでもなく、認知症を取り巻く現在の社会状況は急に出来上がったものではない。それを形成したのは「歴史」に他ならない。高齢化・認知症の人の増加を背景に、「福祉」「知的障害」「身体障害」「精神障害」「精神医学」「介護」「看護」「人権」といった分野の源流が注ぎ込み混ざり合って「認知症」という大流になったのだ。
ここにあげた160種類ほどの書籍をあらためて眺めてみると、書籍は、こうした潮流(蛇行?)を見事に映しだしている。当時使われていた「用語」はもちろんのこと、そのときの医学的見地、介護方法などの到達点もわかる。一時的にブームとなったケア技術(これらは海外からもたらされたものが多い)もある。さらに見逃してはならないのは、認知症ならびに認知症の人が社会(ここには専門職も含まれる)から被ってきた「誤解」や「偏見」が染み込んでいることである。
なお、年代ごとにここに掲載した選書の基準は、①多くの人に読まれた、②話題になった、③当時の世相が反映されている、④認知症を取り巻く状況を進歩させた、⑤先見性があった、の5点である。筆者の主観に基づくものであることを申し添えておきたい。
また、ここでは、書籍とともに映画も取り上げている。今や認知症をテーマにした映画は珍しくないが、1980〜90年代は本当に稀少だった。もう観ることが叶わない映画が多く、非常に惜しいといわざるをえない。
注)各書名を参照できるようにAmazonのリンクを貼っているが、現在入手不可能なものも多い。書名によっては、初版ではなく、その後刊行された改訂版、文庫版、復刻版、Kindle版などのURLを示しているものもある。

「癲癇狂経験編」(土田獻著)

「精神病約説」(ヘンリー・モーズレー著、神戸文哉訳)

「老人病学」(入沢達吉他著、南江堂書店)

「精神病者私宅監置ノ実況及ビ其統計的観察」(呉秀三・樫田五郎著)
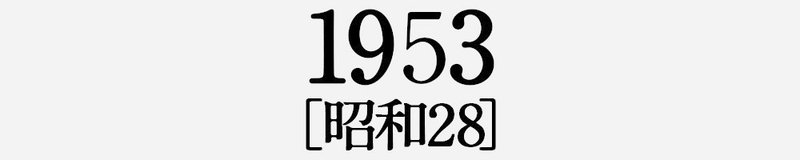
「健康な村」(若月俊一著、岩波書店)

「痴呆」(西丸四方著、みすず書房)
「異常心理学講座——精神病理学 知的側面の病態心理 痴呆」(井村恒郎他編、みすず書房)
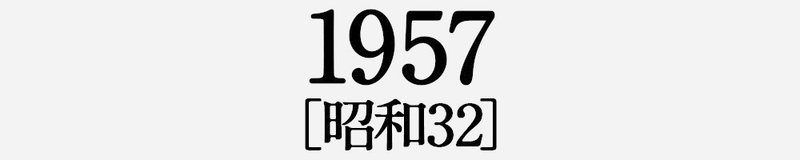
「楢山節考」(深沢七郎著、中央公論社)
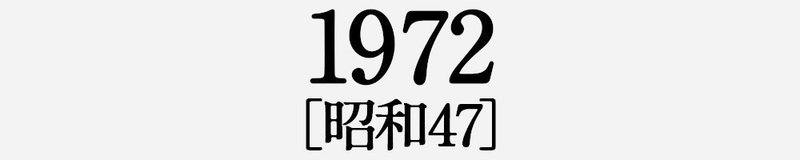
「恍惚の人」(有吉佐和子著、新潮社)

「ルポ・精神病棟」(大熊一夫著、朝日新聞社)
◆映画
「恍惚の人」(豊田四郎監督、有吉佐和子原作)

「痴呆」(チャールズ・E・ウェルズ編、池田久男訳、医学書院)

「わが母の記」(井上靖著、講談社)
◆映画
「カッコーの巣の上で」(ミロス・フォアマン監督、米国)
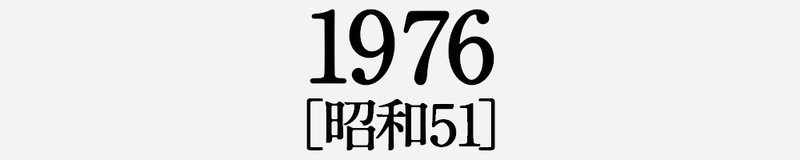
「老人ボケがなおる——世話をする家族へのアドバイス」(長倉功著、社会保険出版社)
「老人の精神病理」(大原健士郎編、誠信書房)

「わらじ医者京日記——ボケを看つめて」(早川一光著、ミネルヴァ書房)

「人間であるために——老人呆けをなおしたある家庭の場合」(敷島妙子著、あかり書房)
「老人のぼけの臨床」(柄澤昭秀著、医学書院)
「最新精神医学入門」(S・H・スナイダー著、松下正明・諸治隆嗣訳、星和書店)

「ぼけ老人をかかえて」(呆け老人をかかえる家族の会著、合同出版)
「老人介護読本——痴呆性老人の理解とケアのために」(東京都福祉局著、東京都福祉局老人福祉部計画課)

「ボケと上手に接する方法」(長谷川和夫著、英知出版)
「ぼけ老人と家族をささえる——暖かくつつむ援助・介護・医療の受け方」(三宅貴夫著、保健同人社)
「ぼけ——理解と看護」(中島紀恵子・石川民雄著、時事通信社)
「ぼけはここまで治せる」(田中多聞著、二見書房)
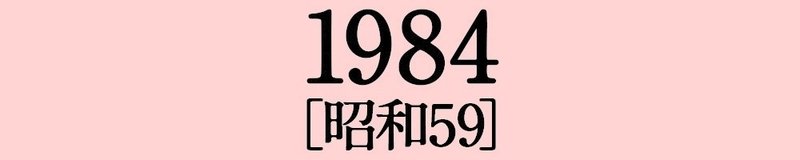
「老年期痴呆」(長谷川和夫編、金原出版)
「ぼけ老人の介護——すぐに役立つ手引書」(厚生省社会局老人福祉課著、老人福祉開発センター)
「ボケの人間学——まちがいだらけのボケ認識」(吉川武彦著、新企画出版社)

「痴呆老人の理解とケア」(室伏君士著、金剛出版)
「老い——貧しき高齢化社会を生きる」(田邊順一著、平凡社)
◆映画
「花いちもんめ」(伊藤俊也監督)

「痴呆性老人の理解と処遇——全国社会福祉協議会痴呆性老人処遇研究会報告」(全国社会福祉協議会編、全国社会福祉協議会)
「老人の生活ケア——〈生活障害〉への新しい看護の視点」(三好春樹著、医学書院)
◆映画
「痴呆性老人の世界」(羽田澄子監督)
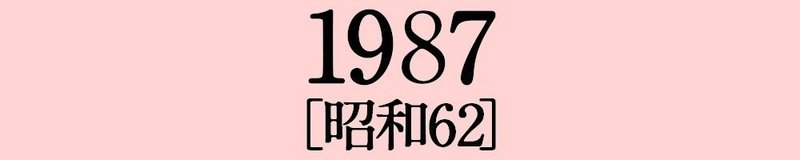
「ボケに強くなる——痴呆のすべてを科学する」(大友英一著、講談社)
「人類とぼけ——ぼけ研究の歩み」(新福尚武著、講談社)
「老人虐待」(金子善彦著、星和書店)
「今からわかるボケる人ボケない人」(フレディ松川著、はまの出版)

「これからの痴呆性老人対策——痴呆性老人対策推進本部報告・解説・全資料」(厚生省保健医療局企画課監、中央法規出版)
「そうかもしれない」(耕治人、講談社)
「ぼけなんかこわくない ぼけの法則——病気のしくみがよくわかり介護の苦労が半分に」(杉山孝博著、リヨン社)
「ぼけ老人110番——電話相談4000件の事例から」(笹森貞子・内田玲子著、社会保険出版社)
「ルポ 老人病棟」(大熊一夫著、朝日新聞社)
「脳が壊れるとき——どうなる・どうする」(金子満雄著、メディカルトリビューン)

「お母さんは宇宙人」(橋幸夫著、サンブリッジ)
「老年期痴呆診断ハンドブック」(室伏君士・平井俊策監、メディカルレビュー社)

「「寝たきり老人」のいる国いない国——真の豊かさへの挑戦」(大熊由紀子著、ぶどう社)
「NHKスペシャル 痴呆症・謎はどこまで解明されたか」(NHK取材班著、日本放送出版会)
「クリッパンの老人たち——スウェーデンの高齢者ケア」(外山義著、ドメス出版)
◆映画
「安心して老いるために」(羽田澄子監督)
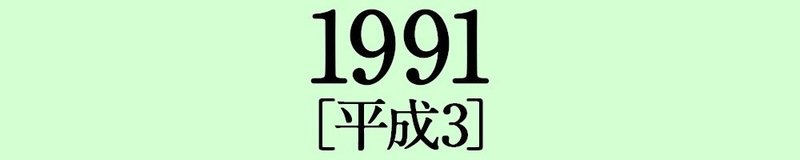
「ぼけとたたかう」(「ぼけの老人をかかえる家族の会」千葉県支部編、新日本出版社)
「高齢者のための知的機能検査の手引き」(本間昭・大塚俊男著、ワールドプランニング)
「体験ルポ 世界の高齢者福祉」(山井和則著、岩波書店)
「老人性痴呆疾患診断・治療マニュアル」(厚生省保健医療局精神保健課監、新企画出版社)
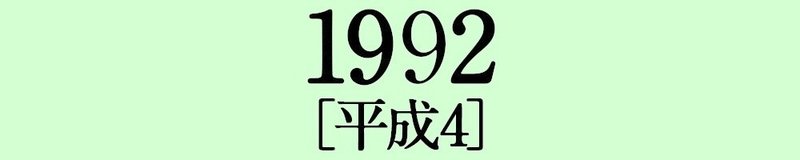
「妻を帽子とまちがえた男」(オリバー・サックス著、高見幸郎他訳、晶文社
「寝たきり老人ゼロ作戦」(山口昇著、家の光協会)

「ICD-10 精神および行動の障害——臨床記述と診断ガイドライン」(世界保健機関著、融道男訳、医学書院)
「痴呆老人百科」(村地俊二編、中央法規出版)
「痴呆の基礎研究——痴呆はどこまで解明されたか」(松下正明編、中央法規出版)

「痴呆老人のアセスメントとケア——リアリティ・オリエンテーションによるアプローチ」(ロバート・ウッズ他著、川島みどり訳、医学書院)
「ボケても心は生きている——エスポアール病院の新たな挑戦」(佐々木健著、創元社)

「DSM-IV 精神疾患の分類と診断の手引」(米国精神医学会著、高橋三郎他訳、医学書院)
「痴呆症状と生活の障害Ⅰ——徘徊・帰宅願望・器物破損・記憶障害・見当識障害」(井上勝也監、中央法規出版)
「医療は「生活」に出会えるか」 (竹内孝仁著、医歯薬出版)
「特養ホームで暮らすということ——ある主婦があたたかな目で記した体験レポート」(本間郁子著、あけび書房)
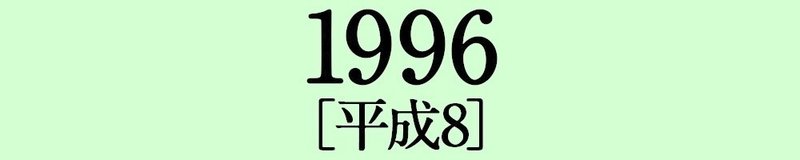
「高齢者医療と福祉」(岡本祐三著、岩波書店)
「痴呆性老人グループホームケアの理念と技術——その人らしく最期まで」(林崎光弘他編著、バオバブ社)
「付き添って——明日はわが身の老人介護」(生井久美子著、朝日新聞社)
◆映画
「よいお年を——元気な亀さん」(宮崎政記監督)

「アルツハイマー病遺伝子を追う——ハンナ家の子孫と探究者の物語」(ダニエル・A・ポーレン著、岩坪威他訳、三田出版会)
「鏡のなかの老人——痴呆の世界を生きる」(竹中星郎著、ワールドプランニング)
「宅老所「よりあい」の挑戦——住みなれた街のもうひとつの家」(井上英晴・賀戸一郎著、ミネルヴァ書房)
◆映画
「ユキエ」(松井久子監督、吉目木晴彦原作)
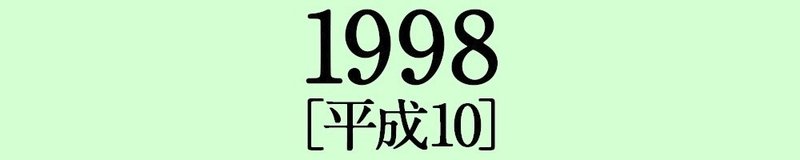
「もうすぐあなたも遠距離介護——離れて暮らす親のケア」(太田差惠子著、北斗出版)
「回想法とライフレヴュー——その理論と技法」(野村豊子著、中央法規出版
「痴呆老人からみた世界——老年期痴呆の精神病理」(小澤勲著、岩崎学術出版社)
「痴呆症に効くやさしい音楽療法」(河合真他著、小林出版)
「いい風吹いて——痴呆老人 出雲からの報告」(原田勉著、松江今井書店)
「PPK(ピンピンコロリ)のすすめ——元気に生き抜き、病まずに死ぬ」(水野肇・青山英康編著、紀伊國屋書店)

「ぼけになりやすい人、なりにくい人」(大友英一著、栄光出版社)
「在宅ケアで出会う高齢者の性」(荒木乳根子著、中央法規出版)
「痴呆性高齢者ケア——グループホームで立ち直る人々」(小宮英美著、中央公論新社)
「縛らない看護」(吉岡充・田中とも江編著、医学書院)
