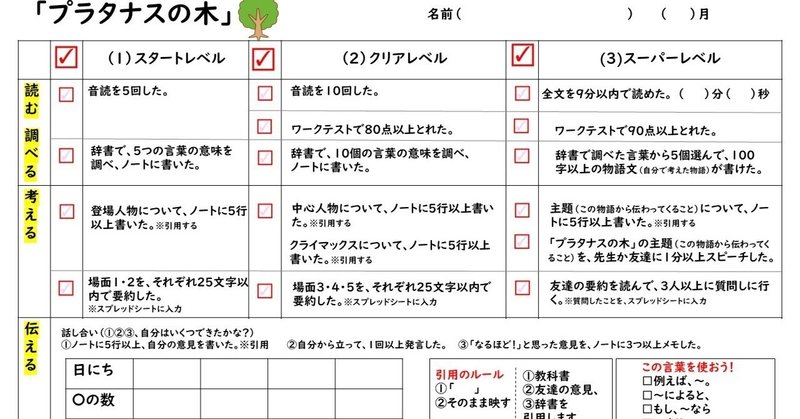
熱中するルーブリックの作り方 ①変化のある繰り返し ②趣意説明
ルーブリック実践を続けて2か月。
TOSSサマーセミナーのときには見えなかったことが、
体感として見えてきました。
子供が熱中するルーブリックには原則があります。
1つ目が、変化のある繰り返しです。
例えば、林が作成した「プラタナスの木」のルーブルック。
_______________________
スタートレベル「音読を5回した」
クリアレベル「音読を10回した」
スーパーレベル「全文を9分以内で読めた( )分( )秒」
________________________
普通なら、スーパーレベルは「15回」となります。
これでは熱中しないのです。
やらされ感があるルーブリックになります。
変化をつけるのです。
なおかつ、同時に趣意説明になります。
「たくさん読めば、早く読めるようになるんだね」という趣意説明です。
これは、どの項目でもそうです。
[調べる]でも、
「5つの意味」→「10個の意味」→「100字以上の物語を書く」となります。
これが、「15の意味」では、子供は熱中しないのです。
調べた言葉を使って、物語を自分で書くから熱中するのです。
「登場人物」→「中心人物」→「主題」→スピーチだから熱中するのです。
このことは、谷和樹先生(玉川大学大学院教授)のルーブリックから学びました。
「あれ?数が増えていくだけではないぞ」と学びました。
また、これらの項目は、「学習指導要領」が土台となります。
例えば、「プタラナスの木」ルーブリックだけで、
下の「内容」と繋がります。
【知識及び技能】文章の内容の大体を意識しながら音読する。
【態度】「プラタナスの木」を進んで読もうとしている。
【知識及び技能】辞書を使い、意味を調べることができる。
【思考力、判断力、表現力B】感じたことや想像したことを書く。
【知識及び技能】引用を正しく使う。
【思考力、判断力、表現力B】自分の考えとそれを支える理由を明確にして書く。
【思考力、判断力、表現力C】登場人物の行動や気持ちなどについて、叙述を基に捉えることができる。
【思考力、判断力、表現力C】文章を読んで感じたことや考えたことを共有し,一人一人の感じ方などに違いがあることに気付くこと。
【思考力、判断力、表現力A】相手に伝わるように、理由を挙げて話す。
【思考力、判断力、表現力C】登場人物の気持ちの変化について、場面の移り変わりを結び付けて具体的に想像することができる。
【思考力、判断力、表現力C】文章を読んで理解したことに基づいて、感想や考えをもつことができる。
変化のある繰り返し、
趣意説明。
なおかつ、「学習指導要領」を土台とします。
↓↓TOSS冬合宿2023の全情報・お申し込みはこちら!
2023年1月7日(土)~8日(日)
@東京ビックサイト会議室605・606/オンライン
https://2023toss-hybrid-camp.peatix.com/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
