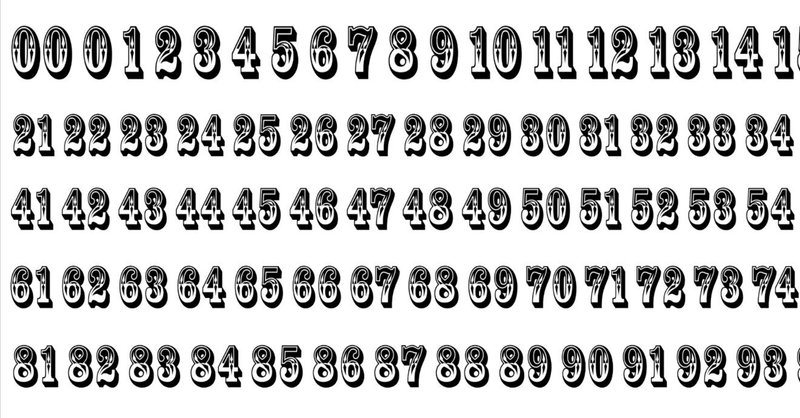
プロ野球背番号の話4番
NPB初の永久欠番
突然ですが、NPB初の永久欠番がどのチームの何番かご存知の方はいらっしゃいますでしょうか? まぁここで取り上げている時点で答えは自明ですが、正解は「巨人の4番」と「巨人の14番」(1947年7月9日同時制定)です。
さて続いて問題です。「巨人の14番」と言えば昭和以前の野球ファンなら大体知っている沢村栄治ですが、「巨人の4番」を着けていたのは誰でしょう? これは結構難問だったりします。正解は黒沢俊夫。読みが同じなので間違えやすいですが、俳優のほうは黒沢年男です。
それでは黒沢俊夫がどんな選手だったか見ていきましょう。戦前のプロ野球が始まった昭和11(1936)年に外野手(主にレフト)として名古屋金鯱軍に入団。その後、球団の合併、改名などがあり大洋軍(のちの大洋ホエールズとは別球団)→応召(一年間の兵役)→西鉄軍(のちの西鉄ライオンズとは別球団)を経て、西鉄軍の解散により昭和19(1944)年に巨人軍に移籍します。
終戦後の昭和21(1946)年に巨人に復帰。千葉茂、川上哲治とクリーンナップを形成し、主軸として活躍するも翌年腸チフスを発症、同年6月に入院し、そのまま33歳の若さで逝去しました。それを悼み、同僚選手たちが提案して、戦死した沢村栄治と共に永久欠番に制定したというわけです。
ところで、黒沢がどれほどのレベルの選手だったかと言うと、確かに在籍していた2年間は主軸として活躍しましたが、特筆すべき記録はありません。しいて言えば、「ホームスチール歴代二位(10回)」がある程度。
そもそも在籍期間で言っても名古屋金鯱およびその後継球団のほうが長く、事情を知らなければ「なぜ永久欠番に?」と思われても仕方のないところ。事実、黒沢は巨人の永久欠番指定者の中で唯一野球殿堂入りしていません。
ちなみに、黒沢は名古屋金鯱軍でも背番号4をつけています(大洋軍、西鉄軍時代のみ3)。
ところでMLB初の永久欠番はどこの球団の何番かわかりますか? 実は奇しくも日本と同じ背番号4なのです。ヤンキースのルー・ゲーリッグで、筋萎縮性側索硬化症に倒れ、引退した1939年に永久欠番に制定されました。
外国人の番号
4=「死」を連想させることから、日本では比較的忌み番として扱われることが多く、事実上の「外国人専用番号」として知られるようになりました。
特に顕著だったのが南海ホークスで、一リーグ最後の年である昭和24(1949)年に一年だけ安井亀和という選手が着けましたが、その後12年間の空き番を経て昭和37(1962)年にケン・ハドリが着けて以降、南海最後の年である昭和63(1988)年に森脇浩司が着けるまで、どの日本人も背番号4を着けることはありませんでした。つまり、南海ホークス史上、背番号4を着けた日本人は安井と森脇の二人だけ(しかも一年ずつ)ということになります。その中で、ハドリとクラレンス・ジョーンズは長く在籍しましたが、それ以外は1~2年で入れ替わり、特に印象に残る外国人選手はいません。異色だったのが台湾出身で後に代表チームの監督も務めた李来発。同僚の高英傑と一緒に来日し、第三、第四の外国人扱いで比較的長く在籍しましたが一軍に出場する機会はほとんどありませんでした。最初、背番号4だった李来発は2年で背番号を29に変更、背番号30だった高英傑と連番にしました(余談ですが、南海は連番が好きです)。
ダイエーに身売り以降は、やはり一年で解雇されるような外国人が着けることもちらほらありましたが、どちらかというと森脇の流れを汲む職人タイプの日本人選手のほうが印象に残っています(詳細は後述)。
ソフトバンクになってからは、ヤクルトで長く背番号4を着けたバレンティンが期待されながらも2年で契約解除されたりします。現在も外国人選手のアストゥディーヨの背中にあります。
(個人的には1~2年でクビになったダメ外国人についても語りたいところですが……)
南海ほど極端ではありませんが、比較的外国人に多く背番号4を着けさせた球団に、中日、ヤクルト、大洋、阪急と消滅した近鉄があります。特に中日は昭和44(1969)年から昭和63(1988)までの丸20年間外国人専用番号だったので南海に準ずるレベルです。その中にはジーン・マーチン、ケン・モッカ、ゲーリー・レーシッチといった名選手もいます。平成に入ってからもレオ・ゴメス、アレックス・オチョアといった長期在籍選手が着けましたが、一昨年引退した藤井淳志が長きにわたって着けたため外国人のイメージは払拭されています。
ヤクルトについては、4番に限らず2~5(場合によって6)を空いた端から次の外国人に使いまわしているため、4番だけが特別という印象はありません。「赤鬼」チャーリー・マニエルと「年間60本」ウラジミール・バレンティンが有名ですが、個人的には「マニエルの後釜」ジョン・スコットが印象的です。
大洋については、南海というかダイエー以降のホークスと同じ感じで1~2年で解雇された外国人選手を職人タイプの日本人選手が挟んでいるという形です。ちなみに守備の名手として玄人人気を博したクリート・ボイヤーは背番号6が有名ですが、入団初年度だけ背番号4を着けています。なお、横浜→DeNA以降はほとんど日本人選手で、言及するレベルの外国人選手はいません。
阪急はのちに通訳としても親しまれた「チコ」ことロベルト・バルボン、阪急黄金期を長く支えたボビー・マルカーノの印象が強いです。オリックスに身売り以降はやはり職人タイプの日本人選手が多く着けましたが、平成24(2012)年から平成29(2017)年まで一時的に外国人専用となります。今年からは「職人」とはとても呼べないタイプの森友哉が着けていますが、背番号4の新しいイメージを作れるか。
実は南海と同じレベルで背番号4にこだわりを感じたのが、球団合併によって消滅した近鉄です。球団創設以降長きにわたって外国人選手or移籍選手しか着けておらず、生え抜きの選手に与えられることは一切ありませんでした。ちなみにヤクルトから近鉄に移籍してきたマニエルは、当然のように背番号4を継続して着けていますが、実はこれが唯一の近鉄における背番号4外国人の成功例です。
ここで初めて背番号4を与えられた生え抜きの選手が、のちにオリックスで監督を務める大石大二郎でした。昭和56(1981)年に背番号43で入団し、二年目に二塁のレギュラーを獲ると、三年目の昭和58(1983)年から背番号4に変更します。他球団も含め、この時期から「背番号4を着けた日本人有名選手」が増えてきた気がします。その意味で、大石の登場は「背番号史におけるターニングポイント」と言えるかもしれません。
話を外国人に戻すと、「着けた選手は多くないけど、印象の強い外国人選手」がいたチームが阪神とロッテです。阪神については別項で詳述しますが、ロッテは他球団とは逆に球団創設から昭和の末まで一貫して日本人が背番号4を着け続けました。そんな中球団史上初めて背番号4を着けた外国人選手が平成元(1989)年入団のマイク・ディアズです。シルベスター・スタローンに顔が似ていることから「ランボー」の愛称で親しまれ、乱闘シーンが何度もテレビで擦られることもありましたが、ファンから愛された助っ人でした。本職は捕手で、実際に試合に出場することもありましたが、基本的には外野手or指名打者でした。
ディアズ退団以降は再び日本人選手の流れに戻りますが、奇しくも別の時期に入団した二人のフランコ(フリオとマット)がそれぞれ背番号4を着けたのは興味深いところ(フリオはすぐに背番号21に変更)。
ちなみに、近鉄消滅を受けて創設された東北楽天イーグルスは、背番号4に対するイメージがだいぶ変わった後の創設とあって、背番号4を着けたのは全員日本人です。
二塁手の系譜
上述の通り、外国人に与えられることが多かった背番号4ですが、守備番号としてセカンドの選手が着けることもゼロではありませんでした。その元祖は小坂佳隆(広島)でしょうか。昭和33(1958)年に当時貧乏&弱小球団だった広島が、初のスター選手として獲得。入団一年目からセカンドのレギュラーを獲得すると、そこから6年間守り続けます。ところが7年目の昭和39(1964)年にケガをしてレギュラーを奪われると、その翌年に引退。指導者にもならず球界を去りました。ただ小坂の時代は背番号4はまだまだ忌み番的な印象が強く、他球団に日本人のスター選手はいませんでした。
小坂の引退後に背番号4をつけてセカンドを守ったのが、基満男(西鉄・太平洋・クラウン)です。昭和42(1967)年に背番号78で西鉄に入団し、一年目から一軍に定着すると、翌年から背番号4に昇格、セカンドのレギュラーになりました。その後、太平洋、クラウンとほぼレギュラーを守り続け、西武への身売りと共に横浜大洋にトレードされました。横浜大洋でも背番号4は空いていましたが、同時に中日からトレードされてきたマーチンに譲り、自身は背番号5を着けています。
流れが変わったのは上述の大石大二郎(近鉄)の活躍からで、そのフォロワーの一人が小坂の後継ともいえる正田耕三(広島)です。昭和59(1984)年のドラフト二位で入団。最初から背番号4を背負い、大石と同じく入団三年目の昭和62(1987)年にセカンドのレギュラーを奪取、その年にスイッチヒッターとしてはNPB史上初の首位打者に輝くと、翌年も連続で首位打者になりました。同年から5年連続でゴールデングラブ賞に輝くなど、守備力にも定評がありました。ただ正田引退以降は、小窪哲也が長く着けましたがレギュラー獲得した選手はいません。
大石引退後に跡を継いだのが高須洋介(近鉄)です。大石からスライドするようにセカンドのレギュラーを掴むと、球団消滅→楽天に移籍してからも背番号4を着け続け、楽天の背番号の流れを作りました。戦力外→独立リーグに移籍後は少々落ち着かない背番号になりましたが、今年から本職セカンドの阿部寿樹が着けています。ただ、セカンドのレギュラーは浅村で固定されているので、なかなか「セカンド背番号4」にお目にかかれないのが残念なところ。
2000年代に西武のセカンドとして活躍したのが高木浩之です。黄金時代を支えた辻発彦が移籍後安定しなかったセカンドのレギュラーとなり、主にショートを守っていた松井稼頭央とコンビを組んでいました。引退後は巨人から移籍してきた清水崇行(隆行)が着けるも一年で引退、美沢将は定着できず番号降格の憂き目に。鬼崎裕司はレギュラーを獲るも2年で背番号を5に変更。現在は山野辺翔が着けていますが、数々のチャンスをものにできていません。
名脇役の系譜
上記のような事情からか、主に背番号4を着けて名球会入りした選手はいません。一桁番号はやはり期待された選手、あるいは期待に応えてブレイク後に与えられることが多く、自然に名球会入りするような選手も多いのですが、その意味で「背番号4」だけは例外のようです。そのため、日本人でもチームの中心と言うよりは「脇役」「いぶし銀」的な選手が多くつけています。
例えば外国人に渡さず、日本人が比較的多く背番号4を着けたチームとして、上述の阪神、ロッテ、そして日本ハム、西武でしょうか。あとダイエー以降のホークスも同じような形です。そして楽天も創設以降背番号4を着けた外国人はいませんが、高須以降レギュラークラスもいないので略します。
まず阪神ですが、なんといっても17年着け続けたレジェンドOB「浪速の春団治」こと川藤幸三です。19年の現役生活で一度もレギュラーに定着したことがなく、当然規定打席も未到達。にもかかわらずレギュラー級の人気を得ていた伝説の選手です。川藤以降も山脇光治、高波文一、上本博紀といったレギュラーに一歩届かない野手が着け、現在もレギュラーに届かない熊谷敬宥の背中にあります。
ロッテの背番号4も脇役の宝庫です。江島巧、井上洋一、田野倉利行、酒井 忠晴……。荻野貴司はケガが多く隔年で活躍する選手でしたが、背番号を4→0に変えてからレギュラーになりました。荻野のあとに背番号4を継いだ藤岡裕大はショートのレギュラーに定着しそうでできない歯がゆい状況が続いています。
日本ハムは特に外国人が少なく、3人の外国人が全て一年で退団、背番号変更しています。印象に残った選手もなく、日本人の番号と言えるでしょう。しかし着けたすべてが脇役的選手です。特に印象的なのが、「シンちゃん」こと五十嵐信一です。内外野どこでも守れるだけでなく、勝負強い打撃で代打の切り札的な仕事もしていました。打席に入った際の「シーンちゃーん」コールはかつての東京ドームに通っていた方ならよくご存じかと。ちなみに後述の「背番号交換」により晩年は背番号15に変更されます。
次に挙げるのが、奈良原浩です。「西武の守備固め」の印象が強いですが、トレード初年にいきなりレギュラーに定着、自身初の規定打席に到達します。しかしその後は「不動の二遊間」金子誠&田中幸雄の定着もあって、西武時代同様守備固めおよび代走としてチームを支えました。
奈良原の後を継いだ飯山裕志も同じように守備固めおよび代走で活躍しました。現在の背番号4は上川畑大悟で、中島卓也の衰え、石井一成の不調もあってショートのレギュラーに定着しています。
埼玉移転及び基のトレードにより西武ライオンズの背番号4はしばらく安定しませんでした。落ち着いたのは南海から片平晋作がトレードで来てから。ファーストを守っていた田淵幸一をDHに追いやり、王貞治さながらの左の一本足打法で移転後初の日本一に貢献します。しかし清原和博が入団した結果、横浜大洋にトレードされました。
背番号4を継いだのが「笘篠兄弟の兄」こと笘篠誠治。内外野どこでもできるユーティリティプレーヤーとして長く重宝されるも、若くして引退→コーチに就任します。奇しくも弟の賢治(ヤクルト)も同時期に背番号4に変更、こちらはケガもあって活躍できず、兄が引退した平成9(1997)年に広島にトレードされます。
その笘篠賢治がいたヤクルトも、外国人の影に隠れ、脇役の宝庫です。
長らく外国人専用番号になっていたところ、久しぶりに日本人で背番号4を着けたのが青島健太です。慶應義塾大学から社会人野球の東芝を経てドラフト外で昭和59(1984)年に入団。入団時既に26歳(開幕時点で27歳)ということもあり、即戦力を期待されたが球団史上初の「初打席初本塁打」がピークで、わずか5年で現役引退→野球解説者兼タレントとして活躍しました。現在は参議院議員を務めています。
青島の跡を継いだのが前年初めてセンターのレギュラーを掴んだ栗山英樹。WBC監督として今年大いに名前をあげましたが、現役時代は非常に渋い選手でした。持病のメニエル病のため背番号4ではほとんど活躍できず、この年限りで引退します。
栗山のあとが上述の笘篠賢治、笘篠が広島にトレードされると、絶品の三塁守備で三球団を渡り歩いた馬場敏史、次いで「二軍では別格も一軍ではレギュラーに届かなかった便利屋」こと度会博文が着け、度会引退後は再び外国人の番号になりました。上述のバレンティンが着けたのはこの時期の話です。
現在は二年目の丸山和郁が入団時から着けています。外野ならどこでも守れ、ケガがちな塩見泰隆、衰えの見えてきた青木宣親、出遅れた山崎晃大朗に代わって4月にスタメンを掴むも、力不足で山崎と入れ替わりで登録抹消されると現在も二軍生活が続いています。
最後にダイエー→ソフトバンクの「脇役の歴史」を見てみましょう。
南海最終年に背番号4に変更した森脇浩司は内野ならどこでも守れるユーティリティーぶりが評価され、8~9回の守備固めとしてベンチになくてはならない存在でした。しかし平成7(1995)年に王監督が就任すると、自身の衰えもあって出番が減り、翌年限りで引退します。
その後を継いだのが柳田聖人です。まだチームが南海だった昭和62(1987)年に入団するも、一軍の壁を破れず平成6(1994)年にヤクルトに移籍。しかしヤクルトでもレギュラーを奪えず、2年でダイエーに出戻ります。2年のヤクルト生活は無駄ではなく、当時監督だった野村克也監督の教えで開眼、ユーティリティープレイヤーを目指すと出戻ったダイエーで森脇の抜けた穴にすっぽりと収まったのです。それどころか、新人の小久保裕紀の出場停止→ケガによる欠場もあって、出戻り2年目から浜名千広と併用ですがレギュラーに定着しました。しかし王監督V2達成の平成12(2000)年には井口資仁の成長、前年中日より移籍してきた鳥越裕介がショートのレギュラーを奪ったことから出場数が激減、翌平成13(2001)年は一軍出場がなく、その年限りで引退しました。
柳田引退後は、途中外野手の出口雄大が2年だけ着けたものの、それ以外は再び外国人が一年ごとに着ける流れになりました。
流れが元に戻ったのは平成24(2012)年にオリックスから移籍してきた金子圭輔が着けてからです。実は金子も柳田同様出戻り選手で、奇しくも移籍期間も同じ2年でした。平成16(2004)年に入団した金子は柳田同様一軍の壁を破れず、平成22(2010)年にオリックスにトレードされます。出場試合こそ少なかったものの一軍に定着。移籍時54だった背番号が翌年には期待を込めて6に昇格しました。しかし、その年は期待に応えることが出来ず、同年オフにソフトバンクに出戻ったわけです。移籍して背番号4を着けた金子は、主に代走と守備固めで渋い活躍をし、5年在籍して引退します。
金子引退後は、内野だけでなく外野も守れるユーティリティープレイヤー川島慶三が35から背番号を変更して着けます。川島は守備だけでなく、勝負強い打撃が売りだったため、特に右打者の少ないホークス打線において「対左投手用の代打、スタメン」として起用されましたが、上述のようにバレンティンがヤクルトから移籍してきたため、移籍前に同僚だった誼から背番号を譲渡し、自身は99に変更しました。
「脇役の例外」水谷実雄
90年代以前の「外国人」と「脇役」ばかりの背番号4において、数少ない(もしかしたら唯一?の)例外が広島及び阪急で活躍した「ミズマー」こと水谷実雄です。昭和40(1965)年の第一回ドラフト会議で広島に投手として入団し、一年目のオフに野手転向。5年目に外野手として一軍定着すると、6年目の昭和46(1971)年から背番号4に昇格し、レギュラーの座を守り続けます。昭和50(1975)年の初優勝時には主に「7番レフト」として優勝に貢献。その後、外国人選手との兼ね合いでファーストにコンバートされ、昭和53(1978)年には首位打者のタイトルを獲得、連続日本一のときには山本浩二の後を打つ「5番ファースト」としてチームの大黒柱の一つとなりました。しかしその2年後、フロントともめ、阪急にトレードされます。
阪急でも引き続き背番号4をつけ、「4番指名打者」として打点王のタイトルを取り、同僚の外国人ブーマー・ウェルズをもじって「ミズマー」のニックネームで親しまれました。しかし、移籍二年目以降はケガのため低迷、その翌年限りで現役引退します。
日本人選手でありながら、外国人選手のような活躍をした貴重なタイプの「背番号4」です。
背番号4の投手
おそらく「背番号9」までは続くであろうこのコーナー。「外国人の番号」の項で省略した阪神についてはここで扱います。というのも、阪神で背番号4を着けた外国人は4人で、そのうちアンディ・シーツを除いた3人が全員投手だからです。
時系列とは逆になりますが、平成19(2007)年に入団したライアン・ボーグルソンは初年度は背番号36でしたが、先発で7勝を挙げ契約更新すると、翌年は希望して背番号4に変更しています。しかし二年目は不振でオリックスに移籍、オリックスでも一年限りでしたが、一年間のマイナー生活を経てMLBのサンフランシスコ・ジャイアンツと契約すると、二年連続二桁勝利をあげてブレイクしました。
さて話を戻しますが、阪神ファンに「阪神の外国人投手と言えば?」と質問すると、70歳以上のオールドファンならほぼ100%「バッキー」と答えるでしょうし、40~60歳代なら「キーオ」と答えるのではないでしょうか。ここで「オルセン」とか「ゲイル」とか答えてもいいけど、まぁ一部の野球オタク(自分含む)しか喜ばないでしょうな。なお30歳代以下になると、外国人枠が拡大された事情で非常に多くの外国人投手がプレイするようになったという事情があるので、たぶんこういった偏った結果にはなりませんので省略します。
大分話がそれましたが、このバッキーとキーオがともに背番号4を着けて大活躍したのです。ジーン・バッキーは昭和37(1962)年シーズン途中に阪神にテスト入団しました。しかし入団当初はノーコンで、「給料が安いから翌年も契約した」レベルの扱いでした。才能が開花したのは3年目の昭和39(1964)年。29勝9敗、防御率1.89、200奪三振をあげ、最多勝と最優秀防御率、沢村賞を受賞、阪神のリーグ優勝に大きく貢献しました。翌年以降も18勝、14勝、18勝、13勝と安定した成績を残しただけでなく、ノーヒットノーランも達成しています。しかし13勝をあげた昭和43(1968)年に王貞治へのブラッシュボールを巡って巨人ベンチと乱闘、その中で右手を骨折し、警察沙汰になったあげくその年限りで阪神を退団→近鉄に金銭トレードされました。近鉄でも背番号4を着け12試合に登板しましたが、一勝もできずその年限りで引退しました。
バッキーが乱闘して右手をケガしたシーズンに、南海をひっそりと一年で退団したマーティー・キーオという選手がいました。彼にはマットという息子がいて日本にも連れてきていました。たった一年の在籍でしたが、父の背番号4と関西弁はマットの記憶に残っていたのでしょうか。それから約20年後、成長しメジャーリーガーにもなったマットが今度は父と同じ選手として来日しました。ポジションこそ内野手と投手で違うものの、背番号は父と同じ4を着けました。阪神も南海と同じ関西のチームということで、マットにはどこか親しみがあったのかもしれません。一年目から三年連続で二桁勝利を達成し、暗黒時代のチームにあって大きな光明となりました。しかし4年目の平成2(1990)年に7勝9敗で終わると、あえなく解雇されてしまいます。キーオ退団後は上述のように脇役の路線が続きます。
異変が起きたのは、平成14(2002)年のこと。当時背番号18を着けていたローテーション投手の藪恵壹が突然背番号を4に変更したのです。確かに近年敗戦数が勝利数を上回る年が続き、前年はとうとう一軍未勝利となにかを変えたほうがいい状況ではありましたが……。ちなみにこの背番号変更については「藪が川藤に勧められて変更した」説と「藪が川藤に申し出て川藤が許可した」説があり、どちらが正しいかは川藤および藪本人しかわかりません。当時、前任者の高波が背番号を入団時に着けていた65番に戻していて4番は空き番だったことから変更自体は特に問題はないのですが、わざわざ投手にしては珍しい背番号4を選んだのは、上述の「バッキー、キーオのイメージを踏襲したい」という気持ちがあったのかもしれません。結局この背番号変更は成功で、その年の藪は4年ぶりに二桁勝利を達成、翌年も勝利数が敗戦数を上回り、平成17(2005)年にはFAでMLBアスレチックスに移籍します。ちなみにこの藪のアスレチックスとの契約を後押ししたのが背番号4の先輩であるマット・キーオでした。もちろんキーオと藪の在籍が重なっていたことはありませんが、退団後も日本球界の情報は仕入れていたようです。その過程で、同じ背番号4の投手の動向もチェックしていたのかもしれません。
時系列は前後しますが、平成4(1992)年。阪神のキーオが退団して間もない頃、日本ハムで異例の背番号交換がありました。若手選手や実績が足りない選手が、移籍してきた有名選手や新外国人に前の球団で着けていた背番号を譲るというのはプロ野球あるあるですが、一軍選手同士が背番号を交換するというのはあまり例が多くありません。まして投手と野手の交換となれば、なおさらレアケースでしょう。それが上述の背番号4を着けた五十嵐信一と背番号15を着けた投手の武田一浩との背番号交換でした。
昭和63(1988)年に入団した武田は、入団二年目でローテーションに定着、しかし三年目にチーム事情で抑えに転向し活躍、抑え二年目で最優秀救援投手のタイトルを取ったオフの話です。契約更改でのあまりの評価の低さに記者の目の前でセカンドバッグを投げつけ「もうリリーフなんてやらねぇ!」と言い放ったのは語り草ですが、そのタイミングで背番号交換が行われたのです。当時の報道で「武田が希望した」という記事を見た気がしますが、ネットのソースがないのでこのレベルの記述にしておきます。
武田はその後先発に復帰し、背番号4で4年間活躍しますが、平成7(1995)年オフにダイエーにトレードされます。ダイエーでは特に背番号4を希望するわけでもなく(当時は引退寸前の森脇が着用)、加藤伸一が戦力外通告(のちに広島に移籍)されて空き番だった背番号17を着けています。
思ったよりも長くなってしまった。
次回、どうなるかわからない「背番号5」をお楽しみに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
