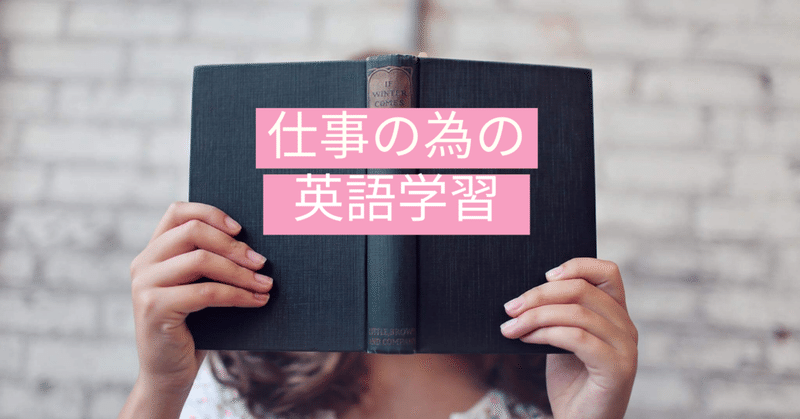
仕事の為の英語学習 ー 外国語は辛いよ編
英語が趣味で楽しんで学習されている方が多くいらっしゃる。趣味の英語学習をビジネス英語の学習に応用できるだろうか?自身の経験上、答えはNoである。ビジネス英語では期待される能力や習得へのアプローチが趣味のそれと明らかに異なる。相手がいるのが前提で、又チーム内・社外といった状況に応じ作法を含めた表現や、コンテクストを変化させる。又、業務内容によりカバーすべき範囲が大きく異なってくる。
事業のグローバル化、リモートワーク促進化で電話会議が多用されるようになった。それをスマートにこなす実践的な英語運用能力が今まで以上に重要視されてきている。私自身、バリュー、プレゼンスを示すため、電話会議でのコミュニケーションにフォーカスした英語運用能力の向上に取り組んできた。日本語で書かれたビジネス英語の良書は存在するもののその内容は限られており、日々遭遇するケースを網羅するため個々に合った対策の重要性を強く認識している。
私はネイティブスピーカーや帰国子女ではないので、まだまだ英語運用能力は発展途上にある。色々もがき、模索する中で見えてきた目下の課題、たどりついた対策方法をこのノートでシェアしたい。
対象読者)英語中級ー上級者
仕事で英語を使う方
英語でのミーティングが多い方
電話会議が多い方
マネジメントポジションを目指している方
まず基本スキルとして必要なものは、以下の5つに大まかに分類されよう。それぞれで対策が異なる。
1. ファシリテーションのスキル
2. 明確に意見を述べるスキル
3. 説明をするスキル
4. 的確な質問をするスキル
5. 議論を保留、カウンターオファーのスキル
又私自身が特に苦手で対策を講じている課題は以下の2つ。
・説明するスキル
・的確な質問をするスキル
今回のノートは特に「説明するスキル」を掘り下げてみる。
職業柄少し込み入ったことを話す機会が多く、特に対策の価値が高いと感じたのでネイティブのチューターと取り組むことにした。
そこで気づいたのだが、どうやら私は説明が下手らしい(笑)。
どう下手なのかというと、抽象化と具体化の程度がどうやら適切ではないらしい。話のとっかかりとして提示する全体像が抽象的すぎてわかりにくく、それに続く具体例は細かすぎるらしい。
又、説明の冒頭でこれから行う話のサインポストがないらしい。結論から話し始め、相手が話の内容についていけずひどく混乱するらしい。ここでいうサインポストとは「これからこういうことをこんな風にこんな流れで話しますよ」というイントロと考えて頂きたい。又、説明のサインポストというのは、ミーティングやプレゼンテーションの冒頭で話す全体の流れではなく、個別事項を詳細に説明する際の話の筋道を意味する。これに関しては「英語は結論から話さないといけない」と信じ意図して行っていたので、その誤解が解けてよかった。
特にプレゼン資料なし、音声のみ使用の社外電話会議でこの問題が顕著化することが判明した。(ちなみにこれが私のデフォルト😭)
そのネイティブ曰く、相手がある程度わかっている前提で話をどんどん進めて、聞き手をひどく置き去りにする癖があるそうだ。又、喋りすぎるらしい(笑)。相手がわかってないと気づくのが遅くなり、その段階での説明追加でかなりの時間のロスにつながっていた。
ここで対策すべき2つの課題が明確になった
1. 説明の筋道を示す練習
2. 抽象化、具体化の練習
1. 説明の道筋を示す練習
これは対策が比較的簡単で、速やかな改善が期待できる部分だ。全ての説明で必要になるとは思わないが、比較的フォーマルな場で、まとまった内容を口頭のみで行う際必要になる。前提のシェアが必要になるケース、話のランディングを明確にしておきたいケース、余計なツッコミで話を脱線させたくないケースで毎回示しておくと間違いがない。
具体的には以下のようなケースが該当するであろう。
ー 相手のトピックスや使用言語に関するベースの理解度が不明
ー 説明事項が複雑・重いトピック
ー 概念的な部分を含む
ー 規制・スタンダード等のリファレンスに沿って話をする
ー 比較しながらの説明が必要な場合
例としてはこのようなテンプレートが使えるであろう。
I am going to talk about X now. For that I will explain A(e.g.前提) first, then share with you B(e.g.現状、分析), and lastly I will address C(e.g.問題点).
説明内容が展開する際、毎回これからAを話しますよと逐一述ベるとよりわかりやすい。テンプレートのような短いイントロを加えるだけで、聞き手はまとまった話を聞く準備ができるし、疑問が生じても話の流れを乱されず、望ましい箇所で質問の受け答えができるであろう。
2. 抽象化、具体化の練習
これは少し時間がかかるトレーニングだ。その理由は、私の感覚では日本人の抽象概念レベルと、欧米人のそれに少し隔たりがありそうだと思うからだ。そこを明確にするには言語、文化的な背景の理解が必要になってくるので、ここでは参考図書*の紹介にとどめ説明は割愛する。
有効なアイテムとそのトレーニングは以下3点
ー 業務関連の書籍、ドキュメントを読む
ー 業務関連書籍のインデックスを把握しておく
ー 英語試験用のライティング、リーディングテキスト(GRE、GMAT. etc)
関連文書の関連パラグラフごとでTopic Sentenceとそれに続く具体例をチェック(精読)し、抽象から具体への展開のバランスを掴んでいくのが一番効率的である。ちなみにTopic sentenceとは各パラグラフの冒頭にくるセンテンスで、そのパラグラフがカバーする内容を明示する重要な情報である。パラグラフ全体を象徴するため比較的ハイレベルな(抽象的な)内容に留まる事が多い。その後具体例が追従し、詳細や内容の掘り下げが行われるのが一般的な英語の構造である。業務上の特定分野であれば範囲も限られており、関連トピックの抽象から具体例を提示するテンプレート、ストックを作ることが可能であろう。
又関連文書のインデックス内容を頭に入れおくのも効果的だ。それをTopic Sentenceのコア情報として用いることで容易に共通の理解を得ることができる。
最後にGRE等の大学院試験用のライティング、リーディングテキストが個人的にはオススメだ。その内容はセンテンス同士の関係性、ロジック展開にまで及び汎用性が高く、非常に学びが大きい。TOEFL、IELTS関連の書籍ではあまり踏み込んだロジックの解説がなく、該当のトレーニングには物足りない様に思う。
以上が私が現在行っている取り組みの一部である。皆さんの取り組みも大変興味深く、是非ともシェア頂きたい。
電話会議で必要な以下のスキルに関しては別のノートで→ こちらから(近日投稿予定)
・ファシリテーションのスキル
・明確に意見を述べるスキル
・的確な質問をするスキル
・議論を保留、カウンターオファーのスキル
又英語ミーティングの表現をネイティブから直接学ぶハックに関してはこちらから → こちらのnote (近日投稿予定)
参考図書
* エリン・メイヤー、異文化理解力:theCultureMap、英治出版
熊谷高幸、「自分カメラ」の日本語「客観カメラ」の英語、新潮社
よろしければサポートをお願いします。ブログ活動の励みになります。今後の記事の向上に使用させて頂きます!
