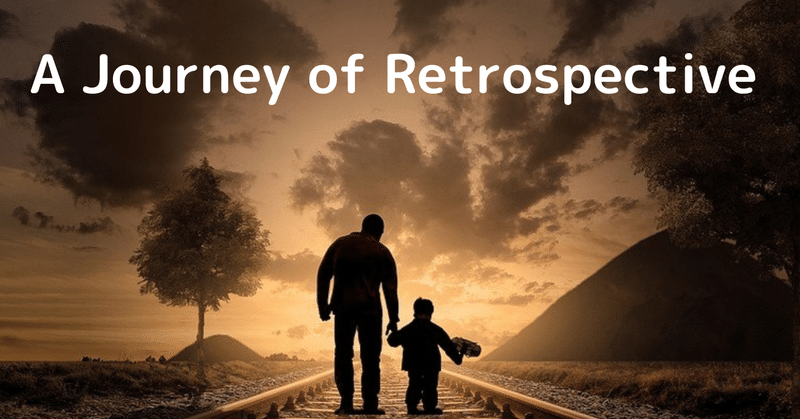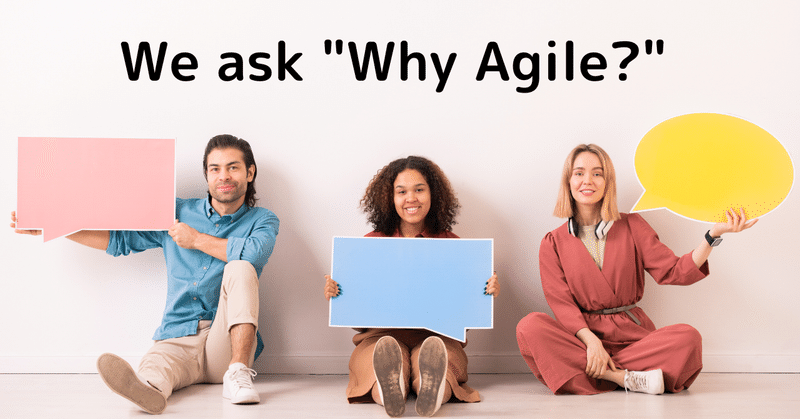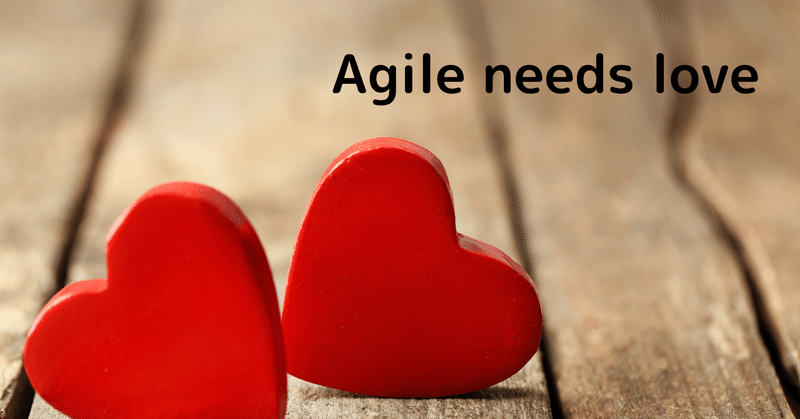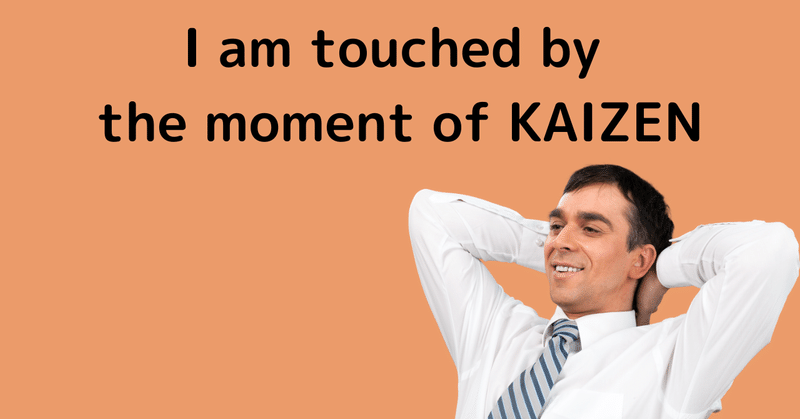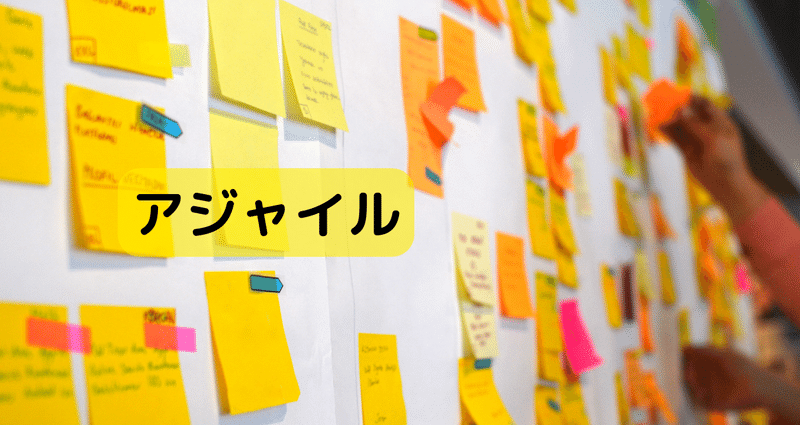
- 運営しているクリエイター
2023年3月の記事一覧

【アジャイル】DevLOVEイベント:右手に「正しいものを正しくつくる」、左手に「組織を芯からアジャイルにする」(左手編)
DevLOVEの市谷さんのイベントに参加しました。 右手編からの続き市谷さんの代表的な書籍「正しいものを正しくつくる」と「組織を芯からアジャイルにする」を扱ったイベントで、2月に行われたのが「正しいものを正しくつくる」の右手編でした。 前回はプロダクト開発や仮説検証、価値創造の観点が強かったですが、今回は左手にあたる「組織を芯からアジャイルにする」の名の通り、組織やチームの観点になります。 全体の印象としては、右手編と繋がる内容やキーワード(芯をつくる、整合を取る、など)