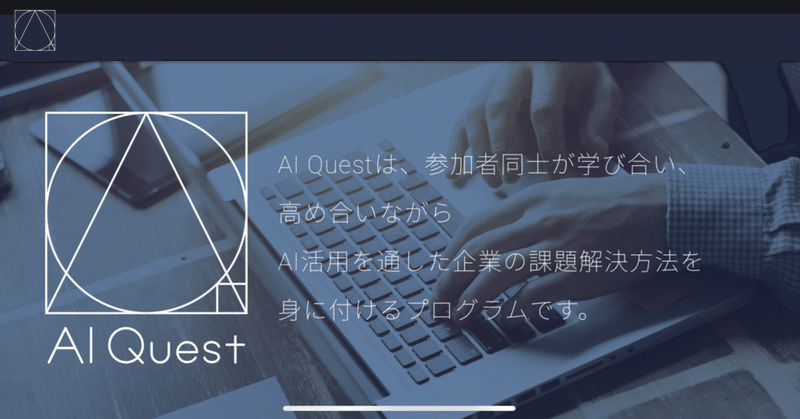
AIQuest2021に向いている人・向いていない人
皆様こんにちは。私は AIQuest 2020 に参加・修了した黒男(Twitter : @Black_Jack_2021) といいます。今年も AIQuest 2021 が開催されるということで、参加を迷っていらっしゃる方もいるかと思い、簡単ではありますが自分の意見を発信させて頂ければと思います。
1. そもそもあなたは誰?
と思われる方もいらっしゃると思いますので簡単に自己紹介だけさせていただきます(興味がない方は飛ばしていただいて結構です。)。私は去年まで学生(経済学系の大学院生)で、今年から金融機関でデータサイエンティストとして勤務しているものです。したがって私が AIQuest に参加したとき、まだ学生でした。当時の自分のスペックは以下のようなイメージです。
1. 機械学習
全く専門といえるほどの知識はないが、大学の講義でかじったり簡単なテーブルコンペに出たりした経験が少しある程度。xgboost とか LightGBM はこの時に多少実装できたかな...というぐらいの知識です。自然言語系とか画像系はほぼ全く知識無しです。
2. 統計学
これも専門といえるほどの知識はないですが、機械学習よりは若干詳しめ。具体的には以下を少しだけかじったことがある程度です。
・因果推論(RCT, 傾向スコア, DID, Causal Impact, IVなど)
・時系列分析(SARIMAX、状態空間モデル、隠れマルコフモデルなど)
・ベイズ統計(事前分布、事後分布、MCMCによる推定等)
・多変量解析(因子分析・主成分分析・パス解析・SEM等)
統計検定準一級の問題を、模範解答を見ながら独学で大体理解できるぐらいのレベルだとお考え下さい。
そんなレベルの学生でした。
2. AIQuest で自分が経験させていただいたこと
今年の具体的な日程等は把握しておりませんが、去年私が参加したときには前半タームと後半タームに分かれておりました。前半は PBL :小売に参加させていただき、後半は実際に小売を営む企業さまと協同し、その企業さまの実データを分析したり、その企業さま向けのAIを開発したりしていました。
また、それだけでなく有志の方々(例えば、この記事を書いている人)がLT会を企画してくださったので、それを聞いたり自分自身も登壇してお話したりしていました。(↓は当時発表に使った投影資料のタイトル)

今年もだとは思いますが、当時は Slack を使い、オンラインで緩く繋がりながら進んでいく方式でした。ですので、積極的に自分から情報発信をするように意識し、なるべく多くの人とつながりが持てるようにしておりました。そうした結果、普通に学生をしていたのであれば絶対につながりを持てない方々とつながりを持つことができ、AIQuest は私にとって本当に尊い経験となりました。
3. 本題 : AIQuest に向いている人・向いていない人
少々前置きが長くなりすぎましたが、そうした自分自身の経験や周りの方々を見ていて、割とAIQuestという会には向き不向きがはっきりしていると感じました。したがって、そうした経験や観察から AIQuest に向いている人の特徴をまとめたいと思います。
1. 主体的に行動する人
「AIQuest に参加したから、あとは指示通り動けば運営側が満足のいくプログラムや知識を全て提供してくれるはずだ」という風に思って参加すると不幸になると感じました。なぜならAIQuest は学び合いが思想の根底に根差していますし、運営の人たちはかなり限られたリソースの中で運営をしているからです。「満足のできない点があるなら、自分から提案してみよう。」そんなマインドを持った人には素晴らしい機会となると思います。
2. Giver としてのマインドを持ち合わせている人
上述したように基本的には学び合いがベースですので、一方的に他の受講者から恩恵を受けようとする姿勢の人は良好な関係を他の受講者と築きづらくなると思います。「この人と関わりを持ちたいな」と相手に思ってもらうために、例えば有益な情報発信のような、自ら積極的に Give をしていく姿勢が重要かと思います。
3. 心理的安全性を崩さない人
オンラインというかなり曖昧な距離感の中で開催されるイベントなので、高圧的だったり、あまりに強く敵対感を出してしまうと学び合いが促進されなくなります。競争的な側面があったとしても最大の目的は共創にある。そういう意識を持って取り組める方には非常に向いていると思います。
4. 終わりに
記事としては以上になります。何かお困りごと等ございましたら Twitter 等でご連絡いただければなるべく対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。長文最後まで読んでいただき有難うございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
