
近藤譲インタビュー 「線の音楽」のはじまりとこれから
聞き手、採録 石塚潤一。2023年5月7日、Skypeを利用してのインタビュー。太字が近藤譲氏の発言。なお、近藤譲氏発言のうち、()で括った箇所は、石塚による注釈。
******
秋山邦晴(批評家 1929-1996)さんの著書『日本の作曲家たち 下 戦後から真の戦後的な未来へ』(音楽之友社 1978)に、先生の幼少期の写真が何枚か収録されています。先生は、ご両親が音楽畑の方だったのではないようですね。
全然違います。父親は石油会社のサラリーマンで、母親は高校中学の英語の教師でした。
英語の先生でいらっしゃったのはお母様でしたか。そうすると、ご自宅にピアノがあるということもなかった?
いや、まったくなかったですね。父親はハーモニカが上手でしたけどね。
秋山さんの本には、幼少時にヴァイオリンを弾いていた写真が載っています。
僕はよく覚えていないですが、幼稚園から帰ってきて、今日こういう歌を習ったよ、と歌うんだけれど、ものすごく音が外れていて、何の歌かわからないから、両親はこんなに音楽がダメじゃ可哀そうだな、楽器でも習わせようか、と思ったらしいんですよね。それで、私が入った小学校が、横浜国立大学付属鎌倉小学校というところで、横浜国大の教育学部がまだ鎌倉にあった頃、そこに隣接した小学校だったんですね。教育大学ですから音楽教育もあって、ヴァイオリンの先生がそこにいらして、戦後の実験教育の一環で、付属小学校の生徒を対象としたヴァイオリン教室をはじめたんです。じゃあ、そこで習わせてみよう、と、通わされることになったようです。
では、自分から音楽を始めたのでも、将来的に音楽家になるつもりもなかったんですね?
もちろん。ただ、最初のころは割と面白いな、と思ってやっていて、数か月で上級生のクラスに入れられましたけれども。でも、僕はそもそも練習というものが嫌いな人間なので、まあ、六年間やったんですけど、もう最後の二・三年はいやいやで、レッスンから帰ってきても、ケースを一度も開けずに翌週のレッスンに行くという、そんなありさまで、小学校卒業と同時にこれ幸いとやめて、中学校三年間は、クラブ活動でひたすらバスケットボールばかりやっていました。
練習しなかったから、高学年になるとそんなに上達されなかった?
最後はモーツァルトの簡単なヴァイオリンコンチェルトくらいは弾きましたけど、その程度ですね。
高校に入ってから、突然音楽をやりたいと思い始めたという話ですが。
高校も二年になると、進路を決めなければいけませんよね。でも、あまり興味のあることもなかったから悩んでいたんです。まあ、音楽を聴くことは好きでしたけどね。加えて、中学の頃、私はキリスト教の信者じゃないですけど、たまたま地元の教会が少年合唱団をやっていて、すでに変声していたから中二か中三だったかな、男声が必要だからとちょっと手伝いに来てくれ、ってお願いされて、歌ったりもしていたんですね。それでも、特に音楽家になるつもりはなかったのですが、ある日、横浜の県立音楽堂に東京のオーケストラ、はっきり覚えていないですが、おそらく日フィルが演奏旅行にやって来て。で、暇だったのでそれを聴きに行って。聴いた曲もよく覚えていないけれど、いわゆるポピュラークラシックね。リムスキー・コルサコフの≪スペイン奇想曲≫とか、チャイコフスキーの≪1812年≫とか、そのようなものだったはずですけど、オーケストラがパーンと鳴った瞬間に、「ああ、作曲やろう」となぜかしらないけど思ったんですよ。それで、すぐに高校の音楽の先生を訪ねて、「作曲をやりたいから誰か作曲の先生を紹介してください」とお願いして、幾つか経緯があって紹介されたのが、長谷川良夫(1907-1981)先生という当時芸大の教授だった方で、長谷川先生について受験勉強を始めたわけです。
高校二年生から芸大の作曲科を目指すとなると相当大変だったのでは。
そうですね。二浪しましたしね。ピアノもゼロからやんなきゃいけないから。
バイエルから。
もちろんもちろん。
それなのに、先生はのちに自作の初演や、松平頼曉(1931-2023)さんの個展などで、ピアノの演奏をされていますね。
まあ、指が回るものはね。ちゃんと練習しないし、そもそも始めたのが遅いから、ピアニストの人たちみたいには指が回らないんですよね。だから、指が回るものについては何とか演奏が出来る感じで。
努力の甲斐があって、二十歳のときに東京芸術大学に入られるわけですけど、当時の芸大はいかがでしたか?
受験時代、もちろん和声や対位法を習っていましたけど、それって現実の音楽を作曲しているわけではないわけですよね。あくまで練習課題ですから。まあ、あまり面白くないんで、「自分で適当に、いろいろな人の真似をして曲を書いていいですか?」と先生に訊いたら、「もちろん。それは是非やってくれたまえ」というから、プロコフィエフの真似して書いたり、シベリウスの真似して書いたり、まあ、小さなピアノ曲みたいなものばかりですけど、そういったやり方で、自分なりの習作を書いていたんですね。それでも、和声なんかは一向に面白く思えなくて、ある日、「こういうことって作曲に役立つんですかね?」と先生に訊いたら、「まあ役に立たないかもしれないけれど、プロになりたいなら、これくらい出来てもいいだろ」とおっしゃられて、やっぱりそういうものか、と思って。そもそも、それをやらないと大学に入れないわけだから。長谷川先生は、「大学に入ったら好きなことをやっていいから」とおっしゃったわけですよ。それで、大学に入って、好きなことをやらせてもらいましょう、ってことで、以前からいろいろな人を真似して書いていたのが、レコードなどで好奇心をもって聴き始めていた(アルノルト・)シェーンベルク(1874-1951)とか、(ルチアーノ・)ベリオ(1925-2003)へと変わっていったのです。ただ、当時の芸大は非常に保守的だったんで、そういうものはほとんど認められなかったんですよね。ピアノパートに内部奏法のあるフルート曲《モノローグと5つの断片》(1968)を書いて、一年の試験に通らなかった、ということがあったんですけど(ラヴェル風の作品を再提出して不可を免れた)、それでも、長谷川先生は自由に書かせてくれました。
当時の芸大作曲科は三講座にわかれていたと思いますけど、作曲の先生は長谷川先生に限られる感じですか?
そうです。あと、長谷川先生が定年に近づかれてから、南弘明(1934-)さん。三年生から、南先生のレッスンになりましたかね。だから、作曲の師といえる方はこのお二方だけです。
これは以前、バリトン歌手の松平敬さんがSNSに書かれていたのですが、先生は芸大の授業で「ある曲が良いと思ったら、あなたがそれを良いと思う理由を突き詰めなさい」とおっしゃったそうで、それが大変印象的だったと。
松平さんがいらっしゃったのは、共通科目の授業だったと思うので、あまりそういうことは言わないような気がするんですが、作曲のレッスンではよく言うことです。
それはやはり、先生が習作としてピアノ曲を書いていた頃の態度に通じるわけですか。
そうです。つまり、たとえばパウル・ヒンデミット(1895-1963)の《画家マティス》のシンフォニー(1934)が面白いな、と思ったとしますよね。面白いな、と思ったときに全体的に面白いな、と思っているだけでは、どう真似をしていいかわからないわけでしょ?そうすると、譜面をみて、この小節のこの和音が面白い、とか、この旋律の音選びが面白い、とか、というふうに、自分が実際に何を面白いと思っているのか。もちろん、面白いと思っても、自覚できない要素もあると思うんですが、それでもなるべく、自分が面白いと思うのはどういうものなのか、非常に具体的に考え自覚していく。この小節のこの和音が面白いとまで思ったらしめたもので、じゃあ、その和音はどういう音程構造でできているか、とか、どういう音程構造の和音を面白いと思うのか、ってことがわかっていれば、自分で和音を書くときの音程構造に反映していく、というような。そういうやり方で、自分の音が見つかっていく。だから、なるべく具体的に考えましょう、という言い方をしているわけです。
自分の感性に引っかかったものを言語化していくのが重要なのでしょうか?
(以下、13500字分を含め、下記のコンサートのプログラムに収録)。


<コンポージアム2023>関連公演
近藤譲 室内楽作品による個展
2023年5月26日(金) 19:00開演 東京オペラシティリサイタルホール
https://note.com/jishizuka/n/n0191da97e28e

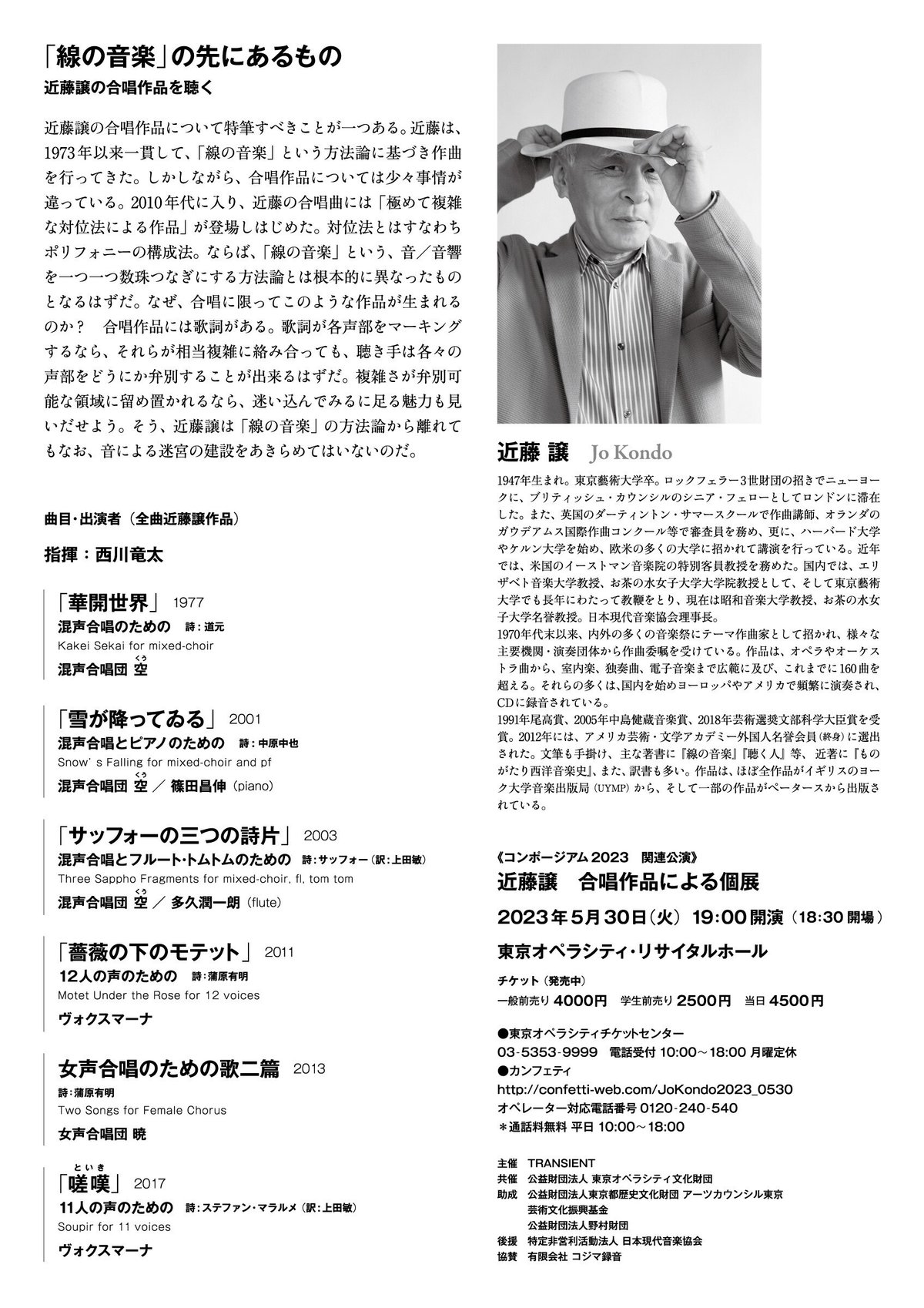
<コンポージアム2023>関連公演
近藤譲 合唱作品による個展
2023年5月30日(火) 19:00開演 東京オペラシティリサイタルホールhttps://note.com/jishizuka/n/n79b4d816f903
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
