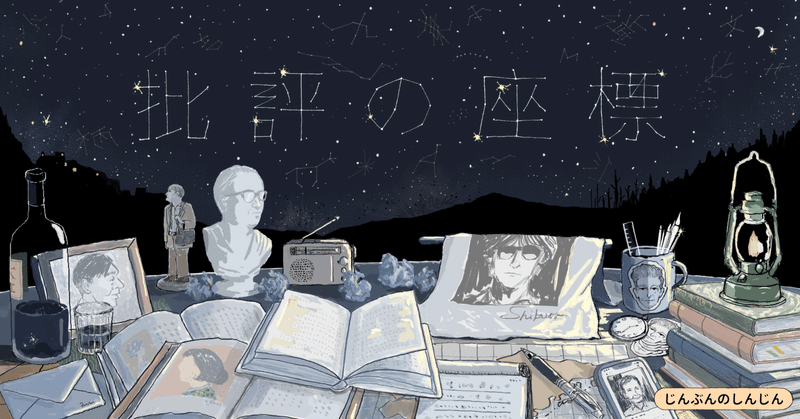
【批評の座標 第22回】蓮實重彥、あるいは不自由な近代人(鈴木亘)
第22回で取り上げるのは、フローベール研究から出発した仏文学者であり、アカデミズムでも批評の場でも第一線で活躍し続けている蓮實重彥です。『表層批評宣言』等の著作を丹念に読み解きながら、「近代」という観点から蓮實にとって「批評体験」とは何か、今月初めての単著『声なきものの声を聴く――ランシエールと解放する美学』を上梓する美学研究者・鈴木亘が探ります。
――批評の地勢図を引き直す
蓮實重彥、あるいは不自由な近代人
鈴木亘
1. 批評体験
蓮實重彥(1936-)は最初の著作『批評 あるいは仮死の祭典』(1974年)の第二段落で、すでに自身の文体的特徴をかなりの程度発揮させながら、しかしいくぶん実存主義の香りを残した調子で、「批評体験」について次のように説き起こしている。
ところでおよそ「作品」と呼ばれるものと関わりを持ってしまうことは、環境として馴れ親しんでいた言葉の秩序が不意にあやういものとなり、無秩序という秩序しか支配していない別の系列へとむりやり移行させられることである。言葉はいきなり白痴の表情をまとい、経験的な「知識」では統御しえない遙か彼方へと身をひそめ、その非人称性と越えがたい距離とによってわれわれを無媒介的に犯し、遂にそれと等しい白痴の表情をまとうことまで強要しにかかる。だから、日ごろの読書行為の中で襲われる眩暈に捉われたまま、われわれは新たなる環境に順応しようと躍起になるのだが、勿論その方法はどこにも示されていない。そこで漂流が、存在の崩壊がはじまる。そしてその崩壊感覚は、生の条件の逸脱にたえず脅やかされているが故に、文字通り危機的な批評体験の始まりを告げるものでもあるのだ。
蓮實にとって「およそ「作品」と呼ばれるもの」を読むことは、未知なるものと不意に出会ってしまうことである。それは日常的な言語使用の基盤を揺るがし、その自明性を解体させる。読書とは通常の認識枠組みに則って言葉から意味を取り出す営みであるどころか、むしろその枠組みが言葉によって裏切られ、失調させられる事件なのだ。それがもたらす「眩暈」は未曾有の感覚であるがゆえに、人はそこから脱する「方法」を持ち合わせていない。こうした状況にあって、それでも何とか存在根拠を確保しようとする格闘に、蓮實は「批評体験」の始まりを見て取っている。
本論考の全体を通じて示されることだが、蓮實の批評活動は最初から今まで、こうした「批評体験」に立脚し続けていると言ってよい。デビュー作で提起されたかかる構えが、文学にとどまらず蓮實のあらゆる批評を、シリアスだったり軽妙だったり語調の差はあれど、貫いているのだ。ジャンルの異なるいくつもの著作で、先の引用に重なる記述が繰り返されている。例えば映画論――「映画のたぐいまれな氾濫の中に身を置きながら深めていった自己の崩壊意識の徹底化(……)見るものと見られるものとの間に展開されるこの絶えることのない相互侵略の闘いを、自分から自分を引き離しながら刻々かちとってゆく苦しげな存在確立の歩みを、われわれはとりあえず「批評体験」と呼んでおく」(『映画の神話学』19頁、強調原文)。あるいはスポーツ批評――「スポーツには、嘘としか思えない驚きの瞬間が訪れる。また、人はその驚きを求めて、スポーツを見る。文化として始まったものが野蛮さにあられもなく席巻される瞬間を楽しむのです。優れた選手とは、文化として始まったものを、いきなり自然によって蹂躙してしまう野蛮な存在にほかなりません」(『スポーツ批評宣言』13頁)。さらには、ふとした日常の些事についても――「地下鉄の中で「地下鉄の乗客」という人にいきなり出会ったわけです。これはかなりすさまじい体験でして、座っていてふっと顔をあげると目の前に「地下鉄の乗客」がいるわけです。(……)その時、初めて、地下鉄には乗客がいる、という未知の現実を事件として体験しました。「あなた、どうしたんですか」と思わず言葉をかけたくなるような、絶対的な「地下鉄の乗客」って人がいるわけです」(『マスカルチャー批評宣言』6頁)。この出発点は最近の著作においても、つまりは半世紀に渡って不変である。「映画は、見るものをたちどころに武装解除しにかかり、それにさからう術は一向に見あたらない」(『ショットとは何か』281頁)。
一貫してこのことにこだわる蓮實の戦略が今なお刺激的であるとすれば、それは人々がこの「批評体験」から目をそらし続けているからだ。事実、未知なもののもたらす「眩暈」を既知の図式へと回収しようとする姿勢もまた、蓮實が当初から批判してやまなかったことである。再び『批評 あるいは仮死の祭典』の言葉を借りれば、「「作品」を前にして迷う権利をあらかじめ放棄」し、「曖昧たることしかありえぬものを捏造された鮮明さに、生の条件としてある混沌を虚濁の透明性に、迷路を直線の透視図に置き換える作業に専念する」態度に、しかもそれこそが「批評」であるとでも言わんばかりの態度に、蓮實は苛立ちを隠さない(88-89頁)。
批判されるべきこの既知の図式は、蓮實においてさまざまに語られている。例えば、語の厳密な意味で夏目漱石を「読むこと」をせず、「則天去私」とか「自己本位」といった「符牒」で漱石を「神話」化すること、「明治」や「女」によってそれらしい漱石の「人影」を確認し、「文学」というおなじみの「制度」を補完すること(『夏目漱石論』)。画面に見えているはずのものを見ようとせず、小津安二郎の映画を「単調さ」や「もののあわれ」といった「小津的なもの」をめぐる「紋切型」、「いまそこには存在しない物語」に還元すること(『監督 小津安二郎』)。美しい「運動」の営みであるはずのスポーツを、得点や勝敗といった「記録」や、フィールド外での「逸話」の集積としか考えないこと(『スポーツ批評宣言』)……。このリストもまた、いくらでも続けることができるだろう。
「神話」、「制度」、「物語」、何と呼ばれようがそうしたものへの還元的思考を廃し、むしろ〈紙面に書かれていること〉、〈画面に見えているもの〉に、つまりは表層に目を注ぎ、それがもたらす「眩暈」あるいは「驚き」の経験を辿ること。それが既存の批評に対するアンチテーゼとしての蓮實の実践なのだと、さしあたり表明してみる。蓮實において批評とは、作品について一定の仕方で書くための方法とか、一定の仕方で書かれた文章を総称するジャンルとか、あるいはその衰退や延命や復権が叫ばれたりするような制度とかである以前に、そのつど一回的で特異な出来事の経験を生きることそのものだ。――ごく基本的な態度に思われよう。だが今なおそれが徹底されないのは、実感されることだと思うが、制度や紋切型の誘惑があまりに強いものだからだ。人は存在を揺るがす真の批評体験に出会おうとせず、心地よい紋切型にたやすく身を委ねてしまうのである。いささか逆説的な言い方をすれば、人がこの誘惑に流され続ける限り、それを教え諭す蓮實の実践もまた延命され続ける。共犯関係、と皮肉を言っても良いかもしれないが、少なくとも彼の批評の有効性が、そのテクスト的強度以前に、あるいは「蓮實派」「蓮實門下」の権勢などといった業界政治の問題ではまったくなく、むしろこうした人間の傾向性に支えられていることは指摘しておくべきだろう。
だがもし、「読むこと」あるいは「見ること」をめぐるこの実践を「方法」として整理し、そこに彼の著作タイトルから借りた「表層批評」の名を与えてみるとすれば、それは蓮實の企図をすぐさま裏切ることになる。これは「表層批評」という紋切型に彼を回収し、その旗手として神話化し、実際のテクストを読まずに済ますための手立てにほかならないからだ。もちろん旧弊な徒弟制ではないのだから、背信それ自体は別に悪くない。本人もまた、“蓮實重彥が蓮實重彥をやっている”とでも形容したくなるような言論活動を通じて、自身をめぐる神話をユーモラスに再演しているようにも思われる。だがこの背信がテクストから目をそらし、偽りのイメージへと還元することに結びつくならば、その一点において、およそ人は紋切型への回収に抵抗しなければならない。蓮實への忠義ではなく、読むことの豊かさの肯定のために。
したがって重要なのは、紋切型への抵抗という彼の問題意識そのものを継承しながら、蓮實重彥と再び向き合うことである。例えば「表層批評」のような紋切型、神話的イメージに丸め込まれる手前で、蓮實のテクストを読むこと、そこに何が書かれており、何が書かれていないかを確かめることである。われわれは以下、彼の著作の中でも最も紋切型の単純化にさらされてきたと思われるテクストを軸に、この読み直しを試みることになる。それは他でもなく、『表層批評宣言』(1979年)その本である。
2. 表層批評?
そもそも『表層批評宣言』には、タイトルや目次を除いて「表層批評」の語は使われていない。蓮實はこの本文で、「表層批評」をそれとして規定しているわけでも、自らの方法として引き受けているわけでもないのだ。なるほど「表層的批評」という表現であれば一度かぎり現れる(242頁)が、それも「あとがき」というパラテクストにおいて、通りすがり的に書きつけられているだけである。蓮實自身、文庫版刊行(1985年)に際して寄せた「文庫版あとがき」で、この著作名そのもののいかがわしさを指摘した上で、自分は「表層批評」なるものを提唱した覚えなどない、と突き放す。
『表層批評宣言』という六つの漢字のつらなりは、表層を批評するぞと宣言すると翻訳さるべきか、表層において何ごとかを批評するぞと宣言していると翻訳さるべきなのか、あるいは批評宣言を表層にかさねあわそうと翻訳さるべきなのかさっぱりわからない。いずれにせよ、文中で触れられてもいるとおり、表層は、あるとき、荒唐無稽な力をあたりに波及させながら回帰すべき現象であって、たえずそこに在るというものではないのだから、表層批評宣言なる六語の組み合わせをどのように翻訳するにせよ、それが方法確立の宣言などであろうはずもない。(244頁)
それにもかかわらず人は、表層批評なる「方法」がそこに示されていると思い込み、それを蓮實重彥の名に帰属させ、蓮實と言えば表層批評だ、という紋切型に安住してきた。ひとえに楽だからだ。「この題名は、他人を安心させるための装置だったのかもしれない」(245頁)。『物語批判序説』という別の著作名を念頭に(あるいは念頭にすら置かず)、蓮實を「物語批判」の担い手に位置づけて済ませるのも同様だろう。
急いで付け加えなければならないが、ここで「表層」という語彙そのものを蓮實から切り離したいわけではない。そうではなく、蓮實におけるこの語の特権性は踏まえた上で、それを紋切型のイメージから少しでも上書きすることが重要である。そのためにも『表層批評宣言』の記述を軸に、「表層」の語にあえて“厚み”のようなものを与えてみたい。
先の引用に読まれる通り、「表層」は「荒唐無稽な力をあたりに波及させ」る動的な契機であってみれば、それが「制度」なり何なりを批判的に捉える契機として、これまで縷縷述べてきた蓮實の批評戦略を引き継ぐ観念であることは言うまでもない。だがそれは議論のための空疎な観念ではなく、むしろ具体的な事物と対応する語として登場する。すなわち「表層」とはまずもって、文字通りの「紙」あるいは「壁」のことなのだ。
蓮實は例えば「書物の歴史」といった学的言説において、印刷術の発明という出来事がことさらに語られる一方、「大量の書物の印刷を支えたはずの「紙」」の生産や流通については、「「書物の歴史」は完全に沈黙し続けている」と述べる(56頁)。また、「民主主義とは、投票用紙と身分証明書を交換しあう「紙」の儀式」(62頁)であるにもかかわらず、その現実が重要視されることはない。あるいはヨーロッパの教会建築論において、「円柱」や「穹窿」には多くの分析が尽くされているのに比して、「壁」は無視され「屈辱的な位置」に押し止められている(54頁)。蓮實が注意を促すのは、現行の「文化」という「制度」において、紙や壁という表層はいたるところに存在し、制度の成立条件そのものをなしているにもかかわらず、まさに当の制度によって、不可視の領域へと排除されているという次第である。
もちろんこの不可視性を指摘し分析することが批評なのではない。それは学問なり理論なりが行うことである。批評とは蓮實にとって不意に遭遇する驚きと眩暈なのであってみれば、表層の不可視性が可視的なものに転じる瞬間はまことに批評的な体験であるだろう。そのことを『表層批評宣言』はこう言い表している。
ここで言説を始動せしめその方向を指示するものとして問われるべき「批評」は、経験的な知の領域においても、反省的な知の水準においても、知そのものとこの上なく密接して生きる何ものかが、そのあまりの遍在性ゆえに視線から脱落し、二義的=周縁的な場へとみずからを貶め、しかもその寡黙な相貌によって、最も有効なかたちで不可視の「制度」を支えているという事実を原理や構造の側から分析し記述することではなく、最も現実的な一点から、「制度」が誇示する顕在と隠蔽の身振りへと踏み込むことによって、可視的な事件として生きることでみずからを消してしまうことにほかならないだろう。(......)平坦で、単調で、運動が廃棄されているかにみえる表面としての「紙」が、あるいは「壁」が「批評」の契機として重視されねばならぬとしたら、それはこうした特権的な表層たちが、いま、その圧倒的な遍在ぶりにもかかわらず、あるいはその遍在ぶり故に、あからさまに虐げられ、貶められた具体性として、人びとの瞳から視力を、そして精神から思考を奪っているからにほかならない。(60-61頁)
ところでここには、ひとがいわゆる「蓮實文体」としてイメージするものの典型が示されているだろう。引用冒頭から延々と続く文章が、「〜することではなく」とやにわに否定され、さらに再び長大なパッセージが続く、というものである。これについては二つ付言しておこう。第一点。引用文に見られる発想や語彙はミシェル・フーコーに由来するが、「〜ではなく〜である」の構文で長大なパッセージを繋げてゆくその文体もまた、かなりフーコー的である。第二点。「なければならない」「ほかならない」の断言調と並んで、書くことと読むことの運動性それ自体を示しているかのようなこうした文体的特徴を、蓮實の「肉体的なエンターテイメント」(241頁)の実践として見ることは容易い。彼がテクストに書いていることと、彼がテクストを通じてやっていることとの興味深い関係――いわばテクストのパフォーマティヴな性格――については大いに展開の余地があるが、ここでは蓮實がジョン・フォード『シャイアン』上映時のパリの映画館で遭遇した、それ自体「映画史が永遠に記憶すべき最も美しい映画的身振り」であるような、一人の少年の挿話を引用しておこう。蓮實の筆致は、日常における「批評体験」と言ってもよいその映画的瞬間を、これもまた活劇的な語り口で、つまりは「エンターテイメント」そのものとして、いわば再上映することに成功している――
真夜中をかなりまわった最終回の上映の終った直後、一人のフランス人の少年が、観客席の椅子を三列ほどとびこえて、夫婦というよりは恋人らしい一組の若い男女の方めがけて殺してやると叫んでとびかかり、総立ちになった観客注視のもとに、その男の首を両手でしめはじめ、激しい抵抗にあっていったんはねとばされると、改めて男の胸につかみかかり、まさにあれこそを組んずほぐれつというのだろうが、人間のたてる声の中でもっとも感動的な吼り声とともに通路をころげまわり、そのいきおいで何人かのミンクのコートの貴婦人が悲鳴とともに横倒しとなり、罵声がとぶ、嬌声があがる、わって入った男の眼鏡が割れる、と、まあ、絵に描いたような乱闘がはじまったのだが、誰もが呆気にとられて見まもるほかなかったその騒動がおさまったとき、ネクタイの乱れを気にもせず息をはずませながら立ちあがった少年は、(……)(『映画狂人シネマの煽動装置』35頁、強調原文)
ともあれ話を戻せば、「特権的な表層」、物質的表層としての紙があってこそ、紙と「言葉」が(これもまた物質的に)密着したものである「書物」が、表層として生み出される(『表層批評宣言』90頁)。われわれのよく知る比喩表現としての「表層」は、そこに基礎づけられている。すなわち表層は、こうした唯物論的条件のもとで初めて、メタフォリカルな意味での「深層」――そこに込められた作者の思想とか、そこに反映している社会的状況とか、作品成立の歴史的背景とか――の対立物として立ち上がってくるのだ。すなわち深層を廃した〈書かれていること〉そのものとしてである。そしてこうしたいわば二重の表層性は、書物からそっくりそのまま映画にも適用される。映画とはフィルムないし画面という物質的な表層に、〈見えているもの〉が密着したものからだ。したがって例えば次のように語られる――「しばしば問題とされる小津的な「無」とは、いささかも宗教的で形而上学的な概念ではなく、フィルムの表層に刻みつけられた建築学的=形而下的な〔つまりからっぽの空間の〕イメージなのだ」(『監督 小津安二郎』124頁)。なお『表層批評宣言』で種明かしされている通り、「表層」という語彙の出どころは『意味の論理学』のジル・ドゥルーズである(99頁)。「表層」は哲学的にも豊かな射程を有する語であるわけだ。
以上すべてからして、蓮實の「表層」は、例えばポストモダンとかニュー・アカデミズムとかと(不適切に)結びつけられるような「軽薄さ」の範疇にはそう還元できるものではない。実際、ここで表層と名指されるものへの着目もまた、時代の徒花ではなく、文学でも映画でも近年まで蓮實に一貫する態度である。それは集大成的文学論『『ボヴァリー夫人』論』(2014年)では「テクスト的(な)現実」と呼ばれ、綺麗な対をなすかたちで、集大成的映画論『ジョン・フォード論』(2022年)では「フィルム的(な)現実」と呼ばれている。もちろんこのことは、「表層」への志向が80年代前後の時代的要請と絶妙に共鳴していたことを否定するものではない。しかし最終節の内容を先取りして言えば、彼の態度がそのもとに括られるべき歴史的条件を指し示す語彙は、ポストモダンではなくむしろ近代である。
3. 遊戯と倒錯
「表層」の体験、「批評体験」を掲げ続ける蓮實。それが「制度」や「物語」にどうしても依拠してしまう人々の傾向性と裏腹であることは述べた通りである。ここで注意すべきは、『表層批評宣言』において、蓮實は両者を正面から対立させているわけでも、前者によって後者を打ち破ろうとしているわけでもないということだ。ことはそう素朴ではない。というのも蓮實にとって制度とは、単なる「悪」として「否定」されうるものではないからだ。それは「不断に機能している」にもかかわらず、「人が充分に恐れるに至っていない」ものである。つまり問題は、人々が制度のもとで「不自由」であるのに、それに気づかず「自由」であると錯覚し続けていることなのだ。蓮實の目論みは「表層」を持ち出してその不自由を思い起こさせることにあるのだが、制度は不断に機能している以上、その目論みもまた、制度の外部にやすやすと立つことはできない。すなわち『表層批評宣言』は、「表層の顕揚を志向しつつもろもろの距離と深さとにとらわれて生きるしかない書物」なのだ(『表層批評宣言』7頁)。
ではどうするか。蓮實が提唱するのは「一つの遊戯的な姿勢」である。それはこういうものだ。
それは、「倒錯」の姿勢である。「制度」の機能を意図的に模倣しながら、その反復を介して「制度」自身にその限界を告白させること。あるいは「制度」がそうした言葉を洩らしそうになる瞬間を組織し、そのわずかな裂け目から、表層を露呈させること。「物語」の説話的持続の内部に、その分節化の磁力が及びえない陥没点をおのずと形成させること。そのためにも、いたずらに「反=制度」的な言辞を弄することなく、むしろ「制度」の「装置」や「風景」を積極的に模倣しなければならない。(同前)
指摘すべきは、この「遊戯的な姿勢」、「倒錯」の姿勢もまた、最初に引用した「批評体験」の変奏として読まれうることだ。先に取り上げた驚きや眩暈は、ここで書かれる「裂け目」「陥没点」によって与えられるからである。ただしここでは最初の引用に漂う受難や危機のニュアンスは薄れ、能動的な戦略性が強調される(なお『表層批評宣言』では、「批評」に「危機」のニュアンスを重ねる発想が悪しき制度化の一環として非難されており(40頁)、その自己批判は微笑ましい)。批評体験は到来を待つというより、制度の「積極的な模倣」によって獲得されるのだ。これは例えば『小説から遠く離れて』(1989年)における中上健次論に具体的に示されている。蓮實によれば中上は、「明らかに意識的な作業として」(170頁)、類型的な物語を小説に――「黒幕と双子」の物語を『枯木灘』に――取り込み、それを一旦は反復しながら、そのクライマックスが不意に失調する瞬間を描き出す――黒幕との対決がカタルシスを形成しない――ことで、物語を宙吊りにしえた作家である。蓮實は中上のこうした作劇に、「批評の実践」(同)とまさに呼ばれるべき試みを見出している。
あえて制度に身を任せ、「反復」させてみることで、制度に自らその限界を露呈させ、自壊させること。この戦略はドゥルーズがマゾヒズムに見出したユーモアのそれだろう。蓮實は1973年に、ドゥルーズの$${\textit{ Présentation de Sacher-Masoch }}$$を『マゾッホとサド』として翻訳出版している。ところで、ここで次のように口を挟みたくなる向きがあるかもしれない。このユーモアの姿勢、制度内破的な実践を、蓮實は自らのキャリアにおいてどれほど果たしえていただろうか?――語学教科書『フランス語の余白に』(1981年)の著者紹介欄に「制度的には東大助教授という身分に拘束されつつ」と自虐的に記していた蓮實は、しかし順当に学部長、副学長を経て、総長という大学制度の中枢に身を置くに至る。それがどれほど成功した「遊戯」たりえたか、そこにどれほどの批評的契機がありえたか、その問いは開いたままにすることにして、本論考は最後に、蓮實のこうした身振りもまたひとつの歴史的条件に規定されていることに触れておく。「近代」と呼ばれるものがそれだ。
4. 凡庸と近代
蓮實が『凡庸さについてお話させていただきます』(1986年)で述べるところによれば、われわれの生きるこの時代は「凡庸さ」の時代である。これもまた蓮實の著作にたびたび登場する概念だが、つまりは作品AよりもBのほうが優れている、作家XよりもYのほうが才能がある、といった「相対的な差異」(14頁)によって比較可能なものが「凡庸」の次元に属するとされる(他方、いわば批評体験をもたらすような絶対的な差異は「愚鈍」と呼ばれる)。これが近代の問題なのは、「いわゆる近代国家が成立した19世紀以後」に初めて、「義務教育の普及と議会制民主主義の確立とにより、権利として誰もが何かになれるという社会が形成」されたからである。かつては例外的な作家のみが芸術に携っていた一方、近代においては誰しもが、「才能の有無にかかわらず、文学なり芸術なりを夢想」するようになる(13頁)。そこで芸術は絶対的な経験の契機であるよりもむしろ、民主的に共有された話題として、相対的な比較によって「凡庸」の次元で語られるものとなる。蓮實によれば小林秀雄や吉本隆明ら「日本の文芸批評の伝統」もまた、誰々のほうが優れている、という判断を通じて「適度に起伏にとんだ光景の凡庸さを補強」する、「きわめて安全な言葉」に満ちている(15頁)。とすれば蓮實の立場は、自らもまた凡庸から脱しえないという不自由さの自覚のもとで、芸術家を「相対的な差異の場」からの「離脱」において捉えることになる(16頁)。
述べられている事柄はやはり、「制度」に対する「批評体験」の擁護という構図の再変奏ではあろう。しかし重要なのは、この構図が近代の問題として歴史的限定を与えられていることである。そこから論点を二つ引き出しておきたい。第一に、ここで近代的凡庸の成立はフランス第二帝政の樹立(1852年)と重ね合わせられている。ナポレオン・ボナパルトの甥である――凡庸な――ルイ=ナポレオンが、クーデタの後に国民投票を経て皇帝の座についたこの帝政を、蓮實は「何かにつけて二番煎じ」と形容し、その非正統的な「二流」ぶりに凡庸の時代の象徴を見て取る。蓮實はまた、この凡庸さを当時の政治の場面にも地続きのものとして、自民党の「ニューリーダー」やアメリカのレーガンを引き合いに、「たいへんな政治的才能の持主なんて居なくても政治は十分機能していける」(40頁)時代なのだと嘆息する(この嘆息の身振りもまた、蓮實が自覚するように凡庸なのだが)。総長となり、フランスから勲章も貰うまでの自らの歩みが、近代の凡庸な政治家たちを模倣し反復していなかったかどうか、蓮實は少なくともそのことに意識的だったはずだ。何せ、ルイ=ナポレオンの義弟ド・モルニーを論じた『帝国の陰謀』から、随所で披露されるカジュアルな政談まで、彼はこの手の話題が嫌いではないようなのだから。
第二に、蓮實はフーコー『言葉と物』の議論を下敷きにしながら、自身にとって特権的な批評対象である(長編)小説と映画もまた、近代の「人間」がもたらした普遍的ならざる産物だという見地に立つ。
私は、映画は「人類」の文化的な資産ではないと思っています。では誰が映画を作ったかといえば「人間」である。その場合の「人間」とは、フーコーのいう「奇妙な経験的=先験的な二重体」にほかならず、それは「日付の新しさが容易に示されるような」ごく最近の「発見」にすぎません。要するに普遍的な「人類」とは異なる「人間」というものが、ひとまず近代と呼んでよかろう一時期に世界に姿を見せてしまった。その有限な「人間」が捏造したもののひとつが散文のフィクションとしての長編小説、もうひとつが現実とも仮象とも決めがたい映画だと考えています。(『映画時評2012-2014』334-335頁)
映画について言えば、それは1890年代の発明という意味で「ひとまず近代と呼んでよかろう一時期」のものだというばかりではない。映画はその物質的側面からして、1秒間に24コマの画像がもたらす「錯覚」であって、普遍的な「世界の再現」そのものではない(335頁)。それは歴史的にも存在論的にも有限な人間の産み出した、普遍を装う「いかがわしい捏造物」(同)であるというのが蓮實の立場である。
小説に関しては、蓮實は様々な著作で、「散文は生まれたばかりのものである」というギュスターヴ・フローベールの言に触れ、それが1852年――第二帝政樹立の年――の書簡によることにも注意を促す。ただし蓮實が言いたいのは、小説がその日付をもって誕生したジャンルだということではない。そうではなくて、小説は詩や戯曲と異なって、「西欧の伝統的な詩学、美学、もしくは修辞学にとっては思考しがたい」(『『ボヴァリー夫人』論』212頁)もの、理論的根拠を持たない非正統的な形式だということである。小説はしたがって、読むそのたびごとに、ひとつの「事件=できごと」(71頁)として無根拠的に現出せざるをえないものである点で常に新しい。つまりその非正統性、いかがわしさゆえに、小説は「古典的な表象体系の透明な秩序」を揺るがしうる、近代に固有の「過剰性」を抱え込んでいるのだ(86頁)。言い換えれば、物語を穿つ陥没点をである。
要するに、蓮實の批評語彙も、その対象も、政治的(にして批評的な?)振る舞いも、近代の枠組みに規定されているということだ。とはいえそれをもって蓮實の乗り越えなどを云々したいわけではない。本論考が見出してきたのは、蓮實の方法ならざる批評、現代的意義や流行り廃りを越えて、語の厳密な意味における「読むこと」と「見ること」に等しくすらある批評だった。もちろんそれもまた、「物語」や「紋切型」や「表層」や「裂け目」の近代的配置と同様、「人間」が「人間」である限りで有効なものではあろう。小説と映画という近代的ジャンルと切り離しがたい動詞かもしれない。それでも、そうした「知識」などどうでもよくなるような経験、歴史性の自覚など失効するような経験を、作品はもたらすのではなかったか。何よりまずこの「批評体験」から出発すること。蓮實がわれわれに与える最良の教えはそれである。
引用文献
すべて蓮實重彥の著作。文庫化・復刊などがなされたものはそちらから引用した。
『批評 あるいは仮死の祭典』せりか書房、1974年。
『夏目漱石論』青土社、1978年(講談社文芸文庫、2012年)。
『映画の神話学』泰流社、1979年(ちくま学芸文庫、1996年)。
『表層批評宣言』筑摩書房、1979年(ちくま文庫、1985年)。
『フランス語の余白に』 朝日出版社、1981年(増補版、2023年)。
『監督 小津安二郎』筑摩書房、1983年(増補決定版、ちくま学芸文庫、2016年)。
『シネマの煽動装置』話の特集、1985年(『映画狂人シネマの煽動装置』河出書房新社、2001年)。
『マスカルチャー批評宣言1――物語の時代』冬樹社、1985年。
『凡庸さについてお話させていただきます』中央公論社、1986年。
『小説から遠く離れて』日本文芸社、1989年(河出文庫、1994年)。
『スポーツ批評宣言 あるいは運動の擁護』青土社、2004年。
『『ボヴァリー夫人』論』筑摩書房、2014年。
『映画時評2012-2014』講談社、2015年。
『ショットとは何か』講談社、2022年。
『ジョン・フォード論』文藝春秋、2022年。
人文書院関連書籍
その他関連書籍
執筆者プロフィール
鈴木亘(すずき・わたる)1991年、栃木県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科助教。専門は美学。著書に『声なきものの声を聴く――ランシエールの解放する美学』(堀之内出版、2024年3月刊行予定)。翻訳にジョルジュ・ディディ=ユベルマン『受肉した絵画』(共訳、水声社、2021年)など。論考に「笑いの二つの身体――植木等と松本人志」(『ユリイカ』2024年2月号=特集:クレイジーキャッツの時代)など。
次回は3月後半更新予定、2023年4月から1年間続けてきた本連載シリーズの最終回となります。長濵よし野さんが竹村和子を論じます。
*バナーデザイン 太田陽博(GACCOH)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
